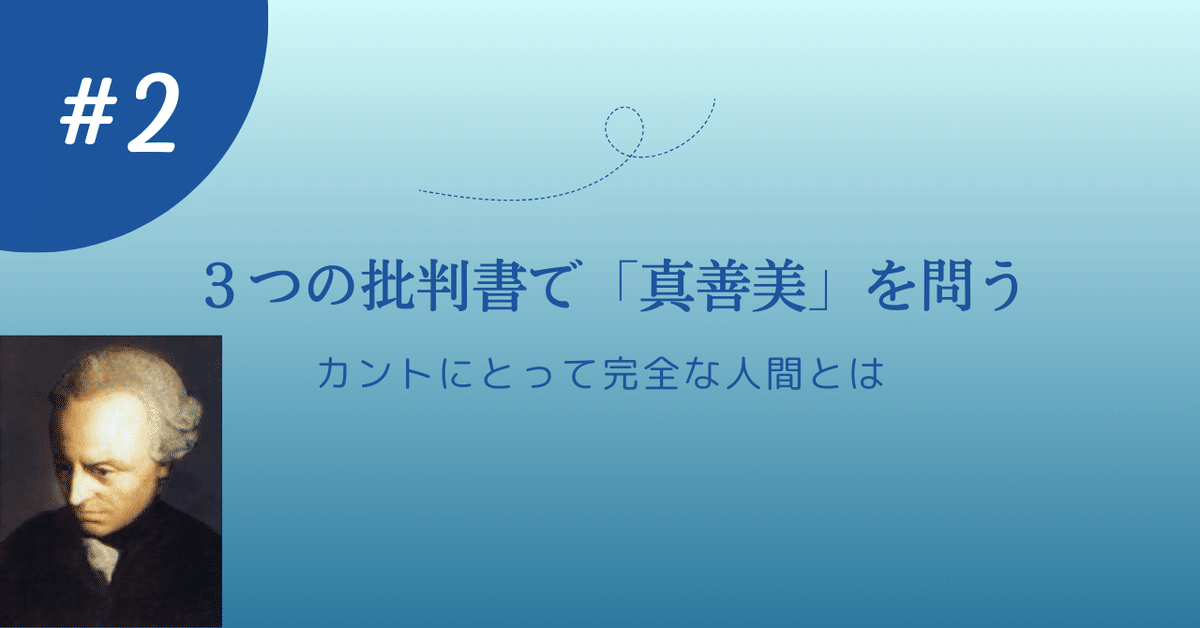
イマヌエル・カント(2)
第一批判書の「純粋理性批判」の内容は前回、述べてきたとおりである。再度、これを要約すると、この「批判書」は「感性論」「悟性論」「理性論」に分かれ、「感性論」のところで、懐疑論に陥ってしまったイギリス経験論の伝統を踏まえ、「理性論」のところで独断論に陥ってしまった大陸合理論の伝統を批判的に踏まえて、両者の総合的統一をはかったのである。
これに対して、第二批判書の「実践理性批判」は、我々の行為が「善」であると言えるのはどうあるべきかを論じた書である。これについても従来、二通りの考え方があった。1つはイギリス経験論者の考え方である。これは、いわゆる我々にとっての善なる行為とは、個人の幸福、あるいは個人の幸福を通しての全体(=国民)の「幸福」を図ることが善なる行為である、というものであった。これに対して、大陸合理論の方は、「神」あるいは「最高存在」の思惑に応えるような我々の行為が「善なる者」であるとする考え方であった。
これに対して、カントにとっての「善なる行為」とは、我々の行為が我々の人格の完全なあり方を実現するような行為であるならば、それを善とするものであった。その際、我々の人格の完全なあり方のために、仮に神のあり方を1つの目標とするというのであれば、それも致し方ないとした。つまり、我々の人格の完全なあり方を求めて、神のあり方を目標とするというのであれば、それもやむを得ないとしたのである。第一批判書で論じられた神の存在の認識不可能性(つまり、論じても無駄だと言う考え方)に対して、第二批判書では、我々にとって完全な人とは何かを考えるにあたって必要とあれば、神の存在を要請するのもやむを得ないとしたのである。ここでも、また神の存在を当然だなどと言っているのではなく、必要あれば要請することもありうる、としただけである。つまり、カントにとって神の存在など絶対必然のものではなく、必要あれば「あってくれ」と願うのもやむを得ないとしただけであることに注目のこと。
さらに第三批判書である「判断力批判」は、「美」論と「目的」論とに分かれる。特に、ここでの美論は、カントに先行したあのバウムガルテンの「美学」(1758年)に背負うところ大であった。バウムガルテンは、西洋思想史上、最初に美学を学問として独立させた思想家として有名であった。
