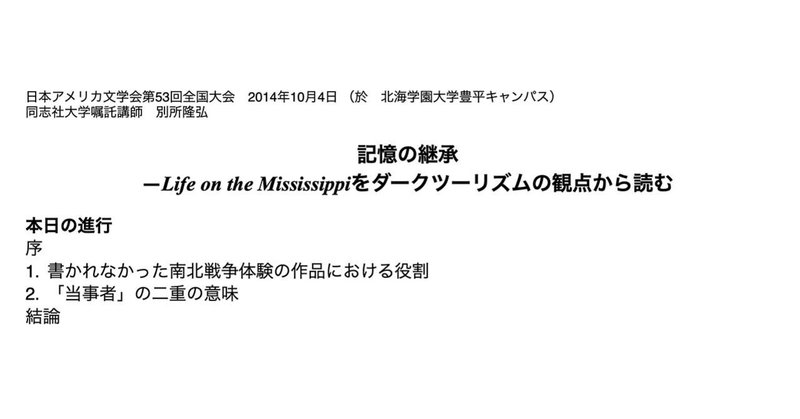
日本アメリカ文学会 全国大会発表「記憶の継承 ―Life on the Mississippiをダークツーリズムの観点から読む」 (2014年10月)
ふとした拍子に、7年前の僕の学会発表の原稿が出てきた。読んでみると、7年前の僕はひたすらに文学に対して真摯で、必死に取り組んでいた。この頃僕は、同時に狂ったように写真を撮っていた頃でもあって、今につながるほとんどの写真をこの頃に撮っている。メタセコイア並木も、飛行機も、桜も花火も。全部2014年。そしてこの二ヶ月後に、東京カメラ部の10選に選ばれる。幾つかの人生の転機になる年があるとすれば、この2014年がそれだった。僕は必死に生きていた。毎日毎日授業に追われ、研究に追われ、先が見えず、でもその不安と暗闇で自分を駆り立てるように写真を撮っていた。睡眠時間を限界まで削って、わずかな撮影時間を捻出していた。もうあの頃には戻りたくないけど、でも、この頃の僕は今の僕よりもずっと必死だ。その記録と記録の断片を、noteに残しておこうと思う。
以下の記事は、2014年の10月に、北海学園大学の豊平キャンパスにて行われた、日本アメリカ文学会第53回の全国大会で発表したものだ。(a)に発表の抜粋を転載しておく。この骨子が当日学会会場で行われるすべての発表を載せた冊子に掲載されたものになる。(b)は当日の発表原稿を載せておく。全国大会で発表された内容は、概ね学会誌にその後論文として発表される場合が多いのだけど、この後僕は本格的に写真家になってしまって、論文にはしなかったと記憶している。なので、この内容は、一度全国大会で発表されたのちには、世に出なかったものだ。だけど、いつか誰かのささやかな参考になればと思い、ここに残しておく。
発表原稿内の引用はページ数のみを記し、参考文献のリストは最後(c)に記した。
(a)発表骨子
記憶の継承 —Life on the Mississippiをダークツーリズムの観点から読む
氏名:別所隆弘
Recording the memory: Reading Mark Twain’s Life on the Mississippi in the Light of Dark Tourism.
Name: Bessho Takahiro
本発表は、Mark Twainの自伝的旅行記であるLife on the Mississippiを、ダークツーリズムの視点から読み解く試みである。1990年代後半以後、人類の負の遺産を巡る旅がダークツーリズムという用語で表現されるようになった。ただ、この概念が用語として規定される以前にも、旅におけるダークツーリズム的要素は、旅行記を始めとする旅をめぐる言説の中には見出すことが出来る。というのも、このダークツーリズムという概念は、失われつつある記憶に対する哀悼の念とその継承を目的とする旅を指すのだが、そうした一種の教養的側面は元来旅行という行為に本来的に備わっているものだからだ。ただ通常の旅やツアー以上に、ダークツーリズムにおいては失われたものを想起しようとする「記憶」における努力と、その記憶を文字や映像などのメディアを通じて「記録」として残そうとする意志が強い。このような性質から鑑みてダークツーリズムは本質的に文学作品に馴染み易い概念と言えるだろう。そして、「記憶」と「記録」の間で揺れ動きつつ、自らの過去を現在と接続しうるナラティブとして再編しなおそうとするTwainの試みもまた、その「記憶」と「記録」への拘泥ゆえに、ダークツーリズムという概念を適用して解釈され得る可能性を有している。
解釈にあたって、本作品の構造的な特質にまず着目したい。周知の通り、この作品は執筆期間が長いために前半と後半では扱っている時代や社会状況、またTwain自身の年齢や立場に大きな変化がある。このような大きな違いがある以上、別々の作品として分けた方が瑕疵は少なかったはずであるにも関わらず、殆ど強引とも思えるやり方で一つの作品に仕立て上げられている。しかし、作品を一つの物として仕上げようというこの動機の核心にあるものこそが、ダークツーリズムと共鳴する要素、すなわち記憶の風化に対する抵抗と、記録に対する意志として見いだすことが出来る。作品はむしろ、時間的/文化的に断裂した空隙を意図的に含み込み、その裂け目が決定的な欠落となる前に繕うという手続きをとることで、一つの継続した歴史として紡がれる。一方そうした手続きには必然的に事実を改竄し、自らが望む形での「歴史」を作り出すという、フィクショナルな手続きを必要とするだろう。 Twainが自らの表象で欠落した歴史を 上書きしようとする時、そこにはその表象を消費する読者との共謀関係を見出すことが出来る。仮に虚構が介在したとしても、共有できる物語として歴史は語られ、そして読まれる必要があるのだ。この時、Twainにおける「記憶」と「記録」にまつわる問題系は、失われつつあるものを表象し、継承する行為としてのダークツーリズムに必然的に近づく。
本発表では、ダークツーリズムという用語の概説と、その文学的適用の範囲を定めた上で、この概念を適用してLife on the Mississippiを読み解き、 Twainの本作における文学的な達成がいかなる意味を持っているのかを考察したい。
(b)発表原稿
序
本発表は、Mark Twainの自伝的旅行記Life on the Mississippiをダークツーリズムの観点から読むという試みです。ダークツーリズムという用語自体、まだそれほど馴染みのない言葉ですので、まずその簡単な説明からはじめたいと思います。
ダークツーリズムとは、1990年代の半ばに、二人の社会学者John LennonとMalcolm Foleyによって提唱された概念です。一般的なツーリズムが有名な観光地を回る旅の形態であるとするならば、ダークツーリズムとは戦争や大災害といった人類にとっての悲劇が起こった土地を選んでそこに訪れる旅のことを指します。例えばアウシュビッツ収容所であったり、日本の広島や長崎といった戦争や災害にみまわれた土地がダークツーリズムの旅先として選ばれます。日本においては、2011年3月11日の大震災以後、この用語をメディアで見かけるようになりました。
さて、このように簡単にダークツーリズムを見てみると、それが一体なぜMark Twainと関わりがあるのか、と思われるでしょう。確かにダークツーリズムというのは、新しい用語ですので、それを19世紀の作家に対して適用しようというのは、アナクロニズムのそしりを免れないかもしれません。しかし、本発表でMark TwainのLife on the Mississippiをダークツーリズムで読もうと考えるに至ったのには、いくつかの理由があります。一つにはダークツーリズムの基本的な形式である「悲劇の起こった土地を旅する」という旅行が、歴史的に見てツーリズムそのものの根幹と結びついているということです。ツーリズム研究の大家である社会学者マキァーネルは、ツーリズムという旅の形態が世俗化された形での巡礼の旅と捉えられるという風に指摘しておりますが、そうした巡礼の旅に内在する宗教的動機は、常に悲劇や悲しみと一体のものであると言えます。つまり、ある意味ではどのような旅にもダークツーリズム的な要素が潜んでいるということになるのです。例えばTwainの最初の旅行記であるThe Innocents Abroadを、まさにそのマキァーネルがツーリズムの最初の典型例として詳しく取り上げていますが、作品内容の後半は聖地エルサレムを旅する一種の巡礼の旅であり、その意味においてはダークツーリズムの要素を内包していると考えうるでしょう。ただ、こうした歴史的文化的な観点から考えられる要素以上に、この作品を読むのにダークツーリズムの観点が適していると私が考える理由は、本作の独特の構造にあります。ここで少し、この作品の構造的な特質について簡単に説明します。
このLife on the Mississippiという作品は、元々は1876年に書かれたOld times on the Mississippiという中編が下敷きになっております。全体の第3章から第18章まで、約4分の1程の量が、その元々の中編になるのですが、そこで一旦作品は完結した後、7年後の1883年に加筆され、現在の形で刊行されました。さて、このような作品成立の時間的な隔たりが作品構造全体を分断しています。というのは、最初の中編に書かれていた内容は、Twainがまだ若い水先案内人見習いであったのに対して、後から付け足された部分は、作家となった21年後の故郷再訪の旅行が付け足されているからです。内容的にも、時間的にも、そして作者の立場や身分さえも大きく異なっているのです。それに加えて、前半部分は南北戦争の前、そして後半部分は南北戦争後のことが書かれており、アメリカという国の歴史という観点から見ても、この前半と後半では大きく違った時空間を扱っていると言えます。そのため、一言で言うならば、この作品は極めて意匠の異なった別々の二つの作品が、無理矢理くっつけられているような印象を受けるのです。さらにこのような印象は、本来ならばこの前半と後半をスムーズに繋ぐべき潤滑油として書かれるべきだった第21章が、極端に少ない文章量で21年もの空白の時間を語るという無茶をしているために、かえってその断絶が強められる結果になっています。次の引用(1)をご覧ください。一章分の文章としてはかなり短い文章であることが一見してわかります。
(1) Life on the Mississippi , Chapter 21 “A Section in My Biography”
In due course I got my license. I was a pilot now, full fledged. I dropped into casual employments; no misfortunes resulting, intermittent work gave place to steady and protracted engagements. Time drifted smoothly and prosperously on, and I supposed -- and hoped -- that I was going to follow the river the rest of my days, and die at the wheel when my mission was ended. But by and by the war came, commerce was suspended, my occupation was gone.
I had to seek another livelihood. So I became a silver miner in Nevada; next, a newspaper reporter; next, a gold miner, in California; next, a reporter in San Francisco; next, a special correspondent in the Sandwich Islands; next, a roving correspondent in Europe and the East; next, an instructional torch-bearer on the lecture platform; and, finally, I became a scribbler of books, and an immovable fixture among the other rocks of New England.
In so few words have I disposed of the twenty-one slow-drifting years that have come and gone since I last looked from the windows of a pilot-house.
Let us resume, now. (Twain 166)
しかし、今この数字の奇妙な一致に気付かれた方もいると思いますが、明らかにこの奇妙に短い一章は、Twain自身の意図を反映したものです。前半と後半が扱っている時間は21年間の隔たりがあり、それを扱う21章は、本来ならば与えられるべきより多くのページ数の全てをはぎ取られて、短くまとめられているのです。つまり、作品は巨大な空白、あるいは分断を意図的に抱えたものとして、Twainによって構成されたのです。
このような些か構成的に無理のある作品を前にした時に前景化される疑問は、この記録の伴わない21年は、作品においてどのような意味を持つのだろうということです。あるいは、この21年のTwainの記憶は、なぜこの自伝とも言いうるような作品の中で、描かれることがなかったのかという疑問です。すなわち、Twainによってある意味では不在の中心として選ばれたこの21年の空白は、記憶と記録の問題として、この作品に大きな論点を与えるのです。そしてそのような記憶と記録に関する問題系をこの作品に読み込む時に、本来ならばアナクロニズムのそしりを免れないダークツーリズムの文脈が有効になってくるのです。では具体的にはどのように繋がってくるのかを次に考察してみたいと思います。
(1) 書かれなかった南北戦争体験の作品における役割
先ほど冒頭で、ダークツーリズムに関して簡単な説明をいたしましたが、その時にダークツーリズムとは人類の負の遺産、悲しみの土地を回る旅行のことであると述べました。そのような性質を帯びた旅行である以上、ダークツーリズムには個人の記憶、特に死や別離、あるいは故郷の喪失といった、失ってしまったものに対する強い拘りが、旅の動機となることは明白です。ここで重要なのは、この喪失を引き起こした原因が、単なる個人レベルを超えた社会的に大きな意味を持つような事件、例えば戦争や大災害といった場合は、個々人の記憶が風化してしまう前に、人類にとっての集合的な記憶にする作業、すなわち記録化に対する強いこだわりが生まれてくるのです。ダークツーリズムにおいて重要視されるのは、この「記憶/記録への強い拘り」なのです。観光学者の出井明の指摘を次の引用(2)で見てみましょう。
(2) ある場所で生じた悲しみは、その場にいてこそ、その重さや辛さをリアルに感じることができる。そして外部の来訪者が訪れることで、悲しみは共有され、地域の人々は癒しを得られる。同時に地域の悲しみはツーリストを通じて外部に伝播していく。その結果として、時代や地域を超えた普遍的な悲しみの存在が認知されるようになり、そのいくつかは “構造的なつながり”を持つことになる。(井出 53, underline is mine)
強調部にありますように、ダークツーリズムの基本的な意義を「普遍的な悲しみの存在」の「構造的なつながり」を明らかにすることと定義しているのも、まさにダークツーリズムの本質的な意義が、この「記録」への拘わりにあるからなのです。つまり、単に「悲劇の地」を旅するという旅そのものの形式的な側面よりも、そこで何が行われ、そしてどのような結果をたどったのか、それを記録することこそが問題になるということです。ダークツーリズムにおける本質的な旅の動機は、記憶と記録の問題、あるいは表象とその消費の問題として一般的なツーリズムから差別化されるのです。
このようにダークツーリズムをまとめてみると、Twainが本作品で行った故郷への旅は、まさしくダークツーリズムそのものであるということがわかります。南北戦争という未曾有の国家的内乱、そしてそれに伴う故郷の喪失にも等しい解体とその再建の歴史的過程といった、個人が直面するには重過ぎる運命をTwainはミシシッピ川で経験しています。その内乱を挟んだ前後において、Twainが慣れ親しんだミシシッピ流域の光景は、おおきく様変わりしました。そのため、Twainはかつてそこにあった風景をもう一度見いだし、記憶から掬い上げる旅を画策します。数年前に私は一度このTwainの風景描写のもつ独特の特質に関して発表したことがありますが、その際に注目したのは、Twainがこの作品において「過去」の風景を「現在」の風景と接続することに拘っているという点でした。つまり、記憶にある過去の風景を、記録へと定着する旅こそが、まさにこのLife on the Mississippiなのです。南北戦争という国家的苦難を媒介にするという点、そしてそこへ赴くことで消えつつある物事への記憶を、なんとか記録へと変換するという強い拘りがある点、この2点こそがまさにTwainの旅を典型的なダークツーリズムとして考えることの出来る理由なのです。
さて、このような文脈で考えた時、本発表の最初に言及した、作品の構造的な分断が再び問題になってきます。つまり、なぜTwainは21年、特に南北戦争期の記憶を描こうとしなかったのでしょう。あるいは、描けなかったのでしょう。作品全体が失われつつある「記憶」を他者と共有しうる「記録」へと変換する作業であると考えるならば、まさにこの南北戦争中の記憶こそ、記録されるべき最たるものであるように思えます。しかし、Twainにとってその作業は、かなり大きな困難を伴う作業であったのです。というのも、周知の通り、Twainは南北戦争から実際には逃げてしまっているからです。自ら結成した義勇軍を伴って南軍側に参加するも、Twainはわずか二週間でそこから離脱し、兄のヘンリーに付き従ってアメリカ西部へ赴く旅に出てしまいます。そして、それ以降の記憶は、Roughing Itという形で作品化されております。
つまり問をより正確に記すならば、Twainが参加した僅か2週間の南北戦争の記憶はなぜ描かれなかったのか、ということになります。そのとりあえずの回答は、本作品の2年後に出された”The private history of a campaign that failed”(「失敗した従軍体験記」)という短編になります。しかし、これは多くの批評家が指摘しているように、戦争から逃げ出したことへの自己正当化以上には読めないような、歯切れの悪い失敗作と見なされる作品です。
ただそうした振るわない内容である一方、この作品のタイトルは、私たちにある示唆を与えてくれるように思います。Twainは、この作品のタイトルをPrivate historyという形で世の中に提示しました。Twainの意識下には、この作品が個人的な物語であって、それは万人に共有できる類いの経験ではないという意識があったということをこのタイトルは示唆します。ただ、そうした意識は、本発表で扱っているLife on the Mississippiという作品の性質とは、実は強く反発するものでもあるのです。次の引用(3)の下線部をご覧下さい。
(3) But the basin of the Mississippi is the BODY OF THE NATION. All the other parts are but members, important in themselves, yet more important in their relations to this. (Twain 30, underline is mine)
ミシシッピ川をThe “Body of the Nation”(国家の根幹)と呼ぶ作品の冒頭を見ると、TwainはこのMississippiという川をアメリカ合衆国という国家の根源に見立てております。つまり、Mississippiの歴史をひもとくということは、アメリカ合衆国の歴史の根幹を読むこと、あるいはアメリカという国家のメトニミーとして読むということに他ならないのです。そのようなTwainの意識は、自らの作品に対する大きな期待と自負心を培います。妻に送った手紙の中の言葉である引用(4)をみてみましょう。
(4) But when I come to write the Mississippi book, then look out! I will spend 2 months on the river & take notes, & I bet you I will make a standard work. (Kruse 6, underline is mine)
強調部にあるように、TwainはLife on the Mississippiを、”a standard work(代表作)”になるものとして考えていました。その結果、引用(5)にあるKruseの指摘にあるように、
(5) It would seem logical, therefore, that in Mark Twain's conception of a standard work all facts must be presented as neither subjective nor relative, but must be endorsed by authoritative statements and definite opinions on the part of the author. (Kruse 23)
作品全体からsubjective(主観的)あるいはrelative(相対的)な要素を可能な限り排除し、作品がauthoritative(信頼できる)でdefinite(具体的)な性質を帯びるようにTwainは注力します。そしてさらに次の引用(6)をご覧ください。
(6) The reason is plain: a pilot, in those days, was the only unfettered and entirely independent human being that lived in the earth. (Twain 122)
本作品第14章において、Twainは蒸気船の水先案内のことを、強調部分にあるように「地球上で唯一、自由で完全に独立した人間である」と誇らしく宣言しております。すなわち、水先案内人を典型的なself-reliant(自己信頼)なアメリカ人の理想型として考えているのです。
つまりTwainの頭の中には、自らを代表する作品としてLife on the Mississippiを仕立てようという意志があったこと、そしてその作品は、ミシシッピの歴史を語ることを通じてアメリカ合衆国全体を代表するような歴史を作ろうとしていたこと、そのような意志があったと考えられます。批評家Lawrence HoweはTwainのこの作品におけるこのような傾向を、次の引用(7)で指摘しています。
(7) The term "representativity" in this context denotes Twain's desire to embody personally the idea and experience of America. This phenomenon, recurring frequently in American literary history, sprang from the interpretative tradition of Puritan typology and assumed secular form in the autobiographical tradition that Franklin inaugurated. (Howe 421)
Howeはこの作品におけるTwainの表現を、「representativity(代表的性質)への欲望」と定義しました。Benjamin Franklinに代表されるアメリカの自伝的作品の多くが、アメリカという国家の一部を描きつつ、その全体を代表するというような、いわばメトニミーとして機能する傾向があったことをHoweは指摘し、この作品もまたこの系列に繋がるものとして提起するのです。
このようなTwainの強い思い入れの結果、この作品に自らの失敗した従軍体験は収録されないことになった、そのように考えることが出来ます。個人の旅の記録でしかないLife on the Mississippiという作品が、アメリカを代表する性質を獲得し、さらには他者と共有可能な歴史となるためには、privateと後に題されることになるあの失敗の記憶は、共有不可能で排除されねばならない性質のものだったのです。批評家Daniel Aaronやあるいは前述のHorstも指摘しているように、Private Historyの作品内におけるTwainを含む兵士たちの描写が、驚く程に幼く、そして無責任に描かれており、そのような子どもじみた姿は、Life on the Mississippiで書かれるような「独立した誇り高い水先案内人」の描写とは好対照をなしていることからも、この南北戦争中の経験がLifeには入れられない性質のものであることを裏付けています。彼にとって、南北戦争中の経験は恥ずべきもの、出来ることなら黙っておきたい類いの歴史なのです。
このようなTwainの決断が本当にあったのかどうかは、飽くまでも推測の範囲をいまだ出ないでしょう。ところが、本作品を読んで行けばこれが単なる推測の範囲では収まらないと言える著述が、Twain自身によってなされています。少なくとも、Twainは南北戦争についての自らの体験を意図的に書かなかったことが、作品中で示唆されます。それは、作品後半が始まってすぐ、ヴィックスバーグという街で体験した内容を語る場所に見られます。Twainはこの土地が南北戦争の激戦地であったことを述べつつ、奇妙なことに、だからこそこの土地の住民は戦争について語ることが出来なくなったと言います。引用(8)をみてみましょう。
(8) A week of their wonderful life there would have made their tongues eloquent for ever perhaps; but they had six weeks of it, and that wore the novelty all out; they got used to being bomb-shelled out of home and into the ground; the matter became commonplace. After that, the possibility of their ever being startlingly interesting in their talks about it was gone. (Twain 259, underline is mine)
Twainは、ヴィックスバーグの住民が戦争について語れなくなった理由を、あまりにも過剰な戦争体験のために感覚は麻痺し、その結果、それらを語る能力が「なくなってしまった」と指摘します。ですが、Twainがヴィックスバーグのことを語りつつ念頭に置いているのは、自らの南北戦争からの離脱体験であることは明白です。ヴィックスバーグの住民たちのことを語るふりをして、自らが戦争を語らずに済ますことの正当性を、ここで裏づけようとしているというわけです。
ただ、ここで注目すべきことはそれだけではありません。もっと注目すべきなのは、直接的に戦争を語る権利を「放棄」することにおいて、その戦争に参加していたという極めて逆説的なロジックが成立するということなのです。自らもまた戦争に参加していたからこそ、戦争については書くことができない、つまりTwainは南北戦争の当事者であることを、それについて書かないことによって裏付けているのです。そしてそのような当事者性を獲得すると同時に、今度は歴史の記述者として、自らが「聞いた」話を作品内に置くことの正当性をも獲得しようと試みます。引用(9)をご覧ください。
(9) Could you, who did not experience it, come nearer to reproducing it to the imagination of another non-participant than could a Vicksburger who did experience it? It seems impossible; and yet there are reasons why it might not really be. (Twain 258, underline is mine)
ここにおいて、another non-participantの方が、ヴィックスバーグの人間よりも、戦争についてより上手く再現出来ると述べられています。つまり、二次ソースを聞いて再現出来るimaginationこそが、当事者の感覚の摩耗を上回るという、眉唾物の理論を提唱することによって、Twain自身が自分の歴史を語らないままに、他者の歴史を代弁することの正当性をも得るのです。ここにおいて、Twainは、書けない「空白」があるからこそ、歴史の代弁者足り得るという、非常にアクロバティックなロジックを成立させているのです。戦争という、国家にとっての一大事から逃げたTwainは、当事者はそれを書かない、書けないというロジックを使うことで自らの空白の期間をむしろ目に見えない充足として補填し、それと同時に、作品としての欠落を埋め合わせるために、「伝聞」という形で他者からのエピソードをその空白に放り込むことの正当性をも獲得しました。このような錯綜した手続きを経由することで、南北戦争前後の個人史における空白に関して、Twainは単なる沈黙以上の積極的な意味合いを与えたのです。
(2) 当事者の二重の意味
ただ、このようなナラティブのありかたは、一般的な「自伝」や「旅行記」ではありえないものです。物語に空白が存在することは、通常はその部分に関する経験がないことを意味するからです。しかし、ダークツーリズムの文脈においては、空白や沈黙はむしろ肯定さえされる場合があるのです。例えば、そのような肯定されうる空白や沈黙の可能性を、社会学者の加藤久子は詩人長田(おさだ)弘のアウシュビッツでの体験を記した手記の中に見出します。引用(10)をご覧ください。
(10) ここでまず指摘できるのは、収容所博物館では、ツーリストおよびガイドにも、コレクトな態度が要請されている点である。また、長田は、ツーリストがアイスクリームを舐めたり、ガイドが壁にもたれて退屈したりする姿に批判的な視線を向けているばかりか、「いかにも今日的なレストハウス」が存在することにすら驚きや戸惑いを隠さない。しかし、これは<アウシュビッツ>に特有の反応ではない。(加藤 247)
ツーリストアトラクションと化してしまったアウシュビッツに対して、長田が嫌悪を感じるというシーンを紹介しながら、加藤はこのような悲劇の地における詩人の反応に、ダークツーリズム一般において「コレクトネス」という要素があると指摘しています。あたかもドレスコードのように、ダークツーリズムにおいてはその場にふさわしい振る舞いの基準があるのです。それは具体的には、小さい声での会話や沈鬱な雰囲気、あるいは寡黙さや沈黙といった、言葉が消失する方向へと働くものです。ダークツーリズムにおいては、言葉が失われることはむしろその場にふさわしい態度とみなされるのです。
一方、作品という側面から考えるならば、そのような語りの不在による物語の空白は、満たされることが要求されます。そもそもツーリズムとは日常世界とは異なる世界を旅する際に、旅行パンフレットから始まり、ツアーガイドや現地通訳、ウェブでの発信やそれを元にした様々な交流といった、言語やヴィジュアルを媒介にした過剰な表象の消費行動を伴うものですが、ダークツーリズムにおいては表象は一層過剰に要求され、消費されることになります。
それは、戦争や災害による死者の沈黙や、あるいは故郷の崩壊といった、かつてあったものが失われた、あるいは失われつつあるなかで、その喪失による空白を埋める緊急の必要性が出てくるからです。このような空白を埋める時に問題になるのが、ダークツーリズムにおける「当事者」の問題です。すでに、Twainのヴィックスバーグの例を通じて、戦争のような悲劇を体験した者が、過剰な経験ゆえに精神が摩耗し、沈黙へと陥るという機序を、マーク・トウェインが自らの「沈黙」の裏付けとして利用したことを説明しましたが、一方でその沈黙や空白を埋めるのもまた、当事者なのです。ここにおいて、ダークツーリズムにおける「当事者」の二面性が出てきます。ダークツーリズムにおいては、戦争や災害を実際に経験した人間が当事者であると同時に、その場に事後に訪れ、本来ならば無関係な人間もまた、その場に参与することにおいて「当事者」と見なされるのです。そのようなダークツーリズムに特有の「当事者性」の二面的な性質を、先の加藤は引用(11)のように指摘しております。
(11) 長田の手記においても、ツーリストである長田が他のツーリストを観察し、論評していることに注意する必要がある。「負」であることが前提として了解されている場において、その場に在り、景観の一部を構成することにより、ツーリストはツーリスト(主体)であると同時に、ツーリズムの対象(客体)として、その場に参加する/巻き込まれることになる。 (加藤 249)
すなわち、ダークツーリストはツアーを遂行する主体、すなわち本来「部外者」でありながら、同時にその場に巻き込まれる客体として、その悲劇の地の「当事者」ともなるのです。「当事者性」のこの二面的な性質のために、ダークツーリズムは、悲劇は軽々に語るべきではないというポリコレ的な「沈黙」と「空白」を内包する一方、そこに参加した/巻き込まれた、事後の旅人の表象によって、その空白は埋め尽くされることになるのです。それはいわば、当事者同士の間で結ばれる暗黙の共謀関係と捉えることも出来るでしょう。そしてそのような一種の共謀関係をダークツーリズムは肯定するのです。先に観光学者出井明の言葉を引用(2)で見ましたが、彼が言うように、悲しみの構造はその経験を共有されることによって初めて明らかになるからです。
(2 再引用) ある場所で生じた悲しみは、その場にいてこそ、その重さや辛さをリアルに感じることができる。そして外部の来訪者が訪れることで、悲しみは共有され、地域の人々は癒しを得られる。同時に地域の悲しみはツーリストを通じて外部に伝播していく。その結果として、時代や地域を超えた普遍的な悲しみの存在が認知されるようになり、そのいくつかは “構造的なつながり”を持つことになる。(井出 53, underline is mine)
こうしたダークツーリズムにおける「当事者」の二面的な性質が、この作品において「語れない」沈黙を持ちながら、事後に別の声で語り始めるという、あの南北戦争の記憶を語るTwainの姿に重なってくることは自明でしょう。Twainは、自らの体験の欠落を正当な空白として肯定する一方で、他者の話を二次的に語るという行為を経由することによって、その空白を埋め合わせようとしました。その二つの行為は、一人がやるという意味においては完全に矛盾しているように見えますが、南北戦争の当事者でありながら、そこから逃げ出した離脱者でもあるという、極めて複雑な立場のために、Twainは現代のダークツーリストの当事者の二つの側面を一人で持つことになるのです。そしてそのようなTwainの複雑な当事者的立場は、内的には分裂しつつも見た目上は統合された、まるでこのポストベラム時代のアメリカそのものであるとも言えるでしょう。図らずも、Twainがミシシッピをthe body of the nation(国家の根幹)と呼んだように、Twain自身もこれ以後国民作家として、このアメリカの歴史の根幹、bodyを構成する、不可欠の要素となって行くのです。
結論
このように、ダークツーリズムを補助線に引いてこの作品を読んだとき、Twainがやろうとしていたこと、そしてその結果この作品に反映されているある特質が浮き彫りになってきます。その一つは、フィクションと歴史の関係性の問題でしょう。Twain自身がヴィックスバーグで語っているように、歴史の空白を埋めうるのは真の意味での当事者ではなく、事後にそこにやってきた、想像力を持った旅人、すなわち部外者であるということです。そのようなロジックは通常成り立たないはずですが、ダークツーリズムという概念の内側では、事後に訪れる旅人もまた「当事者」として記憶を受け継ぎ、語る行為の中に巻き込まれて行きます。そのような中で作られる「歴史」は、真実とフィクションが綯い交ぜになったstoryなのですが、消失しつつある記憶を留めるためには不可欠な手続きであるのです。Twainが作家としてこの作品内において目指すのは、a standard work(代表作)を目指すというあの言葉からもわかるように、「共有しうる歴史」としてのミシシッピの物語だったはずです。そしてそのような態度こそが、先に挙げたHoweの言う「代表」的な性質を持った、アメリカの自伝の伝統に連なる部分でもあるのです。
ところで、なぜそもそもこのような「共有しうる歴史」が必要とされるのでしょう。ここでもう一度ダークツーリズムの定義を行ったLennonとMalcomの議論を参照したいと思います。引用(12)をご覧ください。
(12) [T]he objects of dark tourism themselves appear to introduce anxiety and doubt about the project of modernity... (Lennon and Foley 11)
彼らが指摘するのは、ダークツーリズムという形で我々が問題にしているのは、悲劇が起こった原因に対する不安であり、それはいわば、近現代というあの巨大なプロジェクトもたらすものへの不安であると指摘しています。それまでの戦争や災害では見えてこなかった、近現代特有の大量の人間の死を前にした時に感じる圧倒的な不安の感覚を、ダークツーリズムは「記憶」を「記録」化することで乗り越える道を作ろうとするのです。
ではTwainはどうなのでしょうか。そのような不安感をTwainは共有していたのでしょうか。その一つの表れと見なせる例は、Life on the Mississippiの第20章で描かれている、蒸気船の爆発によって死んだ弟ヘンリーの物語でしょう。テクノロジーの発達の中で不可欠に死んで行く人間という最初の物語原型を、Twainはヘンリーの死の中に見出しているように思います。というのは、この作品の中には、他にも蒸気船の事故によって死んだ人間たちに対する一種の不安が、まるでトラウマのように時々噴出する形で作品の通奏低音として響いているのです。
その不安の音は後期Twainに一つのテーマを与え、その大きな結実はあのコネチカットヤンキーの最後のシーン、近代武器による大量虐殺のシーンに見ることができます。つまり、ダークツーリズムを経由して本作品を読むことで見えてくることは、Mark Twainという作家が、近代のとば口にあって、すでにその帰結を予感していたのではなかったかということなのです。ご清聴ありがとうございました。
(c)参考文献
Howe, Lawrence. “Transcending the Limits of Experience: Mark Twain’s Life on the Mississippi.” American Literature 63.3 (1991): 420-39.
Kruse, Horst H. Mark Twain and “Life on the Mississippi.” Amherst: U of Massachusetts P, 1981.
Lennon, J. and Foley, Malcom. Dark Tourism: The Attraction of Death and Disaster. London: Continuum, 2000.
MacCannell, Dean. The Tourist: A New Theory of the Leisure Class. New York: Schocken, 1976.
Twain, Mark. The Innocents Abroad, or the New Pilgrim’s Progress. New York: Penguin Books, 2002.
---. Life on the Mississippi. 1883. New York: Penguin Classics, 1986.
---. Mark Twain-Howells Letters: The Correspondence of Samuel L. Clemens and William D. Howells, 1872–1910. Eds . Henry Nash Smith and William M. Gibson. Cambridge, MA: Belknap, 1960.
---. “The Private History of a Campaign That Failed.” The American Claimant And Other Stories And Sketches. New York: Gabriel Wells, 1892. 255-282.
加藤久子「負の文化遺産のツーリズム」、 山中弘編『宗教とツーリズム―聖なるものの変容と持続―』、世界思想社、京都、2012
井出明「チェルノブイリから世界へ」、東浩紀編『チェルノブイリ・ダークツーリズム・ガイド 思想地図β vol.4-1』、ゲンロン、東京、2013
記事を気に入っていただけたら、写真見ていただけると嬉しいです。 https://www.instagram.com/takahiro_bessho/?hl=ja
