
人を責めずに仕組みを責めよ。飛行機事故の少なさの秘訣。
はじめに
こんにちは、隆之です。
よく「人を責めずに仕組みを責めよ」という言葉が聞かれますが、実際にみなさんは心の底から納得できていますか?
今日は、みなさんにこの言葉を納得していただけるかを試みてみます。
具体的には、航空業界と医療業界を比較しながらその意義を解説します。どちらも命を扱う厳格なルールを日々進化させている業界です。また、法律を扱う司法や、身近な職場についても考えてみましょう。
飛行機事故の確率は非常に低い

BingAIに毎日飛行機は世界で何回飛んでいるかを聞いてみました。
世界で飛行機は一日に何回飛んでるかというのは、正確には分かりませんが、いくつかのデータやサービスから推測することができます。
例えば、フライト追跡サービスのFlightRadar24によると、2023年7月24日には22万5000回以上のフライトが記録され、1日のフライト数としてはこれまでで最多となりました1。このサービスは、世界中のフライトをリアルタイムで追跡していますが、軍用機など機密性の高いフライトを除外しているので、実際のフライト数はもっと多くなる可能性があります2。
また、ボーイングによると、稼働している航空機の総数は貨物用を含めて約2万3660機と推定されています3。このうち、ピーク時には約1万6000機が同時に空を飛んでいると言われています。
統計によれば、飛行機事故は一般的に数百万回のフライトに一回程度しか大きな事故が起こらないと言われています。この脅威的な事故の少なさを探求してみましょう。
業界の仕組みを比較しよう
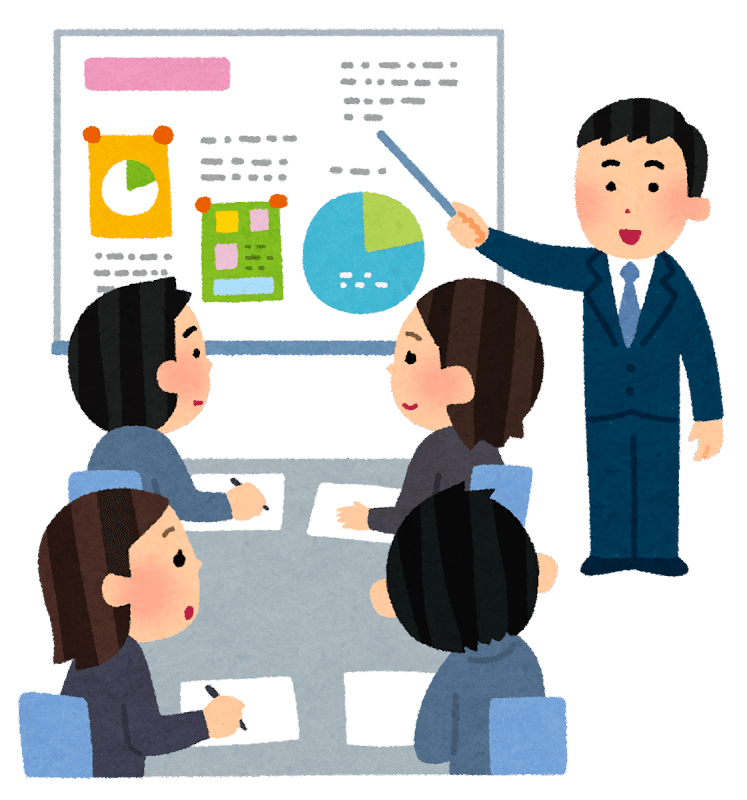
航空業界飛行機の安全に関しては非常に厳格な規則があります。何らかの問題が発生した場合、ブラックボックス(飛行機の各計器類の情報やパイロットと管制塔との通信履歴などを保存して、丈夫な箱に入れて飛行機がバラバラになっても回収できる様にしたもの。)のデータを元に原因を解明します。この業界では、問題を解決することが最優先され、個々の責任を問うものではありません。
医療業界も患者の安全は最優先で、厳格な体制を引いている業界です。その進化は病院に行く度に驚きます。
問題が発生した場合、医療関係者に対する責任の追及がしばしば行われます。司法制度では、一度の判決がその後の事例にも影響を与えるため、柔軟な対応が難しい。
問題が発生した場合、個々の責任の追及が中心となり、システムや制度自体の問題は二の次にされがちです。政治では公共の利益を最優先にするべきですが、現実には利権や党派、意見の不一致が影響を与えることが多い。失敗やスキャンダルが発生した場合、その責任の所在は不明瞭で、しばしば個々の政治家や政党に責任が帰せられます。
学校・教育業界では、生徒や教員の安全と教育の質が重視されます。しかし、問題が発生した際には、教員や学校経営者に対する責任追及が一般的です。教育システム自体の問題に目を向けることは少なく、個々の事例に焦点が当てられがちです。
航空業界の優れた文化

航空業界では、失敗に対する「報告、公開、共有」の文化が根付いています。
このように問題に対処することで、
他の同業者も学び、業界全体が成長する仕組みが形成されています。
公表を促進めるための仕組みもあります。
パイロットがブラックボックスの中身で裁判が不利にならないように、ブラックボックスの内容は裁判で証拠として使用できない様なルールもあるようです。
結果として、事故再発防止が徹底的に行われています。
個で解決できる問題には限りがある。それは個人であれ、企業であれ限界がある。
業界全体で問題を捉える事は大きな知恵と力を生んでいると言う事がわかりました。
自分達の組織はどうか?

これらを比較して、自分たちの組織やチームはどうか考えてみましょう。
失敗を報告した際、上司や仲間は「報告ありがとう」と言える文化でしょうか。
それを公開する事に当事者が前向きにら考えられる文化や風土はあるでしょうか?
責任の追及がキツくなりがちな事はありませんか?
考察
失敗に対してどのように対処するかが、組織の成長や個々の成長にも影響する。
「人を責めずに仕組みを責めよ」という考え方の真意に納得していただけたでしょうか?
まとめ

「人を責めずに仕組みを責めよ」という言葉は単なるスローガンではなく、組織を高めるための実践的な指針でしたね。
それを理解し、具体的な行動に移すことで、より強く、より賢い組織を作り上げることができるのではないでしょうか?
しかし、これはトップダウンだけではなく、ボトムアップもしていかないとなかなか浸透していきません。
職場のみんなが、この言葉を理解して腹落ちしていけば、仕組みを責めることができます。
少しでも、この考え方が浸透していけたら幸いです。身近な人に教えてあげて下さい。
皆様の組織で、少しでもこの記事がお役に立てることを願っています。
この記事がお役に立ちましたら、スキとフォローをお願いいたします。
コメント等もいただけると励みになります。
最後までお読みいただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
