
釣りで解説。モチベーションが生まれる仕組み。
はじめに
今回の記事では、仕事におけるモチベーションと、趣味である釣りにおけるモチベーションに焦点を当てて考察します。特に、「内的動機づけ」と「衛生要因」という心理学的な要素を通じて、モチベーションを深堀りしていきたいと思います。
動機付けとは?
いきなりややこしそうな言葉から始まりましたが、内容はシンプルですのでご安心ください。
まず、動機とは行動するきっかけです。犯行の動機は犯行をするきっかけですよね。
ハーズバーグの二要因理論

内的動機づけは、個人が自分自身から発する動機づけです。達成感や成長、承認などが該当します。これらの要素は、働く上で非常に強い動力になります。
一方で、「衛生要因」は、外部からの刺激や条件によって生じる動機づけです。具体的には、給与、職場環境、人間関係、などがあります。
内的動機づけ:その具体例
仕事の場合、プロジェクトを成功に導いたり、成長している実感を得ることなどが「内的動機づけ」に当たります。これがあれば、多少の困難やストレスがあっても、乗り越えていく力が湧いてきます。
釣りにも同様の要素があります。例えば、大物を釣り上げた達成感、技術の向上による成長感、自分の考えや読みが当たった有効感。これらがあれば、長時間の待機や、当たりがない状況でも、楽しいと感じることができます。
衛生要因:持続性の問題
衛生要因は、当初はモチベーションを高める効果がありますが、その効果は一時的です。例えば、給与が上がれば当初は嬉しいですが、次第にその新しい給与に慣れてしまい、モチベーションは元に戻ります。衛生要因は常に向上していかないと動機付けにはならないと言う事です。
動機付けをすると言うよりは、一時的に不満を減らすといったほうが近いと思います。
釣りでも同様の事象が見られます。新しい釣り具を手に入れた時の喜びや、特別な場所で釣りをする興奮は一時的。何回か釣行すれば、その感覚は当たり前になって喜びは薄れていきます。
結論:内的動機づけの重要性と衛生要因の適切な管理
最も重要なのは、内的動機づけを生む要素を理解し、それを育む環境を作ることです。そして、衛生要因は一時的な喜びを提供するものであり、それだけでは持続的なモチベーションを保つことはできません。
もし、評価制度がうまく連動していれば、衛生要因も自然と満たされる場合があります。衛生要因も大切ですが、それだけに依存するのは危険です。福利厚生の充実は素晴らしいが、それだけで社員のモチベーションを維持することは難しい、というのが結論です。
モチベーションのサイクル:釣りと仕事のモチベーション
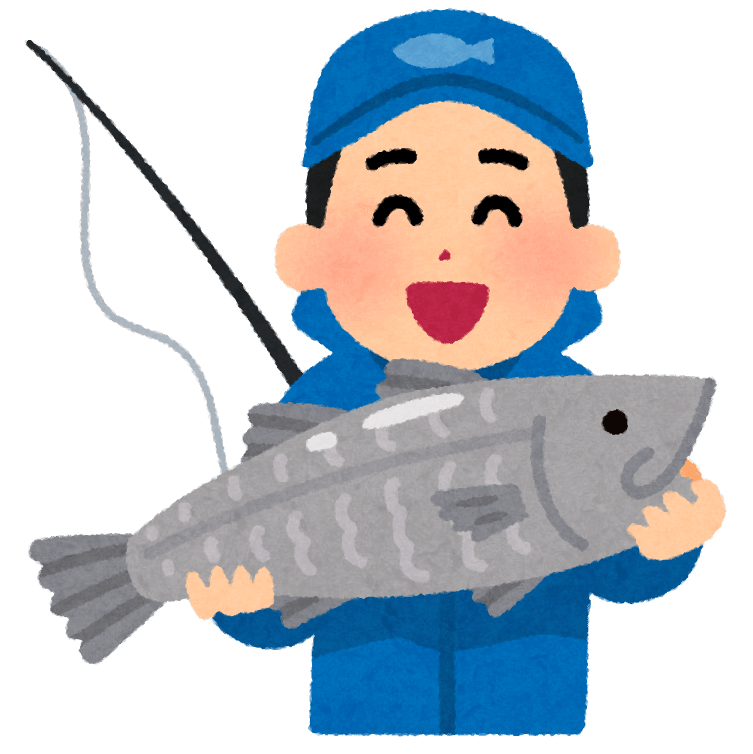
釣りでは、成功体験とその過程で得られる多様な感情がうまく循環していると、人はその活動に繰り返し挑戦したくなります。大きな魚を釣る達成感、釣り方を変えて反応がよくなった時の有効感、周りに認められる承認感、そして成長感。これら全てがモチベーションを高め、活動そのものに意義を見い出させます。
また、この維持において、アドレナリンの役割は大きいです。未確定要素、つまり「次に何が来るかわからない」という不確実性が、人間の脳に興奮をもたらす。これがアドレナリンを生み、人はその活動に没頭する。
キャストする前からおいしそうなポイントがあれば釣れるかもしれないとドキドキしますね。
アタリがあれば、フッキングが決まるかドキドキしますね。
バレないか、もしかしたらデカいかも?
こう言った要素がより動機付けになります。
だから、釣り好きは炎天下でも、真冬でも、早朝から釣りにいけるのです。
仕事におけるモチベーションの仕組み
仕事においても、このようなモチベーションのサイクルを作ることが可能です。成功体験や成長感は、タスクの達成やプロジェクトの成功、更なるスキルの習得といった具体的な結果に結びつく。そして、それが評価され、報酬やプロモーション、承認といった形で返ってくる。このようにして、達成感、成長感、有効感、承認感、関係性といった多様な内的報酬が、仕事におけるモチベーションを形成していきます。
そして、未確定要素による興奮も仕事には存在する。新しいプロジェクト、未知のスキル、競争相手との戦い。これらがアドレナリンを引き起こし、モチベーションを一層高めます。
釣りも内発的な動機がなければ“地獄のような作業”

釣りでも仕事でも、達成感や有効感、承認感などが無い場合、その活動は極めて退屈で、一種の「地獄のような作業」となり得ます。
考えてみてください。釣りでそれらの要素が欠けた場合、何が残るでしょうか?
ただ糸を垂らして魚がかかるのを待つだけ。何時間もただ待ち続け、釣れたら回収。暑い日も寒い日も毎日早朝から出勤。
このような単調な作業は、長時間続ければ続けるほど、人の心をむしばんでいくでしょう。
仕事においても同様です。成果が出ない、成長感が無い、承認されない、有効感が感じられない。これらが欠けた状態で仕事を続けるのは、まさに「地獄のような作業」と言えるでしょう。単純作業が繰り返されるだけで、自分自身がその仕事で何を得ているのか、どのように成長しているのかが感じられない場合、やがてその作業は人を疲弊させ、モチベーションは底をつきます。
どの様にモチベーションを高めるか
では、どのようにモチベーションを高めたら良いでしょうか。

モチベーションは動機の強さ、達成の理由付け
暑い日でも、寒い日でも、雨が降っていても釣りに行くのは目的があるからです。目標があるからです。達成したい理由が明確だからです。
皆さんの職場では、仕事に目標はたてられていますか?達成しなければいけない理由がちゃんと明確に伝わっていますか?
この仕事はなぜやらなければいけない?
この作業をなぜ期日までに終わらせなければいけないのか?
疑問の答えが、仕事だからと思ってしまったら危険信号です。
仕事だからやらなければいけない。これは目的が不明確すぎますね。もっとお客さんに喜んでもらえる、みんなの力になる、自分の成長につながる。こうやって明確な理由があれば、人はどんな行動でもしていくものです。
仕事だからやらなければいけない。そう思っていたら、トラブルや何かしらの障壁が発生したときに、心が折れてしまいますね。
職場のみんなで仕事の理由を話し合おう。
職場のみんながなかなか仕事と向き合ってくれない。モチベーションが低いと思ったら、仕事の目的や理由を職場のみんなで話し合ってみてはいかがでしょうか?
仕事だからではない、別の理由を考えてみましょう。
最後に
この記事を最後までお読みいただきありがとうございます。皆さんの職場が少しでも活気が高まっていただけたら幸いです。
今後はなるべく対策までしっかりお伝えできるようにします。私も人を管理する上でいろいろ悩んだ時期がありました。私の体験から、1人でも同じ悩みを持つ人たちを減らす事が私の目標です。
この記事がお役に立ちましたらスキ、フォローお願いいたします。最後までお読みいただきありがとうございました。
また、次の記事でお会いしましょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
