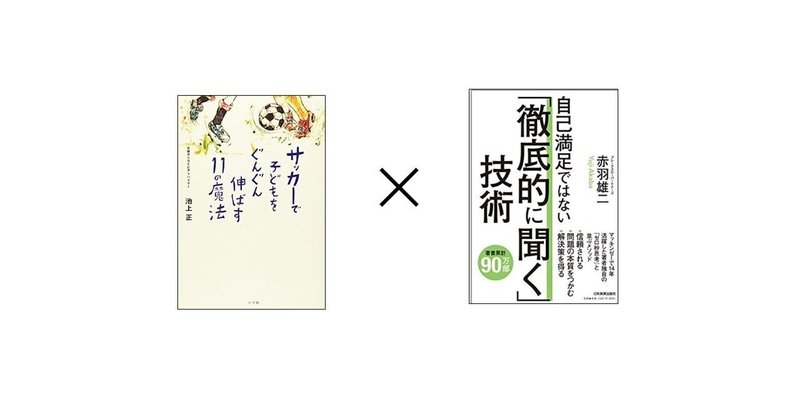
習い始めたばかりのサッカーで「うまい!」とコーチに声をかけられたら、どうする?
赤羽雄二さん『自己満足でない徹底的に聞く技術』で書かれている
アクティブリスニングを実践中の畑中です。
小3次男が、「他人の目から、どうやって見ているのかが『見える目』が欲しいんだよね」と言い出すので、不思議に思って聞き続けていると、「勉強のできる子が、どうやって見ているかが、知りたい」という話の展開に驚いた今日この頃。
そんな小3次男が、6月にサッカーチームに入団しました。
練習に付き添った夫から、コーチと1対1で練習する写真とともに、「『うまい!』と言われている」とショートメールが届きました。
こんなとき、あなたは、どんな反応をしますか?
アクティブリスニングを知る前の私なら、
嬉しくなって、「うまいって!言われたんだって〜。きっと、どんどん練習したらもっと上手くなれそうだね」なんて言葉を、良かれと思って、子どもにかけていたことでしょう。
でも今は、アクティブリスニングと出会い、一見、やる気にさせそうなこんな言葉かけも、どんどん練習して上手くなってほしい!という親の思いがのった、「練習しないと、上手くなれないよ」っというメッセージにもなると感じるようになりました。
なので、こんなときは、放って見守る!の一択。
子どもは、
コーチにかけられた「うまい!」の一言で、
嬉しくなり、
楽しくなり、
もっと上手くなりたいって、
自然と思うようになります。
そんな子どもに、親の思いを語って聞かせる必要はありません。
嬉しくなり、楽しくなり、
もっと上手くなりたいって思う。
そんなときに、子どものそばでアクティブリスニングを徹底していれば、子どもは自然と嬉しい、悔しい、上手にできた、失敗しちゃった、もっと上手くなりたい、疲れ果てた、もう辞めたいなど、いろんな思いを話し出します。その話を、「そうなんだね」と、何の教育的意図や何の期待もせずに話を聞いていれば、子どもは安心して、前に進んでいきます。
こんな気づきを、赤羽雄二さんのオンラインサロンでつぶやいたら、サロンメンバーの一人が、『サッカーで子どもをぐんぐん伸ばす11の魔法』(著:池上正)を紹介してくれました。
今回は、この書籍を読んでの学びや気づきをシェアします。
この本は、こんな一節で始まります。
私は絶対に子どもを怒ったり叱ったりしません。
私も、こんな風に公言できるようになりたい!
アクティブリスニングを実践するようになり、だいぶ怒ることは減りましたが、こんな風には言い切れません。
少し話はそれますが、赤羽雄二さんのオンラインサロン内で、「子どもの話をアクティブリスニングできるようになるために、日々のトレーニングですね」とコメントしたママさんに、赤羽雄二さんが「日々のトレーニングではなく、抜本的な意識改革です」と返信されていたのを思い出しました。
「怒る」・「話を聞けない」には、つい自分が反応してしまうという共通点があります。だんだんと行動を変化させるよりも、子どもに対する自分のあり方が抜本的に変われば、根っこからこういった不適切な行動をなくせそうです。
この場を使って、自分へ外圧をかけるために、
「私は絶対に子どもを怒ったり叱ったりしません」の行動宣言をしておきます。
怒って指導する
「つい怒ってしまう」人以上に困ってしまうのは、「子どもを怒って指導するのは当然」と考えている方々です。
そういう方は、無意識のうちに自分の「部活体験」を参考にして指導されているのはないでしょうか。
時代は変化しています。コーチも子どもも一緒に日々成長し、子どもが伸びしろがあるように大人もそれを持たなければ、子どもにとってマイナスのコーチでしかない、子どもをつぶしてしまう大人になってしまう。
この書籍には、怒るコーチ、怒る母親のエピソードを織り交ぜながら、怒らずに、問いかけ、考えることで、自らの力で判断できる「あと伸びする子」のエピソードが、たくさん紹介されています。
「右へパス!」「そこでシュートだ!」試合中、子どもを煽っていませんか?
こんな声かけは、指導・指示ではなく、「煽り」になるのですね。
子どもへの期待
子どもより先に自分の望みを語っていませんか?
親の期待を伝え過ぎて、つぶれてしまうケースが少なくないそうです。本当に頑張れる子というのは、失敗することが怖くない子だそうです。
親が過度な期待を抱いている親は、自分が隠しているつもりでも、必ず子どもに伝わり、「お父さん(お母さん)は結果を気にしている」と感じ、子どもは失敗を恐れてトライしなくなってしまうそうです。
サッカーを通した子どもへの関わりも、アクティブリスニングをしておけば、大丈夫そう!
サッカーが楽しいという気持ちを育てる
本を読み終わり、「楽しむのが一番」とばかりに、「一緒にサッカーやりに行こー!」と小3次男を誘ってみました。
公園までの道中、並んで歩きながら、
「サッカーは、楽しければ良いらしいよ?」と言うと、
「でも、色々考えちゃんうんだよ。だってパスってさ・・・」と、彼が考えていることを話し出します。
なんだか、私の考えたこともないことを話している次男を見ながら、
「楽しめば良い」なんて言われなくても、楽しいから、毎日、学校から帰ってきたら、サッカーボールをもって公園に行き、友だちとサッカーをしていることに気づきます。
公園に着き、サッカーボールを一緒に蹴りはじめ、「ボールを見て蹴るんじゃなくて、前を見て蹴るんでしょ?」と本で学んだことを伝えると、小3次男から「そうだよ!」と軽い返事がきます。
「いやいや、どうやってボールを見ないで蹴れるのさ?」と空振りしそうになりながら、上手に前を見ながらボールを蹴っている息子のマネをして、蹴ってみます。
私:「おー!できた。できた!」
小3次男:「お!いいね!」
なんか、楽しい。この感覚が大切なのね。
あれ?サッカーの楽しさを教えてもらってる??
「サッカーは、楽しければいいらしいよ?」なんて、よくも、上から目線で言ったもんだと、自分にツッコミを入れながら、一緒に、サッカーボールを蹴って楽しい時間を過ごしました。これは、日課にしたいです。
次男の習いごと
今回、サッカーチームへ入団するために、小3次男は自ら、友だちに体験できる時間や場所を聞いてきて、「体験に行きたいから、一緒に来てほしい」と私に頼んできました。
頼まれたので同伴し、彼は、2時間の体験をしたあとに、その場で、入団すると決めていました。
そんな次男は、過去に2つ習いごとを辞めています。どちらの習いごとも、アクティブリスニングを実践しはじめる前の私が、3歳上の長男が楽しく続けてるし、弟にも習わせておこう!と、上手いこと口車にのせて、通うことになった習いごとです。
そんな流れではじめた習いごとは、だんだんと連れて行くのにも苦労するようになり、結局、辞めました。そんな失敗やアクティブリスニングとの出会いもあり、次の習いごとは、次男が「やりたい」と言い出すまで放っておき、アクティブリスニングをし続けようと心に決めた結果、今に至ります。
入団したサッカーチームの練習は、土日です。
学校がお休みなのに、朝8時からの練習に行くために、自ら、前日に荷物を準備し、登校するよりも早い時間に、さっさと家を出て行きます。
でも、土日ともいくわけではなく、基本は日曜日に行くんだそう。「せっかくだから、土曜日も行ったら?」とは言いません。彼がどうするかは、アクティブリスニングして、見守るだけです。
親が前のめりにはじめさせた習いごとに連れて行かれ、「なんで、習いごとに連れてきてあげているのにやらないの!」と怒っていたけど、やらないのは、私がやらせようとしていたからです。
怒っても、変わるわけもありません。
でも、アクティブリスニングをしていると、こんな変化があるのです。
苦しくつらい子育てから抜け出し、家庭を安全基地にしたい方へ、情報を更新しています。
よろしければ、フォローしていただけると嬉しいです。他の投稿も参考にしてみてください。
↓↓↓Twitterのフォローもよろしくお願いします↓↓↓
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
