
第11回「信玄との密約」(予習)
永禄3年(1560年)5月19日 「桶狭間の戦い」(岡崎城へ帰還)
永禄4年(1561年)4月11日 「牛久保城攻め」(今川氏から独立)
永禄5年(1562年)1月15日 「清須同盟」(織田信長と和睦)
永禄5年(1562年)2月4日 「上ノ郷城攻め」(人質交換)
永禄6年(1563年)7月6日 「元康」から「家康」に改名
永禄6年(1563年)10月 「三河一向一揆」勃発
永禄7年(1564年)2月28日 「三河一向一揆」終結
永禄7年(1564年)4月8日 飯尾連竜、松平家康と対面
永禄8年(1565年)11月11日 二女・督姫(母:西郡局)誕生(旧説)
永禄8年(1565年)12月20日 今川氏真、飯尾連竜を誅殺。
永禄9年(1566年)5月 松平家康、三河国を平定。
永禄9年(1566年)12月29日「松平」から「徳川」に改姓。「三河守」に。
永禄11年(1568年)12月6日 武田信玄、駿河国へ侵攻開始
永禄11年(1568年)12月13日 武田信玄、駿府を制圧
永禄11年(1568年)12月13日 徳川家康、遠江国へ侵攻開始
永禄11年(1568年)12月18日 徳川家康、引間城を落とす。
1.武田信玄と徳川家康の今川領への同時侵攻
永禄11年(1568年)12月6日、武田信玄が駿河国への侵攻を開始すると、12月13日、徳川家康も遠江国へ侵攻を開始した。同時侵攻の密約があったのであろう。この密約の仲介者は、織田信長で、武田方の窓口は穴山信君で、徳川方の窓口は酒井忠次だったという。
■武田信玄の第1次駿河国侵攻ルート
・薩埵峠→江尻城→上原→府中(駿府今川館)→久能山(久能城)
今川氏真は、武田信玄の侵攻を薩埵峠で食い止める予定で、清見寺に本陣を置いたが、調略されていた瀬名氏、庵原氏、葛山氏ら21武将が陣払いをしたので、戦わずして負けた。

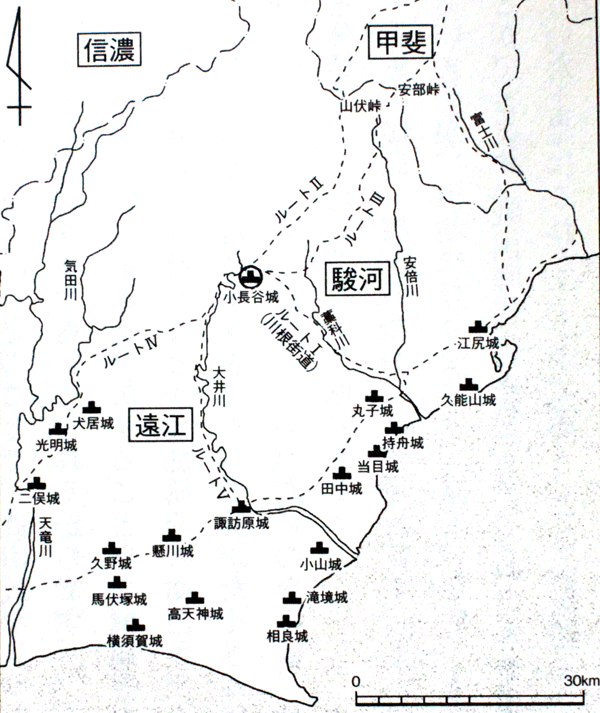
今川氏真は、駿府今川館を捨て、建穂寺(式内・建穂神社)で指示をした後、藁科(わらしな)川を遡り(「川根街道」。通称「今川街道」)、山村に潜んでいたが、掛川城主の誘いで掛川城に逃げ込んだ。
氏真、安部川を過ぐる迄、従者二千余。
土岐の山家に至る時は、纔(わずかに)百騎に足らず。
武田信玄は、12月13日、駿府今川館の鬼門の守り・龍雲寺を焼き払い、寿桂尼の墓を破壊してから駿府今川館に入って焼いた。この時、国宝級の品々が灰になったという。愛宕山城や八幡城も落とされ、「小京都」と呼ばれた美しい駿府の町は焼失した。
この後、武田信玄は、久能山に入り、久能寺(現・鉄舟寺)を山麓に移して久能城(現・久能山東照宮)に改修したとされるが、既に「花倉の乱」の時には福島氏の久能城があった。
※久能寺:有度浜の天女踊りを伝える寺。なお、戯曲化に際し、天女は「三保の松原」に舞い降りたことに変更された。
■徳川家康の遠江国侵攻ルート
・甚三(後の陣座)峠→井伊谷→瀬戸→祝田→見付→橋羽→普済寺→引馬城
徳川家康は、「井伊谷七人衆」のうちの(後に「井伊谷三人衆」と呼ばれることになる)3人の道案内で、井伊谷を通って侵攻し、橋羽街道を南下して東海道に入ると、天竜川を渡って国府所在地・見付に達した。
橋羽(はしわ。橋端。『科註拾塵抄』「奥書」では「蒲郷端和」)妙恩寺に戻って引間城の開城交渉を行ったが(『科註拾塵抄』「奥書」)、拒否されたので、普済寺に本陣を置いて引間城(「引馬」「曳馬」「匹馬」とも書くが、浜松市では地名は「曳馬」、城名は「引間」で統一)を攻めた。この時、築山殿は、普済寺の末寺・西来院に入った(『西来院廟堂記』)。
★『科註拾塵抄』(日蓮宗本山・身延山久遠寺の身延文庫):妙恩寺(静岡県浜松市東区天龍川町。開基は日蓮上人の叔父で、蒲荘を支配していた金原法橋左近将監)で、日詮『科註拾塵抄』を永禄13年(1570年)2月7日に(妙恩寺11代住職・常住院日豪上人(武田家家臣・馬場美濃守の末子)が?)写した。この本の「奥書」は、(日豪上人によって?)史実が書かれた貴重な同時代史料だという。
多くの寺へ取材に行ったが、ご住職の性格は、超良いか、超悪い(変人)かで、中間層が少ないように感じている。妙恩寺のご住職は郷土史家でもある超良い方で、質問したらホワイトボードを取り出して説明され始めたのには驚いた! 話し慣れておられるようで、説明が分かりやすかった。
さらに徳川家康は、永禄11年12月27日、引間城から不入斗に移り、「掛川城攻め」のための砦を築いた。砦の数については、『科註拾塵抄』「奥書」には3ヶ所とあるが、実際は13ヶ所とされる。北に龍穴峰砦(八幡山砦)、東に笠町砦(二藤砦)、南に杉谷城、青田山砦(陣場峠)、さらには、高天神城攻めでも使われた小笠山砦などが築かれた。そして、徳川家康は、永禄12年2月、不入斗から龍尾山砦(天王山砦。式内・真草神社の論社・龍尾神社)に本陣を移した。(「掛川城攻め」の詳細は次回。)
※不入斗:普通は「いりやまず」「いりやまぜ」と読む。関東地方に多い地名であるが、東海地方にもある。「貢租を納めるまでに至らない不毛の地にある小さな集落」の意で、正しい表記は「不入計」(年貢の計算に入れない土地)だという。(『新編相模国風土記稿』には「不入の地にして、往古国守を置れし頃、其の貢租を免除せられし義なり」とある。)
徳川家康が本陣を置いた「不入斗」について、『浜松御在城記』に「入山瀬」、『甲陽軍艦』に「いり山瀬」とあることから、静岡県掛川市入山瀬(いりやませ)だと考えられてきたが、現在は静岡県袋井市国本の不入斗(ふにゅうと)であると考えられている。式内・郡辺神社の論社である遠江三宮・冨士浅間宮の神領であったので、免税されて「不入斗」と呼ばれたという。徳川家康の本陣は、この冨士浅間宮であろう。この冨士浅間宮は、後に武田信玄によって焼かれたが、天正18年(1590年)、地頭・本間源三郎が現在地(静岡県袋井市国本)に再建した。檜皮葺きの本殿は、国の重要文化財に指定されている。


【大意】永禄6年以降、引間城主・飯尾連竜などが今川氏真に叛き、「遠州錯乱」が起きたが、永禄9年12月20日に、飯尾連竜を含む逆臣116人を駿府に呼んで討ったので、遠江国の騒動は沈静化した。
永禄11年12月13日、武田信玄は、駿河国へ侵攻し、駿府を焼いたので、今川氏真は、掛川城へと逃げ込んだ。この時、徳川家康は、12月17日に妙恩寺に本陣を置き、遠江国の国衆の調略を行うと、まずは馬伏塚城主が12月21日に従属し、他の国衆も次々と従属したが、掛川城主と宇津山城主だけは従属しなかった。そこで徳川家康は、本陣を不入斗に移し、掛川城に向けて3ヶ所に砦を築くと、翌年の2月、龍尾山砦(「掛川城攻め」の本陣)に入った。
2.徳川家康の「引間城攻め」(『改正三河後風土記』)
今川氏真は永禄6年(1563年)、1万人の軍勢を率いて出陣し、東三河の牛久保城(愛知県豊川市牛久保町)に陣取り、5000人の兵で一宮砦を攻めた。この時、神君・徳川家康公は、僅か2000の兵で出撃し、危機を救った。これを「一宮の退口」「神君一宮後詰」といい、「神君大高城兵糧入れ」と共に、「徳川家康二大武勇談」として語り継がれている。(この後の「佐脇城(愛知県豊川市御津町下佐脇郷中)&八幡砦(愛知県豊川市八幡町東赤土)の戦い」では、徳川家康は、「妻の実家の関口家の墓には触れるな」と命じたので、関口家の墓は現存している。)
この時、引間城主・飯尾致実(連竜)は、既に徳川家康と内通していたので、「体調不良。引間城へ帰る」と言い、新居や白須賀の今川軍の陣に放火しながら帰城すると、今川氏真は、駿府に戻り、「すぐに飯尾致実(連竜)を捕らえて、放火の件を問い質せ」と言って小林砦(静岡県浜松市浜北区小林)を築いて井伊谷にいた新野右馬助親矩(「左馬助」の誤り)を大将に、兵3000人を入れた。ある日、引間城の東の引間橋で戦いが3度行われたが、3回目に大将・新野親矩は鉄砲で撃たれて(一説に矢で射られて)亡くなった。この日を『武徳大成記』では永禄5年4月とする(「神君一宮後詰」には永禄5年説がある)が、新野親矩の命日は永禄7年9月15日である。
今川軍が敗れて、今川氏真は益々怒り、すぐに朝比奈泰能、瀬名親隆、瀬名氏範、朝比奈秀盛等を送ったが、引間城は落ちなかった。この時、飯尾致実(連竜)は、「誰かの讒言により、徳川家康に内通しているとか、今川軍の陣に放火したとされているが、無実である」と書いた起請文を矢に結び付けて射た。この起請文を駿府の今川氏真に見せると、今川氏真は、兵を呼び戻して飯尾致実(連竜)を赦免した。喜んだ飯尾致実(連竜)が駿府へお礼を言いに行くと、今川氏真は、飯尾致実(連竜)を誅殺した。

飯尾致実(連竜)の正室・於田鶴は、飯尾致実(連竜)の死後、「女城主」(『どうする家康』では「女主(おんなあるじ)」)として君臨し、遠江一宮の式内・小國神社(静岡県周智郡森町一宮)がある森町の真田城(静岡県周智郡森町一宮)の城主・武藤刑部丞氏定を通して武田信玄と内通していた。徳川家康は、このことを聞き、徳川方に内通していた飯尾家の家老・江間兄弟へ、松下常慶と後藤太郎左衛門を使者として遣り、「引間城を明け渡せば、飯尾致実(連竜)の妻子の面倒はみるし、家臣は全員召し抱える」と告げたので、江間兄弟はこの破格の厚遇を喜び、於田鶴を説得したが、於田鶴は承知しなかったので、徳川家康は、酒井忠次と石川数正に引間城を攻めさせたが、初日は敗北した。翌日、外郭に入ることに成功すると、於田鶴は、緋縅(ひおどし)の鎧に同じ毛の兜を被り、薙刀を手に持ってうって出た。侍女等も7~8人(一説に18人)、同じ格好でうって出た。同時に城兵も50~60人うって出て、全員討死した。そして、
・於田鶴は「其の志操の節烈は、丈夫にも勝りたり」と賞賛された。
・引間城には酒井忠次が入った。
・家老の江間兄弟には、「初めから内通していた」として飯尾領が与えられた。(この本『改正三河後風土記』の原書『三河後風土記』に、「飯尾致実(連竜)が病死すると、今川氏真は、飯尾致実(連竜)の子・義広に家督を継がせた」とあるのは誤りである。)
①平岩親吉『三河後風土記』(全45巻)
②成島司直『改正三河後風土記』(全43巻):①の誤りを修正した本
③沢田源内『三河後風土記正説大全』(全50巻):①②を基にした偽書
今川氏真は去年、三州発向。佐脇、八幡に在陣せし時、飯尾豊前守致実が徳川殿へ内通し、病(やまひ)と称し、「居城・遠州引間へ引き返す」とて其の道すがら、新井、平須賀辺の駅舎に放火して帰りし事を大いに憤り、氏真、駿州へ帰府の後、「早速に引間を故致実を生け捕りて、其の虚実を鞠問せん」とて、新野右馬助親矩、其の弟・式部少輔之規を大将とし、三千余人を差し添へ、引間の城へさし向け、短兵急に攻めさせしに、豊前守さる古兵(つはもの)なれば、少しも恐れず、矢、炮を飛ばし、防戦す。寄手の大将・新野右馬助、鉄炮にあたりて、うたれ死す。(『大成記』、「引間城攻め」を永禄五年四月とす。誤れり。)依て、散々に敗れ、駿州へ迯(に)げ帰れば、氏真、益(ますます)怒りかさねて、朝比奈備中守泰能、瀬名陸奥守親隆、其の子・中務大輔氏範、朝比奈兵太夫秀盛等に大勢を差し添へ、攻めかこみ、昼夜を分かたず攻しかども、致実、防戦の術を尽くし、寄手の手負ひ、死人ばかりにて、城落つべしとも見へず。其の時、致実、矢文を射出し、「其の讒者の為に無実の罪を蒙り、遺恨せん方なし。一時の急難をのぞかんが為、防戦するといへども、全く異心を抱くにあらず。早く讒者の虚実を糺明有て、恩免を蒙らば、弥々(いよいよ)二心なく忠勤すべし」としたため、起請文に添へて贈りければ、討手の輩、是を駿府に贈り、氏真に見せしむ。氏真、爰に於いて、討手の輩、呼び返へし、致実が罪を免(ゆる)し、此の後は懇意に恩義を施しければ、致実も忝くや思ひけん、礼謝の為に駿府へ来りけるを、氏真、謀をめぐらし、壮士を伏せ置き、不慮に殺害せり。
致実が妻、女ながらも、けなげなる性質にて、夫の横死を憤り、城兵を指揮し、堅固に篭城し、小国の武藤刑部丞をたのみ、甲州の武田へ内通す。神君、此の由、聞こし召し、飯尾が家臣・江間安芸、同・加賀両人へ御内意有りて、松下覚右衛門、後藤太郎左衛門を御使ひとせられ、「徳川家へ其の城を渡すに於いては、飯尾が幼子、寡婦を御懇ろに御養育ありて、其の家人等、悉く召し抱へられ御扶助有るべし」と仰せければ、依て安芸、加賀両人、其の旨を以て飯尾が妻を種々と諌め諭しけれども、彼の妻、さらに承引せず、爰に於いて、引間の城を乗っ取るとて、酒井左衛門尉、石川伯耆守両将を差し向けらる。然に彼の妻は防戦の指揮を為し、城兵、屡々(しばしば)突き出て烈(はげ)しく戦へば、寄手、大いに敗走せり。其の翌日は、酒井、石川、又攻め寄せて烈しく攻め立て、遂に外郭に乗り込めば、飯尾が妻は、緋縅の鎧に同じ毛の兜を着、長刀をふるって敵中に切って入る。侍女、婢、七、八人、同じ粧(よそおひ)出で立ちて、城兵五、六十人と同じく勇戦し、男女一人も残らず討死す。彼の妻、死、去就の是非は、論ずるに足らざれども、「其の志操の節烈は、丈夫にもまさりたり」と感ぜぬ者なし。扨(さて)、酒井、石川の両将、城を乗っ取れば、左衛門尉に此の城を守らしめさる。江間安芸、加賀の両人は、「最初より御内意を蒙りし者なれば」とて、飯尾が所領は悉く此の両人へ下されける。(原書、「飯尾、病死し、氏真より、其の幼子に家督を継がせし」とあるは誤り也。「引間城攻め」の事は、基業による。)
https://dl.ndl.go.jp/pid/993836/1/208
★今後の『どうする家康』
・第11回「信玄との密約」
・第12回「氏真」
・第13回「家康、都へゆく」
・第14回「金ヶ崎でどうする!」
・第15回「姉川でどうする!」
・第16回「信玄を怒らせるな」
・第17回「三方ヶ原合戦」
・第18回「真・三方ヶ原合戦」
・第19回「お手付きしてどうする!」
・第20回「岡崎クーデター」
・第21回「長篠を救え!」
・第22回「設楽原の戦い」
・第23回「瀬名、覚醒」
・第24回「築山へ集え!」
ノベライズ どうする家康 二 発売しました
— 木俣冬@「どうする家康 ノベライズ」「ネットと朝ドラ」発売中 (@kamitonami) March 17, 2023
起承転結のまさに「承」。動き出します、意外性の作家・古沢良太さんの筆が乗ってきています
表紙の花がきれい
ちょうど本文も花の名前を意識的に出すようにしたのでうれしい 内容とは直接関係ないですが花を思い浮かべながら読んでみてほしいです pic.twitter.com/SJbBg2sf3x
※ノベライズ3巻は6月、4巻は9月発行予定です。
記事は日本史関連記事や闘病日記。掲示板は写真中心のメンバーシップを設置しています。家族になって支えて欲しいな。
