
2022年NHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』(第19回)「果たせぬ凱旋」
源義経「私は決めた。この先、法皇様第一にお仕えする。京の都で、源氏の名に恥じぬように生きる。私は検非違使尉、源九郎判官義経だ」
源義経を見てると、韓ドラ『善徳(ソンドク)女王』の毗曇(ピダム。新羅第27代善徳女王(在位632-647)の政権末期に突如として登場した真骨と推定される貴族)を思い出します。
史実の毗曇の誕生年や親、出生、業績などの記録はほとんど無いのですが、『善徳女王』の毗曇は、とにかく強いけど、親の愛を知らず、純真で、側近の話を信じてしまう人物として描かれ、史実でも、ドラマでも、善徳女王から新羅の最高官職である上大等の地位に任命されるも、647年に「毗曇の乱」を起こして誅殺されています。
『鎌倉殿の13人』の源義経も、毗曇のようにとにかく強いけど、親の愛を知らず、純真で、「日本一の大天狗」こと後白河法皇に操られ、殺された人物って感じですね。
大事なのは信じ通すことです。
毗曇と善徳女王は愛し合っていたのですが・・・毗曇が襲われ、刺客が「善徳女王に頼まれた」と嘘の自白をしたので、泣き喚き、善徳女王の愛が信じられなくなった毗曇は「毗曇の乱」をおこしました。
源義経と源頼朝は兄弟愛で結ばれていたのですが・・・源義経が襲われ、刺客・土佐坊昌俊が「源頼朝に頼まれた」と自白をしたので、源義経は源頼朝を討つことにしました。(『鎌倉殿の13人』の源義経は、土佐坊昌俊を郷御前が雇ったことを知らず、それを知っている源行家に「源頼朝が雇った刺客だ」と教えられて泣き喚き、源頼朝の愛が信じられなくなった源義経は、挙兵したとしています。)
なお、毗曇とは、毘曇(びどん。阿毘達磨、阿鼻達磨)のことで、源義経の幼名「遮那王」の「遮那」は、「毘盧遮那仏」(びるしゃなぶつ。大日如来)の略です。
※以下は高校日本史の復習(山川出版社『詳説 日本史図録』)による。
1.高校日本史の復習(1)鎌倉殿

源頼朝の立場は、鎌倉を拠点とする源氏の嫡流としての存在=鎌倉殿であった。これは公的な地位ではなく、東国武士団が棟梁として、頼朝に求めた資質に裏づけられた立場である。その資質とは、東国に確立した軍事的で実質的な支配権を、朝廷に公的に認めさせる政治交渉力と、所領訴訟にあたって公平な裁定を下す調停力であった。
武士の階級構造は「鎌倉殿<御家人」とされるが、実際は「鎌倉殿<門葉(○○守を受領した源氏一門)<准門葉(北条氏など)<御家人」である。
2.高校日本史の復習(2)守護・地頭設置の背景
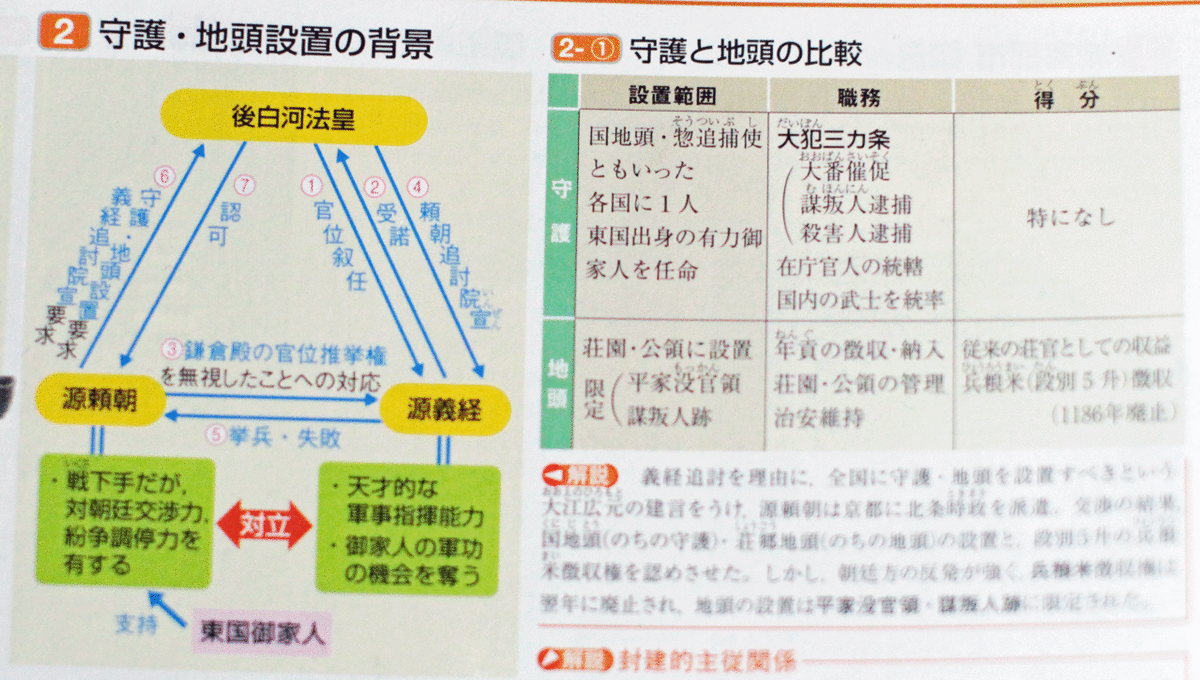
義経追討を理由に、全国に守護・地頭を設置すべきという大江広元の建言をうけ、源頼朝は京都に北条時政を派遣。交渉の結果、国地頭(のちの守護)・荘郷地頭(のちの地頭)の設置と、段別5升の兵粮米徴収権を認めさせた。しかし、朝廷方の反発が強く、兵粮米徴収権は翌年に廃止され、地頭の設置は平家没官領・謀叛人跡に限定された。
源義経が謀叛を起こし、どこかに逃げてくれたおかげで、「源義経を捜索する」という名目で守護・地頭が置かれた。そして、源義経が奥州平泉に逃げてくれたおかげで、平泉藤原氏を討つ名目が生まれた。(どちらも源義経と源頼朝の謀なら凄いが・・・。)
3.高校日本史の復習(3)問注所
『吾妻鏡』によると、元暦元年(1184)10月6日に公文所吉書始が行われ、同20日に問注所が開設されました。御家人を統制する軍事機関である侍所に続き、文書の制作・発給を担当する公文所、裁判を担当する問注所という、二つの文治的な政治機関が源頼朝のもとに設置されたのです。
公文所の長官である別当に就任したのは、広い知識と高い政治的判断力を有する大江広元。中原親能、藤原行政、足立遠元らが寄人として広元を補佐しました。一方、問注所の長官である執事に就任したのは、頼朝の流人時代から献身的に支え続けた三善康信でした。三善康信は元暦元年(1184)4月14日に京から鎌倉に下向したようです。
https://www.nhk.or.jp/kamakura13/story/19.html
4.高校日本史の復習(1)御家人体制

「御恩」と「奉公」。
源義経が挙兵しても兵が集らなかった。これは、「戦功に応じた「御恩」が無い」と考えられたからであろう。
▲「13人の合議制」のメンバー
【文官・政策担当】①中原(1216年以降「大江」)広元(栗原英雄)
【文官・外務担当】②中原親能(川島潤哉)
【文官・財務担当】③藤原(二階堂)行政(野仲イサオ)
【文官・訴訟担当】④三善康信(小林隆)
【武官・有力御家人】
⑤梶原平三景時 (中村獅童)
⑥足立遠元 (大野泰広)
⑦安達藤九郎盛長(野添義弘)
⑧八田知家 (市原隼人)
⑨比企能員 (佐藤二朗)
⑩北条四郎時政(坂東彌十郎)
⑪北条小四郎義時 (小栗旬)
⑫三浦義澄 (佐藤B作)
⑬和田小太郎義盛(横田栄司)
▲NHK公式サイト『鎌倉殿の13人』
https://www.nhk.or.jp/kamakura13/
▲参考記事
・サライ「鎌倉殿の13人に関する記事」
https://serai.jp/thirteen
・呉座勇一「歴史家が見る『鎌倉殿の13人』」
https://gendai.ismedia.jp/list/books/gendai-shinsho/9784065261057
・富士市「ある担当者のつぶやき」
https://www.city.fuji.shizuoka.jp/fujijikan/kamakuradono-fuji.html
・渡邊大門「深読み「鎌倉殿の13人」」
https://news.yahoo.co.jp/byline/watanabedaimon
・Yusuke Santama Yamanaka 「『鎌倉殿の13人』の捌き方」
https://note.com/santama0202/m/md4e0f1a32d37
・Reco「『鎌倉殿の13人』関連記事」
https://note.com/sz2020/m/md90f1f483984
▲参考文献
・安田元久 『人物叢書 北条義時』(吉川弘文館)1986/3/1
・元木泰雄 『源頼朝』(中公新書)2019/1/18
・岡田清一 『日本評伝選 北条義時』(ミネルヴァ書房)2019/4/11
・濱田浩一郎『北条義時』(星海社新書)2021/6/25
・坂井孝一 『鎌倉殿と執権北条氏』(NHK出版新書)2021/9/10
・呉座勇一 『頼朝と義時』(講談社現代新書)2021/11/17
・岩田慎平 『北条義時』(中公新書)2021/12/21
・山本みなみ『史伝 北条義時』(小学館)2021/12/23
記事は日本史関連記事や闘病日記。掲示板は写真中心のメンバーシップを設置しています。家族になって支えて欲しいな。
