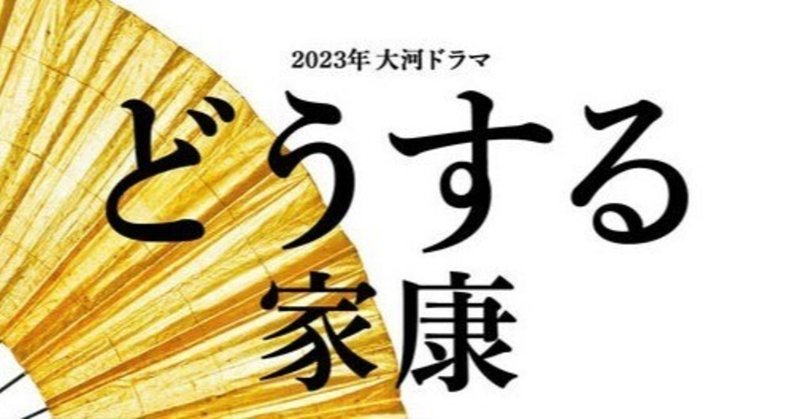
遠州忩劇(遠州錯乱)-井伊氏と飯尾氏-
「三河一向一揆」は、徳川家康の3大危機の1つであり、今川氏真が攻めてきたら、徳川家康は討ち死にしていたであろう。
今川氏真が三河国の徳川家康を攻められなかったのは、彼が「遠州忩劇(遠州錯乱)」と呼んだ反乱(永禄5年(1562年)から永禄9年(1566年)までの遠江国の国衆(井伊氏、天野氏、飯尾氏など)の今川氏からの離反)が(本拠地・駿河国と三河国の間の)遠江国で起きていたからである。
一、遠州引間の城主・飯尾豊前守は、駿州今川の先鉾として、尾州織田軍勢と所々にて合戦。然に永禄三年(五月脱)十九日、義元、尾州桶狭間にて討死の後、氏真、亡父の弔合戦之心掛も無之、朝夕酒宴遊興に長らるる故、権現様、永禄四年より信長公と御和睦被成候。(自是先は今川と一味。)遠州引間の城主・飯尾豊前守、同国井伊谷の城主・井伊肥後守、同国(注:三河国の誤り)嵩山の城主・奥村修理を始め、大方、氏真を叛き、信長公及び権現様江内通仕候。此の由、氏真、聞及び、永禄五年三月は井伊谷、同年四月
は引間、同七月は嵩山、此の三城へ駿河より人数を差し向被攻候。井伊谷、嵩山は落去、引間の城にては、寄手の大将・新野左馬助討死。城内にも、飯尾同心・渥美、森川、内田等の歴々討死仕候得共、猶堅固に守に依て、氏真、調略を以て、致和談候。此れ以後 永禄七甲子、氏真、三州表江発向。権現様と所々にて攻合、同国一の宮より人数を引取被申候刻、飯尾は、権現様江御味方の体相見候につき、氏真より遠州二俣の城主・松井左衛門(初、強八と申し候哉)、豊前守姉婿なるにより、渠を媒として縁者に取くみ、駿府江呼び寄せ、永禄八年極月廿日、駿府ニノ丸飯尾屋敷江押し詰め、被誅之。然共、引間城は、豊前守家臣・江間安芸守、同・加賀守持固候故、翌年二月、権現様より御慇之御書被下候由。

■略年表
永禄5年(1562年) 12月14日 井伊直親、掛川郊外原川で誅殺さる。
永禄6年(1563年)10月 「三河一向一揆」勃発
永禄7年(1564年)2月28日 「三河一向一揆」終結
永禄8年(1565年)12月20日 今川氏真、飯尾連竜を誅殺
永禄9年(1566年)1月6日 松平家康、引間城家老・江馬に誓書を与える。
永禄9年(1566年)5月 松平家康、東三河を平定し、三河国平定成る。
永禄9年(1566年)12月29日 「松平」から「徳川」に改姓。三河守叙任。
永禄11年(1568年)12月 徳川家康、遠江国へ侵攻開始(引間城落城)
■井伊直親(なおちか)
「遠州忩劇」(永禄5年(1562年)~永禄9年(1566年))は、「徳川四天王」井伊直政の父・井伊直親の徳川家康への内通に始まるという。
『井伊家伝記』等によれば、徳川家康と井伊直親は、遠江国と三河国の国境で、「鹿狩」と称して何度も会っていたというが、西三河平定中の徳川家康が、今川領である東三河を越えて、遠江国へ行けるか疑問であり、これは下克上を企む家老・小野政次の讒言であろう。
『井伊直政御一代記』等によれば、謀反を今川氏真に疑われた井伊直親は、弁明のために駿府今川館に向った。駿府に着けば、新野親矩の尽力で赦免される手はずになっていたが、新野親矩の顔を立てて赦免としたことを口惜しく思っていたに今川氏真は、井伊直親暗殺の密命を掛川城主・朝比奈泰朝に出した。朝比奈泰朝は、やってきた井伊直親に「弁明は駿府で新野親矩がしているので、返事は原川の宿で待てという今川氏真のご命令である」と嘘をつき、宿を夜襲して井伊直親を討った。
■飯尾連竜(つらたつ)
永禄7年(1564年)2月、今川氏真、引間城を攻撃(「御家中諸士先祖書」)
永禄7年(1564年)3月、今川氏真、頭陀寺城を攻略(「都筑家文書」)
永禄7年(1564年)4月8日、飯尾連竜、徳川家康と対面(「東漸寺文書」)
永禄7年(1564年)9月15日、新野親矩、引間橋にて討死。
永禄7年(1564年)10月、今川氏真、飯尾連竜を赦免(「頭陀寺文書」)
永禄9年(1565年)1月6日、江間兄弟へ起請文
永禄9年(1565年)2月10日、徳川家康から江間加賀守時成へ起請文
今川上総介氏真旗下奉行
高一万石
一、飯尾豊前守乗連 同豊前守連竜
右、天文、弘治、永禄の頃迄三十八年程居
飯尾長連┬賢連─乗連─連竜┬義広…御子孫(静岡県浜松市在住)
└為清 └正宅…御子孫(東京都渋谷区在住)
永禄6年(1563年)、今川氏真が1万人の軍を率いて「今川義元の弔い合戦」だとして東三河(佐脇城)まで進撃した時、飯尾連竜も従軍した。しかし、白須賀に布陣していた殿軍(最後尾)・飯尾軍の陣から火が出て、今川氏真は「放火だ、反乱だ」と判断して撤退した。
飯尾連竜の本拠地は引間城と頭陀寺城であった。永禄7年(1564年)2月、今川氏真は、引間城を攻撃させたが、落とせなかった。翌3月には、引間城の支城・頭陀寺城を落とした。
『井伊家伝記』等では、引間城主は高齢の井伊直平であり、若い飯尾連竜を城代としたとする。白須賀の殿軍の陣から火が出ると「挟み撃ちでは負ける」とし、今川氏真は、本坂峠を越えて駿府に戻り、「放火ではなく、強風で篝火が倒れての失火であって、反乱ではないのであれば、反今川の天野氏を攻めよ」と井伊直平に命令した。井伊直平は、永禄6年(1563年)9月18日、天野氏討伐に向う途中、有玉旗屋(静岡県浜松市東区有玉南町)で落馬して死亡した。一説に、出陣直前に於田鶴が飲ませた茶に毒が入れられていたという。
永禄七年、氏真参州出張之時、遠州浜松城主・飯尾豊前守も相随て在陣仕候。曽祖父・江馬加賀守異見により、権現御味方に志し、則ち、加賀守を使として岡崎へ奉り、此の旨を言上仕処、「於一味は早々吉田表を引き払ひ、浜松江可帰之旨」仰せらるに付き、豊前守、夜中に新居、白須賀を放火して本坂道を浜松江引取候。依之、今川方周章し、翌朝、吉田表を引き払ひ、浜松を通て、本坂より大菩薩通を引帰、其の後、今川方より浜松城を為可攻人数五千余出張之処、浜松より鷺坂伊賀守に人数三百計着添、天龍川辺江出向ひ、堤を隔てせり合ひ、敵兵、多討取候。今川方より飯尾長門守を以て、重而、浜松城を攻る刻、権現様より為御加勢。本田百助、渡辺半蔵、中根喜蔵以下三十騎被遣(按ずるに、東照宮より援兵をつかはされとあるは信じがたし)、城兵相共に浜松の向宿上松迄出向処、敵、跡を取切及一戦。鷺坂伊賀守致討死。味方危く相見候処、小笠原新九郎、馬伏塚より出て横鎗を入切崩、敵将・長門守を小野田彦右衛門請取奉る人数を引取。
永禄7年(1564年)10月2日、今川氏真は詫び状を提出した飯尾連竜を赦免し、飯尾連竜が篭る頭陀寺城(静岡県浜松市南区頭陀寺町)の破却を命じることで事を収めた。
就今度飯尾豊前守赦免頭陀寺城破却故、先至他之地、可有居住之旨、任日瑜存分領掌了、然者、寺屋敷被見立、重而可有言上、頭陀寺之儀者、云今度悉焼失、日瑜云居住于他所、以連々堂社寺家可有再興、次先院主并衆僧中、以如何様忠節、令失念訴訟之上、前後雖成判形、既豊前守逆心之刻、敵地江衆徒等悉雖令退散、日瑜一身同宿被官已下召連、不移時日頭陀寺城被相移以忠節、頭陀寺一円補任之上者、一切不可許容、兼又彼衆徒等憑飯尾、頭陀寺領事、雖企競望、是又不可許容者也。仍如件。
永禄七年
十月二日
上総介(花押)
千手院
しかし、永禄8年(1565年)12月、飯尾連竜が再び松平家康に内通したことが発覚し、12月20日、飯尾連竜は駿府に呼び出されて処刑された。
飯尾連竜は駿府に行く前に「怪しい。何かあったら引間城は徳川家康に差し上げるように」と家老・江間兄弟に告げていた。江間加賀守時成は納得したが、江間安芸守泰賢は武田信玄に心を寄せていた。
◆引間城内部の派閥
・徳川家康派:城主・飯尾連竜、家老・江間加賀守時成
・武田信玄派:正妻・田鶴の方、家老・江間安芸守泰賢
◆「江間氏の祖」
説①江間小四郎近末:『鎌倉殿の13人』では江間次郎。江馬小次郎の父。
説②江間小四郎義時:後の北条義時。「江間太郎」とは北条泰時のこと。
説③江馬小四郎輝経:北条時政の妾(平経盛の妾)の連れ子。
説④江間義光:北条義時の孫(北条義時の次男・江間遠江守朝時の子)。
説⑤江馬遠江守光時、江馬孫四郎政俊:北条義時の弟・北条時房の子孫。
○廿日。遠州敷智郡引間の飯尾豊前守致実が姪女、今川氏真が寵を得て頃
年致実も殊遇を蒙りしが、神君に内応の由、風説し、氏真、渠を駿府に召し寄せ、軍士百騎許を以て其の屋鋪を闈み攻て鏖(みなごろし)にす。時に飯尾が士、二、三十騎死戦をなす故、寄手、多く討たる。致実が室、無雙の強力、屡々奪ひ戦ふ(是を「駿府の小路軍」と世に称す)。
其の臣・両江馬氏、引間の城を守り、神君に心を通ずといへども、今川が多勢来て城郭を攻撃故、一旦の禍を避けて、妻子を質とし、寄手に降ると云々。
此の節、今川方より曖を入、其の後、豊前守を駿府へ謀寄、主従八十四人生害之。元来、和議疑敷存故、駿府江参る刻、「若し我不慮之義有之者、浜松城を権現様江差上、可奉頼」由、家老・江馬安芸守(自注加賀守従父兄)、同加賀守に申し含め候。依之、加賀守方より以飛札、岡崎江右之趣致言上候。江馬安芸守、同・加賀守、浜松城を守り、旧主之仇を可報旨相謀処、安芸守は甲州方江志し、加賀守は偏に岡崎御味方可仕と相談未決之処、加賀守、家老・川口郷左衛門を使として岡崎江差上、酒井左衛門尉、石川内記を以、右之趣致言上奉頼時、酒井、石川両人より連判起請文差し越す。
敬白起請文御返答之書
一 被仰越候段、聊相違有間敷事、
一 加勢異儀有間敷事、
一 御知行方不沙汰有間敷事、
右之條々於相違者、
上は梵天帝釈四大天王惣而、日本国中大小之神祗別而伊豆箱根両所権現之蒙御罰、於現世白癩黒癩可成者也。仍如件。
永禄八乙丑年 酒井左衛門
極月晦日 忠次(血判)
石川内記
頼正(血判)
江安
同加
御返報
■『改正三河後風土記』
今川氏真は永禄6年(1563年)、1万人の軍勢を率いて出陣し、東三河の牛久保城(愛知県豊川市牛久保町)に陣取り、5000人の兵で一宮砦を攻めた。この時、神君・徳川家康公は、僅か2000の兵で出撃し、危機を救った。これを「一宮の退口」「神君一宮後詰」といい、「神君大高城兵糧入れ」と共に、「徳川家康二大武勇談」として語り継がれている。(この後の「佐脇城(愛知県豊川市御津町下佐脇郷中)&八幡砦(愛知県豊川市八幡町東赤土)の戦い」では、徳川家康は、「妻の先祖の関口家の墓には触れるな」と命じたので、関口家の墓は現存している。)
この時、引間城主・飯尾致実(連竜)は、既に徳川家康と内通していたので、「体調不良。引間城へ帰る」と言い、新居や白須賀の今川軍の陣に放火しながら帰城すると、今川氏真は、駿府に戻り、「すぐに飯尾致実(連竜)を捕らえて、放火の件を問い質せ」と言って小林砦(静岡県浜松市浜北区小林)を築いて井伊谷にいた新野右馬助親矩(「左馬助」の誤り)を大将に、兵3000人を入れた。ある日、引間城の東の引間橋で戦いが3度行われたが、3回目に大将・新野親矩は鉄砲で撃たれて(一説に矢で射られて)亡くなった。この日を『武徳大成記』では永禄5年4月とする(「神君一宮後詰」には永禄5年説がある)が、新野親矩の命日は永禄7年9月15日である。
今川軍が敗れて、今川氏真は益々怒り、すぐに朝比奈泰能、瀬名親隆、瀬名氏範、朝比奈秀盛等を送ったが、引間城は落ちなかった。この時、飯尾致実(連竜)は、「誰かの讒言により、徳川家康に内通しているとか、今川軍の陣に放火したとされているが、無実である」と書いた起請文を矢に結び付けて射た。この起請文を駿府の今川氏真に見せると、今川氏真は、兵を呼び戻して飯尾致実(連竜)を赦免した。喜んだ飯尾致実(連竜)が駿府へお礼を言いに行くと、今川氏真は、飯尾致実(連竜)を誅殺した。
今川氏真は去年、三州発向。佐脇、八幡に在陣せし時、飯尾豊前守致実が徳川殿へ内通し、病(やまひ)と称し、「居城・遠州引間へ引き返す」とて其の道すがら、新井、平須賀辺の駅舎に放火して帰りし事を大いに憤り、氏真、駿州へ帰府の後、「早速に引間を故致実を生け捕りて、其の虚実を鞠問せん」とて、新野右馬助親矩、其の弟・式部少輔之規を大将とし、三千余人を差し添へ、引間の城へさし向け、短兵急に攻めさせしに、豊前守さる古兵(つはもの)なれば、少しも恐れず、矢、炮を飛ばし、防戦す。寄手の大将・新野右馬助、鉄炮にあたりて、うたれ死す。(『大成記』、「引間城攻め」を永禄五年四月とす。誤れり。)依て、散々に敗れ、駿州へ迯(に)げ帰れば、氏真、益(ますます)怒りかさねて、朝比奈備中守泰能、瀬名陸奥守親隆、其の子・中務大輔氏範、朝比奈兵太夫秀盛等に大勢を差し添へ、攻めかこみ、昼夜を分かたず攻しかども、致実、防戦の術を尽くし、寄手の手負ひ、死人ばかりにて、城落つべしとも見へず。其の時、致実、矢文を射出し、「其の讒者の為に無実の罪を蒙り、遺恨せん方なし。一時の急難をのぞかんが為、防戦するといへども、全く異心を抱くにあらず。早く讒者の虚実を糺明有て、恩免を蒙らば、弥々(いよいよ)二心なく忠勤すべし」としたため、起請文に添へて贈りければ、討手の輩、是を駿府に贈り、氏真に見せしむ。氏真、爰に於いて、討手の輩、呼び返へし、致実が罪を免(ゆる)し、此の後は懇意に恩義を施しければ、致実も忝くや思ひけん、礼謝の為に駿府へ来りけるを、氏真、謀をめぐらし、壮士を伏せ置き、不慮に殺害せり。
https://dl.ndl.go.jp/pid/993836/1/208
記事は日本史関連記事や闘病日記。掲示板は写真中心のメンバーシップを設置しています。家族になって支えて欲しいな。
