
2022年NHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』(第14回)「都の義仲」
鎌倉時代について、授業の半分も覚えていない私が『鎌倉殿の13人』についての記事を書けるのは『吾妻鏡』で復習しているからである。ところが、今回は寿永2年(1183年)の回である。『吾妻鏡』の寿永2年の記事は欠落しているので、寿永2年の様子は、
・『百練抄』(公家の日記などの諸記録を抜粋&編集した歴史書)
・『玉葉』(関白・九条兼実(ココリコの田中直樹)の日記)
・『平家物語』(軍記物)
等から推し量るしかない。
※『東鑑目録』「1183年」
http://www5a.biglobe.ne.jp/~micro-8/toshio/azuma/118307.html
◆「後白河法皇と源行家の双六」(『鎌倉殿の13人』の後白河法皇は、「接待双六であり、源行家は、わざと負けるので面白くない」と言っているが、『玉葉』には、訪問者を帰すほど熱中していたとある。)
■『玉葉』「寿永2年(1183年)閏10月29日」条
先廿七日参上之処、与行家御双六之間、無他事、雖入見参、空退出。昨日参上奉仰云々。
(後白河法皇は双六が大好きである。27日に興福寺別当・信円という僧が用事があって後白河法皇の院御所にへ行ったが、後白河法皇は、源行家との双六に熱中で、「明日(28日)来い」と仰せになられたという。)
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1920201/332
◆「源頼朝、後白河法皇へ大量の贈り物」(北条親子とは規模が違う。これにより、源頼朝の流罪は、10月9日、正式に取り消された。)
■『玉葉』「寿永2年(1183年)10月1日」条
一日壬辰。天陰、雨下。昼間、天晴、及、晩、風吹。伝聞。先日、所遣頼朝許之院庁官、此雨三日以前帰参与巨多之引出物云々。頼朝、載折紙申三ヶ条事云々。
(3日間、雨が降り続いたが、昼には晴れ、夕方には風が吹き始めた。4日前(雨が降り出す前)、後白河法皇が源頼朝に派遣した使者が巨多(きょた)のプレゼントを持って帰洛したという。源頼朝は、返書で3つの約束をしたという。)
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1920201/324
※「牛車の乗り降りの仕方 」
https://note.com/sz2020/n/n0b784f760736
※「鼓判官」こと平知康
https://note.com/sz2020/n/n4b62080073f9
1.あらすじ(敬称略)
寿永元年(1182年)、北陸に逃れてきた以仁王の遺児・北陸宮を擁した木曽義仲(青木崇高)は、嫡男・木曽義高(市川染五郎)を鎌倉へと送ると、寿永2年(1183年)5月11日、10万とも言われる平維盛率いる平氏の北陸追討軍を倶利伽羅峠で「火牛の計」を用いて破り(「倶利伽羅峠の戦い」)、続く寿永2年(1183年)6月1日の「篠原の戦い」にも勝利した。この時、平家方の伊東祐清(竹財輝之助)と江間次郎(芹澤興人)が討ち取られたという。
敗れた平宗盛(小泉孝太郎)は、皇位継承に必要な天皇家のレガリア「三種の神器」(八咫鏡、八尺瓊勾玉、草薙剣)と安徳天皇(5歳。「安徳天皇女性説(安徳天皇姫宮説)」を採用してか、相澤智咲)と共に都を落ち延びる(世に言う「平家の都落ち」。後白河法皇(西田敏行)は、早朝、比叡山に逃げた)。
「木曽義仲に先を越された」(先に上洛された)と焦る源頼朝(大泉洋)であったが、大江広元(栗原英雄)は「木曽義仲と後白河法皇は合わないから大丈夫」と予言する。実際、その通りとなり、(さらに、源行家(杉本哲太)が「木曽義仲が謀叛を企てている」と讒言し、木曽義仲に馬鹿にされた使者の「鼓判官」こと平知康(矢柴俊博)が木曽義仲討伐を進言したことにより)後白河法皇は、源頼朝に謀反人・木曽義仲を討つよう命じ、源義経(菅田将暉)が出陣した。(この後、源義経が鎌倉に戻ることはなかった(涙)。)
一方、鎌倉では、御家人たちが源頼朝から離れようとしていた。御家人と源頼朝との結び役は北条氏であり、宗主・北条時政(坂東彌十郎)が伊豆に引っ込んだ今、鎌倉に残った北条義時(小栗旬)は、どうしたものかと悩んでいた。そんな時、大江広元は、北条義時に、「上総広常(佐藤浩市)に御家人たちの会合に出るように勧めよ」と策を与えた。(実際は、「寿永二年十月宣旨」により、御家人は源頼朝を中心としてまとまり、「東国独立国家論」を強く主張している上総広常が邪魔になっていた。)
「義仲は皇位選定で院と対立。一方、寿永二年十月宣旨によって頼朝の家人たちの在地における立場は安定し、頼朝の求心力が高まる。宣旨の執行のために義経が伊勢・近江に向かって義仲を牽制する。そのような状況を利して頼朝は上総広常を粛清する。…という理解が、研究者間の一般的理解だと思います。」(京都女子大学名誉教授・野口実)
https://twitter.com/rokuhara12212/status/1513132325290188807
2.寿永2年(1183年)略年表
5月11日 北陸合戦「倶利伽羅峠(砺波山)の戦い」
6月1日 北陸合戦「篠原の戦い」
7月25日 平家都落ち(巡り巡って讃岐国屋島へ)
7月27日 木曽義仲、入洛。
7月28日 木曽義仲、後白河法皇から平家追討を命じらる。
7月30日 平家追討の勲功は「第一頼朝、第二義仲、第三行家」。
8月10日 木曽義仲、受領&任官(従五位下、左馬頭、越後守)。
8月16日 木曽義仲は伊予守(旭将軍)、源行家は備前守に任替。
8月18日 卜筮で四之宮(尊成親王)を皇位継承者に決定。
9月19日 後白河法皇、木曽義仲を呼ぶ。
9月20日 木曽義仲、平家追討のため、播磨国へ下向。四之宮、践祚。
10月9日 源頼朝、従五位下右兵衛佐に復位。
10月13日 木曽義仲、従五位上に昇叙。
10月14日 「寿永2年10月宣旨」(東国支配権)と木曽義仲討伐要請。
閏10月1日 木曽義仲軍、「水島の戦い」で平家軍に敗北。
閏10月15日 木曽義仲、帰洛。
閏10月27日 後白河法皇、源行家と双六。
11月19日 「法住寺合戦」
12月1日 木曽義仲、院御厩別当に任官。
12月10日 木曽義仲、左馬頭辞任。
3.源義仲の挙兵と上洛
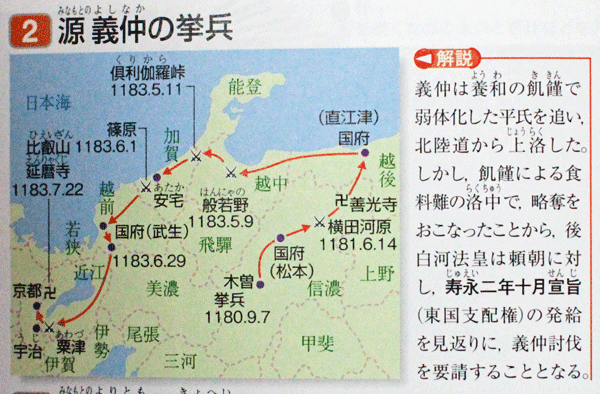
■高校日本史『詳説日本史図録』(山川出版社)
解説 義仲は養和の飢饉で弱体化した平家を追い、北陸道から上洛した。しかし、飢饉による食糧難の洛中で、略奪をおこなったことから、後白河法皇は頼朝に対し、寿永二年十月宣旨(東国支配権)の発給を見返りに、義仲討伐を要請することとなる。
後白河法皇が平家に替わる木曽義仲に期待したのは、「養和の飢饉」や戦乱による食糧難と、「平家都落ち」で無法地帯と化しつつあった京都の治安回復であったが、木曽義仲が入洛すると、さらに京都の治安が悪化し、木曽義仲は、伝統や格式を重んじる法皇や公家達から、宮中の政治、文化、歴史の知識や教養がない粗野な人物「木曽の山猿」として疎まれた。
『鎌倉殿の13人』では、①「三種の神器」を知らず、自分の太刀で代替させようとしたこと、②牛車の降り方を知らないこと(「牛車に乗る時は後ろから、降りる時は前から」というのが決まりがあるのに、木曽義仲は後ろから跳び降りて失笑をかった。現在であれば、バスや電車に乗ったことがなく、乗り降りの仕方を知らない田舎者)と紹介された。
※「牛車の乗り降りの仕方 」
https://note.com/sz2020/n/n0b784f760736
木曽義仲がどれほど京都の文化を知らなかったのか分からないが、安徳天皇がいなくなって、次の天皇を決める時に、「三種の神器」を知らない木曽義仲が、「天皇」(高倉上皇)の皇子が2人(三之宮・惟明親王と四之宮・尊成親王)もいるのに、「王」の子にすぎない北陸宮(以仁王の子)を即位させようと口出しした。これが、木曽義仲が後白河法皇や公家達に嫌われた本当の理由だと思う。
後白河法皇は寿永2年9月19日に源義仲を呼び出し、「天下静ならず。また、平氏放逸、毎事不便なり」と責めた。立場の悪化を自覚した源義仲は、「明日の朝、平氏追討に向かう」と奏上したので、法皇は自ら剣を与えた。
翌・寿永2年(1183年)8月20日、源義仲は樋口兼光(今井兼平、樋口兼光、根井行親、楯親忠の4人で「義仲四天王」)を京都に残して播磨国へ下向した。 また、この日、「三種の神器」がないのに、安徳天皇が退位していないのに、四之宮が践祚した(第82代後鳥羽天皇)。
■『玉葉』「寿永2年9月21日」条
廿一日。癸未。伝聞。義仲、一昨日参院。被召御前、勅云。「天下不静。又、平氏放逸、毎事不便也」云々。義仲申云。「可罷向ハ、明日早天可向」云々。即、院、手取御剣給之。義仲取之退出。昨日俄下向云々。
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1920201/323
4.平家追討の論功行賞
源頼朝の悩みは、
①上洛を木曽義仲に先に越され、人々の心が木曽義仲により始めていること
②上洛したいが、坂東武者の反発や藤原秀衡の脅威もあって上洛できないこと。また、未だに罪人の身分であり、上洛しても朝廷に物申せる身分ではないこと
であった。

■「寿永2年7月30日付中原広元宛文書」(『鎌倉殿の13人』での復元)
本日(午时)於院有儀定平家輩敗走■凋還御事當时成功偏源氏等勲功云々勧賞等級者
第一 頼朝(京官任国加級)
第二 義仲(任国叙爵)
第三 行家(任国叙爵)
叡慮云今度義兵造意在■■■时随申請可有任官歟云■■披露給候恐々謹言
七月卅日 ■■■■(花押)
安藝介殿
※■は見えない文字
※「午时」ではなく「午刻」、「随」ではなく「隨」では?
※「安芸介殿」は中原広元(1216年以降「大江」)。誰が報告してきた?(実はこの時、中原広元は、まだ京都にいて、元暦元年(1184年)に鎌倉に下向して公文所別当に就任し、同年9月17日に「因幡守」に任官している。)中原広元は、寿永2年(1183年)4月9日に従五位上に昇級している。「安芸介」は従六位上相等なので、この時はもう「安芸介」ではないかと。
--------------------------------------------------------------------------------------
源義仲の上洛後に行われた朝廷の論功行賞では、源頼朝による「源頼朝が源氏の棟梁」と思わせる政治的交渉が功を奏し、寿永2年7月30日に院御所で開かれた公卿議定において、勲功の「第一頼朝、第二義仲、第三行家」とされた(『玉葉』「寿永2年7月30日」条)。源頼朝が「源氏の棟梁」であり、源義仲や源行家を指揮したと考えられたのであろう。『鎌倉殿の13人』では、源頼朝が後白河法皇に「西は平家、東は源氏が支配するのはいかがでしょう」と手紙を出し、後白河法皇に源頼朝を「源氏の棟梁」だと勘違いさせたとする。
しかし、源頼朝が「源氏の棟梁」ではなく、今回の「平家都落ち」に大きな働きをしていないことが判明し、源頼朝の「京官、任国、加級」は取り消され、源義仲は、受領&任官(従五位下、左馬頭、越後守)を果たした(『玉葉』「寿永2年8月11日」条)。源行家は、源義仲との扱いに差があり過ぎるとして忿怨(ふんえん)し(恨み)、院御所へ文句を言いに行ったが、既に閉門していたので帰ったという(『玉葉』「寿永2年8月12日」条)。
寿永2年8月16日、源義仲&源行家が任国を嫌い、源義仲は、河内源氏ゆかりの伊予守(受領の最高峰で、かつては源頼義が受領し、源義仲の死後は源義経が受領することになる)に、源行家は、備前守になった。こうして源義仲は「源氏の棟梁」と認められ、「旭将軍」と呼ばれたという。
■『玉葉』「寿永2年7月30日」条
卅日壬辰。天晴。早旦、泰経卿送書於季長朝臣許曰「今日、於院、可被議定大事。巳刻可予参」者、午一点、着冠直衣、参蓮花王院。先是、左大臣、大納言実房、忠親、中納言長方等、在御堂南廊東面座(依風吹垂簾)、余、同加彼座頭、弁兼光朝臣奉仰来、仰左大臣云、条々事、可計申者(其事三ヶ条具載左)
一、仰云。「今度義兵、造意雖在頼朝、当時成功事、義仲、行家也。且欲行賞者、頼朝之欝難測。欲待彼上洛。又、両人愁賞之晩歟。両ヶ之間、叡慮難決。兼又、三人勧賞等可有等差歟。其間子細可計申」者。
人々申云。「不可被待頼朝参洛期。加彼賞、三人同時可被行。頼朝賞、若背雅意者、隨申請改易、有何難哉。於其等級者、且依勲功之優劣、且隨本官之高下、可被計行歟。惣論之、第一頼朝、第二義仲、第三行家也」。
頼朝(京官、任国、加級。左大臣云「於京官者、参洛之時可任」。余云「不可然。同時可任」。長方、同之。)
義仲(任国、叙爵。)
行家(任国、叙爵。但以国之勝劣任之、尊卑可差別云々。実房卿云「義仲従上、行家従下宜」歟。)
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1920201/313
■『玉葉』「寿永2年8月11日」条
十一日。癸卯。雨下。先日、所進太神宮之剣箱等、今日、参着日也。仍神斉、修祓遥拝(衣冠)、見去夜聞書、
義仲(従五位下、左馬頭、越後守)
行家(従五位下、備後守)
云々。
■『玉葉』「寿永2年8月12日」条
十二日。甲辰。雨下。伝聞。行家称非厚賞忿怨、且是与義仲賞懸隔之故也。閉門辞退云々。
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1920201/316
※『玉葉抜書』「玉葉のなかの義仲」
https://katsumi-maruyama.com/gyokuyou.html
■『平家物語』「源氏共勧賞行はるる事」
十日、法皇蓮花王院の御所より南都へ移らせ給ひて後、三条大納言実房、左大弁宰相経房参り給ひて、小除目行はる。木曽冠者義仲、左馬頭になされて越後国を給はり、十郎蔵人行家は、備後守にぞ成されにける。各国を嫌ひ申しければ、十六日の除目に、義仲は伊与国を賜り、行家は備前守に移されぬ。安田三郎義定は遠江守に成されにけり。
http://www.kikuchi2.com/heike/engyo/eneall.html
5.「寿永二年十月宣旨」
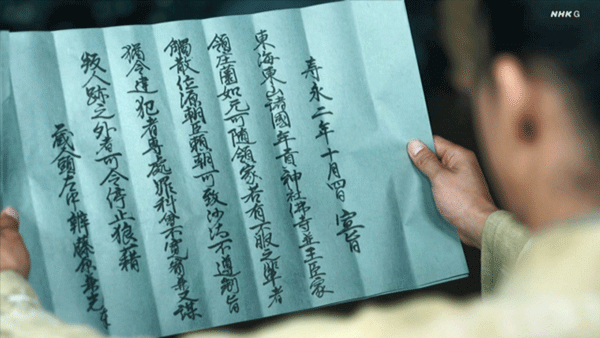
■「寿永二年十月宣旨」(『鎌倉殿の13人』での復元)
寿永二年十月四日宣旨
東海東山諸国年貢神社佛寺並王臣家領庄薗如元可随領家若有不服之輩者觸散位源朝臣頼朝可致沙汰不遵別旨猶令達犯者専處罪科會不寛宥兼又謀叛人跡之外者可令停止狼藉
蔵人頭左中辨藤原兼光(花押)
※「十月四日」ではなく、「十月十四日」では?
源頼朝の復位(流罪を正式に取り消し、官位を元の従五位下右兵衛佐に戻す)は10月9日のことである。10月4日の文書に「散位源朝臣頼朝」(散位(さんい/さんに)とは、執掌を持たず、位階のみを持つ者)とあるということは、10月4日の時点で位階「従五位下」があることになり、おかしい。(『玉葉』「寿永2年7月30日」条の「頼朝(京官、任国、加級)」は取り消されている。)
※旧字になってない。「寿」ではなく「壽」。「並」ではなく「并」。
※藤原兼光は、養和元年(1181年)には左中弁に進み、寿永2年(1183年)に安徳天皇の蔵人頭、後鳥羽天皇の蔵人頭を務めた。
--------------------------------------------------------------------------------------
上洛した源義仲軍は、京都で兵糧を略奪したため、たちまち京都市民の支持を失ってしまった。これをチャンスと考えた源頼朝は、寿永2年10月9日、復位してもらい(『百錬抄』に「前兵衛佐頼朝復本位」)、
①東国における荘園&公領の領有権を旧来の荘園領主、国衙へ回復させることを命じる。
②その回復を実現するために、源頼朝の東国行政権を承認する。
という「寿永二年十月宣旨」(「寿永の宣旨」とも)を出させたという。
この「宣旨」(院旨=後白河法皇の命令ではない! 宣旨=天皇の命令である)は、東国に年貢を納めさせるのと引き換えに、源頼朝の東国支配権を承認するというもので、御家人は「源頼朝による土地の安堵&宛行が、天皇(朝廷)による土地の安堵&宛行に等しくなった」として、源頼朝を中心としてまとまり、朝廷との結びつきを断つ「東国独立国家論」を強く主張している上総広常が邪魔になっていた。
※この「寿永二年十月宣旨」をもって鎌倉幕府の成立とする学者がいるくらい。重要なである。(鎌倉幕府の成立は、昔は1192(いいくに)年説、今は1185(いいはこ)年説が有力。)
■鎌倉幕府成立6説
1180年 南関東武家政権の樹立(幕府=軍府)
1183年 「寿永二年十月宣旨」(東国支配権の承認)
1184年 公文所&問注所の設置
1185年 守護&地頭補任の許可
1190年 源頼朝、右近衛大将に就任(右近衛大将=「幕府」の唐名)
1192年 源頼朝、征夷大将軍に就任(幕府=将軍府)
■『百錬抄』(巻第八)「寿永2年」条
十月九日。前兵衛佐頼朝復本位。又、紀伊国丹生高野神奉加一階。
十月十三日。雷鳴。
十月十四日。大地震。東海、東山諸国年貢、神社、仏寺並王臣家領庄園、如元可随領家之由、被下宣旨。依頼朝申行也。
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/991104/80
■『玉葉』「寿永2年閏10月13日」条
抑、東海、東山、北陸三道之庄園、国領、如本可領知之由、可被宣下之旨、頼朝申請。仍被下宣旨之処、北陸道許(ばかり)、依恐義仲、不被成其宣旨。頼朝、聞之者、定結鬱歟。太不便事也云々。此事、未聞、驚思不少々々。此事隆職不耐不審。問泰経之処、答云。「頼朝ハ雖可恐在遠境、義仲、当時在京、当罸有恐、仍雖不当被除北陸了之由」。令答云。「天子之政、豈以如此哉。小人為近臣、天下之乱無可止之期歟」。
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1920201/329
■『玉葉』「寿永2年閏10月22日」条
廿二日。癸未。天晴。伝聞。「今日、義仲、参院」。又聞。「頼朝使、雖来伊勢国、非謀叛之儀」。先日宣旨云。「東海、東山道等の庄土、有不服之輩者、触頼朝可致沙汰」云々。「仍為施行其宣旨、且為令仰知国中、所遣使者を遣也」云々。而国民等悪義仲郎党等之暴虐、寄事於頼朝之使、切塞鈴鹿山、射義仲、行家等之郎党了云々。因之、義仲郎従等遣伊勢国畢。
今日、家重書等遣山上了。法印無動寺房也。
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1920201/326
(「東海道、東山道、北陸道の庄園&国領は、以前のように領知すべきである(領有権を回復する)と宣言しなさい」と源頼朝が申し出たので、そのように宣旨を下したが、北陸道は(今、都にいる)源義仲の占領下にあったので、宣旨を下さなかった。源頼朝は、これを聞いて(源頼朝と源義仲を天秤にかける後白河院の政治的意図を感じて)落ち込んだようだ。実に都合が悪いことである。(「寿永二年十月宣旨」の発布を知った源義仲は、激しく怒り、後白河院に対し「生涯の遺恨」とまで言うほどの強い抗議を行っている(『玉葉』「寿永2年閏10月20日」条)。)
また、こうも聞いた。源頼朝の使者が伊勢国に来たが、これは謀反ではない。先日発布の「寿永二年十月宣旨」に「東海道、東山道等の庄司で不服を申し出る者がいれば、源頼朝の名の下に沙汰しなさい」とあったので、この「寿永二年十月宣旨」を施行するため、かつ、国中に知せしめんがために、使者を遣わしたのだという。)
※岩田慎平「鎌倉幕府と寿永二年十月宣旨について」
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/lt/rb/677/677PDF/iwata.pdf
▲「13人の合議制」のメンバー
現時点の北条義時は若く、北条政子の父・北条時政は伊豆に帰っている。
比企能員は源頼家の乳母夫になっただけで、まだ娘達を源範頼や源義経に嫁がせていない。(まだ幕府内の影響力が小さい。)
源頼朝の参謀は、京都の事に詳しい中原広元(後の大江広元)で(史実の中原広元は京都にいる)、「東国独立国家論」を唱える御家人(関東武士団連合)の中で影響力の強かったのは上総広常。
【文官・政策担当】①中原(1216年以降「大江」)広元(栗原英雄)
【文官・外務担当】②中原親能(川島潤哉)
【文官・財務担当】③藤原(二階堂)行政(野仲イサオ)
【文官・訴訟担当】④三善康信(小林隆)
【武官・有力御家人】
⑤梶原平三景時(中村獅童)
⑥足立遠元(大野泰広)
⑦安達藤九郎盛長(野添義弘)
⑧八田知家(市原隼人)
⑨比企能員(佐藤二朗)
⑩北条時政(坂東彌十郎)
⑪江間(北条)義時(小栗旬)
⑫三浦義澄(佐藤B作)
⑬和田小太郎義盛(横田栄司)
▲NHK公式サイト『鎌倉殿の13人』
https://www.nhk.or.jp/kamakura13/
▲参考記事
・サライ「鎌倉殿の13人に関する記事」
https://serai.jp/thirteen
・呉座勇一「歴史家が見る『鎌倉殿の13人』」
https://gendai.ismedia.jp/list/books/gendai-shinsho/9784065261057
・富士市「ある担当者のつぶやき」
https://www.city.fuji.shizuoka.jp/fujijikan/kamakuradono-fuji.html
・渡邊大門「深読み「鎌倉殿の13人」」
https://news.yahoo.co.jp/byline/watanabedaimon
・『嵐山町web博物誌』「木曽義仲」
http://www.ranhaku.com/web05/c1/1_01.html
▲参考文献
・安田元久 『人物叢書 北条義時』(吉川弘文館)1986/3/1
・元木泰雄 『源頼朝』(中公新書)2019/1/18
・岡田清一 『日本評伝選 北条義時』(ミネルヴァ書房)2019/4/11
・濱田浩一郎『北条義時』(星海社新書)2021/6/25
・坂井孝一 『鎌倉殿と執権北条氏』(NHK出版新書)2021/9/10
・呉座勇一 『頼朝と義時』(講談社現代新書)2021/11/17
・岩田慎平 『北条義時』(中公新書)2021/12/21
・山本みなみ『史伝 北条義時』(小学館)2021/12/23
この記事が参加している募集
記事は日本史関連記事や闘病日記。掲示板は写真中心のメンバーシップを設置しています。家族になって支えて欲しいな。
