
牛車の乗り降りの仕方
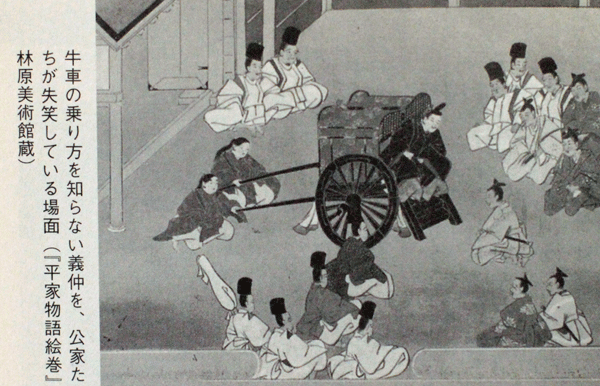
2022年NHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』(第14回)「都の義仲」において、 「牛車に乗る時は後ろから、降りる時は前から」というのが決まりがあるのに、木曽義仲は後ろからとび降りて公家たちの失笑をかった。
───この程度か。
『平家物語』の木曽義仲はもっとすごい。
■『平家物語』「木曽、京都にて頑ななる振舞する事」
是のみならず、かやうにをかしき事共ありけり。木曽「官なりたる験もなく、さのみひたたれにてあらむも悪し」とて、布衣に取り装束きて、車に乗りて院へ参られけるが、きならはぬ立烏帽子より始めて、指貫のすそまで頑ななる事云ふ量りなし。牛童は平家の内大臣の童を取りたりければ、高名の遣手なりけり。我が主の敵と目ざましく心憂く思ひける上、車にこがみ乗りたる有様、云ふはかりなくをかしかりけり。人形か道祖神かとぞ見えし。鎧打ち着て馬に乗りたるには似(に)ず、あやふく落ちぬべくぞ覚えける。
牛車は屋嶋の大臣のを押し取りたりけり。牛童も大臣殿の二郎丸、世に随へば取られて仕はれけれども、主の敵なれば、目ざましく思ひて、いと心にも入れざりけり。牛は聞こゆる小あめなり。逸物の此の二、三年すゑかうたるが、門出を一ずわへあてたらむに、なじかはとどこほるべき。飛びて出でたりければ、木曽さらのけに車の内にまろびにけり。牛はまりあがつて躍る。こはいかにと木曽あさましく思ひて、起きあがらむとしけれども、なじかは起きらるべき。袖は蝶の羽をひろげたるが如くにて、足を空にささげて、なまり音にて「しばし、やれやれ」と云ひけれども、牛童空聞かずして四、五丁計りあがかせたりければ、共にありける郎等共走り付きて、「いかに、しばし、御車留めよ」と云ひければ、「御車、牛の鼻の強くて留めかねて候ふ。其の上『しばし、やれやれ』と仰せ候へばこそ仕りて候へ」とぞ陳じたりける。
車留めて後、木曽ほれぼれとして起きあがりたりけれども、猶あぶなう見えければ、牛童よりて、「其に候ふ手形に取り付かせ給へ」と云ひければ、いづくを手形とも知らずげにて見まわしければ、「其れに候ふ穴に取り付かせ給へ」と云ひける折、取り付きて、「あはれ支度や。是はわ牛小舎人の支度か、殿の様か、木の成りか」とぞ云ひける。
院の御所に車懸けはづれたりけるに、車の後よりおりむとしければ、「前よりこそ下りさせ給ひ候はめ」と雑色申しければ、「いかがすどほりをばせむずる」と云ひけるぞ、をかしかりける。
http://www.kikuchi2.com/heike/engyo/eneall.html
※「牛車の正しい乗り方講座」
───木曽義仲が嘲笑されていた、牛車の正しい乗り方を教えてください。
牛車というのは、後ろから乗り、前から降りるというのが、男も女も貴族も武士も関係なく、基本的なルールになっています。牛車の後ろの部分を建物の縁側にビタっとくっつけてそこから乗り、目的地に着いたら牛を外して前から下車するものなんです。義仲は後ろから、しかも、高さ1メートル超くらいのところから飛び降りるというすさまじいことをしちゃったわけですが、あれはとんだ間違いです。
───履物はどうしているのですか?
履物は履かず、従者に持たせちゃいます。だから、懐から履物をポイっと投げてそのまま飛び降りたのは本当に義仲の無知ゆえの行い。逆に誰も義仲に正しい乗り方を教えないわけですよ。そんな義仲を見てほくそ笑むっていうものすごく陰険な世界がそこにはあって、義仲はそういう目にかなりあうんですよね。ロケで間近に見て、これはみんなびっくりしただろうなあとつくづく思いました。
───どちらの足から降りないといけないとか、乗らないといけないといった規則はないのでしょうか?
たしか左から降りるっていうのはよくありますよね。江戸時代くらいになると結構うるさくいわれるようになるのですが、このころにそこまでやっていたかは怪しいです。江戸時代はこういう朝廷貴族社会の事象に意味をつけたがる時代だったので、そういうことがえらく進むんですよ。平安時代の貴族文化が中世の応仁・文明の乱や戦国期の戦争で京都が戦場になり多くが失われてしまったからです。一種のあこがれです。だけど、このころの人たちにとって牛車は普通の乗り物です。例えば、われわれが車に乗るときに右足から乗るとか左足から乗るとか、あまり気にしないじゃないですか。当然スタイリッシュに乗り、スタイリッシュに降りるっていうのは公家の文化でも共有されていますが、おそらく少しは作法に余裕があるんだと思います。もしかしたら義仲も、1回目で恥をかいたあとは、10年も前から乗っているような顔をしていたかもしれないですね。
おもしろいのは、「寝殿造り」って貴族の住宅があるじゃないですか。あの住宅の縁側の高さは牛車の乗り口と同じ高さになっている部分もあるんですよ。場合によっては縁側から乗る設備のない屋敷もあるわけですが、そういうときは後部を縁側の階段のところに可能な限りくっつけるんです。そうすると女性でも簡単に乗れるんですね。途中で乗り降りするとき用に、「ご榻」という踏み台を牛飼童が担いで持っていたりもします。雨よけの「雨皮」というカバーみたいなものも実は持っていたりするのですが、さすがにそこまで再現することはできませんでした(笑)。
───付き添いの従者がいろいろと持たされていたんですね。
そうです。牛車に主人が乗っていないときには、ご榻に座ってくつろいでいたり、枕代わりに寝たりするやつがいたりするんですけど、今回はちゃんとそこまで描かれているので、これまでの大河の中で一番しっかり再現されているかもしれませんね。
また、牛車に牛をつけて牛をコントロールする人を「牛飼童」とか「牛童」というのですが、今でいうロン毛の髪型をしています。実はこれには理由があって、当時も牛ってかなりの猛獣なんですが、子どもに対してはそういう猛獣な部分を出さないで従順に言うことを聞くとされていたんです。今でも、犬とか猫は小さなお子さんに対して、ちょっかいを出されたり、力いっぱい抱きしめられたりしても怒らないといわれるじゃないですか。牛飼童がロン毛にしているのは、牛にとって御者をやっている童が子どもに見えるようになんですよね。
───ちなみに、義仲はどのように牛車を調達したのでしょうか?
義仲の場合を考えると、義仲自身が牛車を持っていたり牛飼童を雇用したりしていたわけではなく、誰かが牛車と牛飼童と牛をセットで貸してくれたのだと思います。中には、すごく有名な牛飼童と牛のペアがいたりもするんですよ。たぶん義仲もそういうのを利用して借りてきているんだろうけど、牛飼童も意地が悪いですよね。義仲に乗り方を教えてやらないわけですから。
義仲のこのシーンは、武士と貴族たちの位置関係っていうんですかね。当時の貴族たちがいかに武士を嘲笑していたのかということを表す、すごく象徴的で社会的なシーンなんですよ。
https://www.nhk.or.jp/kamakura13/special/column/008.html
この記事が参加している募集
記事は日本史関連記事や闘病日記。掲示板は写真中心のメンバーシップを設置しています。家族になって支えて欲しいな。
