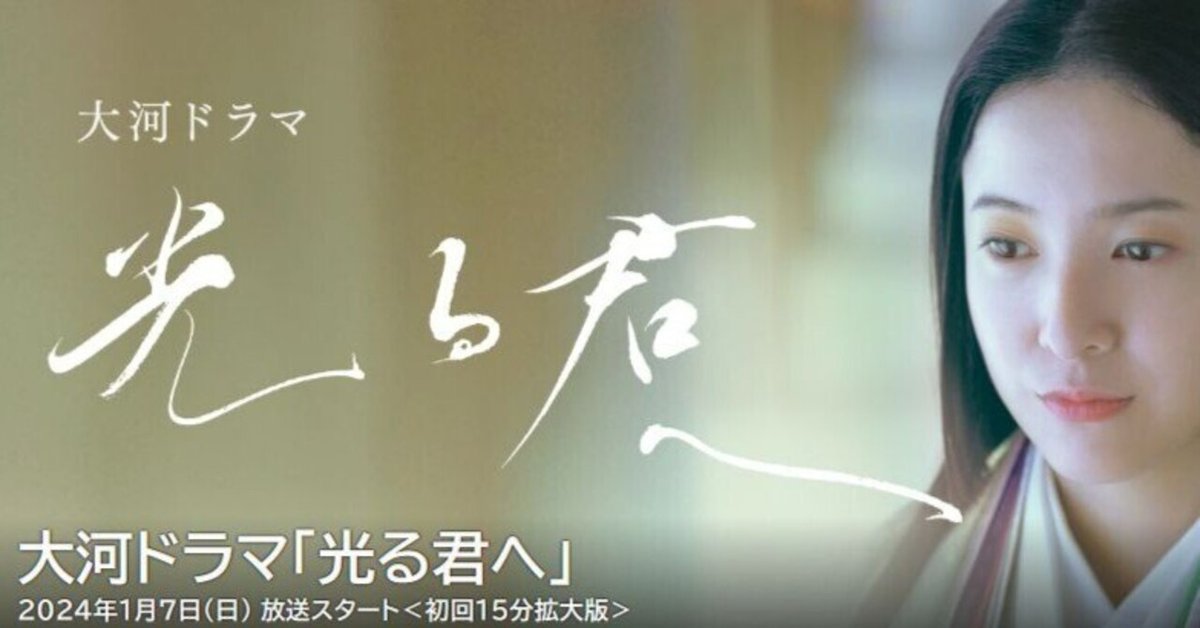
『承安五節絵』
『承安五節絵』は承安元年(1171)の五節の行事を描いたとされる絵巻で、原本はすでに失われ、時代が遙かに下った江戸時代の模本しか現存しないが、平安時代末期の内裏や儀式、装束などの様子を伝えている貴重な資料である。
五節とは、大嘗会および毎年陰暦11月の新嘗会に行なわれた五節の舞を中心とする儀礼の行事で、丑・寅・卯・辰の四4日にわたって行われる。
本絵巻はこの一連の行事を記録した9段の絵と詞書からなり、史実に即していない箇所もあるが、描かれた人物には官職や名前、年齢を注記しているものが多く確認できる。

<「五節」(陰暦11月)の日程>
丑日 五節の参り。帳台の試(常寧殿でのリハーサル)。
寅日 淵酔(えんずい)。諷詠乱舞。御前の試(リハーサル)。
卯日 新嘗祭、飲宴、童女御覧、小忌(おみ)、等。
辰日 豊明節会(とよあかりのせちえ)。五節の舞(本番)。

霜月の中のうしの日、五節のまいりなり。火ともす程より、殿上人まいりつどふ。蔵人頭(くろうどのとう)まいりぬれば、蔵人よびて、「五節どもは、まいりたりや。朔平門見せにつかはせ、五節所ども、たつねにつかはしめる」とおほすれば、蔵人のたうのことねりおよひて、たづねにつかはす。「はいりたり」といへば、又、滝口、「こなたへまいれ」など、お伺をて、小庭におりたちて、蔵人二人にしそくさゝせて、北の陣にめぐるに、殿上人、みなしたがひて、めぐるなり。
【現代語訳】11月の中旬の丑の日は、「五節の参り」(「五節定め」によって選ばれた「五節の舞姫」が、御所の常寧殿に設けられた五節所に参入すること)である。(暗くなって)松明を点す時くらいから、(清涼殿の殿上間に昇ること(昇殿)を許された)殿上人たちが参上して集まった。蔵人頭(蔵人所の長)が参上すると、蔵人を呼んで、「「五節の舞姫」たちは来ているか?(「五節の舞姫」たちを)朔平門に並べ、五節所へ連絡に行って(それぞれの迎えの殿上人に)会わせよ」と命じると、蔵人頭の小舎人(こどねり。蔵人所 に属して殿上の雑事に使われた雑用係)を呼んで(「五節の舞姫」に関係する殿上人へ)連絡に行かせた。
「五節の舞姫が入られた」と言うと、今度は「滝口」(滝口の武者。清涼殿東庭北東の「滝口」と呼ばれる御溝水 (みかわみず)の落ち口近くにある渡り廊を詰め所「滝口陣」にして宿直した清涼殿警護の武者)に「こちらへ来なされ」と言われ、許可を得て、小庭に降りると、蔵人の2人に紙燭(夜間の儀式に用いられた照明具。しそく、ししょく、脂燭)を持たせ、北陣(朔平門。門の近くに衛門府があったため、こう呼ばれた)の筵道(えんどう。筵 (むしろ)を敷いた天皇や貴人が徒歩で進む道。今ならレッドカーペット)を巡り歩くのであるが、殿上人たちは、皆、従って(決められたコースを)巡り歩いた。
【解説】11月中旬の丑、寅、卯、辰の4日間は「五節」である。「五節の舞姫」は、初日の丑の日の逢魔が時(「五節の舞」の発端となった天武天皇が豊受大神に仕える天女に会った時刻)に御所の朔平門へ行くと、蔵人が、既に御所に入っていた殿上人(父親とか、親戚とか)に、「五節の舞姫」が到着したことを小舎人に報告させ、「五節の舞姫」は、迎えに来た殿上人と従者たち(付添いの童女、下仕)を引き連れて筵道を通って玄輝門の内に入り、宣耀殿の前から五節所(常寧殿)に入る。これを「五節の参り」という。その後、「帳台の試(こころみ)」といって、五節所(常寧殿)で試し舞(リハーサル)を行った。
記事は日本史関連記事や闘病日記。掲示板は写真中心のメンバーシップを設置しています。家族になって支えて欲しいな。
