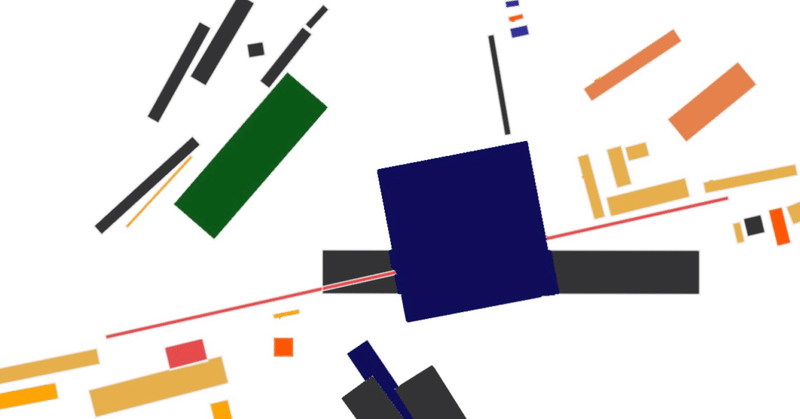
新しいヘーゲル (3)
第4章 人類の叡智(続き)
この章では、ヘーゲル の3体系、つまり、論理学、自然学、精神学のうち、精神学について解説される。
精神学についての解説は、芸術、宗教、学問の順で述べられる。
ヘーゲル は、これらを人間活動の最高位と名付ける。
まずは、芸術について。
「芸術作品は、芸術家個人によって作られるものでありながら、そこに同時に時代の共同精神が込められることによってこそ、真に芸術的な美しさを獲得できる」(p112)
ヘーゲル に取って、芸術が人間活動の最高たる所以は、時代の共同精神が体現されていることにあると述べている。
その問題意識の根底には、近代社会において、「社会から距離を置いた孤独の仕事場で黙々と作品制作にはげむ、というのが芸術創造の一般的ありよう」に対する懸念があった(p113)。
芸術が共同体精神を体現していた歴史的な例として、古代ギリシャが挙げられる。
「彫刻家の創意が生かされるのは、内面と外面との調和をどう打ち立てるか、共同体精神にしなやかに寄りそい、共同体精神をうまく織りこんだ個性をどう表現するのか、という点に限られます」(p116)
共同体精神を織り込んだ作品というのは、シンボルのことであろう。様々な人々が仲間意識を育み、集団を構成する場合、シンボルが必要となる。
「サピエンス前史」の知見を取り入れて解釈し直せば、いくらか抽象的な議論を現代的な議論に引き戻すことができる。
この時代においては、芸術は宗教と融合している。
「宗教がもっと精神化されると、内省と黙想だけで十分とされ、彫刻作品などは余計な贅沢としか見なされませんが、ギリシャの宗教のように感覚的・直感的宗教では、芸術的な活動がそれ自体宗教的な活動であり満足であって、国民にとっても、作品を見ることがたんなる鑑賞というにとどまらず、宗教や生活の一部をなしているがゆえに、制作はどこまで行ってもやむことがありません。」(p123)
しかし、このような、素朴な精神性の時代は終わりを告げ、次にロマン芸術の時代がやってくる。
「おのれの内面に還っていく精神にたいして、外界に物体の姿をとって立つ芸術作品は、もはや完全な満足を与えることができない。」(p129)
そうなると、内面の深まりを表現するために、「美しくないものが必須の要素」として登場してくる(p131)。
その典型が、イエスの受難物語だ。
「十字架に両手両足を釘打ちされてだらりと垂れ下がる痩身で面長の男」という醜く歪んだ外形を造形することによって内面の真理に至ろうとするところに、精神の深さと強さがある(p131)。
ギリシア古典芸術からロマン芸術への移行に関して、「古典芸術の彫像では、主観的な内面と外形がぴったり即応し、外形が内面を過不足なく形象化し、内面と離れて勝手な動きをすることがなかった。が、ロマン芸術では、内面が内にこもってしまうがゆえに、外界の内容自体がそれ自体で独立し、それとして独自な特殊な形を取ることが許されます。」(p132)
精神の内面化、という形でヘーゲル は論じているが、現代的な側面から捉えるとどうなるだろうか。
おそらく、少人数をまとめるためなら、美の象徴とも言えるシンボルを掲げれば、そのシンボルを誰もが自分のものとして捉えることができた。
しかし、ローマ帝国の登場以来、社会が複雑化し、巨大化し、様々な人種が交錯する中で、そのような画一的な、上からの美の構築は不可能になった。
そこで、誰もが共有している内面性を軸に、シンボルを作る必要が生まれてきた。
このように捉えることが可能ではないだろうか。
そうすると、美術史の説明に、精神という抽象的で検証不可能な命題を取り出す必要はなくなり、事実的な側面の観察に、論理的説明を適用すること、つまり、科学的な社会変動の観察+論理学に解消できるのではないか。
次に、ヘーゲル は宗教についての説明に取り掛かる。内面化して成長する人間の精神は、「芸術の王国の上に立つ宗教」に到達する。
宗教は、芸術に祈りが付け加わったものである。そして、「祈りが登場してくるには、芸術が感覚的な外形として客観化したものを、主観が心情のうちにとりいれ、自らそれと一体化することによって、イメージや内密の感情といった内面の状態が絶対者の存在に取って不可欠の要素になるのでなければならない」(p135)
ある意味究極的な芸術の鑑賞スタイルは、祈りだ。
宗教的な精神は、外形的な芸術(もちろん、聖書などの文学も含む)から生み出される。
しかし、そうであるがゆえに、外形的な芸術が人間の精神に取って不適切なものであると、人間の精神、宗教は損なわれる。
その典型例としてヘーゲル はカトリックを痛烈に批判する。
「初めから最高度に外形的な関係を設定するカトリックでは、そこから他のすべての外面的で、不自由で、非精神的で、迷信的な関係が流れ出てくる。たとえば、平信徒は神の真理についての知識や意識と良心の指導を、聖職者が外から与えてくれるのを待たねばならないし、聖職者は聖職者で、精神のみの力でその知識に到達できるわけではなく、到達できたかどうか外面的な叙階の式によって決定されるのを待たねばならない。ほかにも、ただ唇を動かすだけで魂の籠らぬ祈祷法があって、そこでは、主体が直接神と向き合うことがなく、他人に祈祷を依頼したりもするし、奇跡を起こす図像や、さらには骨にまで祈りを捧げて奇跡を期待したりする。」 「要するに、外面的なものによって正義をあらわしたり、自力で獲得すべき功績を他人にゆずったりといったやりかたが、精神の空洞化をもたらしているので、ために、精神の内奥の本質が誤解され、歪曲されて、法と正義、共同体精神と良心、責任能力と義務が根元から腐ってきている。」(p138−139)
ここで指摘されているのは、「最高度に外形的な関係」が精神にもたらす悪影響である。
精神に対して、組織力を元に、形式的な信仰を押し付けることは、精神の活動を損ねる。
ヘーゲル は精神論的な説明をしているが、何も宗教といった話に限定せず、圧倒的な力関係を持った組織が個人に及ぼす影響として、一般的な現象について当てはまる議論ではないだろうか。
このような宗教の先に、学問が現れる。
芸術→宗教→学問という流れを、ヘーゲル は総括する。
「芸術にあっては、神がどんなものか、神の啓示がどのようになされるかを教えるために、まず神が外面的な形をとって意識にあらわれ」る。
次に、宗教にあっては、「イメージが内面化され、会衆の心を満たし動かすものとなる。が、心情やイメージにもとづく内面の祈りは、内面性の最高の形式ではありません。」
最後に学問にあっては、「学問は自由に思考しつつ、同じ内容を意識にもたらし、こうして、これまで主観的な感情やイメージだったの内容にすぎなかったものを、体系的思考によって概念的にわがものにするという、精神的な礼拝が完遂される。」(p141−142)
ヘーゲル は精神の進歩過程として、芸術・宗教・学問を捉えている。
これを現代的に解釈すればどのようになるだろうか。
芸術は、外部の物質的な形の操作に対応。
宗教は、外部のものを脳内にシミュレートして行うイメージ操作に対応。
学問は、脳内において物質的なイメージに頼らずに行う情報操作、論理操作に対応。
というように解釈すれば、芸術→学問への移行は、物づくりが、彫刻→絵画・デザイン→プログラミングへと移行していく様に似ている。
彫刻よりも絵画・デザインはスピードが速いし、絵画・デザインよりもプログラミングはスピードが速い。
しかし、どういう要素がレベルアップしていると説明すればしっくり来るかが分からない。
ここを自然科学的な厳密さで説明できれば、ヘーゲルが言う人間活動の最高位「芸術、宗教、学問」は、人間の活動を、何らかの自然科学的な「複雑さ?」が増していく順序に並べて解説したものとして、現代的に読み直せる可能性がある。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
