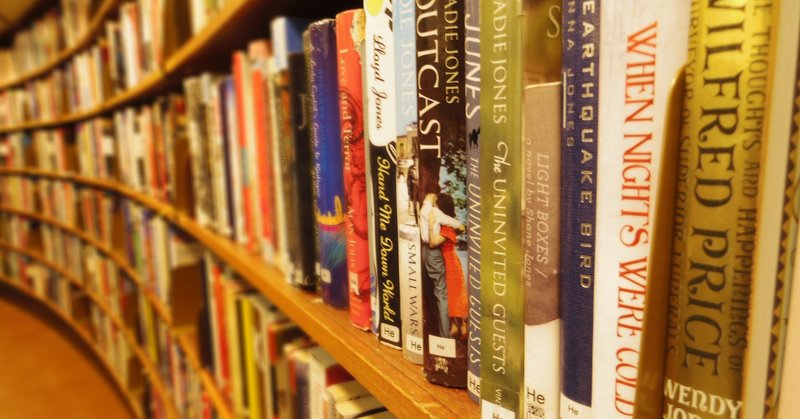
新しいヘーゲル (1)
書籍情報
講談社現代新書「新しいヘーゲル 」(長谷川宏著、講談社現代新書、第1版16刷)
現代にヘーゲル を生かすという視点から、ヘーゲル をわかりやすく解説したことで定評のある長谷川氏の入門書を読んでいきます。
太字の部分が要約で、細字の部分が私の見解です。
太字の部分だけ読んでいただけば、簡単な要約をお楽しみいただけます。
無論、140年前に同じことをしたマルクス主義の成果も取り入れていきます。
第1章 ヘーゲル は難しいか
この章では、ヘーゲル 哲学の入門的な事項が述べられている。
中でも目を惹くのは、弁証法についての説明である。
自然界についての弁証法(p18ー19)
ひまわりの種がある。それを地面に撒くと芽が出てくる。やがて茎が伸び、茎は葉をつけ、夏になると大きな花が咲く。花びらが散った後、花の中央にたくさんの大きなたねが実り、年を越して春になると、この種がまた芽を出す。それがひまわりという有機生命体の生命過程である。 ・・・弁証法の要項として、「否定」と「まとまり」の2点に特に注意を喚起したい。
自然界にも弁証法的な見方が当てはまる、という点は重要である。
社会についての弁証法(p21ー)
「否定」と「まとまり」という過程を通じて発展していくという弁証法的な見方は、自然よりも、人間社会にもっとも良く当てはまる、という点がまず指摘される。
次に、ヘーゲル の弁証法の使い方が示される。
自立した個人の存在と社会という共同体の維持というジレンマを抱えた時代を近代社会の特徴とし、そのジレンマを解消するアイデアとして弁証法が用いられる。
このような社会の捉え方は、精神的であり、裏付けがない場合、妄想ですらある。
このことを頭に入れておくことが重要であり、これが、人間社会に対するヘーゲル における弁証法の適用が、物質的な側面ではなく、精神面にばかり適用され、現実面では力を持たず、精神論に終始し、現在の社会や政治を追認するに止まることを運命付ける。
「近代社会を対立と矛盾のるつぼと化し、まとまりのつかぬ混沌体にしているのは自由にして自立した、揺るぎない個人の存在である」(p25)
近代社会の観察として、このような観察は適切か?
実際に、個人は自由で自立していたのか?
物質的な側面からの検証が不可欠である。
哲学的な観点からの観察はあまりに一面的である。
第2章 精神現象学
ヘーゲル の主著である精神現象学の内容が解説されている。
「意識という名の主人公が、様々な境遇に投げ込まれて成長を重ね、精神的に成長していく過程を辿る物語」(p41)
弁証法的な運動を通じて、意識が成長し、絶対知に至る過程が述べられている。
意識は、否定を経つつもまとまりを維持して展開し、あらゆる経験を包摂していく。
しかし、注目すべき点は、「意識は外界に触れて、自己を否定されるが、その否定を再度自己に統合して、成長する。」という形式で述べられていることだ。
意識は外界に対し、物理的には、ひたすら受動的なのだ。
ここが重要なポイントで、精神という上部構造が外界という下部構造に限定を受けてしまう可能性が示唆されている。
その結果、意識はどこに到達するか?
「意識が自分の本当のありさまにまで突き進むと、意識のまわりにあるものが意識とは違う異質なものだという事態が消滅し、意識にあらわれる者と意識の本質とが一致し、意識の表現がまさしく本来の精神の学問と一致するような、そういう地点に意識は到達する。このように、意識がみずからおのれの本質をとらえるに至ったとき、そこに絶対知というものがすがたをあらわすのである。」(p50)
これは「悟り?」。
現実を変えることをやめ、寺に篭って修行を続ける僧侶や、研究室に篭る研究者を彷彿とさせる。
「こと志とたがう場面に遭遇して意識は幾たびも敗北感や挫折感を味わうが、それこそが真に知的な経験というものである。自他のうちにある非理性や反理性とのたたかいのなかで、はじめて強靭な理性の光が輝くのだ。挫折や敗北を通してこそ、知と思考に厚みと広がりが備わるのである。」(p68)
意識は、敗北感や挫折感を、知や思考の力で自己の成長、ポジティブな経験に変換できるという強い力を持つ。
しかし、裏を返せば、惨めな状況を知的な経験としてポジティブに捉え、そこに甘んじてしまう可能性がある。
先に、弁証法的な思考は「否定」と「まとまり」が核心だと説かれていたが、「否定」の力が弱いと、惨めな状況に置かれた自分を肯定し、小さく「まとまって」しまう。
これが、弁証法的に運動する意識の「強み」でもあり、究極の「弱み」でもある。
次回は第3章「世界の全体像ー論理・自然・精神」です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
