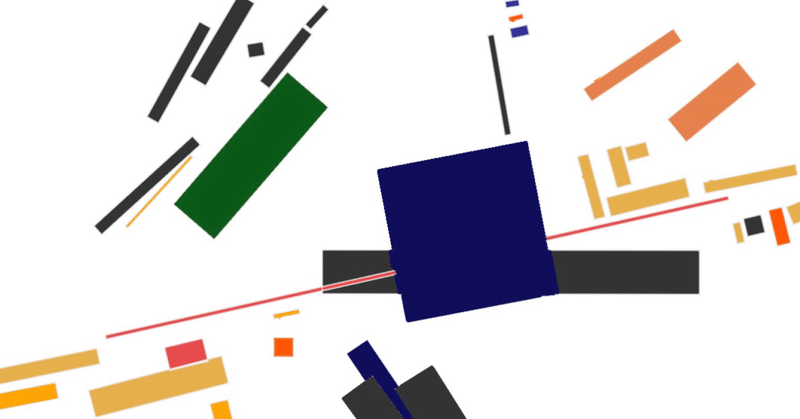
新しいヘーゲル (2)
書籍紹介
講談社現代新書「新しいヘーゲル 」(長谷川宏著、講談社現代新書、第1版16刷)
現代にヘーゲル を生かすという視点から、ヘーゲル をわかりやすく解説したことで定評のある長谷川氏の入門書を読んでいきます。
太字の部分が要約で、細字の部分が私の見解です。
太字の部分だけ読んでいただけば、簡単な要約をお楽しみいただけます。
140年前に同じことをしたマルクス主義の成果も取り入れています。
第3章 世界の全体像
この章では、まず、古代、中世、近代に至る西洋哲学の発展が説かれる。
古代ギリシア哲学、キリスト教神学を経て、近代西洋哲学が登場する(p72−76)。
西洋近代哲学を代表するヘーゲル の哲学は、論理の学、自然の学、精神の学という体系を持っており、この体系にしたがって、へーゲル の講義要綱である「エンツュクロぺデー」3巻は構成されている(p76)。
「論理が下部にあり、その右上に自然があり、その自然と並びつつ、その自然よりやや高い左側に精神がある」(p84)というのがヘーゲル の体系だ。
「体系を欠いた哲学はおよそ学問的なものではありえない。(p77)」
これは、哲学を知恵の寄せ集めであるハウツー本とを分ける大きなポイントだ。
「哲学の内容は、生きた精神の領域で根源的にうみだされ、そこから自ずと生じてきたものが、世界ー意識の内外に広がる世界ーという形をとったものである。(p78)」
ヘーゲル は、哲学の精神性を強調する。しかし、これでは、自然科学を哲学に含むことができない。
カントは、思考を経験の領域内にとどめようとする認識論、不可知論を取っていた(p81−83)。
しかし、ヘーゲル においては、「思考は自然のいきおいとして、定められた枠組みを踏み越えてその先へと進もうとする。」(p83)
この思考の「いきおい」によって、現代の科学は観念、常識の壁を打ち破り、大発展を遂げてきた。
ここに、弁証法の面目が躍如している。
ヘーゲル の、精神中心の世界観は、現代的ではないが、弁証法で捉えた思考の発展過程は、現代にも通用している。
次に、ヘーゲル の体系の第一、論理学についての解説が行われる(p85−94)。ただし、紹介自体が簡素で、特に内容はない。
その次に、体系の第二、自然学についての解説が行われる(p94−107)。自然は精神より劣ったものである云々の議論が紹介される。
精神中心の世界観であり、現代においてこれを取り上げる意義はないと思われる。
第4章 人類の叡智
ここでは、ヘーゲル の体系の第3、精神学についての解説が行われる。
精神学は、芸術、宗教、学問の順で取り上げられる。
ここでは、他者との共同性という観点が出てくる。
これは重要な観点だ。
精神が自然を作るという前の章の議論は、現代から見れば、自然科学に明らかに抵触するので論外だが、人間同士の関わり合いになると、精神から解き明かそうとするヘーゲル の考えを、そう簡単に排斥することはできない。
人間同士の関係について、自然科学は未だ不十分な成果しかあげていない。人間同士の関係を、精神作用から分析するヘーゲル の見方は、未だ自然科学と矛盾しているとは言えないため、耳を傾ける価値がある。
では、次回は、芸術、宗教、学問の関係について、ヘーゲル が解説している部分から、検討していきます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
