
この記事制作から感じたこと
前回に引き続き、2本目の記事を書くことになったシナジーマーケティング松崎です。
なぜこのような記事を書かなければいけないのかというと、noteというメディアでのマーケティング活動の一部として記事の作成依頼があったからとなります。
特にtipsやノウハウもなく、今記事を書いている状況をもとに感じたことを書かせていただきます。
この記事制作の始まり
私の会社の上期は1月~6月となり、下期は7月~12月となります。
noteの良さはなんとなく昨年度より聞くことが多かったですが、今年度に入りnoteを活用することでリード獲得につなげられないか?というプロジェクトが立ち上がりました。
その時の心境としては、一般的なコンテンツマーケティングで考えると、数十本の記事の制作が発生し、タイパ/コスパが今年度では割に合わないという感想を持ちました。
後ろ向きな記事制作
自身でも1本記事を書きましたが、過去にセミナーで登壇したときの内容を記事に流用したにすぎませんでした。
noteという媒体の特性も見やすさも考慮していない、タスクとしてこなした最低限の記事でした。
そのような状況で書いた記事は、閲覧者のアクションを生むこともなく、何なら閲覧されることすら少ない結果となっています。
コンテンツマーケティングを他社にサービス提供する際は「ユーザーが欲しい情報」「ユーザーが検索しているキーワード」「独自性のあるコンテンツ」など、複数の要素を考慮したうえで進めていくのに、自身が執筆する記事ではそのようなことは一切行っていませんでした。
「社内のことになると途端にできなくなる。」
よくある話ではあるものの、「公開されるコンテンツということを認識してもう少し丁寧な作成などができたのではないか?」と後ろめたさを感じる記事となりました。
前向きな記事制作
そんなこんなで進んでいた記事制作ですが、下期も記事の制作をすることになりました。
上期とは違い、SEOなどは一切気にせず書き手の書きたいことをまずは書いていこうという変更がありました。
おそらくこれは、ガチガチに縛ってしまうと記事を制作しにくくテーマを決めるだけでも大変だから変更されたのではないかと思います。
またもう1点、PM含めプロジェクト推進メンバーのやる気というか推進力が目に見えて変わりました。
書き手が書きやすい環境を用意しつつも、「盛り上げていこう」といった趣旨の発言や連絡が多くなり、触発されて以前よりもフラットな形で記事制作に臨めるようになりました。
また、他のメンバーもそうであるのか、もしくは指示内容が良かったのか、記事は多様性に富み、明らかに上期の固い記事よりも、将来的な集客力は上がりそうだと感じています。
今回あえてマーケティングとは程遠いこのような内容の、なんなら記事ですらないメモのような内容を書いているのは、依頼の仕方やプロジェクト全体の雰囲気が結果的に記事の質を変えていき、記事の本数も増えており、良い結果につながっていたので、徒然なるままに記載しています。
振り返ってみると
ただこうやって書いていくことで、
「結局は社内社外問わず、マーケ視点で目的目標だけあってもうまくはいかず、環境やモチベーションといった要素も、成功するかしないかに大きくかかわっている」と改めて痛感しました。
クライアントとの案件でも、今回の社内プロジェクトのように、明るい雰囲気を醸成し、成功へと導いていきたいと思います。
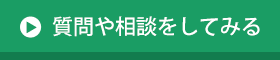

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
