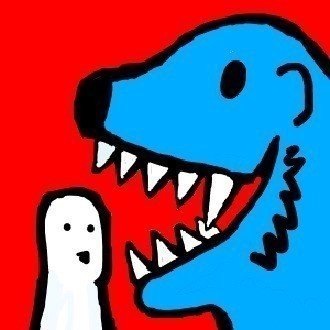犬から主人を引き算したあとに残った世界
たぶん、ポール・オースターの小説だったと思うのだけれど、「犬から主人を引き算した世界に何が残るというんだ?」みたいな一節があって、僕たちが生きているこの世界にはとても残酷な算数がわりとたくさん存在している。そして人間は数字を数えるのが得意な生き物だから、自分の人生から何が引き算され、何が残っていて何が残っていないのか、わりと正確に算出することが出来る。つまり、30歳で借金以外何も残らなかった発達障害者は、主人を失った犬よりもだいぶ希望が残っている、だからもう少しだけ足掻いてみる価値がある。つまりはそういうことで、そういうことだった。
ポール・オースターはこういった悲しみを扱うのがとても上手な作家で、彼自身は親の遺産で文章を書くまさしく穀潰しだったというのに、「貧しさ」とか「希望のなさ」みたいなものをストーリーの主題としてとても上手に扱うことができた。それらはみんな結局のところそれなりに救いのあるものみたいに感じられる小説で、僕もそういうものを書きたいな、と思ってこの歳まで頑張ってきたつもりで。二冊の本を書いてそれなりの部数を売ったけれど、まぁ、そのなんだ。どこまでいっても救いのないものには救いがない。そういう結論に辿り着くことしかできなかった。どこに線引きがあるのかはいまだにわからないけれど、それは所謂結果論というやつだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?