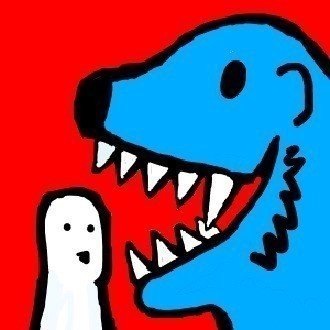さよなら、大先生たち
「発達障害者は児童教育に強い関心を抱きがち」
こんな俗説がある。統計的事実かは別として、思い当るフシはあるか? と問われたら、「ビタで合っています、僕以外の例もたくさん見ました」と答えるしかない。僕が最初に入学したのは教育学部だったし、学生起業で補習塾をやっていた時期もあった。生活費にも事欠くくらい金欠だった学生時代に、時給を稼ぐべき時間と僅かなバイト代をつぎ込んで、僕は授業について行けない子どもたちに勉強を教えていた。公民館を借りたり、バイト先の喫茶店を借りたり、あらゆる方法でコストを安くして少しでも授業料を下げようと努力していた。僕は若い頃、学問の「先生」、いや「大先生」を赤字でやっていたのだ。
今となってはあまりにも明瞭過ぎて、言葉にするのすら憚られるけれど。僕は、「誰かを救えば自分を救うことが出来る」と考えていたのだろう、言語化など到底出来ないままに、僕は間違いなくそう考えていた。そして、僕は自分自身の報われなかった学校生活の復讐を、授業についていけない(そして一般的な補習塾の学費も捻出できない)子どもたちを用いて遂げようとしていた。メサイアコンプレックス、一言で片付くありふれたクソみたいな出来事。授業についていけない子どもたちにはもちろん問題があるけれど、それ以前に僕の人生が問題まみれだというのに。睡眠薬依存から抜け出せないクソガキが、未来ある子どもたちに何を教えるつもりだったんだ? ふざけてんのか?
でも、少なくとも主観的に、僕は大真面目だった。この「大真面目」とは「バカ」と完全に同義だ。
愚かな学生起業は「利ザヤがあまりにも少ないので拡大を目指すしかないが、拡大とともに人件費や管理コストが増大し、薄い利ザヤすら押しつぶされる。初期設計が間違っている事業が成功するわけがない」という至極当たり前の結果に終わった。問題は、僕がこの「当たり前」を理解しないまま大学を卒業してしまったことだ。同じ愚は数年後にスケールアップして再演されることになり、僕は大借金を抱えた借金玉になった。まぁ、これは別のお話なのだけれど(本当にそうか?)。
誰かを救えば自分が救われるのではないか、そんな迷妄に取りつかれる人は多い。特に、恵まれない若年時代を送った人にこの傾向は顕著だ。社会貢献と緊急入院を往復して生きている人間を、僕は少なくとも三人知っている。その三人と僕の何が違うかといえば、運くらいのものだろう。
僕はツイていた。起業に二度も失敗する機会を与えていただいたし、三回目は「収益事業として回さなければ成り立たない」ことを学んでいた。だからこうして「なんとか今年も決算をまとめられた」と安堵しながら、この文章を書いている(弊社は八月決算なので今月はちょっとした地獄だった)。マトモな人間なら二回目には学んでいて当たり前のことだ、僕は愚かな人間なので三回目が必要だった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?