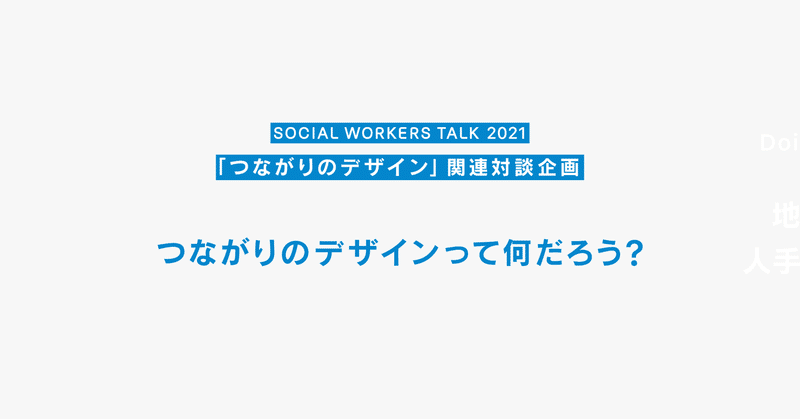
つながりのデザインって何だろう? | SOCIAL WORKERS TALK 2021 | 関連対談
SOCIAL WORKERS LAB(以下SWLAB)は、ソーシャルワーカーという概念を介し、 多様な⼈々が出会い、関わり、学び合う社会実験プロジェクト。
3年⽬となる今年のトークイベントのテーマは「つながりのデザイン」です。
社会は「つながり=関係性」で成り立っています。そして「福祉」とは、個人と個人、個人と社会などの「つながり」を支えるものであり、「つながりをデザインする」という営みは、「福祉的」ともいえるのではないでしょうか。
今回の対談は、10月16日(土)、11月20日(土)に開催するSOCIAL WORKERS TALK2021をより実りある時間にするために、イベントテーマ「つながりのデザイン」そのものを紐解き、理解を深める目的で企画されました。
当日は、社会福祉法人愛川舜寿会の馬場拓也さんをお迎えし、SWLABのメンバーとともに「つながりのデザイン」について語り合いました。これからの社会における「つながり」や「福祉」の可能性と価値に対する、示唆に富む濃密な時間となりました。
登壇者のプロフィール

馬場拓也
社会福祉法人愛川舜寿会 常務理事 / 一般社団法人FUKUSHI FOR CONVIVIALITY 代表理事
1976年神奈川県生まれ。大学卒業後外資系企業を経て2010年、現法人に参画。2016年、特養「ミノワホーム」の庭を地域に開放。2019年、「カミヤト凸凹保育園+plus(認可保育園+障害児通所支援事業)」を開園。2022年、地域共生文化拠点「春日台センターセンター」+「洗濯文化研究所」がオープン予定。著書に「介護業界の人材獲得戦略(幻冬舎2015)」「わたしの身体はままならない(共著/河出書房新社2020)」「壁を壊すケア「気にかけ合う街」をつくる(共著/岩波新書2021)」がある。日本社会事業大学専門職大学院福祉マネジメント研究科修了。

田中悠介
designと 代表 / デザイナー
1985年大阪生まれ。大学、大学院で建築を学ぶも、建物を建てるという手法だけでなく、あらゆる領域の課題に対してニュートラルな視点を持って解決できるようになりたいと思い、デザイナーになることを決意。数社のデザイン事務所を経て、2016年に「designと」を設立。デザインの分野にしばられず、さまざまな領域の課題に取り組む。SWLABにおいては、プロジェクト全体のアートディレクション、デザインを担当。

今津新之助
SOCIAL WORKERS LAB ディレクター
1976年生まれ。大阪出身。大学卒業後に沖縄に移住し、’03年に株式会社ルーツを創業。人づくり・組織づくり・地域づくりを行う多中心志向のコンテクスト・カンパニーを展開。現在はプロジェクト・デザイナー兼コーチとして、人間の可能性が開花していくプロセスに伴走しながら、新たにはじめたり、局面展開させたり、領域横断し結びつけたりを多数。一般社団法人FACE to FUKUSHI理事、一級建築士事務所STUDIOMONAKA取締役。9歳の娘ラブ。
多様性に、いかに寛容になれるか
今津:みなさん、こんにちは。SWLABディレクターの今津新之助です。今日は「つながりとデザイン」をテーマに、社会福祉法人愛川舜寿会の馬場拓也さん、そしてSWLABのアートディレクターでもあるdesignとの田中悠介さんと3人でお話できればと思っています。
馬場さんは、2010年に社会福祉法人愛川舜寿会を二代目として引き継がれ、特別養護老人ホーム(以下、特養)「ミノワホーム」の壁を取り払い、ホームの庭を地域に開放するなど、地域の人々とのつながりをデザインされ続けています。まずは簡単に自己紹介をいただければと思います。
馬場さん:こんにちは、社会福祉法人愛川舜寿会の馬場です。愛川舜寿会は、神奈川県の愛川町という街で福祉事業を営んでいます。
人口4万人ほどの愛川町には、神社が37社、寺院が19寺もあります。これが何を意味するかというと、古くから「祈りの場所」がコミュニティーの中心だったということなんですね。自治会や地域ごとに神社があって、家の近くで初詣や盆踊りをすることにより人が集まり、つながりを生んできた歴史がありました。
こうした元々その地域に息づいているコミュニティを源泉に、愛川町というフィールドで、愛川舜寿会は「共生」「寛容」「自律」という3つの言葉を理念として活動しています。これらの言葉に辿り着いたのには、哲学者・文明批評家のイヴァン・イリイチが唱えた「コンヴィヴィアル(自立共生)」という概念が大きく影響しています。コンヴィヴィアルは、いまよく耳にする「共に生きる」という意味だけではすくい取れないニュアンスで、もう少しニュートラルな視点で、自分とは異なる他者との出会いや、そうした他者と同じ空間や時間を分かち合うこと。「生きることを共にしていく」というような概念であり思想です。多様性を前提として、いかにその多様性に対して寛容にかまえていけるか。この言葉が自分にはとても腑に落ちました。

社会「を」やさしくする
馬場:多くの人は、ケアと聞くと「介護、福祉、支援」などを思い浮かべると思います。でもケア(Care)の語源って「気にかける」とか「耕す」なんです。だから僕らはケアという言葉を広義の意味で捉えていこうとしています。社会福祉法人などの専門職だけが社会「に」やさしくするのではなく、地域の中でつながりをつくり、ケアしあえる=気にかけあえる。そんなふうに「社会をやさしくする」ための行動変容や意識変容を起こしていくことが活動のビジョンです。具体的な取り組みの話は、また後ほど。
ちなみに余談ですが、イヴァン・イリイチが著した「シャドウ・ワーク」や「脱学校の社会」は、今のコロナの時勢にもすごく腑に落ちるところがあるんじゃないかと思っています。
今津:馬場さんありがとうございます。僕は大学の頃にイヴァン・イリイチを研究しており、お話に出てきて嬉しくなりました。続いて田中さんお願いします。

デザインとは、関係性をつくること
田中:デザイナーの田中です。「design と」という屋号で活動しています。「designと」という名前には、たとえば「デザイン と 教育」、「デザイン と 福祉」 など、デザインが単体で何かを解決する手段になるのではなく、いろんな分野に寄り添いながら、いっしょに課題を解決したり、社会をよりよくしていけたらいいなと想いを込めています。
デザインと聞くと、かっこいいものやおしゃれなものがデザインだと思われがちなんですが、実は世の中のすべてのものにはデザインが存在しています。たとえば身の周りのペンや携帯電話にもデザインが存在しているし、みなさんがこのトークイベントに参加する際に使ったPeatixには、「仕組み」という名のデザインが存在しています。このようにデザインは、とても幅広い解釈をすることができるんですね。
そのうえで僕は、デザインとは「関係性をつくること」だと考えています。たとえば商品やサービスは、その効果や魅力をポスターやWEBサイトなどの手段を用いてお客さんに伝えます。でも本当は、そういった形あるものだけがデザインではなく、売り場の雰囲気や店員さんの接客やふるまい方を設計することも広い意味ではデザインです。つまり、商品・サービスとお客さんとの間に双方向の関係性をつくることが、本来的なデザインの役割だと思っています。
デザインにより双方向の関係性をつくることによって、福祉施設の見え方が変わり、地域の人との新たなつながりが生まれる。馬場さんの活動は、まさにつながりをデザインされていて、自分の中でもとても腑に落ちるものがありました。

「つながりのデザイン」のデザインについて
今津:ありがとうございます。「designと」という屋号そのものがつながりを表現しているんですね。今回の「つながりのデザイン」のフライヤーも田中さんに制作していただきました。デザインについてお話しいただけますか。
田中:SOCIAL WORKERS TALK 2021「つながりのデザイン」のキービジュアルは、ひらがなの「ふくし」という文字をビジュアルとして使用しています。「ふくし」が3次元的に一筆でつながるように見えることで、福祉がつながりで成り立っていることを表現しています。また、よく見るとこれらの文字が大小さまざまなドットで構成されており、福祉が多様な人で成り立っていることを表しているようにも見えます。「ふくし」をビジュアルにすることで、「福祉」という言葉が持つイメージや先入観を超えたところで興味を持ってもらえたらいいな、とも思っています。

地域と福祉を分断する「壁」をこわす
今津:馬場さん、特養「ミノワホーム」や来年春にオープン予定の福祉施設「春日台センターセンター」の取り組みについてもお話しいただけますか。

馬場さん:この写真は、うちの特養「ミノワホーム」でのお祭りの風景です。人口減少でどんどん地域が縮小している中で、老人ホームのお祭りがどんどん大きくなり、1000人以上が集まるお祭りになっています。
盆踊りや祈りの場所というものへの帰属意識が薄れつつある現代で、生きることを共にしていくことを求めたときに、もう一度地域の中でつながり、コミュニティを育む場所が必要なんじゃないかとずっと考えていました。そこで僕らは、これまでずっとミノワホームを囲っていた80mくらいの壁をすべて取り払ったんです。建築家、造園家、職員たちに加え、建築を学ぶ大学生と福祉を学ぶ大学生を混ぜ、「距Reデザインプロジェクト」と題した、地域と福祉の精神的距離を再考する取り組みでした。つまり、分断は空間やデザインからも引き起こされてるんじゃないだろうかと。

馬場:こうして福祉が地域にひらかれていったときに、やはりそこには人と人の新しいつながりが彩られていくんですよね。僕らが壁の内側や建物の中で地域に背中を向けて、粛々と一人の人を大事に大事にケアしていくことは、それは慎ましいことではあるかもしれないけれど、「ひらかれた福祉」という視点を持った時に、どちらに自分のじいちゃん、ばあちゃんを入れたいか、を考えると答えはおのずと出るのではないでしょうか。
場の記憶から、つながりをデザインする
馬場さん:「春日台センターセンター」は、1969年から地域で利用されてきたスーパーの跡地で、みんながその場所の記憶をもっています。そんな場所で福祉事業を地域と連関させてやっていこうと進めています。具体的に何があるかというと、生活に密着した「洗濯」を中心に人がつながる洗濯代行サービスやセルフランドリー、また、地域の人が憩えるスペースや、そこにコロッケスタンドを設けて、それらが就労支援の場になったり。さらに高齢者のグループホームと小規模多機能居宅介護、放課後等デイサービスなど、もはやなんと名付けたらよいのかわからない複合的な福祉施設ですね(笑)
田中:とても共感します。社会って合理的になればなるほど、どんどん閉じようとする。でも馬場さんはどんどんひらこうとしておられます。合理性を求めるとたしかに閉じるのが合理的なんですが、人の気持ちを考えると本当はひらいたほうが豊かだったり幸せだったりしますよね。
いいデザインというのは見た目ではなく、その事業の本質的な部分とつながっているからこそのいいデザインだと思うし、取り組まれている活動そのものがデザインとも捉えられるんじゃないかと感じました。
馬場:昨日も春日台センターセンターの求人説明会をやったんですよね。そしたらコロッケを揚げるのが得意というおばちゃん、児童相談所で働いている方、企業で人事をされている方など、本当にいろんな方々が来てくれるわけです。つまり福祉はすでに専門家だけが提供する「メニュー」ではなく、誰もが関われる「概念」なんですよね。僕は福祉サイドの人間だけど、福祉と完全に同化しきらずに、俯瞰的に福祉の営みを見ることで、本質的な目的を置き去りにしないようにしています。

福祉施設は、運営から経営へ
今津:とはいえ福祉事業は国費であり、売上を追求するための構造ではない中で、デザインに力を入れることはコスト的に困難ではないでしょうか。
馬場:確かにデザインに注力しようと思うとコストがかかります。じゃあそのコストをどう捻出するか。その答えは、運営を経営に変えることなんですよね。これまでの社会福祉法人は行政の下請けとして施設を運営してきた側面がありますが、これからは社会福祉法人も独立した経営主体になっていかなきゃいけないということです。これまで意識しなかったかもしれない、一つひとつのコストについて真剣に考える。これは非常に大切な課題だと思います。
今津:社会福祉法人の経営もありかたそのものをデザインし直すことで、春日台センターセンターのような実際的なデザインに取り組めるということですね。
馬場:そうです。福祉業界にとってデザインは、想いを正確に伝えるためのコミュニケーション手段であり、とても重要なものであるはず。表面的な解釈でイロモノと捉えるのではなく、日本はデザインへの正当な認識をもう少し深めていく必要があると思っています。そのためには、田中さんの「みんなのうえん」のお話しにもあったように、その活動とデザインをAction(行動、展開)させることが大事だと思います。それが、やがて福祉サイドと社会サイドにInteraction(相互作用)を生み出していきますから。
田中:「イロモノ」に捉えられるというのは、デザインが付加価値的要素として思われているということですよね。デザインに力を入れると、お金をかける余裕があるんだと思われたりとか。でも、自分がやりたいことを正しく伝えるためにやるのがデザイン。事業を経営するうえでも、もっと重要視されてもよいのかなと思いますね。
大事なことを伝えるために、
非合理的な「余白」を大切にする
今津:「つながりのデザイン」というテーマで、ここまでお話ししてきましたが、まさに共感が込み上げてきた時間でした。まだまだお話は尽きませんが、最後にひとことお願いします。
田中:デザイナーという仕事は、さまざまな業界と関わる仕事でもあります。そのときに大事にしていることは、その業界の専門じゃないからこそ見える、外からの視点です。馬場さんは福祉業界にいながら、福祉を俯瞰して見ておられ、どんどん外にひらいている姿勢が印象的でした。そして実際に地域の人と新しいつながりをデザインされていて、またぜひミノワホームにも伺いたいと思いました。ありがとうございました。
馬場:人と関わる仕事をしてきて、ぼくが必要だと思ったのは、「余白」だったんですよ。「余白」って、生産性という視点で考えたら非合理的に感じられることもあるかもしれない。でも何か大事なことを伝えようとするときに、たとえば文章だったら(まだ書き込める空間はあるのに)行間をあけたり改行をしたりするじゃないですか。そうやって余白をつくることで、そこに書かれている想いが齟齬なく伝えられるという経験をみなさんしていると思うんです。そういうことと今回のテーマはすごく似ているような気がしました。
ぼくが考えるデザインとは、コミュニケーションの手段。で、その思いを齟齬なく伝えるための余白の設定をしていくことで、周りの人がアクセスしやすい隙間ができるのかな。そうした一つひとつの関係性の設定がデザインなんじゃないかという気がしています。楽しかったです。ありがとうございました。
今津:またぜひ、こんな場をもたせていただければ嬉しく思います。今日はみなさん、ありがとうございました!

* * *
◯お話の中に出てきた本
「シャドウ・ワーク」(岩波書店、1982年)イヴァン・イリイチ著
「脱学校の社会」(東京創元社、1977年)イヴァン・イリイチ著
* * *
いかがだったでしょうか?今年のトークイベントのテーマ「つながりのデザイン」を深堀りする対談企画。これからはじまるSOCIAL WORKERS TALK 2021が、みなさんにとってより充実したい内容になれば嬉しいです。次回もぜひご参加ください。
* * *

SOCIAL WORKERS TALK 2021
つながりのデザイン
Vol.1 2021年10月16日(土)14時〜16時
「地域とのつながりが生まれる場所」
Vol.2 2021年11月20日(土)14時〜16時
「カルチャー、メディア、ふくし」
小野裕之 greenz.jp ビジネスアドバイザー / 株式会社散歩社 代表取締役
中田一会 マガジンハウス「こここ」 編集長 / 株式会社きてん企画室 代表
申し込みはこちらから▼
https://swtalk2021-2.peatix.com/
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
