
【解説】🏮お盆と提灯について🏮【風習】
ご先祖様や亡くなった故人をお迎えしご供養する夏の風習「お盆」。
「お盆」について漠然としたイメージはあるものの、
一体何をどうしたらいいのか?分からないという方も多いかと思います。
鈴木茂兵衛商店は提灯の専門店として約160年提灯を製造販売しております。当社の目線でお盆のなぜ?を解決しながら、読んでいただいた方が
少しでもお盆の風習について考えていただければと思います。

ダウンロード版
疑問に思う項目を下記の目次から選んで読んでもらうのがオススメです!
1.お盆ってなに?
そもそも「お盆」とは一体どのような風習なのでしょうか。
現在広く認識されている意味合いとしては、ご先祖様や亡くなられた
ご家族の霊が自宅へ戻ってくる期間だとされており、
特にご家族が亡くなられてから初めてお迎えするお盆は新盆や初盆と
呼ばれ、お飾りやお供え物を厳かに行う地域/ご家庭が多いようです。
【お盆】
ご先祖様の霊をご自宅にお迎えし、家族や一族が集まってご先祖様や故人様を偲び供養する日本独自の風習のこと。
新盆・初盆については、故人の四十九日が終わってから初めて迎えるお盆のことと言われて来ましたが、今日においてはご家庭ごとの考え方次第で
前倒しに行うこともあるようです。
【新盆とお盆の違い】
故人様を自宅にお迎えして供養するという点では同じですが、新盆は故人様が初めてご自宅に帰って来られる一度きりの機会という点で違いがある。
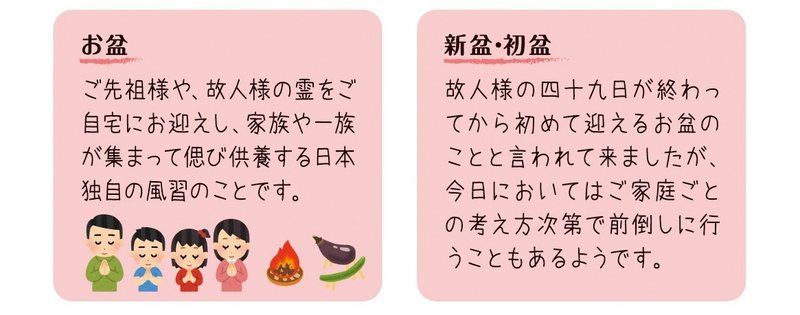
2.期間はいつからいつまで?
時期は地域によって異なり、
旧暦の日付を引き継いだ7月のお盆と、新暦により日付は異なりましたが時期を引き継いだ8月のお盆とに大きく分かれます。呼び方は様々あるようですが、当社では7月盆・8月盆と呼んでおります。
【お盆期間】
7月盆の場合 7月13日~7月16日
8月盆の場合 8月13日~8月16日

お盆飾りは地域やお寺などで決まりがない限り、
お盆の入りまでにそれぞれのご都合に合わせて飾り始めて問題ありません。
ただ新盆(初盆)の場合、お盆中に都合の付かない方が直前の週末にお参りに来ることもありますので、それまでに飾ることをお勧めします。
3.お盆で用意するもの
一般的には、お盆用に祭壇を組むかお仏壇の周りを整理して、
その上や周りにお供え物、お花、お盆提灯などを飾ります。
香炉やおりんはお使いのものがあれば、必ずしも新しいものを
ご用意する必要はありません。
お参りに来るお客様がいらっしゃる場合、お線香やローソクが切れないように準備し、お茶菓子や返礼品をご用意します。
地域ごとに作法や相場が決まっている場合がありますので、
事前にご確認することをお勧めします。
ただし、必ずこれがなければいけないという決まりはありませんので、
それぞれの環境や考え方に応じて故人の霊をお迎えするご準備をすれば良いです。

4.お盆提灯の役割
お盆提灯の役割とは一体どういったことでしょうか。
盆提灯の明かりを目印としてご先祖様が帰ってくると考えて飾られるようになったのです。
そこにさらに家紋を入れるのは、「ご先祖様が我が家を見つけやすいように」「ご先祖様が用いていたのと同じ家紋をたどって、帰ってくることができるように」という意味があったと考えられています。
初盆を迎えられたご当家が提灯を飾る、あるいは、
親戚や故人と親しかった方が盆提灯をご当家へ贈るという習わしがある。

5.家紋について
家紋とは「家系」や「家柄」を表す紋章で、家族や親戚など血縁者が共有するシンボルマークです。盆提灯ではご当家がご先祖様や故人様をお迎えするにあたり目印で入れるのが一般的です。
家紋がわからない場合は墓石や紋付袴をご確認ください。

6.お盆提灯の種類
盆提灯は大きく「置くタイプ」と「吊るすタイプ」に分けられますが、昨今の 住宅環境の変化とともに様々な種類の盆提灯が出てきています。
その中でも代表的な種類の名称と主な特徴は以下の通りです。
●お迎え提灯
主に玄関前に飾られる吊るすタイプの盆提灯。家紋や家名を入れて使われることが一般的ですが、戒名を入れて飾る地域もあります。

●お迎え提灯
主には、持ち手のついた弓張提灯という種類の提灯に家紋や家名を入れたものが一般的です。正面に家紋が入る場合や正面に家名、左右に家紋が入る場合など仕様は地域やご家庭により様々です。盆の入りと明けにお迎え提灯を持ってお墓参りをする風習が今でも見られる地域もあります。

●行灯(あんどん)
三本の脚を持つ代表的な置くタイプの盆提灯の一つ。提灯の火袋は絹や紙で作られており、一重のものと二重のものがあります。絵柄が入ったものもあれば、家紋を入れるものもあります。大内行灯と呼ばれる脚や枠が木製のものや、絵柄の入った筒状のフィルムを電球の熱で回転させる回転行灯などがあります。

●住吉(すみよし)
筒状の形をした吊るすタイプの盆提灯の一つ。行灯と同じように火袋が絹や紙で出来ており、一重のものと二重のものがあります。同じく絵柄が入ったものや家紋を入れるものがあります。家名・戒名・御霊前などの文字を正面に入れる地域もあります。

●新しい考え方の提灯
住宅事情により、昔のように大きくなものやたくさんの量のお盆提灯を飾れない家庭も増えてきています。ご先祖様や故人様をお迎えする気持ちをそのまま、小さなお盆提灯で飾る方も増えております。インテリアとしても飾れる提灯でお盆を迎えてはいかがでしょうか。

7.最後に
鈴木茂兵衛商店の店舗では以上の内容をまとめた「手引書」をご来店いただいたお客様に配布しております。
「お客様がお迎えするお盆をあたたかいものにするために」当店では
お客様の気持ちに寄り添ってご案内させていただきます。
