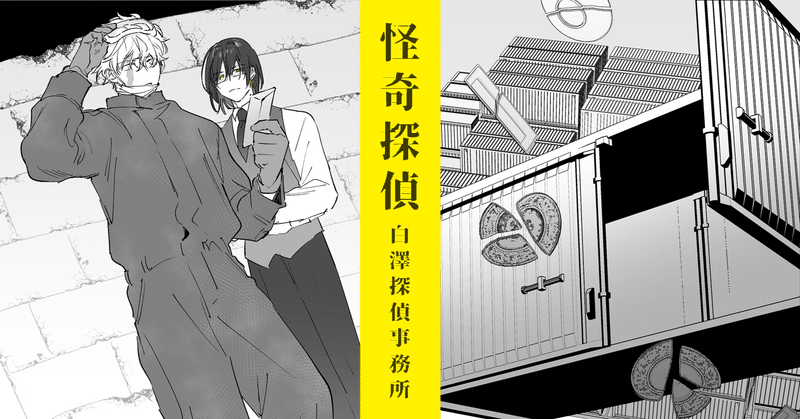
【小説】#30 怪奇探偵 白澤探偵事務所|曰く付きの絵皿
あらすじ:商人のエチゴから急な依頼を受けて港のコンテナを訪ねた白澤と野田。そこには曰く付きの絵皿が大量に集められていた。エチゴは積み上げた絵皿を割ってほしいと頼み――。
【シリーズ1話はこちら】
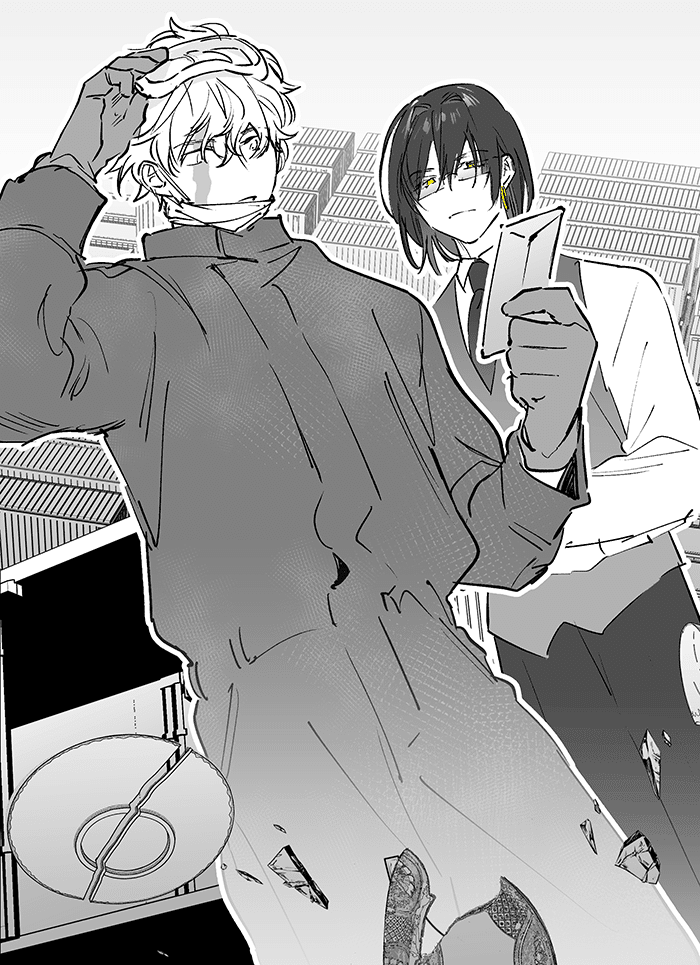
潮風の匂いに、思わず眉を顰める。生っぽい何とも言えない臭いに短く呼吸を止め、息を吐いた。
日の沈みかかった海から吹いてくる風は冷たくて、思わずぶるりと体が震える。海面に視線をやるが、夕暮れの仄かな明るさでは波が揺れるばかりで何も見えなかった。ただちゃぷちゃぷと揺れる海面が、暗くて見えないというだけで恐ろしいもののように思えた。
幻永界の商人であるエチゴさんから、仕事を手伝って欲しいという依頼があったのは今朝のことだ。急な依頼だったが、人手不足で猫の手も借りたいということで、業務をあらかた片付けてから向かうことになった。
「野田くん、エチゴさんが居るコンテナがわかった。向かおうか」
「……あ、了解す」
ぼんやりと海を見つめていたら白澤さんに声をかけられた。どうやら慣れない場所で気が散っていたらしい。すでに歩き始めている白澤さんの背を追って、積みあがったコンテナの集まる埠頭の中へ足を踏み入れた。
「今日って、どんなお手伝いなんすか?」
「動きやすい服装でと言っていたから、また荷物を運ぶとかそういうものかもしれないけれど……」
白澤さんは小さく笑っているが、普段と変わらないスーツ姿である。俺はといえば、しっかり動きやすい服装に整えてある。自分で言うのもなんだが、肉体労働担当という自覚がある助手である。実際、知識では白澤さんに適わないのだからこれでいい気もする。
「……場所もちょっと変わってますね。コンテナがこんなに並んでるの、はじめて見ました」
待ち合わせとして指定された場所というのが、港湾にあるコンテナ埠頭だった。
目にしたとき、こんな場所が東京にあったんだ、と素直に驚いた。立ち並ぶコンテナは普段の生活で見ることのないもので、珍しさから周囲をきょろきょろと見回してしまう。いつだか再放送で見た昔の刑事ドラマで見たような景色だ。
コンテナたちはそれぞれ細部は違うが、一見して他と何が違うかはわからない。白澤さんが居なかったら、どれが目的のコンテナかはわからないだろう。はぐれてしまえば再会するのは大変そうだ。
「野田くん、こっちだよ」
ぼんやりと周囲を見ているうちにどうやら足が止まっていたらしい。置いて行かれないように、慌てて足を速めた。
仕事だというのに、何だか落ち着かない。これではいけないと思いながらも、どうしても頭の片隅で考えてしまうことがあってすぐに気が散ってしまう。原因は明らかで、ついそのことばかり考えてしまうのが困り物だった。
少し前、俺の記憶を隠した男と顔を会わせることがあった。
それが偶然だったのか、あの男が計画していたことなのかはわからない。顔を会わせた瞬間から眩暈が酷くて、ろくに言葉を交わすこともできなかった。聞きたいことも言いたいこともあるはずなのに、頭が真っ白になってしまったのだ。
男はと言えば、一方的に喋って、何が入っているのかわからない封筒を置いてどこかへ去っていった。
残された封筒は、持ち帰った。いっそ置いていこうかとか、捨ててやろうかとも思ったのだが、さすがに数少ない手がかりの一つを無下にすることもできない。それをわかっていて手渡してきたのだとしたら、腹が立つことこの上ない。
事務所に持ち帰っていざ封を切ろうとしたのだが、封筒は何故か開かなかった。
見た目は普通の茶封筒だった。しかし、はさみやカッターを使っても封が切れない。俺が視ても特別な痕跡はなかったから、きっと特別なものなのだろうと白澤さんがあれこれ調べてくれている。その一環で、エチゴさんにも封筒を見てもらおうという話になっていた。
エチゴさんは幻永界の商人だ。向こう側の目線からの助言が得られないか、という淡い期待があった。もし開ける手段がなかったとして、その方法を調べられるのではないか、とも思っている。
白澤さんの後に続いていくつものコンテナを通り過ぎた頃、前方に明かりが漏れるコンテナを見つけた。よく見れば、見覚えのある少年が懐中電灯を手に持って立っている。エチゴさんの部下であるニィくんだった。
「お待たせしました。今日はよろしくお願いします」
「中でエチゴが待ってます。どうぞ」
白澤さんが声をかければ、ニィくんにコンテナの中に通された。
コンテナの入口を通った瞬間、一瞬こめかみがつきりと痛んだ。もしかしたら、幻永界の仕組みがあったのかもしれない。何となく、外と空気が変わったような気がしたのだ。
コンテナの中は、煌々と光る電球がいくらかぶら下げられていた。発電機らしいものからケーブルが伸びていて、本来ならここに電源はないのだろうということがわかる。光が届く範囲に何やらこまごまとした物が積まれているのが見えたが、それが何かまではよく見えなかった。
「お待ちしてました! 今日はよろしくお願いしますね」
「ええ、よろしくお願いします。今日は何のお手伝いを?」
ぺこりと頭を下げる。視界の端で、ニィくんがコンテナの隅から木箱を一つ運んでくるのが見えた。
「ええ、こちらの皿を全部割っていただきたくて……」
木箱の蓋が開くと、その中にはぎっしりと皿が並んでいた。
実用的な皿というより、飾るのが目的であろう高価そうな絵皿ばかりが入っている。いかにもな白に青で描かれた皿、金で縁取られた豪華な皿、カラフルなパターンが描かれた皿と、統一感が全くない。
これを全て割る、というのがにわかに理解できず思わず立ち尽くしてしまった。
白澤さんは箱の中にある絵皿を一つ取り上げ、それで納得したようだった。俺は見ただけでは何もわからず、どちらかというと触るなとか壊すなとか言われそうな絵皿に怯んでしまっている。
「これ、何か……曰く付きだったりするんですか?」
皿を割る。つまり、壊してしまいたいというのなら、何か理由があるのだろう。あまり深く聞いてはいけないだろうかと思いながらも素直に疑問を口にすれば、エチゴさんは腕組みをしたまま小さく唸った。
「曰くつきではあるんですが、これらはそうなるように作られたものなんです」
エチゴさんはにわかに厳しい顔つきになった。普段は穏やかな表情が、どこか冷たく見える。真顔、とでもいえばいいのだろうか。柔和な人から笑顔が消えると途端に無機質で恐ろしいもののように感じてしまう。
「持ち主のいない間に皿が足りなくなったり、絵柄が変わったりする。割れたのに戻ってくる、なんていうのもあります」
どこかで聞いたことのあるような話だ。足りない、足りないという人に足りない分の皿を補充したらどうなるのだろうと全く関係ないことを考えてしまった。
「そういう風に成った皿ならいいんです。けれど、そうなるように作られたのだとしたら、別のものですよね? この木箱に入っているものは、そういう作りものなんです。商人が手を尽くして探して手に入れた商品に成り代わろうとしているんですよ」
一息に言い切ると、今度はエチゴさんは深くため息を吐いた。
「……作りものだと、何が困るんですか?」
「成り立ちを含めて商品になっているものだと、騙して物を売ることになります。信用第一の商売ですから、お客様を裏切るようなものが出回ると困るんですよぉ……」
なるほど、品そのものではなく、それがどのようなものかまで含めて売っているものだと困る、ということだろうか。しかし、出回る、という言い方が少し引っかかった。
「最近、何だかこういうインスタントなものが流行っちゃって……ジョークグッズとして使われているならまあいいかなぁと思っていたんですけど、段々それと知らない人も手に入るようになってしまって……」
エチゴさんはすっかり頭を抱えている。事情をわかっている人が買うならまだしも、それとわからない人が騙されるような事態を危惧しているようだった。商品が売れれば売れるだけ良いという考え方をしないあたり、儲かればいいとだけ考えている人ではないのだなと改めて感心してしまう。
「ニィくんの手では足りないほど増えてしまったんですか?」
「ええ、もうあれこれ回収し始めたら止まらなくなってしまって……ニィくんはもうお皿見たくないっていうし、もっと大きいのを壊さないといけなくて」
もっと大きいもの。皿より大きいものといえば、壺だろうか。いや、今回とは全く別件かもしれない。とにかく、ニィくんは別件で手が離せない、というところだろう。
「……もしかして、家とか?」
白澤さんがぽつりと呟くと、エチゴさんははっと顔を上げた。
「知ってるの、白澤くん? 今、人工の訳あり物件が流行ってて……本当に困ってるの。行ってみるまで作りものか本物なのかわからなくて……」
どうやら、エチゴさんは人工的に作られたものに対して懐疑的であるらしい。そうなってしまったものと、そうなるように作られたものでは確かに意味合いが違ってくるだろうから、それらを分けておきたいというのは自然な感情なのかもしれない。
「今日だけで三件回ってきたんです。ニィくんもさすがに限界で、でも作りものは山のように集まってしまって……それで、壊す部分だけでもお願いできないかなと思いまして」
「壊してしまえば、あとの処理は任せられるということですね?」
「そこはお任せください! あ、野田さんは怪我しちゃうと何があるかわからないので、私のほうでゴーグルとか安全靴とかご用意しました。今着ているものの上から着用してくださいね」
皿の破片が危ない、ということだろうか。用意してもらったのは素直にありがたいが、何となく言い方が引っかかる。とりあえず着替えを済ませてしまおうとニィくんの方へ向かえば、エチゴさんの言う通りゴーグルや安全靴、ついでにツナギまで用意されていた。
「……人間の血に反応する皿もあるんで、肌が出ないように気を付けて」
「……わかった」
なるほど、何があるかわからないとはそういうことか。怪我がないようにというのは常々気を付けているが、今日はより気を付ける必要がありそうだった。
ツナギに安全靴、ついでに頑丈な手袋も貰った。ゴーグルをつければ準備万端、というところで白澤さんが俺をちらと見た。その視線に何か意図があるような気がして、ゴーグルを手元で畳む。
「我々からも、少々お願いしたいことがありまして」
白澤さんが懐から封筒を取り出す。エチゴさんの瞳が、かすかに光った。目に留まった、という言葉がこんなに似合う瞬間もないだろう。
「野田くんが、例の――に手渡されたものです。あれこれ試してみたけど開かない。原因についてお知恵を貸していただけませんか?」
途中、白澤さんの言葉が欠けた。ごにょごにょとした音だったような気もするし、全く何も音が聞こえなかったような気もする。たぶん、俺にはわからない言葉なのだろう。そういうものが出てきても驚かなくなってきた自分に今更気づく。
「うーん……簡単な検品であれば、今お時間いただければ調べられますよ。念のため、確認しながら進めたいので白澤くんも付き合ってくれますか?」
つまり、俺ひとりで皿を割るということである。もとよりそのつもりであったし、構わないと伝えれば二人はコンテナの隅にある組み立て式の机の方に向かった。
調べもので俺が役に立つ場面はないし、これでいい。しかし、木箱いっぱいの皿をどうやって破壊したらいいものだろう。うっかり落として割ったとか、洗い物の最中にシンクに打ち付けたとか、そういう経験しかない。割ろうと思って皿を割るのは、結構どきどきする。
「コツを教えてあげる」
ニィくんが木箱から皿を一枚取り出して、フリスビーのように構える。まさかと思うより先に、皿は宙を舞った。壁に叩ききつけられた皿は、軽い音を立ててあっけなく砕け散った。ただコンテナの壁に叩きつけられただけで、こんなにもあっさり割れるものだろうか。
「あそこの壁だけ、ブロックが詰んである。石に叩きつければ皿は割れる」
「……なるほど。ブロックに向けて投げる」
「あとは、人間が使いやすそうなものはこれ」
どこから取り出したのか、金属バットを渡された。こういうときはわかりやすくハンマーやトンカチを渡されそうなものだが、どうやら違うらしい。
「これは軽くて疲れにくい。木箱はまだあるから、どんどん行こう」
そういうと、ニィくんは俺に背を向けてコンテナの隅から再び木箱を持ってきた。もしかしてあれの中身も全て皿なのだろうか。一瞬気が遠くなったが、とにかく手を動かすことにした。
皿が割れる音にも随分慣れてきた。
普段はこの音が出ないように物を取り扱っているんだな、と改めて認識する。皿をブロックに投げつけるより、地面に落として割ってから金属バットで細かくしてしまうのが簡単だとコツが掴めてきた。
気付けば、コンテナからニィくんの姿が消えていた。どうやら仕事に出向いたらしい。白澤さんとエチゴさんの調査はまだ続いている。何かわかっただろうか。
ふと、ニィくんの持ってきた木箱の上に、皿が一枚立っていることに気が付いた。全部しまわれていたはずだが、いつの間にそこに置かれたのだろう。いや、全て曰く付きの皿だとエチゴさんは言っていたから、勝手に出てきたのかもしれない。
手に取って、そのまま地面に落とす。皿は乾いた音を立てて真っ二つに割れた。
「野田くん、ちょっと来てくれるかな」
「あ、はい」
顔を上げる。さっきも見た皿が、再び木箱の上に載っている。なるほど、増える皿か。皿が足りない家にはこれがあれば助かるんじゃないだろうか。くだらないことを考えながら、白澤さんのところへ向かった。
「封筒、開きそうですか?」
「うん。古い契約様式に則った封筒なのはわかっていたのだけど、何を使うかまで私も詳しくなくてね」
「とても珍しい様式でして、それに古いから開け方を知ってる人は多くないはず……これは決まった道具を使わないと開かないんです。この手の封筒は久しぶりに見ましたね。逆に言えば、これを渡してきた人は、開けられると思っていなかったかも」
エチゴさんは俺のことをじっと見つめた。このまま開けないこともできる、ということだろうか。けれど、見ないままにすることもできない。
白澤さんを見る。白澤さんは俺の目を見て、小さく頷いた。
「開けます。中身を、見ないといけないと思うので」
「わかりました。では、私の道具で封を開けますのでお待ちください」
俺の返事を待ってから、エチゴさんは封筒に手をかけた。古い契約様式で、開け方を知っている人も多くないと言っていたが、エチゴさんはそれを知っているようだった。
折りたたみ作業机の上には道具が色々乗っている。しかし、机の半分ほど、俺の目には見えないものがある。ぼやぼやと霞がかって見えるものもあれば、何の変哲もない鋏のように見えるものもあった。
「中身に何か、細工がしてあることってありますか?」
「あまりないですねえ……人間だとあるんでしょうか?」
話しながらも手を止めないあたり、エチゴさんもきっちり仕事をする人なのだとわかる。霞がかった何かが、封筒の上に重なる。封筒がさらにぼやけて見えなくなった。
「手紙を送ることが多かった時期には多少あったかな、剃刀とか」
「え、危ない……人間てすごいこと思いつきますね……」
封筒の上にあった霞が急に晴れる。エチゴさんは鋏を手に取り、しょき、と封を切る。あまりにあっさりと、封が開いた。
「野田さん、どうぞ」
「あ、ども……」
封筒を受け取る。
中には、紙が一枚入っていた。そっと取り出す。手触りは普通の紙と変わらない。
恐る恐る開くと、見慣れた文字の形がある。読めない言語で書かれていたらどうしようと思っていたが、どうやらその心配はなさそうだった。
問題は、一行目にでかでかと請求書と書かれていたことだ。思わず怪訝な顔をしてしまい、不思議に思ったらしい白澤さんがそっと傍に立った。
「……請求書?」
「目の使用料の取り立てとか言っていたような覚えはありますけど……」
冗談じゃなかったのか、と頭を抱えたくなった。
請求書をよく見てみると、俺の目にはぼやけて見える文字がいくつかあった。またわからない言葉である。少しもどかしい。
白澤さんはエチゴさんを招き、請求書の文字列を見せる。ぎょっとしていたから、きっとエチゴさんから見ても信じられないような内容なのだろう。
「あ、この金額……白澤くんが野田さんをオークションで落札した時と同じじゃないですか?」
エチゴさんが請求書を指さす。ゼロの数が多すぎて、もはやよくわからない。ただの記号の羅列のように見える。
オークションというのは、以前エチゴさんの主催するオークションで誤って俺が出品されたときのことだ。あの時も、珍しい目だと言って値付けをされた覚えがある。その場では白澤さんに落札してもらい、エチゴさんからは丁寧な謝罪と菓子折りをもらった。
「あの時にはもう見つけていた、ということだろうね」
「請求書だけじゃ何がしたいのかわからないすけど……」
「ここに、支払いに応じない場合は点検を受けること、とあるね。また姿を現すかもしれない……あと、名前がある」
白澤さんの指先が紙の末尾を差した。もう一度目を通してみると、目を凝らさないとよく読めないような小さな字がぎっしり並んでいる。質の悪い契約書でもあるまいし、もう少し見やすくしてくれればいいものを。ろくに読ませる気がないらしい。
「……これ、何て読むんですかね?」
「素直に読めば、龍川(りゅうかわ)琉生(りゅうせい)かな。しかし、偽名だろうね」
「偽名と、また来るってこと以外は……わからない、ですね」
何かわかればと思っていたが、わからないことが増えただけだった。そんなにすんなりと答えは得られないだろうと思っていたが、ここまでとは思わなかった。
「エチゴさん、この件で引き続き調べていただきたいことがあるんですが」
「龍川琉生の件ですね。かしこまりました、何かわかりましたらすぐに」
二人の話は早い。偽名だろうが何かわかるかもしれないと考える白澤さんと違い、俺はといえば何もわからなかったことに少し気落ちしている。何かわかるとは思っていなかったが、実際に何も得られないとがっかりするのだなとどこか冷めた自分もいた。
「……じゃあ、俺はあと少し割ってきます。木箱、あと一つなので」
「私も行くよ」
白澤さんは防護服がいらないらしい。エチゴさんは破片の片づけをするための道具を取りに行くといって、一度コンテナを出て行った。
木箱から出した皿を、二人がかりで片っ端から地面に叩きつけていく。無心で体を動かしていると、段々落ち着いてきた。突然、一方的に表れた人間のことなんて何もわからなくて当たり前だろうとか、白紙じゃなくて良かったとか、そういうことを考えてしまう。
何度見たかもわからない絵柄の皿を地面に落として顔を上げると、なぜか白澤さんと目が合った。一瞬驚いた様子のあと、金色の瞳が細くほほ笑む。俺の様子を見ていたようだ。
「野田くん。帰りに時間を少しもらえないかな」
「え? はい、それは構いませんけど……」
「よかった。美味しいものでも買って帰ろう」
「それは、まあ……付き合いますが」
「……うん、まだ何も君に言えることがなくて。私も少し、情けない気持ちなんだ」
白澤さんなら何でもわかると思っているが、出来ないこともある。それはわかっていたが、白澤さん自身がどういう気持ちでいるのかは知らなかった。今、初めて気が付いたと言ってもいいかもしれない。
「焦ってはいけないとわかっているが、あまりに情報が少ない。点検をすると言っている以上、また姿は現すと思うけど……しばらくは離れずに行動しようか」
「了解す。俺も、一人のときにあいつと会うのはちょっと……怖いので」
怖い、と言っていいのかどうか少し迷った。けれど、隠しても仕方がないことでもある。何が起きるかわからない。何を話すのかもわからない。どうして、と聞きたい気もするし、何も話したくない気もする。いろいろ考えてしまうことが恐ろしいから、できれば二人きりで会うのはしたくない。
「私も君を怖い目に合わせたくはないから。しばらく、気を付けておこう」
「そうですね……」
木箱に入っていた最後の一つを床に落とす。ぱりん、と甲高い音をして皿はあっけなく割れた。もやもやとした気持ちも少し晴れたような気がして、小さく息を吐く。また現れたらという不安は、随分軽くなっていた。
コンテナを出ていたエチゴさんがニィくんを伴って戻ってきた。空になった木箱を見て、わっと歓声が上がる。普段あまり表情の変わらない様子のニィくんも微かにほほ笑んでいるように見える。二人の様子を見るに、本当にこの皿たちに悩まされていたらしい。
「お二人とも、ありがとうございました。これはささやかなお礼です」
「……これは何ですか? 粉?」
「入浴剤です。疲れがとれますよ!」
今日はたくさん働いてもらいましたから、というエチゴさんの表情は晴れやかだ。エチゴさんから手渡された銀色の袋を揺らすと、さらさらと粉の音がする。白澤さんの方を見やれば柔らかく微笑んでいた。俺が貰っても大丈夫、ということだろう。
「……ありがとうございます。封筒の件も、助かりました」
「いえ、お役に立てて何よりです。今後とも御贔屓に!」
エチゴさんとニィくんのお辞儀に送り出され、コンテナを出た。
日はとっくに沈み、夜も深い時間になっている。暗闇の中で、海面が埠頭の光を跳ね返してかすかに光って見えた。ツナギを脱いで潮風を浴びると思いのほか気持ちがいい。体は重いが、まあ心地よい程度の疲労だ。
「何買って帰ります?」
「野田くん、食べたいものは?」
「寿司ですかね」
いいね、と笑う白澤さんの横顔を盗み見る。封筒が開いたから、という理由だけではない安堵があった。見上げれば、雲の向こうに月が隠れている。仄かな明かりだが、ないよりずっといい。
そうだ、何もわからないよりはいい。少しは前に進んだはずだ。この先に何があるかはわからない。
先を歩く白澤さんの背を追う。少なくとも、この背を見失うことがなければ迷うこともない。はぐれることがないように、白澤さんの影を踏んで歩いた。
