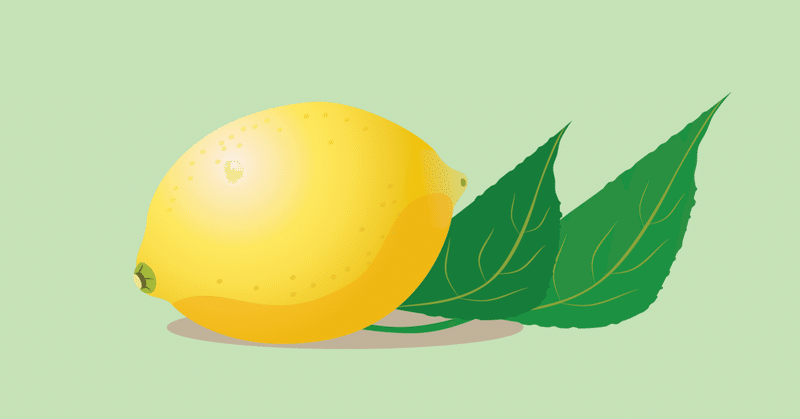
レモンソーダの哀しみに
私には年の離れたいとこのお姉さんがいた。
名前は今となっては憶えていない。私はお姉さんと呼んでいたし、お姉さんは私を名前で呼ばなかった。小さいからちぃちゃんとか、あなたとか、ねぇとか、一度も名前で呼んでくれたことはなかった。
十程も離れたお姉さんは、私の記憶の最後にあるところで精々高校生だ。大人ではなく、しかし子供でもなかったお姉さんとはもう長く会っていない。
***
お姉さんと会うのは決まって夏だった。
おじさんの家にはもっと頻繁に通っていたはずなのに、お姉さんの記憶ときたらすべて夏だ。
夏休みになって、子供っぽいボストンバッグに必要以上の着替えを詰め込み、海辺のおじさんの家に行く時、私はいつも以上におませだった気がする。埋められない年の差を背伸びで埋められると信じていたのはいくつまでだったのだろうか。
「あ、来たね。また大荷物ねぇ」
駅まで私が来るとお姉さんは左手に鞄を持ってくれて、右手を差し出してくれた。
きらきら光る指輪やイルカのブレスレット、派手に塗られた爪や細いベルトのバックル。そんな些細なものがとても洗練されて見えた。本当は私の方が都会に住んでいたのに、そういうことを知ったのはもっと大きくなってお姉さんと会わなくなってからだ。
同い年の友人にはもちろん都会的な子もたくさんいた。ポニーテールにした髪を茶色に染めたり、飴玉のようなヘアゴムを光らせたり、時には人気の男の子に媚びを売ったり、そういうことは悪いこととは思えなかった。日傘を差し、聞いたこともない料理を食べるのはごく自然なことで、私もいつかあんな風になる。それは確かに自覚していたはずなのだ。
「水着、持ってきた? 今日は暑いから海が気持ちいいよ」
塩水で色の抜けた長い髪を海風に任せ、褐色に焼けた肌を惜しげもなく日光に晒す。そんなお姉さんと可愛らしい友人、その両者の魅力がどのように違うのか、説明できるだけの言葉を私は持ち合わせていなかった。
***
お姉さんの部屋はお父さんと同じ煙たい匂いがして、そのことを告げるとお姉さんはいつだって内緒よ、と人差し指を立てた。
「大好きな人の匂いなのよ」
私以外にお姉さんの部屋で寝ることを許された存在がいる。そんなありふれた絶望を感じながら髪を乾かしてもらう一時がたまらなく幸せで耐え難く辛かった。
「そうだ、爪、塗ってあげよっか」
お姉さんはいつだって唐突で、思い立ったら止まらない。
引き出しを開けるたびに甘い匂いがして、それはお母さんの鏡台の匂いとは似ても似つかない。
「何色がいい?」
赤や青や黄色。そんなありふれた言葉だけで世界を区切ろうとする大人の大雑把さが時々許し難い。ざくろの色をした瓶を手に取ると、お姉さんはお揃いになるね、とにっこり笑った。
前屈みになると白いシャツからレースと控えめな膨らみが覗く。片膝を立てるとショートパンツの太腿がきゅっと伸びる。これをイケないものと見るのなら、その人がきっとイケない人なんだと思う。
***
昼下がりの日差しの中でタオルケットを蹴飛ばすと、お姉さんはお腹だけにそっとかけてくれる。二人で昼寝をしているのに、どうしてそううまい具合に起きられるのか、とても不思議だった。うっすら汗をかいた髪の匂いはとても無防備で、暑いとわかっていても抱きしめたくなる。
「喉乾いたでしょ。何か飲もうか」
赤いラベルの炭酸水はお姉さんのお気に入りで、私の憧れだった。透き通ったグラスに泡の鎖が上っていく。レモンの輪切りは嘘のように鮮やかで、私に知らなくていいことを教えてくれる。
お姉さん、ずっと一緒にいたいよ。
言っちゃいけない言葉をレモンソーダと一緒に飲み込む。
多分お姉さんはお姉さんじゃなくなって、私は子供じゃなくなる。それはとても自然なことだ。知らなくていいことを知らないといけないから、大人はわざと目を瞑るのかもしれない。
それなら、私は決して目を閉じないでいよう。
レモンが目に沁みて、それでも私は泣きながら大人になる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
