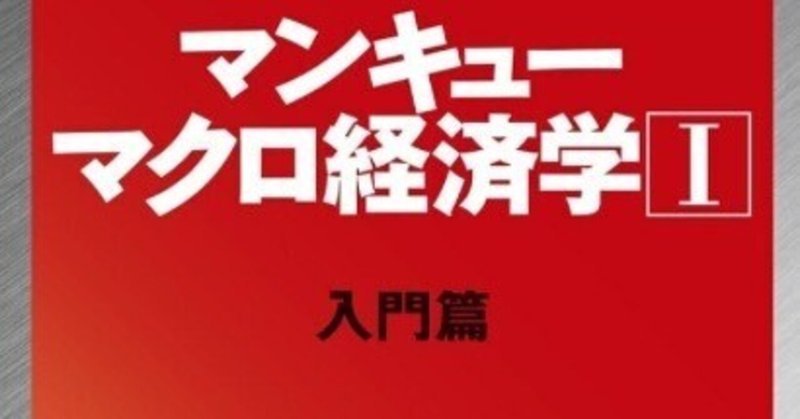
書記の読書記録2024.3.10『マンキュー マクロ経済学(第4版)』(全2巻) 『気象学の教科書 (気象ブックス047)』 『鏡映の数学』
1
『マンキュー マクロ経済学(第4版)』(全2巻)のレビュー
レビュー
「長期から短期へ」という方針でモデルを組み立てていく,マクロ経済学の定番の教科書。
もくじ
Ⅰ 入門篇
第1部 イントロダクション
第1章 科学としてのマクロ経済学
第2章 マクロ経済学のデータ
第2部 古典派理論:長期の経済
第3章 国民所得:どこから来てどこへ行くのか
第4章 貨幣システム:どのようなものでどのように機能するか
第5章 インフレーション:原因と影響と社会的コスト
第6章 開放経済
第7章 失業と労働市場
第3部 景気循環理論:短期の経済
第8章 景気変動へのイントロダクション
第9章 総需要Ⅰ:IS-LMモデルの構築
第10章 総需要Ⅱ:IS-LMモデルの応用
第11章 開放経済再訪:マンデル=フレミング・モデルと為替相場制度
第12章 総供給およびインフレーションと失業の短期的トレードオフ
Ⅱ 応用篇
第1部 成長理論:超長期の経済
第1章 経済成長の源泉としての資本備蓄
第2章 人口成長と技術進歩
第3章成長の実証と政策
第2部 マクロ経済理論とマクロ経済政策のトピックス
第4章 経済変動の動学モデル
第5章 安定化政策に関する異なる考え方
第6章 政府負債と財政赤字
第7章 金融システム:好機と危機
第8章 消費と投資のミクロ的基礎
終章 わかっていること,いないこと
2
稲津 將『気象学の教科書 (気象ブックス047)』のレビュー
レビュー
気象学の各論が1章ごとに示されている,全体的には平易な言葉遣いの多い入門書。気象予報士への入門としては充分な量と思われる。
もくじ
第1章 光 1.1 光と電磁波
1.2 散乱
コラム1 阿弥陀如来
コラム2 直達日射と全天日射
1.3 反射と吸収
1.4 放射平衡
コラム3 金星と火星の運命
1.5 気象衛星
コラム4 十種雲形
第2章 水 2.1 水蒸気の飽和
コラム5 洗濯物を干す方法
2.2 雲
2.3 雨
2.4 雪
コラム6 雪結晶の撮影
コラム7 ホワイトアウト・ブラックアウト
2.5 降水と雲の観測
コラム8 雪を掘る観測
コラム9 宇宙からのレーダー・ライダー観測
第3章 熱 3.1 気圧と気温
コラム10 気象骨董市①水銀気圧計
3.2 乾燥空気の安定性
コラム11 気象骨董市②百葉箱
3.3 湿潤空気の安定性
3.4 断熱図
コラム12 ヒートアイランド・クールアイランド
3.5 パーセル法による対流の診断
第4章 風 4.1 陸と海
コラム13 六甲おろし
コラム14 世界大紀行①緑のサハラ
4.2 天気図の風
4.3 上空の風
コラム15 世界大紀行②ジェット気流に乗って
4.4 物質の輸送
4.5 風の観測
第5章 渦 5.1 水平風と鉛直風
コラム16 霧の摩周湖
5.2 ハドレー循環とロスビー波
コラム17 十二支の方角
コラム18 世界大紀行③最北の不凍港ハンメルフェスト
5.3 温帯低気圧と前コラム19 世界大紀行④吠える40度、狂う50度、叫ぶ60度
5.4 台風
コラム20 富士山レーダーと台風観測
5.5 寒冷渦とポーラーロー
コラム21 成層圏の渦
第6章 対流 6.1 大気境界層内の対流
6.2 積乱雲を伴う対流
コラム22 雷
コラム23 飛行機事故とダウンバースト
6.3 メソ対流系
6.4 日本の夏
コラム24 世界大紀行⑤ウンカ、海を渡る
第7章 予報 7.1 気象予測
コラム25 世界大紀行⑥数値不安定の地、巡礼
7.2 気象情報の伝達
7.3 季節予測
コラム26 季節内予測
7.4 気候変動
コラム27 世界大紀行⑦水没国家の危機線
3
『鏡映の数学』のレビュー
レビュー
和書ではあまり見かけない,鏡映群に関する教科書であり,1章ごとの量を少なくして簡潔な説明にこだわっている。
もくじ
まえがき
第I部 幾何学的背景
第1章 アフィン空間ARn
1.1 ユークリッド空間Rn
1.2 アフィン空間ARn
1.3 アフィン部分空間
1.4 半空間
1.5 基底と座標
1.6 凸集合
第2章 ARnの等長変換
2.1 等長変換群の固定点
2.2 Isom ARnの構造
第3章 超平面配置
3.1 超平面配置の面
3.2 部屋
3.3 ギャラリー
3.4 多面集合
第4章 多面錐
4.1 有限多面錘
4.2 単純生成系
4.3 双対性
4.4 単体錘の双対性
4.5 単体錘の面
第II部 鏡,鏡映,ルート
第5章 鏡と鏡映
第6章 鏡系
6.1 鏡系
6.2 有限鏡映群
第7章 二面体群
7.1 2個の対合によって生成される群
7.2 定理7.1 の証明
7.3 二面体群:幾何学的解釈
第8章 ルート系
8.1 鏡と法ベクトル
8.2 ルート系
8.3 平面的ルート系
8.4 正ルート系および単純ルート系
第9章 An-1,BCn,Dn型のルート系
9.1 An-1のルート系
9.2 Cn型およびBn型のルート系
9.3 Dn型のルート系
第III部 コクセター複体
第10章 部屋
第11章 生成性
11.1 単純鏡映
11.2 折りたたみ
11.3 ギャラリーと道
11.4 C上のWの作用
11.5 道と折りたたみ
11.6 C上のWの単純推移性:定理11.6の証明
第12章 コクセター複体
12.1 コセクター複体のラベル付け
12.2 Wの元の長さ
12.3 反対の部屋
12.4 等方群
12.5 放物型部分群
第13章 剰余
13.1 剰余
13.2 例
13.3 剰余の鏡系
13.4 剰余と凸性
13.5 剰余:ゲート性
13.6 反対の部屋
第14章 一般化置換多面体
第IV部 分類
第15章 生成元と関係式
15.1 鏡映群とコクセター群
15.2 定理15.1の証明
第16章 有限鏡映群の分類
16.1 コクセターグラフ
16.2 可約鏡映群
16.3 ラベル付けされたグラフと双線形形式
16.4 正値グラフの分類
第17章 ルート系の構成
17.1 An型のルート系
17.2 Bn型のルート系(n≥2)
17.3 Cn型のルート系(n≥2)
17.4 Dn型のルート系(n≥4)
17.5 E8型のルート系
17.6 E7型のルート系
17.7 E6型のルート系
17.8 F4型のルート系
17.9 G2型のルート系
17.10 結晶条件
第18章 鏡映群の位数
第V部 3次元鏡映群
第19章 3次元空間の鏡映群
19.1 平面鏡系
19.2 鏡系による球面のタイル張り
19.3 球面三角形の面積
19.4 3次元空間における有限鏡映群の分類
第20章 正二十面体
20.1 構成
20.2 一意性と剛性
20.3 正二十面体の対称性の群
第VI部 付録
付録A 忘れられた技芸:黒板の図画
付録B 演習問題のヒントと解法
本記事のもくじはこちら:
学習に必要な本を買います。一覧→ https://www.amazon.co.jp/hz/wishlist/ls/1XI8RCAQIKR94?ref_=wl_share
