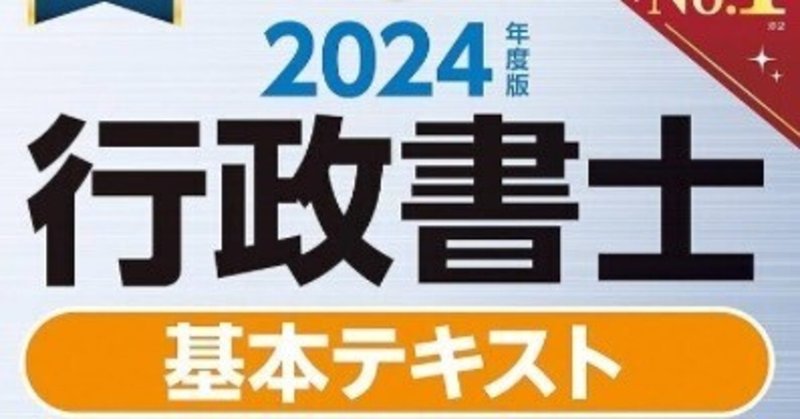
書記の読書記録2024.3.3『合格革命 行政書士 基本テキスト 2024年度 [試験科目変更に対応!知識量と読みやすさを兼ね備えた基本書](早稲田経営出版)』 『光科学の世界』 『マクロ経済学: 動学的一般均衡理論入門 (Minervaベイシック・エコノミクス)』 江沢・島『群と表現』
1
行政書士試験研究会『合格革命 行政書士 基本テキスト 2024年度 試験科目変更に対応!知識量と読みやすさを兼ね備えた基本書』のレビュー
レビュー
行政書士試験に必要な知識が一通り網羅されていることに加え,分冊となっていることで持ち運びやすさにも優れる参考書。
もくじ
第1分冊(憲法;行政法)
第2分冊(民法)
第3分冊(商法;基礎法学;基礎知識)
第4分冊(別冊六法)(別冊六法)
2
大阪大学光科学センター『光科学の世界』のレビュー
レビュー
レーザーやダイオード,光触媒反応などの最新技術をまとめた本。
もくじ
1. 特殊な光の世界
1.1 量子力学の不思議な光――量子もつれ光
1.1.1 はじめに
1.1.2 量子力学的重ね合わせ状態
1.1.3 量子もつれ状態
1.1.4 発生法
1.1.5 応用
1.1.6 まとめ
1.2 広い分野で活躍する放射光と自由電子レーザー
1.2.1 序論
1.2.2 高エネルギー電子が放射する光
1.2.3 放射光
1.2.4 自由電子レーザー
1.3 未来を拓く超高強度レーザー
1.3.1 はじめに
1.3.2 高強度レーザー
1.3.3 超短パルスレーザーの構成
1.3.4 超短パルスレーザーの要素技術
1.3.5 高エネルギー超短パルスレーザー装置
1.3.6 LFEXに用いられた要素光学素子技術
1.3.7 まとめ
2. 社会に貢献する光の世界
2.1 省電力で光る――発光ダイオードと半導体レーザー
2.1.1 はじめに
2.1.2 半導体の発光と発光波長
2.1.3 発光ダイオード(LED)
2.1.4 半導体レーザー(LD)
2.1.5 高性能LED、LD
2.1.6 新しい半導体レーザー:量子カスケードレーザー
2.1.7 まとめ
2.2 光ファイバー通信の長距離・高速化に向けて――光信号再生技術
2.2.1 はじめに
2.2.2 全光信号再生と光電気変換型信号再生
2.2.3 光QPSK信号の全光学的位相再生
2.2.4 光電気変換型DQPSK信号再生器
2.2.5 まとめ
2.3 エネルギー問題解決のホープ――太陽電池
2.3.1 はじめに
2.3.2 今日につながる太陽電池研究・開発の歴史
2.3.3 太陽電池材料
2.3.4 太陽電池の基本動作原理と変換効率
2.3.5 太陽電池の低コスト化を目指した取り組み
2.3.6 まとめ
3. 光で操る・光を操る世界
3.1 光エネルギーを用いた化学変換――有機光反応
3.1.1 概観
3.1.2 光異性化
3.1.3 環化反応
3.1.4 電子環状化反応
3.1.5 その他の光反応
3.2 光触媒――光エネルギーを化学に活かすキーマテリアル
3.2.1 光触媒反応とは
3.2.2 光触媒反応のメカニズムと特徴
3.2.3 光触媒反応の利用
3.3 レーザーによるイオンの冷却
3.3.1 はじめに
3.3.2 イオントラップ
3.3.3 レーザーによるイオンの冷却
3.3.4 レーザーによる冷却イオンの量子状態制御
3.3.5 冷却イオンの応用
3.3.6 おわりに
3.4 光の波長を変える非線形光学結晶
3.4.1 はじめに
3.4.2 波長変換の基礎
3.4.3 主な非線形光学結晶
3.4.4 おわりに
4. 光で探る世界
4.1 超精密な生産技術の基盤となる光計測
4.1.1 超精密とは?
4.1.2 長さの定義と光
4.1.3 変位の計測
4.1.4 寸法、形状の計測
4.1.5 さらなる超精密への挑戦
4.2 ミクロの世界を探索する――ミクロ分子分光
4.2.1 単一分子分光の黎明
4.2.2 単一分子計測から得られる情報
4.2.3 光学的単一分子計測装置
4.2.4 単一分子検出の材料科学への応用例
4.2.5 単一分子イメージング法のさらなる進歩:3次元分解能の実現
4.2.6 おわりに
4.3 エレクトロニクスとフォトニクスをつなぐテラヘルツテクノロジー
4.3.1 はじめに
4.3.2 テラヘルツ分光で何がわかるか
4.3.3 時間領域分光法とは
4.3.4 テラヘルツ時間領域分光法に用いられる発生・検出法
4.3.5 超短パルスレーザーとその波形
4.3.6 超広帯域時間領域分光法の現状
4.3.7 高強度化とさらなる発展
4.4 光で探索する超伝導の世界
4.4.1 はじめに
4.4.2 固体中の電荷応答と光学スペクトル
4.4.3 金属の光学応答
4.4.4 超伝導体の光学応答
4.4.5 まとめ
索引
3
林 貴志『マクロ経済学: 動学的一般均衡理論入門 (Minervaベイシック・エコノミクス)』のレビュー
レビュー
マクロ経済学のなかで動学的一般均衡理論に特化した教科書で,マンキューなどで古典モデルを身につけた後で使う予定。
もくじ
はしがき
数学的記法
第1章 ソロー・スワンの経済成長モデル
1.1 モデル
1.1.1 均斉成長
1.2 ソロー・スワンモデルの拡張
1.2.1 貯蓄率の内生化
1.2.2 不確実性の導入
1.2.3 人的資本蓄積の内生化
第2章 抽象的な一般均衡理論
2.1 2財ケース
2.1.1 消費と選好
2.1.2 限界代替率
2.1.3 予算制約と需要
2.1.4 交換経済の一般均衡
2.1.5 競争均衡の効率性
2.1.6 生産経済
2.1.7 限界変形率と限界生産物
2.1.8 利潤最大化
2.1.9 生産経済の一般均衡
2.1.10 競争均衡の効率性
2.2 一般ケース
2.2.1 選択と需要
2.2.2 限界代替率
2.2.3 予算制約と需要
2.2.4 交換経済の一般均衡
2.2.5 生産経済の一般均衡
第3章 一般均衡と集計
3.1 効率性と社会厚生関数の最大化
3.2 競争均衡に対応する厚生加重
3.3 代表的消費者
3.3.1 所得分布に依存しない記述的代表的消費者
3.3.2 所与の所得分配ルールにおける記述的代表的消費者
3.3.3 規範的代表的消費者
3.4 代表的企業
3.4.1 代表的企業の収穫一定性
3.5 代表的個人・代表的企業のもとでの競争均衡
3.6 財の集計
第4章 動学的一般均衡理論──2期間モデル
4.1 通時的消費と選好
4.1.1 選好の関数表現
4.1.2 割引効用選好
4.2 貸借経済
4.2.1 2期間貸借経済の予算制約
4.2.2 インフレーションの取り扱い
4.2.3 逐次的均衡
4.2.4 逐次的均衡からアロー・デブリュー均衡へ
4.2.5 公債に関する中立命題
4.3 生産経済
4.3.1 生産と企業
4.3.2 アロー・デブリュー均衡
4.3.3 逐次的均衡
4.3.4 逐次的均衡からアロー・デブリュー均衡へ
第5章 動学的一般均衡理論──多期間モデル
5.1 通時的経済における消費者
5.1.1 時間整合性の問題
5.1.2 定常割引選好
5.2 貸借経済
5.2.1 貸借経済におけるアロー・デブリュー均衡
5.2.2 貸借経済における逐次的均衡
5.2.3 逐次的均衡からアロー・デブリュー均衡へ
5.2.4 公債と課税に関する中立命題
5.3 通時的生産経済
5.3.1 通時的経済における生産と企業
5.3.2 通時的生産経済におけるアロー・デブリュー均衡
5.3.3 通時的生産経済における逐次的均衡
5.3.4 逐次的均衡からアロー・デブリュ―均衡へ
5.3.5 均衡動学とオイラー方程式
5.3.6 効率性と最適成長
5.4 無限期間モデル
第6章 動学的確率的一般均衡理論──2期間モデル
6.1 不確実な消費と選好
6.1.1 期待割引効用選好
6.2 条件付財の交換経済におけるアロー・デブリュー均衡
6.3 金融経済における逐次的均衡
6.4 証券価格と状態価格
6.5 逐次的均衡とアロー・デブリュー均衡
6.6 「代表的個人からなる純粋交換経済」における証券価格
第7章 動学的確率的一般均衡モデル──多期間モデル
7.1 不確実な通時的経済における消費者
7.1.1 期待効用定常割引選好
7.2 通時的条件付財の交換経済
7.2.1 アロー・デブリュー均衡
7.2.2 金融経済における逐次的均衡
7.2.3 逐次的均衡からアロー・デブリュー均衡へ
7.2.4 証券価格決定
7.3 不確実性下の通時的生産経済
7.3.1 通時的経済における生産と企業
7.3.2 通時的生産経済におけるアロー・デブリュー均衡
7.3.3 通時的生産経済における逐次的均衡
7.3.4 逐次的均衡からアロー・デブリュー均衡へ
7.3.5 均衡動学と確率的オイラー方程式
7.3.6 効率性と最適成長
7.4 無限期間モデル
第8章 内生的成長理論
8.1 宇沢=ルーカス型内生的成長モデル
8.2 アロー・デブリュー均衡
8.3 通時的生産経済における逐次的均衡
8.4 逐次的均衡からアロー・デブリュー均衡へ
8.5 逐次動学とオイラー方程式
8.6 効率性と最適成長
8.7 無限期間モデル
第9章 もう1つの動学的一般均衡理論──世代重複モデル
9.1 世代重複経済
9.2 競争均衡の非効率性と社会保障制度
9.3 生産経済
9.3.1 逐次的均衡からアロー・デブリュー均衡へ
9.3.2 均衡動学と資本蓄積経路
練習問題解答
関連図書
あとがき
索 引
4
レビュー
有限群と連続群に関する表現論について,吉川『群と表現』と似たような範囲を扱っている。
もくじ
まえがき
1 群の構造
1.1 群とは何か
1.2 部分群,剰余類,共役類
1.3 正規部分群と剰余群
1.4 同形と準同形
1.5 変換群
1.6 群の直積と半直積
演習問題
2 有限群の表現
2.1 表現の定義と同値性
2.2 既約表現
2.3 表現のテンソル積
2.4 指標
2.5 誘導表現
2.6 対称群の表現
2.7 表現の簡約――物理学への応用
演習問題
3 位相構造
3.1 開集合と閉集合
3.2 位相空間の部分空間
3.3 写像の連続性
3.4 直積位相
3.5 コンパクト性
3.6 連結性
演習問題
4 連続群
4.1 古典線形群
4.2 位相群
4.3 SU(2)とSO(3)
演習問題
5 線形Lie群とLie代数
5.1 行列の指数関数
5.2 古典線形群のLie代数
5.3 群の局所構造とLie代数
5.4 随伴表現
演習問題
6 連続群の表現
6.1 不変積分
6.2 コンパクト群の表現
6.3 SU(2)と回転群SO(3)の表現
6.4 線形Lie群の表現とLie代数の表現
6.5 sl(2,C)の表現
6.6 実Lie代数の複素化と複素表現
演習問題
7 ルートとウェイト
7.1 Lie代数のイデアル
7.2 半単純Lie代数
7.3 Cartan部分代数とルート
7.4 ルート系
7.5 複素単純Lie代数の分類
7.6 ウェイト
7.7 sl(r+1,C)の表現
7.8 素粒子の対称性
演習問題
付 録
A.1 古典線形群
A.2 線形Lie代数
A.3 古典線形群の基本群
A.4 Cartan行列
参考書
演習問題解答
索 引
本記事のもくじはこちら:
学習に必要な本を買います。一覧→ https://www.amazon.co.jp/hz/wishlist/ls/1XI8RCAQIKR94?ref_=wl_share
