
MH3コモンカードPauper評価
2024年6月14日発売の『モダンホライゾン3』のコモン評価です。
常に禁止カードを輩出してきたモダンホライゾン・シリーズの最新作ということで強力なカードが期待されていましたが、発売前から禁止確実というぶっ壊れから新枠では初の伝説のクリーチャーまでインパクト抜群の収録内容となっています。
強力なだけではなく、これは面白いことができそうだというカードも紹介しているので、何かの参考になれば幸いです。
白
《激震の目覚め》
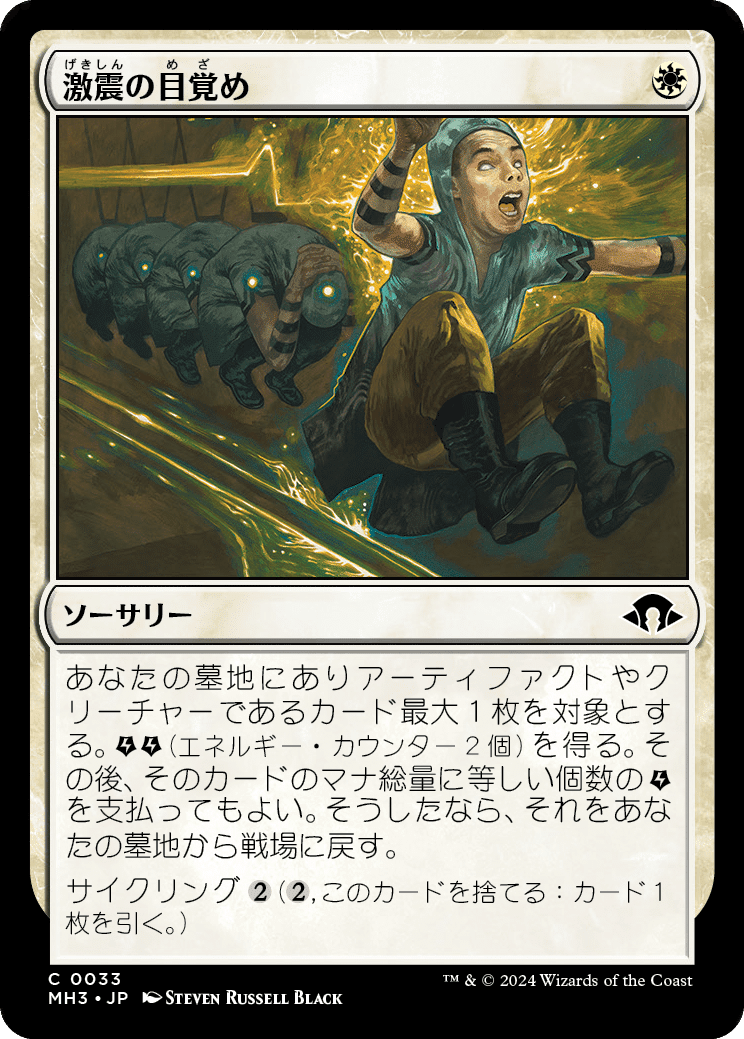
近年では白にも《再稼働》のような対象に制限のある軽量リアニメイトが増えていましたが、これは元になったであろう《発掘》にさらに寄せた性能となっています。
1マナという軽さはもちろん、対象のない状況でもサイクリングがあるので腐らない点も優秀ですが、他の手段でエネルギーを稼ぐことで重く強力なクリーチャーのリアニメイトにも対応しています。
《熟考漂い》を対象に取れるエネルギー5個に届くとかなり熱いですね。
一方で、単体だと2マナまでしか対象に取れず、少し範囲が狭い点が難点。
最悪、空撃ちしてエネルギーを稼ぐという手段もありますが、効率は悪いのでデッキをエネルギー軸に寄せるか、《湿地帯のグロフ》のような2マナでも強力なクリーチャーをリアニメイト先として準備しておきたい。
地味にアーティファクトも対象なので、墓地に落とした《税血の刃》を再利用するというのも面白いかもしれません。
《ニクス生まれの一角獣》

熊としてのスタッツを備えながら授与と教導によりサポート性能に優れています。
《民兵のラッパ手》に対応したパワー2なのも嬉しいポイント。
授与コストは4マナと重いものの修整値は悪くなく、教導によりエンチャント先以外も継続して強化できるとなると十分に見合う性能。
白系アグロでのマナフラッド受けとして良さそうです。
《スレイベンの魔除け》
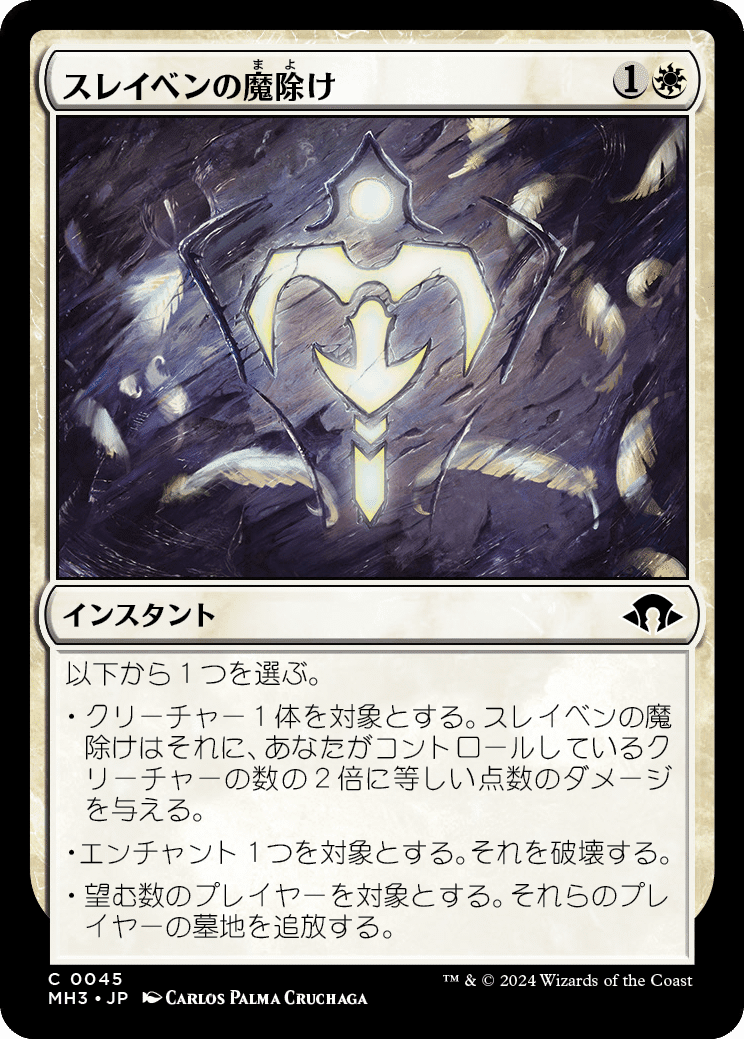
除去のモードは《出し抜き》系統ですが、タイミングに制限がなく、しかもコントロールしているクリーチャーの2倍のダメージというのが凄い。
他のレアリティを見渡しても同系統の除去でここまで効率が良いものは存在しません。
これにより3体程度のクリーチャーをコントロールしていれば環境のほとんどのクリーチャーを除去できる性能になります。
これまでにも《未達への旅》といった除去は存在しましたが、エンチャント破壊に弱かったり、ソーサリー・タイミングという制限が辛かったりしていたので、ダメージによる使い易い除去を手に入れたのは大きい。
このモードを軸に安定して確定の除去として使いたいのであれば、スタンダードのボロス召集の《門道急行の事件》と同様に、1~2マナの軽量クリーチャーを厚く採用したり、1枚から複数体のクリーチャー展開できるカードを採用することは必要でしょうが、やはりクリーチャー1体当たり2点と効率が良いため、他のモードを軸にワンチャン除去として使えれば十分という程度であればノンクリーチャーかそれに近い構成でもない限り運用に問題はなさそうです。
エンチャント除去については、パウパーには《血染めの月》のようなゲームに強烈に影響を与えるものは少ないですが、《黒死病》のようなエンチャントも存在しますし、相手の《未達への旅》で追放されたクリーチャーを解放するのに使えたりします。
現状でも《邪悪を打ち砕く》のエンチャント破壊のモードがそこそこ使われている印象ですし、こちらも活躍するでしょう。
そして、最後の墓地対策のモードですが、これが本当に画期的です。
インスタントであるため《古術師》や《戦慄の復活》に差し込むこともできますし、《拷問生活》のように墓地全体でシナジーを形成するカードにも劇的に刺さります。
これまで複数のモードの中に墓地対策があるというタイプは《黎明運びのクレリック》のように1枚程度しか追放せず、無いよりマシという類の性能でしかありませんでした。
それがタイミング次第では一発でゲームを決めるレベルの墓地対策になっているのは驚愕です。
総合して、白系アグロで赤や黒を触らない場合のメインの除去手段、あるいは白を触るアーキタイプで採用可能な汎用的かつ強烈な墓地対策としてサイドボードに居場所がありそうです。
青
《霊気の撃ち込み》

軽量カウンターとしての性能は及第点未満。
エネルギーを稼げる可能性もワンチャン存在するものの、《火消し》として使えれば十分、大抵はエネルギーを追加で消費して《マナ漏出》ということになりそう。
だったら最初から《マナ漏出》で良いよね感。
《語りの調律》

キャントリップとしての性能は及第点未満。
せめてドロー後にでも占術が欲しかったです。
現在のパウパーでは影も形もないエネルギー軸の構築が組めるようになるなら採用の価値ありですが、根本的にコモンのエネルギーは出力先が弱い(《霊気池の驚異》のようなカードは原則ハイレアリティでしか刷られない)ため、微妙。
黒
《呪われた匪賊》

《肉袋の匪賊》が2マナになり実質《残酷な布告》と並ぶ性能となりました。
トークンが生け贄にできないという点も裏目はありますが、概ね除去としては強化されていると言って良いでしょう。
使い道としては現在の《肉袋の匪賊》と同様に、再利用し易いクリーチャーというカード・タイプを活かし《拷問生活》等で繰り返し利用したいです。
また、2/2/1とギリギリではありますがアグロ適性のある水準になったので、サクリファイス軸の黒系アグロにも居場所がありそう。
《腸抜きの洞察》

《命取りの論争》以降、《高くつく強奪》の亜種が色々と作られ環境で活躍していますが、ある意味では正統進化とも言えるフラッシュバック付き。
純粋なアドバンテージ獲得力では最も優秀ですし、《胆液の水源》のような生け贄にする手段と併せてこそ価値のあるカードを採用する際には2回サクる手段となる点で安定性を大きく向上させます。
一方で、マナを加速したりライフを回復するということがないので、ゲームのレンジを伸ばすための除去はしっかりとスロットを確保しておかないと、フラッシュバックに届かずに特にメリットのない《高くつく略奪》になりかねないので注意。
総じて重量級の除去コントロール向け。
《刷新された使い魔》

中マナ域のコストで2/1飛行にEtB能力でアドバンテージ獲得と、白で例えるなら《鼓舞する監視者》ポジションのクリーチャーですが、何故か親和(アーティファクト)持ち。
アーティファクト・土地や《血の泉》のあるパウパーにおいて、これを1マナで唱えることは造作もないことです。
相手の手札が空のときにはドローになるという保険付きなのも意味が分からない凶悪さ。
自身もアーティファクトなので《マイアの処罰者》など後続の親和(アーティファクト)のサポートにもなり、《きらめく鷹》での回収にも対応。
飛行を持つことによる相打ち範囲の広さ、あるいは装備品を装備させた際の攻撃性能も高く、攻守に隙の無い優秀なクリーチャーです。
《改良版人体改造機》

類似の能力を持つ《しつこい標本》は、戦場に戻したところでサイズが貧弱すぎて生け贄えのコストにするくらいしかできず活用し辛さがありましたが、3/3であれば話が違ってきます。
コントロールのメイン盾である《ボーラスの占い師》を単体で突破できるので、戻して殴るだけで十分に活躍してくれます。
起動コストこそ4マナと重いですが《しつこい標本》ですら3マナを要求したことを考えれば1マナの増加は気にならないレベル。
黒系アグロのマナフラッド受けとして用意したり、切削シナジーを軸にする際のアドバンテージ要員としての可能性を感じます。
何気にクリーチャー・タイプがゾンビと優秀なのでゾンビ軸のアグロに組み込むのも強そう。
《枯死と開花》

除去としての性能は《最後の喘ぎ》なので凡庸そのものですが、除去でありながらクリーチャー強化というのはあまり例のない斬新な組み合わせ。
特に今回のセットで+1/+1カウンター関連のシナジーが大きく強化されているため、手札を消費せずに+1/+1カウンターを生み出すことには大きな価値があります。
シナジーありきの性能ではありますが、《喪心》などの汎用除去と枠を入れ替えることを検討できそう。
赤
《牙持つ炎》

欠色の付いた《溶岩コイル》なので現状の《溶岩コイル》の採用率を考えたら取るに足りない性能。
ということはなく、その欠色が非常に優秀で《ギルドパクトの守護者》や《真紅の見習い僧》のプロテクションを貫通できますし、相手からの対策カードである《青霊破》も受け付けず、《虹色の断片》でも無色は指定できないため、信頼性の高い除去となっています。
射程も《マイアの処罰者》や《王神の信者》に届きますので、ダメージ軽減に苦しめられる赤系アグロから《ギルドパクトの守護者》の対処に難儀するコントロールまでサイドカードとして広く採用されそうです。
《電気放出》
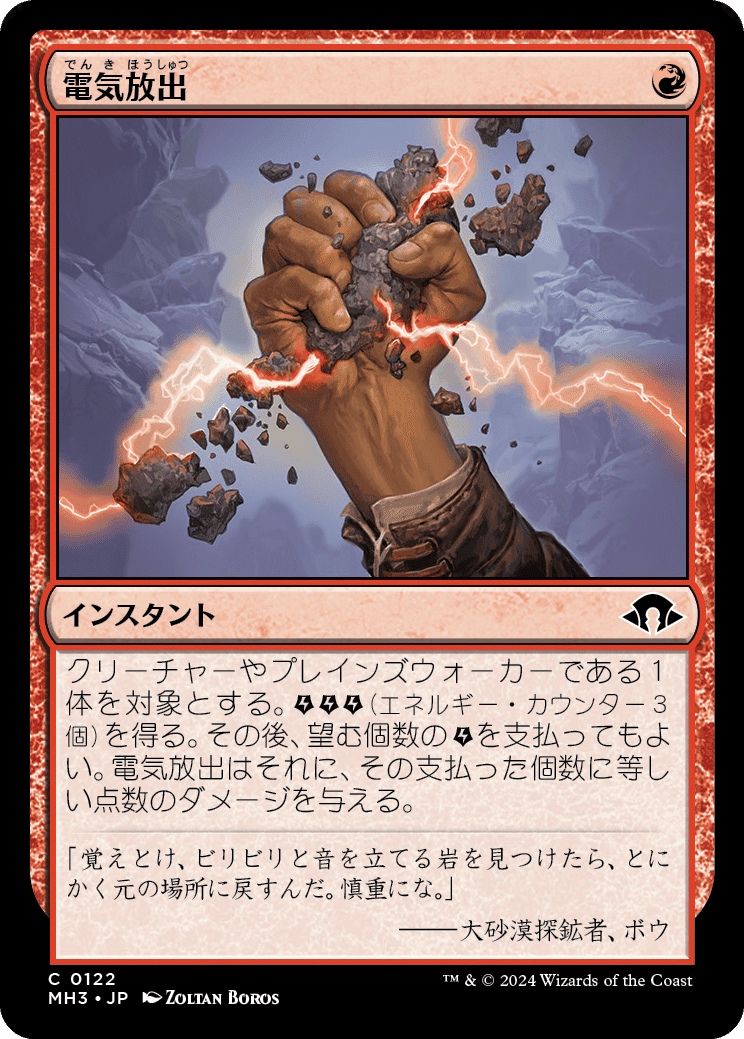
アンコモンの《蓄霊稲妻》の上位互換がいきなりコモンに来るとは驚き。
現状インスタントかつ1マナで確実に3点のダメージを出せる赤い除去は《稲妻》しか存在せず、余分なエネルギーを回せれば4点以上の出力を出せる可能性があることを加味すれば《稲妻》と比べても上位互換・下位互換の関係にない性能と言えます。
エネルギー関連のシナジーを用意できればさらに強力ですが、1枚目は1~2個のエネルギーしか消費しないというケースも往々にしてあるため、4枚採用が前提にはなるものの、単体でも運用は可能でしょう。
《不可能の一瞥》

衝動ドローとはいえ1枚のカードからの3ドローは(ストーム付きの《電位式リレー》を別にすれば)赤のコモンでは初。
最も3マナとそれなりに重く、同一ターンまでしかカードをプレイできないタイプなので、どこまでカードを増やす効果があるかは未知数。
一方でプレイできずに残ったカードの枚数分のエルドラージ・落とし子・クリーチャー・トークンを生成するため、最大3マナのマナ加速カードとしての側面もあります。
マナ加速から《乗り込み部隊》に繋げられ、続唱で捲れても痛くない衝動ドローという性質はこれまでになく、続唱との相性の悪さから衝動ドローの採用を敬遠していたというケースでは期待の新星となるかも。
《発明者の斧》

個人的に《ミラディンの悪断》入りの赤単を捏ねていた時期があるのですが、装備コスト3マナは《決闘のレイピア》より軽くなったといえど、まだまだ実用には足りない印象でした。
それが回数制限ありとはいえ0マナでの再装備が可能となり今度こそやってくれるかも?
エネルギーが切れた後は《カルドーサの再誕》のコストにしてしまえばいいですし、1枚目で残したエネルギーで2枚目を2回装備したりといったパターンも考えられるので、見た目より小回りが利くかもしれません。
《霊気追跡者》も先制攻撃を持ち装備品と相性が良いのでワンチャン?
《溶鉄の門番》

生きた《衝撃の震え》はトークンをばら撒くタイプの赤単のバフ要員からクリーチャーを出し入れする無限コンボのフィニッシャーまで夢があります。
特に蘇生を持っている点が素晴らしく、赤単であれば途中で除去されても最後の《カルドーサの再誕》→《ゴブリンの奇襲隊》のターンに蘇生させることで大きくリーチを伸ばせ、コンボであれば切削等を活用することで探しに行くことができます。
3マナという重さが《実験統合機》と併用する際のネックになりそうなのが懸念点ですが、大きく上振れを狙うのであれば枚数を抑えて赤単に採用したい。
《包囲破砕》

コモン初の刹那呪文という歴史的な価値があります。
アーティファクト対策のモードが追放でない点が非常に残念ですが、《マイアの処罰者》を対象にした際に《勢団の取り引き》のコストにされることなく除去できたり、《大祖始の遺産》に能力の起動をさせることなく対処するといったことが可能です。
クリーチャー強化のモードは、相手が構えているのが《稲妻》と確定しているときに《窯の悪鬼》に使ったら強いんじゃないですか、知らんけど。
(実際《岩石樹の祈り》のような被覆とまではいかずとも、何かしらの除去耐性を付与できないと解決した後に除去を投げられてしまうだけで、タフネスが+2しかされないことも含め刹那が活きる状況が限定的すぎる。)
結局1マナ軽い《似姿焼き》と同水準の性能という印象ではありますが、選択肢にはなり得そう。
《熾火魔道士、スコア》

遂にパウパーに登場した比較的まともな性能を持つ伝説のクリーチャー。
これでもうレジェンド初出のバニラ連中に頼る必要はなくなります。
戦場に出たときの4点ダメージがプレイヤーにも入るため、盤面の除去からフィニッシュまで使え、6マナという重さながら相応の性能はありそうです。
壮大の起動コストは、まんま《火炎破》のピッチコストのため、盤面への対処に使用するには窮屈ですが、最後のトドメとしては最高峰。
本体が着地した際の4点と併せて8点までが射程になると考えると相手へのプレッシャーはかなりのものになりそう。
壮大能力を打ち消すことは困難なため、打ち消しを握っていたとしても「1枚なら大丈夫」と通した瞬間に手札から2枚切られて12点で終了なんていう場面もあり得なくはない。
ステッカー禁止により6マナを捻出する方法には工夫が必要ですが、その点をクリアできるならフィニッシャー候補。
何気に《喪心》耐性が嬉しい。
緑
《日を浴びる繁殖鱗》

順応の数値はささやかですが、自力で3/3になりながら横にトークンを並べられるのでビートダウンには悪くない性能。
しかし、最も注目されているのは《サディスト的喜び》との無限コンボ。
エンチャントしたうえで能力を誘発させれば無限無色マナ&無限サイズアップになります。
即勝利に結び付けるには、戦闘で通したり《消耗の儀式》で投げ飛ばす等の工夫が必要ですが、どちらにせよコンボパーツがどれも軽いため序盤から狙い易く、奇襲プランとしては面白そうです。
《巨大な戦慄面》

比較的に最近のセットである『ファイレクシア:完全なる統一』のアンコモンだった《シルヴォクの戦座》が、同じコストでミラディンのために!(2/2のレベルに装備)、+4/+4、トランプル付与で装備コストが7マナだったので、それと比較して修整値と装備コストが大幅に強化されています。
《東屋のエルフ》からのマナ加速を軸とする戦略では、フィニッシャーを対処されたあとジリ貧になっている状況をたびたび見かけますが、これがあれば遊んでいるマナクリーチャーを強化して攻めを継続できるかも。
2枚以上を引きたくはないですが、1枚入れていたら助かったということがありそう。
《進化の証人》

3マナで出した瞬間は貧弱ですが、その後に2マナでサイズアップしながらアドバンテージを獲得する様は往年の《棲み家の防御者》を彷彿とさせます。
カウンターを乗せる瞬間に除去をされると弱いものの、+1/+1カウンターを乗せる手段があれば何度でも墓地からパーマネント・カードを回収できるため、一度パターンに入ると延々とアドバンテージを稼ぎ出します。
《獰猛器具》との組みあわせは2マナ1ドローと悪くない効率でドローを稼ぎ、ついでに本体のサイズがどんどん上がっていく様はまるで往年の《不屈の追跡者》。
《戦旗皮のクルショク》と併せるとインスタントのタイミングで2マナにつき+1/+1カウンターが2個の効率で巨大化するため、うっかり通すと一瞬でゲームが終わるなんてこともありそう。
また、《サディスト的喜び》とも《野生の朗詠者》や《ブラッド・ペット》との組み合わせで無限サイズアップが可能。
シナジーなしでも強く、強力なシナジーも豊富、これからの緑絡みのミッドレンジの根幹になり得る逸材。
《ニクス生まれのハイドラ》

元レアの《キヅタの精霊》が霞む圧倒的な本体性能を持ちながら、授与による他クリーチャーの支援もでき、脳筋でありながら頭脳派、ゴリラでありながら得意技はサポートといった風体。
両方の性質を活かすには大量のマナを出せ、かつ、授与先のクリーチャーに困り難いということで《ティタニアの僧侶》を軸にしたエルフが良さそうに見えます。
成長した《エルフの先兵》にトランプルによる突破力を付与できたり、《紆余曲折》でヒットする点もエルフと良く噛み合っています。
エンチャントであることは割られ易さに繋がってはいるものの、《精霊との融和》でヒットするというメリットにもなりますので、上手く利用していきたい。
多色
《頭蓋槌》

パウパーのフォーマット成立と同時に制定された唯一の初期禁止カードである《頭蓋囲い》をそのまま生体武器にしたかのような性能。
色拘束こそ厳しいですが、何気にタフネスも+1されることもあり、装備コストの2マナは何かの間違いかと思うほど軽いです。
通常の生体武器はコストに対する修整値が弱く、トークン自体は戦力にカウントし辛いという問題がありましたが、これは一瞬でパワーが無視できない数値に上昇するため弱点を完全に克服しています。
またシナジーに目を向けると、現在のパウパーで専用にデッキを組めば2桁の修整値に届くことは余裕であり得ますし、0/0のトークンは使い捨てても痛くないため《投げ飛ばし》との組み合わせは非常に低リスクかつ高リターンとなります。
消耗戦の末に《頭蓋槌》が着地→トークンを《投げ飛ばし》→《羽ばたき飛行機械》に装備して殴って20点オーバーなんてゲームも容易に想像できますね。
ちなみに、発売前から既に禁止カード入りが検討されているという情報もあるため、今後の動向には注意が必要です。
《広がる軟泥》

これ自体はアドバンテージを稼ぐわけでもなく、一見して凡庸なクリーチャーですが、単体で3ターン目に展開から4ターン目に5/5で殴れるというのは悪くないクロックですし、その後は6/6、7/7とマナを使うことなくサイズを上げていけるので、見た目以上にゲームを決める力がありそう。
最も、実際のところ単体の性能云々より一緒に採用されるであろう《進化の証人》のトリガー手段として優秀というのが本音。
単体でも相手を倒せるだけの圧力を持ちつつ継続的に+1/+1カウンターを乗せることが可能というのは他にはない性能なので、シナジー込みで採用を検討しても良さそう。
《忠実な番犬》

単純にスタッツが優秀。
このコストとサイズだと《番狼》や、コモンだと《議事会の招集》から出るトークンを想起させられますが、警戒により盤面への影響力が向上しています。
性能の通り、出して殴る以外の活用法はありませんが、強いて言えば《大霊の盾》をエンチャントすると、そのサイズと警戒を存分に活かすことができそうです。
2/3/3でありながら《民兵のラッパ手》でヒットするのは狡い。
《噛み付く虚空袋》
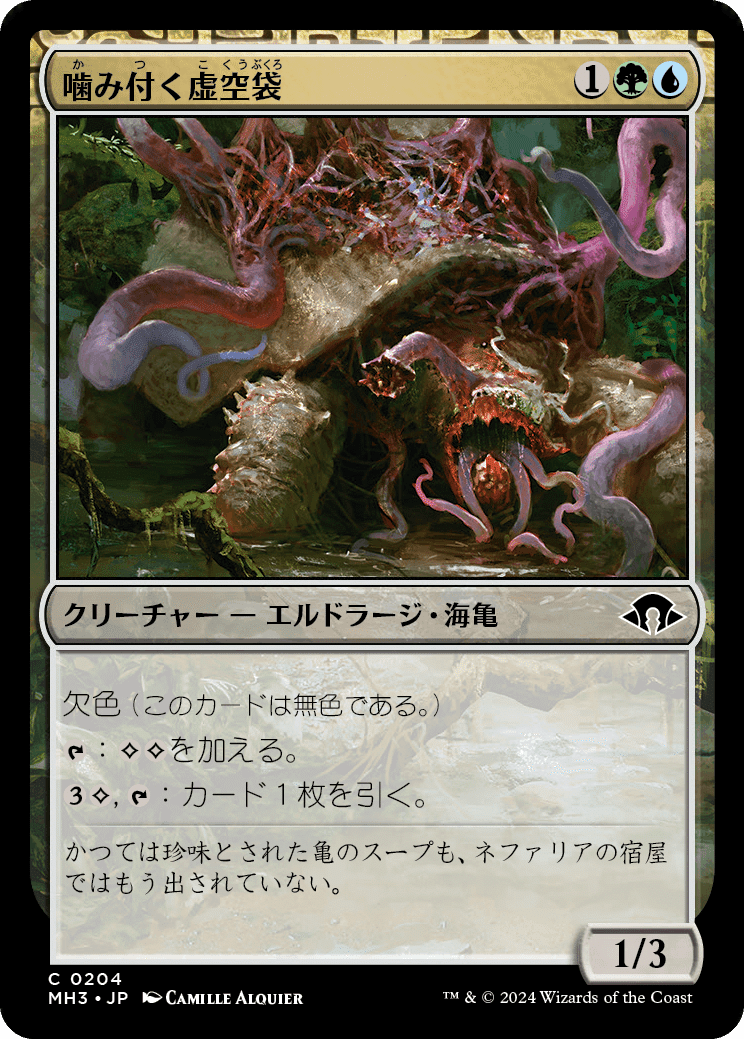
正直《稲妻》されるだけでだいぶ苦しいようには見えますが、2マナ加速のマナクリーチャーということで存命した際のリターンは大きいです。
また、最終的には毎ターンのドローソースとなれる点も強く、ランプ戦略に非常にマッチしているのは間違いありません。
やはり、除去されたときの裏目が大きく、手放しに強力と言い切れませんが、ワンチャンを感じさせる性能です。
《こそこそサクサク》

ノーコストで2/1飛行が出てくるのは強力ですが、如何せん墓地に落とす方法が悩ましく、個人的には”面白そう”の域を出なそうではあります。
2/2/1として出してから相打ちなどで落とすのは悠長かつ旨味も少ないので、切削で墓地に落としたりルーティングを活用するなどして上手く回していきたい。
3枚ドローする方法は《渦まく知識》が簡単ですし、《綿密な分析》のフラッシュバックで大丈夫なので難易度は低いですが、さすがに毎ターン安定させるというのは無理なので、クロックの面で頼り切るのは難しい。
フェアリーではありますが、《呪文づまりのスプライト》を採用するデッキとは目指す方向性が違っているようにも見えるため、誰か上手い人が良いアイディアを出してくれれば感。
《のたうつ蛹》

唱えるだけでエルドラージ・落とし子・クリーチャー・トークンを2体も生成するため、4マナですが最低限《対抗呪文》への耐性があり、通ってしまえばサイズアップにより4/4/5到達というスタッツとなります。
その際に出せるマナを有効に使えるなら実質3/4/5到達や2/4/5到達、2枚目以降が生み出すトークンも考えればコストに対して驚異的なサイズとなります。
サイズ以外には取り立てて優秀なところはありませんが、欠色により《古きものの活性》でヒットしたり、トークンと併せて《ギルドパクトの守護者》を《バジリスク門》で強化されても3回はブロックできたりというのは覚えておくと使えそうかも?
土地
《豊潤地帯》

他9種の全10種サイクル。
基本土地を4種類以上採用するのでなければ無色マナの出せる《進化する未開地》。
マナベースとしては任意の2色を出せる土地よりやや弱いですが、それでも『ニューカペナの街角』の《貴顕廊一家の劇場》などは偶に見かけるため、十分に採用に足りるでしょう。
特に色が3色とも合致していると『イコリア:巨獣の棲処』のトライオームのようにマナフラッド時のサイクリングに回せるため強力。
また、パウパーの多色デッキでは《ロリアンの発見》による島サイクリングがマナベースとして重要な働きをしていることに加え、壁として《ボーラスの占い師》を立てる場面も多く、序盤から無色マナの使い道がある程度は存在するため、捻出できる無色マナは立ち上がりを円滑にしてくれます。
また、無色土地として利用することでフェッチの起動を任意のタイミングまで引っ張ることができ、最高のタイミングで《渦まく知識》→フェッチをできる可能性も高まります。
『モダンホライゾン2』の橋のように見るからにヤバさが漂っているというわけではないですが、パウパーの多色デッキのポテンシャルを底上げしてくれそうな良い調整。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
