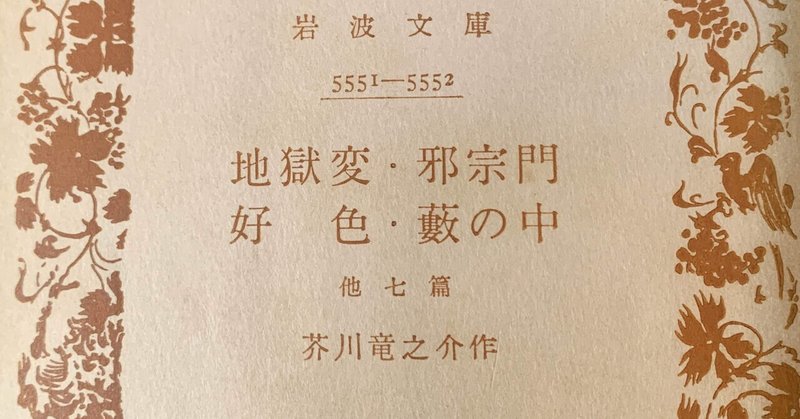
賞レース
年に二回の芥川・直木賞レースがありました。私は賞の受賞には作者の思いだけでなく、出版社や諸々の関係者思惑があるし、また作者自体がそれなりに知名度がある人だと、メディアが担ぎ出すこともあるから、作品自体の評価とは直接授賞は関係ないと思っています。
まあ賞の創設者の菊池寛氏も、商売で始めたわけだからね。
それでも、特に受賞作であるかどうかは関係なく、各審査員の書評を読むのは面白いです。作品より審査員自身の力量や視点がよくわかります。
もちろんこのタイミングで今まで縁のなかった作家に遭遇するという嬉しさはありますね。同様にノーベル文学賞で全然知らなかった作家が受賞されると、どんな本なのか図書館で借りたり、翻訳されていない作家だと急遽翻訳されるのも楽しみです。
昨年夏の芥川賞候補作であった小砂川チトさんの「家庭用安心坑夫」も全く知らない作家で、とても面白く次作以降も期待できる人だと思いました。
氏の本を図書館で目にしてパラパラとめくり、これを読んでみようと思ったのは、昨年暮れに「林修のニッポンドリル」というバラエティ番組でたまたま見た「学者と巡る巨大廃墟遺産 神子畑選鉱場跡」の光景が記憶にあったからかもしれません。番組は
「兵庫県の神子畑選鉱場跡を探索。円形状の謎施設の正体は巨大濾過装置。錫など重要な金属を選別した後、泥と水になったところで、このシックナーと呼ばれる濾過装置で再利用できる水を作り出す装置。さらに今回、特別に選鉱場に運ぶ鉱石が採掘されていた明延鉱山の撮影許可も下り、坑道を調査。明延鉱山の深さはなんと東京タワーが3つ分の約1000m。網目のように広がった坑道の総距離は約550kmにも及んでいた。」
というものでしたが、これがまさに小砂川チトさんの主要な舞台の一つ「尾去沢鉱山」(こちらは銅山)に書かれている光景に重なったからで、イメージしやすかったこともあるかもしれません。
そうそう、この中に主人公の「小波」が自衛隊の大規模接種センターでワクチンを打つシーンがあります。その場面で、そうじゃな~と感じたところを抜き出すと。
「接種を終えた小波は吐き出されるように建物の外へ出て、どこかウットリとしたままで歩き出す。注射のショックも相まって、小波は半ば興奮、半ば放心していた。自衛隊ってやっぱりすごい、と思いながら、少し口もとを緩ませて周囲を見回す。ここでは誰もが、キビキビと立ち働いていた。生き延びようとする明るい意志のようなものに満ちあふれていて、小波はなんとなく、今ここにいる人間のなかに今日明日にでも死のうと企てているひとはいないのだな、ということを考えずにはいられなくて、どうにも不思議な気持ちがしたし」
というところ。そう言えば私も接種会場で受けたが、その会場ではなんとなくダラダラした雰囲気と、「早く早く」という担当者たちの機械的な動きしか印象に残らなかったが、よく考えたら小砂川氏の指摘にあるように、あの会場にいた人は「今日明日生きよう」という大なり小なり「生」に執着している人たちの集団だったのだということに気がつく。う~ん…
さて、今回の受賞者はこちら。
結構なことだが、皆さん存じ上げず、読んだこともないので、図書館に予約を入れようとサイトをあけました。すると、もう何十人も予約が入っていて断念しました。そんなに焦る必要はない、小砂川チト氏みたいに、いずれ何かの拍子に「あっ、読もう」という機会が来るのだと思っています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
