
手話通訳者全国統一試験「ことばの仕組み」2020過去問⑭解説〜手話表現〜
2020年度手話通訳者全国統一試験の過去問について、参考文献をもとに独自に解説をまとめたものです。
問14.ことばの仕組み<手話言語>
手話の構成要素には手の形の位置と動きがあります。構成要素のうち二つが同じ例を下記の(1)〜(4)の中から正しいものを1つ選びなさい。
(1)「家族」「人々」
(2)「黄色」「なるほど」
(3)「作る」「食べる」
(4)「良い」「病気」
問題解説
(2)が正しい。
手話はだれが使うことばなのか
手話は耳が聞こえない人(ろう者)が集団を作ってお互いに意思を通じさせようとした時に自然に生まれた言語である。聞こえる人たち(聴者)が周りで話されている音声言語を自然に身につけるように、生まれた時から手話が使われている環境の中で育ち、自然に手話を身につけた手話の母語話者たちはネイティブ・サイナーと呼ばれる。聴覚障害児の出生率はおおよそ千人に一人と言われ、両親がろう者の家庭でろうの子どもが育つ確率は高くない。ろうの子どもの90%以上が聞こえる親である。
逆のケース、つまり両親が聞こえなくても生まれた子どもが聞こえる場合はある。ろう者の親の下で育った子どもたちをコーダ(CODA:Child of Deaf Adults)と呼ぶ。彼らの中には手話を母語として持つものもいれば、他の兄弟姉妹が手話を使えると、そのきょうだいに頼って親との会話を通訳してもらって自分はほとんど手話がわからない者もいる。
耳が聞こえない人すべてが日本手話を使うわけではない。聴覚障害者として、障害者手帳を持つ人の数は2019年現在約34万人だが、手話を日常生活で使っている人はそのうちの18.9%の6.4万人である。生まれた時から耳が聞こえず、ろう学校に通って手話で生活してきた人もいるが、途中で失調した人も含まれる。
日本手話の「音」
日本語の単語は、母音ひとつからなる単語(ア−唖、イ−胃、ウ−鵜、エ−絵、オ−尾)もあるが、母音と子音の組み合わせによってできている(アカ−赤、サカ−坂、カサ−傘、サカ−坂)。母音一つからなる単語もある(アイ−愛、イウ−言う、ウエ−上)。aka(アカ)と saka (サカ)のようにsの違いだけでまったく別の単語になるように日本語にとっては、重要な意味の違いをもたらす。
手話の場合、通常3つの要素の組み合わせが単語を作り、それらは手話の「音韻」と呼ばれている。3つの要素とは、手の形(手型)、表される場所(位置)、手の動き(動き)で、それに手のひらの向きを加えて4つの要素と考える場合もある。
aka(アカ)と saka (サカ)のように一つの音韻が違うとまったく意味が変わってしまう単語の対のことをミニマル・ペアという。手話の例をみてみよう。
<男>と<女>は手型が親指か小指かで<男>と<女>が区別される例で、位置と動きは共通している。
<男>の手話表現
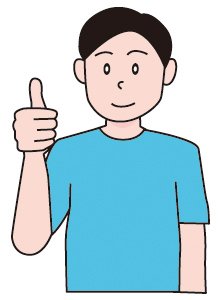
<女>の手話表現

<買う>と<売る>は、お金を出す手型が体の前に出ていくときは<買う>、体の方に近づいてくる場合は<売る>になるという動きが違う例である。
<買う>の手話表現

<売る>の手話表現

<見る>と<言う>は同じ人差し指を一本立てた手型が目の位置から前に出ると<見る>、口から前に出ると<言う>になるという位置の違いによる例である。
<言う>の手話表現

「手話=手の動きがすべて」か
手で話すと書くと手話だが、実際に一番大事なのが手の形と動きかというと、そうではない。顔の動きの方がずっと大事なのだ。顔のパーツである目、眉、口、舌、頬、あごなどが重要な文法の役割を持っている。見ることによってはじめてコミュニケーションが成立する手話では、目の役割はとりわけ重要で、目を見開いて眉があがっている顔、そしてあごが体の方にひきつけられている顔は疑問の顔である。この顔は、相手にイエスかノーかの返答を求めている。疑問文であると理解できないと、次のコミュニケーションが成立しない。
顔の動きは文法を担っている。表情というと悲しいと時には悲しい顔、うれしい時にはうれしい顔、といった感情の表情と思われがちだが、手話の顔の動きが担っているのは文法であるため、個人差はない。
イエス/ノー疑問文の顔はだれが表しても同じイエス/ノーの顔である。また、いつ、どこで、だれが、というようなあらたな情報を求めるWh疑問文には別の動きがある。基本的には、眉あげ、目開き、細かい首ふりである。手が動いている胸のあたりに集中するのではなく、ぐっと引いて視野を広げて、目や眉、頭の動きを見る必要がある。
✔木村晴美・岡典栄,手話通訳者になろう,白水社,2019
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
