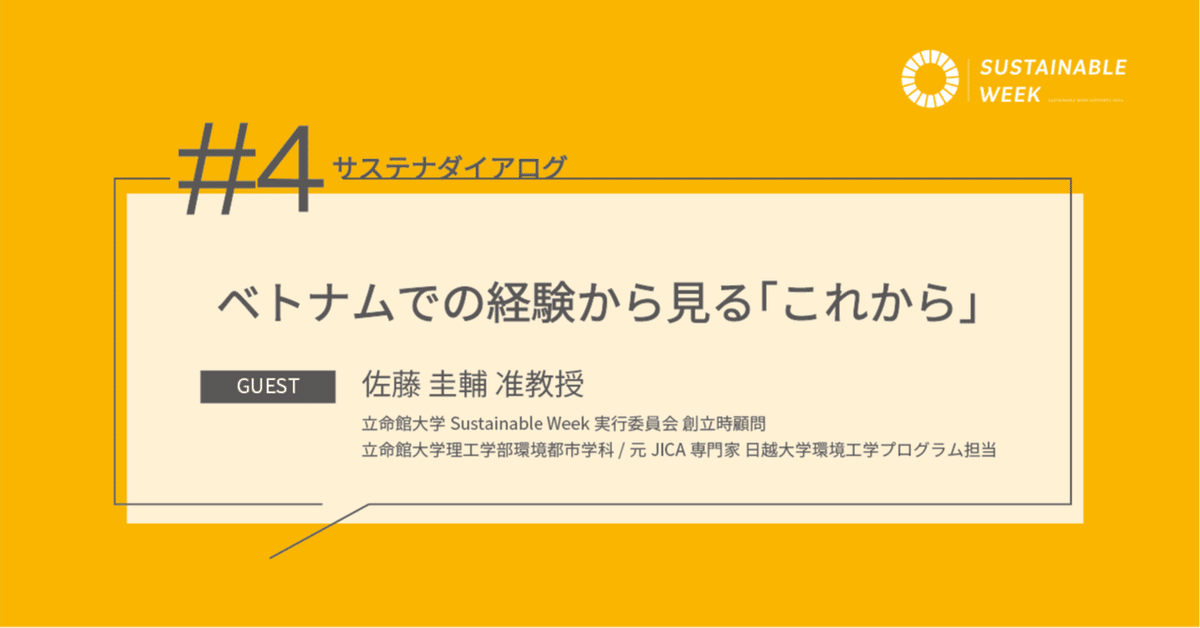
【サステナダイアログ#4】ベトナムでの経験から見る「これから」
こんにちは。Sustainable Weekの藤枝 樹亜です。
Sustainable Weekメンバーが毎回ゲストをお招きして、SDGsやこれからの社会について対話する企画が「サステナダイアログ」です。
今回は、Sustainable Weekの藤枝 樹亜と中西 優奈が、佐藤圭輔 准教授 (実行委員会創設時顧問/立命館大学理工学部環境都市工学/元JICA専門家 日越大学環境工学プログラム担当 )をゲストにお招きし、お話を伺いました。
「ベトナム」という共通点

佐藤 藤枝さんはベトナムに住んでいたと伺いました。ホーチミンとハノイどちらに住んでいたのですか?
藤枝 ホーチミンの方で5年半ほど暮らしていました。佐藤先生はどちらにお住まいだったんですか?
佐藤 私はハノイに住んでいました。2年間住んでいて、つい最近帰ってきたばかりなんです。
中西 今日は2人の共通点でもあるベトナムのことについて話を聞けたらと思っています。今でローカルに活動してきたSustainable Week実行委員会ですが、今年はグローバル展開させようという話が出ています。ベトナムのように日本では発展途上国と捉えられているけど実際は想像よりずっと発展している国もありますし、SDGsに取り組む上でグローバルな視点で様々な国の話を聞く機会を作りたいなと考えています。
佐藤 中西さんはハノイに来たことがあるんでしたっけ?
中西 はい。予想よりとても発達していました。「Grab」というタクシーのサービスが普及していたり、高いビルがたくさんあったりして驚きました。

佐藤先生が住んでいたハノイのマンション

マンションから見える街の様子
佐藤 発展しているところもある反面、やはり途上国的な側面もありますよね。藤枝さんはそういう面も見てきたんですか?
藤枝 私は両親にいろいろなところに連れて行ってもらっていたので、普通なら行かないようなローカルなご飯屋さんに行ったり、孤児院に行ったりしたこともあります。なかなか珍しいタイプだとは思います。
中西 私はハノイのような都市部や農村の方にも行ったりしました。一緒に行動していたメンバーの1人がパクチーのようなローカルな食べ物が合わなかったみたいで、日本食を食べに行くことが多かったです。
佐藤 私もパクチーがダメなので、絶対に抜いてもらうようにしています。パクチーの発音がなかなか通じないので写真を見せたり、厨房まで行って指をさして伝えたり、野菜全般を抜いてもらうよう伝えていたりしました。日本人はこういう交渉力がない人が多いですよね。伝えようという意思が強ければなんとかなるんですけどね。
中西 そう考えると日本の飲食店はとても親切ですよね。ラーメン屋で紙にネギあり・なしって書いて伝えられるようにしてあるところとか。
佐藤 向こうに住んでいるとそういうことがないので、精神的に強くなっていくんですよね。
藤枝 そうですね。日本以外の国に住むことのメリットの1つかもしれないですね。それまで気が付かなかった日本の良さにも気づけますし、日本に足りないところ・欠けていることにも気づくことができるようになると思います。
Otsu Water Planet -水でつながる滋賀とベトナム-
佐藤 ベトナムといえば、去年小学生を呼んで滋賀とベトナムを「水」で繋ぐ、みたいな企画にオンラインで参加したんですよ。
その企画に関係している動画をSustainable Week実行委員会の協力のもとつくったと聞きました。動画の出来が良かったのでそのままにしておくのはもったいないと思って、私が立命館の広報課に広報を頼んだところ、それを見た人から「本当に学生がつくったんですか?」というような反響の声があったらしいです。
中西 私は動画制作には関わっていなかったのですが、制作している人をみていたので、製作期間も長くとても細かいところまでこだわって作っていた印象があります。
佐藤 そのようなこともあるみたいなので、これからはSustainable Week実行委員会での成果は大学を通して広報してもらえるように頼んでもいいかもしれませんね。そして今回のイベントを通して、別の学部や学科との連携ができたのもよかったと思っています。
あのイベントでは科学の情報を入れながら仕上げたい意図があったと思うのですが、本来はそこだけではなく市民の水に対する認知や本当に水の処理が必要だと思うかなども取り入れたい情報ではあるんですよね。日本は雨水は多少利用してはいるのですが、そもそも「再生水を使った方が良い」という市民的なマインドがないんですよね。
その理由は水に困っていないというところにあります。再生水を使っていこうと考えたときに、技術的には可能でも誰も使わないんです。市民がそれが大事だという風に考えていない、もしくは考えるための機会が十分に誘導されていないのです。一方でベトナムのような国は、飲み水にお金を出して買うので「お金で水を買っている」という感覚があります。
中西 日本では水はひねればでてくるものという感覚ですね。蛇口から出てくる水がきれいでなかったらクレームが入りますよね。

ベトナムでは水は「買うもの」という感覚(ウォータサーバー)
佐藤 そうです。そういうところからも人任せにしていることが分かると思います。水を大切にする。というマインドを持っている人は少ないです。私は何度かシンガポールに行っているからわかるのですが、シンガポールではそのマインドを誘導しようとしていて、教育で水に対する認識を変えようとしています。そのような認識が海外では広がっているのですが、日本ではなかなか浸透していないんですよね。きれいな水が出るのが当たり前で、誰がつくっているのか、これからどうしていかなければならないのかということを考えている人は少ないです。
中西 環境問題を考えるときに雨水を使うなどといった案は出ますけど、実際に日本でそれをやるかといわれるとやらないですよね。やった方がいいことは理解しているけど、今の便利な状況ではなかなか実行されないと思います。
佐藤 苦労しなければならないというわけではなく、その考え方が当たり前になればいいですよね。
藤枝 日本ではなかなか水の問題などは自分事にならない問題がありますね。
Otsu Water Planet 動画
Part1「君に知ってほしい水のこと」
Part2 「水道水が届くまで」
Part3「みんなが知らない浄水場のセカイ」
ベトナムに住んでわかったこと
佐藤 ベトナムに住んで分かったことがあって、ベトナムのような途上国は自己責任が大きい国だけれども共助も成り立っている国なんです。逆に日本のような発展している国はシステムを強靭につくって失敗を防ごうとするところがあります。例えばベトナムは車とかの保険が全然なくて、その代わりに誰かがけがをしたらみんなでお金を出し合って医療費を捻出するんですよ。
中西 日本はたくさんの保険がありますよね。
藤枝 日本人は「迷惑をかけることはよくない」と思う人が多い気がしますが、ベトナムでは「迷惑をかけあって、助け合う」というマインドの方がメジャーですよね。
佐藤 日本はルールを守る風潮がありますね。ルール主義・計画主義という感じですよね。
藤枝 そういう違いも面白いですよね。日本では「グローバル」というとアメリカやヨーロッパが連想されがちだと思いますが、Sustainable Week実行委員会ではベトナムのような発展途上国にフォーカスしてもいいかもしれません。
Sustainable Week の始まりとこれから
藤枝 佐藤先生はSustainable Week実行委員会創設の時の顧問でいらっしゃるんですよね。
佐藤 上田さんや地域連携課の安原さんが最初にアイデアを出したと思うのですが、そこからお話をいただいて顧問を引き受けることになりました。私は何かあったときにサポートをする役目、くらいのスタンスでいました。今も取り組みの中で役に立てることがあればやりますよ。
藤枝 そうなんですね。私は今年からSustainable Week実行委員会に入ったので創設時のことは全然知らないんです。是非、何かあったらよろしくお願いします。
佐藤 SDGsの取り組みといえば、他大学にも協力してくれそうな先生を知っているので必要であれば紹介させてもらいます。
藤枝 ほかの大学と何か一緒にできたら楽しそうですね。私もアイディアを考えてみようと思います。
さいごに
最後までお読みいただきありがとうございます。サステナダイアログではこのようにこれまでに私たちの活動に関わってくださった方をゲストにお迎えしお話しさせていただいています。フリーアジェンダのため、ゲストによって様々なトピックで盛り上がっています。ぜひほかの回もご覧いただけますと幸いです。
以上、サステナダイアログ#4でした!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
