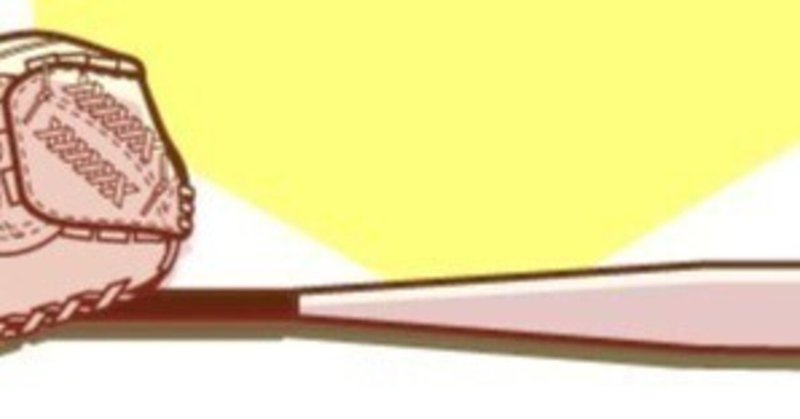
「小説 雨と水玉(仮題)(20)」/美智子さんの近代 ”偶然の再会”
(20)偶然の再会
確かにたか子の言う通りだった。
もうあれから二年半、就職してからでも一年半になろうとしているのに、過去にこだわっているのは他ならぬ自分だった。
もうこだわるのはやめよう、これからのことを考えて前を向いて歩いていかなければいけないんやわ、そう思ったら気が晴れてきた。
その日は期末の棚卸の忙しい時期を終えた十月十三日、梅田のお店でなく豊中の卸先に直接立ち寄る予定で八時過ぎに家を出た。
いつものように曽根駅の改札を通り、上り線ではなく下り線に向かって構内の踏切を渡って階段を下りホームへ登り始めた時、こちらに向けて会釈をしている人が。
美智子はハッとして胸が閊えたようになった。そこにいたのは啓一だった。
「お久しぶりです。お勤め先へ行くところですか?」
「はあ、、、」
「そうですか。今日はいい天気ですねえ。」
「豊中までちょっと。」
あとが続かなかった。電車の走る音が大きく響いていた。
阪急電車で曽根から豊中まではものの三、四分の間だった。豊中駅に着いて、
「それでは。」
とだけ言って別れた。
美智子は後悔していた。
思い切って啓一のことは忘れてこれからのことだけ考えようと決めたところだった。
不意を打たれて、胸の奥に整理していないものが喉元に迫ってきて、何も話をすることができなくなった。
こんなことってあるんやろうか?
そんなアホな。
胸が締め付けられるように痛かった。
あの梅田のデートから二年半はやっぱり長かった。素直になれない自分がいたのかもしれない。
でもこんなことって、、、、
その夜は気分が重かった。
わたしってなんでこんな巡り合わせなんやろ。
父が持っているウイスキーをこっそりグラスに半分ほど入れて一気に飲んだ。初めてのことだった。
蒲団をかぶって目から汗のように出るものにタオルを押し当てているうちに寝てしまっていた。
翌日の土曜の朝、たか子が部屋に来て、
「お姉ちゃん、今日は一緒に出掛けようか?わたし買いたいもんあるねん。」
「うん、ええよ、そうしよ。」
「なんかお姉ちゃん、目が腫れてるで。
なんかあったん?」
「うん、ちょっと」
「なにがあったん?教えてみてみ。」
「昨日朝、曽根の駅で先輩に会った、偶然。」
「は!、それでどうしたん?なんか話した?」
「なんも話されへんかった。」
「そうかあ、、、
、、、でもそれって偶然なん?」
「偶然、ほんまの偶然やと思う。」
「でも、お姉ちゃんを待ってたんと違うの?」
「それやったら、上りのホームに居たはず。昨日は豊中の取引先へ行くために下りのホームへいって、そこで逢ったの。」
「でもそんなことってあるんやね。彼氏大阪に勤めているんと違うよねえ。
東京の方に勤めてるんでしょ?
これってやっぱり赤い糸が結ばれてるんと違う?」
「なんやほんまにようわからへんねん。自分でも。
でもどうもならへんのとちゃうかなあ。
そう思ったら気イ重くなってきて、、、、、、」
「わかった!、とにかくおいしいもん食べに行こ!
お姉ちゃん、気持ちを楽にせんといかんよ、わかった?
そうしよ、そうしよ!」
ほんとにたか子は優しい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
