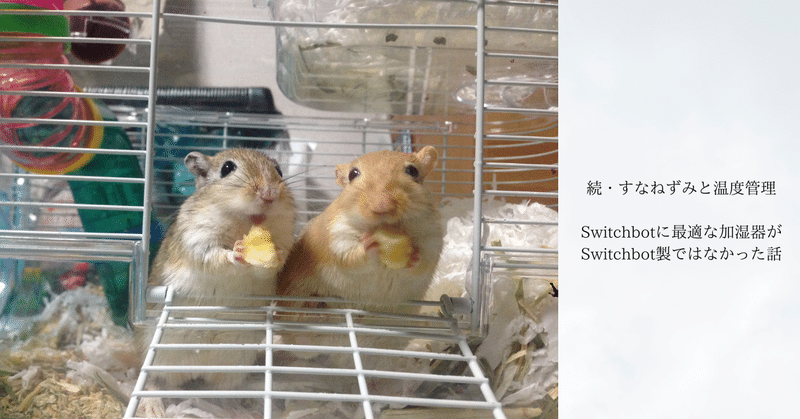
続・すなねずみと温度管理 Switchbotに最適な加湿器がSwitchbot製ではなかった話
このnoteについて
導入したPanasonicのFE-KXU07-Wでは加湿能力に不足がある事が判明し、新たな加湿器を探したところ怪我の功名的に最適な加湿器に出会うことができた。
Switchbotに最適な加湿器はSwitchbot製ではない、というお話。
(もちろん使用用途に依るが)
これまでの話
ダイキンの空気清浄機一体型MCZ70Y-Tの加湿器だけでは湿度を50%に保つことができず、湿度が下がりすぎてしまう問題が発生した。
そこで、追加で専用の加湿器を導入したところ、無事に目指す温度湿度を達成する事が出来た。(と、この時は思った)
加湿器増設後の温度・湿度
温度:25.8℃~26.8℃(平均26.3℃)
湿度:44%~55%(平均50.2%)
問題発生
しかし、問題が2つ発生した。
加湿性能が不足していた
電源・モード管理に不満
1.加湿性能が不足していた
事前調査を怠った怠慢故の結果だが、単純にDAIKIN MCZ70Y-Tと追加で購入したPanasonicのFE-KXU07-Wだけでは加湿性能が足りなかった。
ある程度の期間使用したところ、両機をフル稼働(ダイキンを湿度設定:高、Panasonicをターボモード)しても、湿度が48%までしか到達しない日が複数あった。
目的の湿度が50%なので、はっきり言って誤差レベルとも言えなくもない。
しかし、これから寒さが本格化し、暖房の稼働率が上がった時も48%を保てる保証はない事と、ある意味気化式の加湿限界を感じた事、そもそも湿度50%を目指すという本来の目的を達成できていないのでは意味がない事などから、別の加湿器の検討を考え始めた。
もちろん電気を使わないタイプの安価な加湿機を追加する事も検討したが、安物買いの銭失いになる可能性が高く、余計なものが増えるだけな気がしたのでやめた。
ちなみに、奥さんには平謝りした。
怒るタイプの人ではないが、「しかたないね」と笑って許してくれたのが救いだった。
2.電源・モード管理に不満
PanasonicのFE-KXU07の加湿ON・OFFはSwitchbot プラグミニとSwitchbotボットで行っていたが、どうも期待通りに動かない場面が出てきた。
具体的には、夜中、既定の湿度以下になっているのに加湿器が動いていなかった日が複数あったのだ。
原因はトリガーの発動条件。
昔からSwitchbotを使っている人からすると常識なのかもしれないが、僕はSwitchbotにフラグ1とフラグ2を設定した際、(時間差があっても)単純にこれらを満たせばその時点でトリガーがかかると思っていた。
具体的には、以下のフラグを「タイミングを問わず」両方満たしさえすれば良いと思っていた。
フラグ1:プラグミニの電源がOFF
フラグ2:湿度が47%以下
しかし、どうやらこれらのフラグを「同時に」満たさないとトリガーがかからない可能性が浮上してきた。(念のため、メーカーに確認中)
こうなるとSwitchbotボットによる電源管理は現実的ではなくなり、やり方を変えざるを得なくなった。
ダメと分かりながらも、一度はプラグミニがオフであるというトリガーを無くして湿度が47%以下時にトリガー発動で運用してみたが、当然のように以下の状態が発生した。
湿度が47%以下になりトリガー発動、Switchbotボットが電源ボタンを押す(加湿器がONになる)
一度湿度が48%以上に上がったあと、再び47%以下に下がる。
これは夜中に起きる現象で、気温が下がる→室温が下がる→暖房温度上昇→湿度低下というタイミングで起きる。再度、湿度47%以下のトリガーが発動してしまい、加湿器が稼働しているにも関わらずもう一度電源ボタンを押してしまう。
当然この時は加湿器は動いているので、電源ボタンを押す事で逆に加湿器をOFFにしてしまう。
解決方法
トリガーの仕組みを正確に把握できないので、トリガーを使っての加湿器制御は諦め、再び前回の選定基準に則り加湿器の買い替えを行うことにした。
加湿方式が気化式であること
Switchbotで制御可能(=外からでも制御可能)
水のタンクが大きい(6時間はもってほしい)
電気代が安い
選定機種:ダイニチ HD-LX1222
1.加湿方式が気化式であること
クリア。
この機種はハイブリッド式(温風気化と気化式)を採用している。
ちなみに、他社が呼称しているスチームと気化式のハイブリッドではない。
ハイブリッド式のメリット
湿度が低い時は温風気化で素早く湿度を上げ、設定温度近くになると気化式に切り替えることで、気化式のみのデメリットである加湿能力不足を補っている。
ハイブリッド式のデメリット
単純な気化式より消費電力が高くになる。
2.Switchbotで制御可能
クリア。
標準でスマートリモコンに対応している。
この点に関しては後述する。
3.水のタンクが大きい
クリア。
タンク容量:7.0L
連続加湿時間:5.8~11.7時間
我が家の場合、9時間程度でタンクが空になった。
4.電気代が安い
クリアならず。
これはダイニチの圧敗で、Panasonicの方が断然安い。
はっきり言ってスペック表では消費電力が一桁違う。

左がPanasonic、右がダイニチ。
ダイニチのエコモードですら、Panasonicのお急ぎモードに消費電力で敵わない。
実際の消費電力
せっかく2台持っているのだから、実際に1週間稼働した平均値で比較する事にした。
Panasonic (7日平均)
0.22kWh/日(一日あたり5~6円程度)
ダイニチ
データ取得中だが、おそらくPanasonicの数倍。
単日で見ると2kW/hに迫る勢い。
特にecoモードから標準モードに切り替えた際、一時的とはいえ650Wに到達する勢いなので、ecoモード以外を使うと電気代が跳ね上がる。
モードに依って大きく異なるが、言っても一日あたりの電気代は50〜60円程度だと思う。
現在はecoモードをベースとしてトリガーを設定し直し、消費電力のログを取り直している。

15以降がダイニチ
追記
一日あたりの消費電力が2kWhに迫る勢いだったので、さすがにこれは電気を使いすぎだと考えて、消費電力を抑えたトリガーを検討した。
おまけの項目に新しいトリガーを記載した。
長期的な判断はこれからだが、消費電力を1/5程度に抑えることができたので、これならばPanasonicのFE-KXU07の0.3kWhとそれほど見劣りしない。

追記2
その後、湿度を50%に維持する事を最優先に稼働させた結果を記載する。
期間:2022年12月1日~12月23日
平均消費電力:3.68kWh(最低0.5kWh、最高10.43kWh)

上記の通り、湿度50%を優先すると当初の想定を大きく超えて電力を消費していることが分かった。
ダイニチの加湿機が最高消費電力を記録した日、Nature Remo E liteによると、我が家の1日の消費電力は以下の通り44.1kWhだった。
ざっくり全体消費電力の25%が加湿器という事になる。
これをどう考えるかは判断が分かれるところだと思う。

Switchbotに最適な加湿器は?
まず前提としてSwitchbotの加湿器は超音波式である事に注意してほしい。
そのため、下記ノートの通り、電子機器が多い我が家には不向きだし、ある程度の大きさがある部屋には加湿性能が低すぎる。(Switchbot加湿器の加湿性能は220ml/h)
逆に、Switchbot加湿器の方が良い場合は以下だと思う。
数値は後述のダイニチのHPにある必要加湿量計算フォーム*2を使っている。
部屋が小さい(9m²以下、天井3m以下)
その部屋が複数ある
電子機器がない
1台あたりの単価を抑えたい
あくまで上記の数値は、吹き抜けがなく、暖房などを使用していない場合であることに注意してほしい。
まとめ
ダイニチの消費電力が大きすぎるので迷ったが、加湿性能が足りなかったり加湿方式をスチームにするよりはマシだと考えてダイニチ HD-LX1222を選んだ。
しかし、Switchbotによる制御がかなり想定通りにできたので、消費電力の件を踏まえても非常に満足がいく買い物になった。
おまけ
ダイニチ HD-LX1222をSwitchbotで管理する
ダイニチの取り扱い説明書*3を参考に設定をする。
電源ON・OFF、モード選択、ターボなど一通りの操作がSwitchbotから行える。
現在のトリガーは以下。
但し、このトリガーは電力消費が高いことが判明したので現在再考中。
湿度48%以下:電源ON/標準モード/湿度50%設定
湿度45%以下:電源ON/標準モード/湿度60%設定/ターボ
湿度49%以上:電源ON/エコモード/湿度50%設定
湿度52%以上:電源OFF
湿度53%以上:電源OFF(バックアップ)

トリガー見直し
前述したとおり2kW/hに迫る勢いの消費電力だったので、トリガーを見直した。
結果長期的なモニターができていないので、天候やその他要因を排除しきれていないが、まずは下図まで消費電力を抑えることができた。(0.4kWh~0.5kWh)

新しいトリガー
下記2つのトリガーを追加した。
湿度48%以下:電源ON/エコモード/湿度50%設定
湿度47%以下:電源ON/標準モード/湿度60%設定
トリガー変更の方向性としては以下の通り。
湿度が下がり始めたタイミング(48%)で早めにエコモードを使って湿度50%になるようにする
今までは標準モードを使って湿度を上げるトリガーだったが、ダイニチの加湿器は加湿性能がかなり高いので、エコモードでも十分に湿度を上げることができる事がわかった。
このトリガーを追加する事で、電力を大きく使う標準モードやターボモードをなるべく使わない事ができるので、結果として消費電力を大きく下げることができた。
ちなみに、標準モードを使うと10分で4%程度湿度を上げることができる。
赤外線登録方法
詳細は取り扱い説明書*3に記載されているが、少しわかりにくかったので記載する。
(Switchbotアプリ操作)Switchbotハブミニからリモコンを追加
(Switchbotアプリ操作)メーカー検索画面の一番下にあるカスタマイズモードをタップ
(ダイキン加湿器操作)赤外線登録モードにしておく
(Switchbotアプリ操作)画面一番下にある赤丸の追加ボタンをタップ
(Switchbotアプリ操作)アプリが学習モードになる
(ダイキン加湿器操作)登録したいボタンを押し、□入タイマーを押す
Switchbotアプリで登録完了
後は項目4~7を繰り返して各種ボタンを登録していく
今回の教訓
ダイニチのHPにある必要加湿量計算フォーム*2 などを使ってあらかじめ部屋の大きさを考慮した加湿性能を把握しておくべきだった。
リファレンス
*1 電気代計算シミュレーター
*2 ダイニチのHPにある必要加湿量計算フォーム
*3 ダイニチHD-LX1222取り扱い説明書(PDF)
https://www.dainichi-net.co.jp/uploads/manual/humidifier/hd-lx1022_1222.pdf
サポートありがとうございます。すなねずみ達の為に使わせて頂きます。
