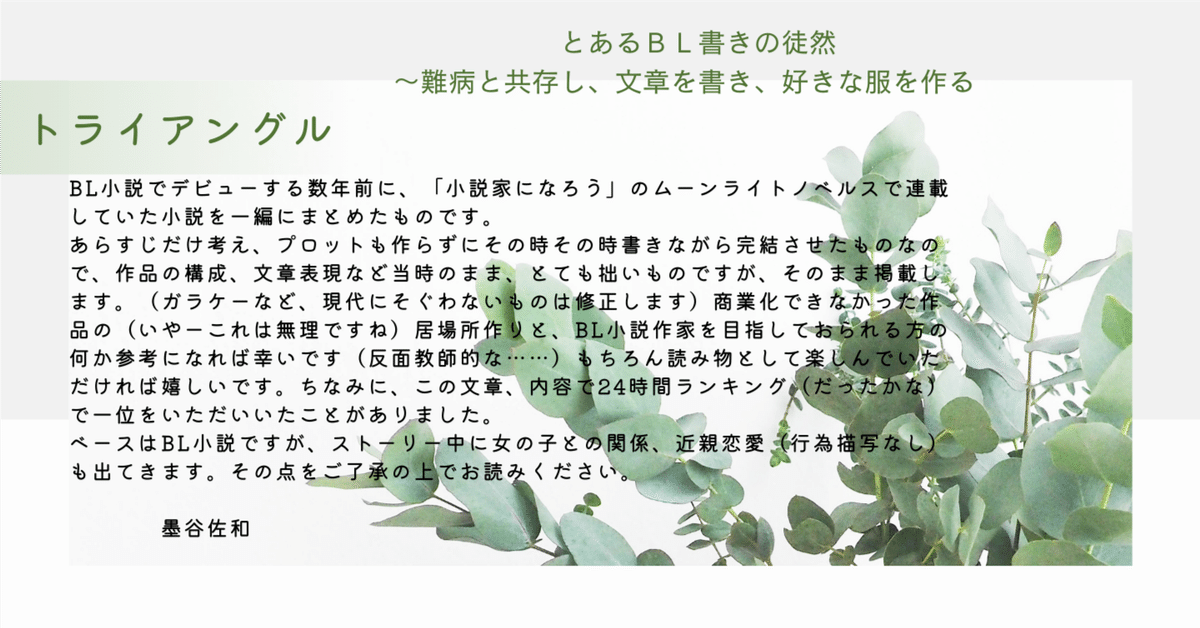
トライアングル 6
第六章 デイ・ドリーム 1 <side トモ>
その家は、昼なお暗く、暖かい陽射しも、人の笑い声も、そこに住まう者が伸び伸びと呼吸することすらも拒絶するような、そんな家だった。
ごく普通に家というものが育むはずの、そこに住んでいる人々の息づかいとか、存在の痕跡とか、もっと具体的に言えば生活の匂いとか足音とか……そんなものさえ感じられない、そこは家という名の、ただの容れ物にすぎなかった。
俺はそこで九歳まで暮らしていた。一緒に住んでいたのは、祖父母と母と、そして、めったに帰ってこない父。そして何故だか、親戚という「人たち」の出入りが多い家だった。
厳格で笑った顔を思い出せない祖父母は離れに住んでいて、俺がそこに近づくのを嫌った。父は……俺の顔を見たくないから帰ってこないのだと、親戚の一人が言っていた。そして多分、父だけでなく祖父母も同じ理由で俺を避けるのだろうと、幼いながらに俺は理解していた。
金銭的、物質的には恵まれた生活だったけれど、俺はいつも声をひそめ、足音を気にし……そうでなければ、ここに居られないのだと感じながら暮らしていた。けれど、俺には優しい母さんがいた。息詰まる家の中、まるで敵ばかりの家の中で、母さんだけが俺を愛してくれた。彼女の前でだけ、俺は思い切り笑顔になれたし、子どもらしく拗ねたり泣いたりできたのだ。
母を喜ばせるために、勉強も習い事も頑張った。同時に、そうでなければ祖父母が母さんに辛く当たることも知っていたからーー俺は母さんを守るために「良い子」であり続けた。でも、母さんは俺が勉強ができなくても、習い事をさぼっても、きっと俺のことを嫌いになったりしない。
それがわかっていたから平気だった。
ほとんど家に帰ってこない父のことは、祖父母や親戚の会話から伺い知るしかなかった。どこか別に家があるらしくて、そこから仕事に行っているのだと聞いていた。父とは年に数回顔を合わすだけだったから、俺はとてもその人のことを「お父さん」とは思えなかった。
時々やってくる、ほとんど知らない男の人。
彼にかけられた言葉で覚えているのは「俺には似ていない」だった。俺に会うたびに彼は吐き捨てるようにそう言って、向こうへ行ってしまう。「似てない」ことが腹立たしいのか、安堵なのか、よくわからなかった。でも、そんなこと「僕の責任じゃない」小さい俺はいつもそう思って、その棘を受けとめていたものだ。
「父」に会うたびに俺は少しずつ傷ついて、母さんのところに逃げて行く。
「ごめんね。智行のせいじゃないのに、ごめんね」
母さんはいつもそう言って、俺を抱きしめて泣いた。
何故、母さんが俺に謝るのかわからなかったけれど、本当は、あらゆる人から最も「ごめんね」を言われるべきは母さんだったのだ。そして俺は、この世でただ一人自分を愛してくれる母さんを泣かせないように、強くならなくちゃと思っていた。
(母さんを守れるのは僕だけだ。)
なのに、俺は母さんに聞いてはならない一言を投げつけてしまった。あれは、いつのことだったろうか……もう、秋も終わりの肌寒い夕方だった。
その日は大きな法事があって、いつもより多くの親戚が出入りしていた。俺はこういう日が大嫌いだったけれど、おとなしく部屋の隅っこに座っているしかなかった。おとなしくしている他にすることがなくて、手に持った数珠をなんとなくもてあそんでいたら、
「そんなことしたらダメじゃない。大切なものなのに」
俺を諌める声がした。大人ではない、子どもの声だ。それ自体がめずらしくて、俺は思わず顔を上げた。
そこには、クマのぬいぐるみを抱えた女の子が立っていた。俺と同じ年くらいなのに、その子は、責めるような目で俺を見下ろしている。
「……だれ?」
俺が聞くと、彼女はクマを膝に乗せて俺の前に座った。
「桜子」
目線が同じになると、彼女はまっすぐに俺の目を覗き込んできた。
「本家の、ヒトでしょ?」
彼女は大人びた口を聞き、俺はその言い方がすごく気に入らなかった。だから、思いっきり感じ悪く尋ね返した。
「親戚の子?」
彼女は頷いて、また俺をじっと見る。
なんだか、彼女の顔を見たことがあるような気がするけれど、どこで見たのかが思い出せなかった。不自然に会話が通わない。普通、子ども同士だったら、人見知りし合うか、いきなり意気投合するかどちらかだと思うけど、この時の俺たちはそのどちらでもなかったと思う。子どものくせに、らしからぬ探り合いをしているような……そんな雰囲気だった。
その時だった。
「桜子!」
喪服姿の女の人が走ってきて、彼女の手首をぐいっと掴んだ。
「そっちへ行ったらダメだって言ったでしょう!」
ヒステリックに叫ぶ、その女の人の顔は知っている。時々現れる親戚連中の中によく居る人だ。
「何を話してたの?」
女の人は、今度は俺に向かってきつい口調で言った。
「桜子が話しかけただけよ。ごめんなさい」
俺の代わりに彼女が返事をする。まるで、俺を庇ったような言い方だった。
「すみません。お義姉さま」
いつの間にか母さんもやってきて、何も悪いことをしていないのに、その女の人に深く頭を下げた。
「玲子さん、ちゃんと見ててくださいって言ったでしょう!」
「ちょっと待ってよ。母さんは何も……」
「智行さんには聞いていません!」
女の人は怖い顔で言った。その子だって……と続けて言おうとしたけれど、何も言えなかった。結局、俺たちは引き離され、彼女も何処かへ連れて行かれたが、幼いながらに事の不自然さに納得が行かなかった。あとで母さんに聞いてみよう。でも、母さん困るかな……。
そんなことを考えて廊下を歩いていたら、俺の耳にその会話は流れ込んで来たのだった。
本当にもう、抗いようもなく。
「智行は沙織に似てきたわよね」
自分の名前が聞こえたから、俺はその場に立ち止まってしまった。立ち聞きなんてするつもりじゃなかったけれど、でも部屋の前をそのまま通りすぎるわけにも行かなかった。
「沙織ね……お父様やお母様も、智行のあの顔を見るのは辛いわよね」
この声は、さっき母さんが「お義姉さま」と呼んでいたあの人だ。
「いっそ、玲子さんが智行を連れて出て行けばいいんじゃないの?」
「いくらなんでも、そんな都合のいい事は望めないわよ。だいたい、玲子さんが自分の子どもじゃない智行を育てているのは、この家の相続のためでしょ? 確かにお父様たちに押し付けられたには違いないけど、それでも、それぐらいの見返りがないと玲子さんだってやってられないでしょうよ?」
「そうねえ……出て行くとは思えないわね」
「玲子さんはともかく、智行はこの家の跡取りには違いないからね。沙織と博幸の子どもなんだから」
「じゃあ、桜子は……」
俺は目の前が真っ暗になった。床が真っ直ぐでなくなったみたいに、ちゃんと立っていられない。膝ががくがく震えた。今聞いたことの半分はよくわからなかったけれど、確かにあの人たちは「玲子さんが自分の子どもじゃない智行を」と言ったのだ。
桜子の名前が出たあたりで、俺はそのあと、どうやって自分の部屋に戻ったか覚えていない。親戚が引き上げるまで、俺は自分の部屋に篭っていた。俺一人がいないことなんて、なんの不都合もないし、母さんは親戚の接待でそれどころじゃない。俺は、さっき聞いた会話を一生懸命、頼りない頭の中で整理しようとしたけれど、難しくて、不安で、寂しくてどうしようもなくて、一人で膝を抱えて泣くしかできなかった。
この家の中で、たった一つの拠り所。
僕が母さんの子どもじゃなかったら、僕はどうしたらいいの? 自問しても自問しても、答えなんか出てこなかった。
どれくらい、そうしていただろうか。
気がつくともう暗くなっていた。泣きながら、ちょっと眠ってしまったらしい。不自然な体勢だったので肩や腕が痛い……でも、もっと痛いのは心だった。目覚めても、心はちっとも落ち着いていてくれなかった。
「智行……」
優しいノックの音と一緒に、母さんがドアを開けた。
「どうしたの? 明かりもつけないで。お食事持ってきたの。一緒に食べようか?」
母さんが照明のスイッチを入れた。部屋が明るくなると、俺が明らかに泣いた顔でいるのがバレてしまった。
「……どうしたの?」
母さんは食事の乗ったトレイを置くと、俺の前に膝を折って座った。俺は泣いていたのがわかってしまって、恥ずかしくて、そして母さんが来てくれたことで安堵して、まだ涙の残る目をぐいっと袖で拭った。
「誰か……叔母様たちに何か言われたの?」
俺は子どもだった。これを言えば母さんがどう思うだろうとか、悲しむだろうとかそんなことを考える余裕はなかった。ただ、目の前の大きな不安を取り除きたくて必死だった。
「ぼく……」
「ん?」
母さんが俺に額を寄せて、優しく聞き返す。
「ぼく、母さんの子どもじゃないの?」
問われた母さんは唇を噛んだ。その一瞬の青ざめた表情を、俺は今でもよく覚えている。
「智行は、母さんの子どもよ」
彼女は何かに宣言するようにはっきりと言い、そして俺を抱きしめた。けれど、俺の髪に触れる指がかすかに震えていた。口調ははっきりとしていたけれど、異様なほどに高鳴る母さんの心臓の鼓動は嘘をつけない。俺は、母さんの腕の中ではっきりと知ってしまった。
僕は、この人の子どもじゃないんだ……。
でも、同時に深く深く、わかったこともあった。
僕は母さんの子どもじゃないかもしれないけど、僕の母さんは……母さんなんだ。もっと大きくなったらいろんなことがわかるのかな。僕が子どもじゃなくなったら、母さんは本当のことを話してくれるのかな? 早く大きくなりたい。母さんを守れるように、そしていろんなことに立ち向かえるように。
けれど、その「本当のこと」を知るのは、そう遠い未来ではなかった。運命ってヤツは、俺が大人になるまで待ってはくれなかったのだ。
あの日。
学校から帰ると母さんが居なかった。
買い物に行ったり、祖父母の用事を言い付かったり、母さんが家を開けるのはめずらしいことではないけれど、あの法事の日以来……親戚から俺のことを聞いたあの日から、俺は母さんが目の届くところにいないとすごく不安になって、少し神経質になっていた。もちろん、母さんはあの日から何も変わらず居てくれたのだけれど、自分が学校に行っている間に、母さんが何処かへ行ってしまったらどうしようと、いつも心配でならなかったのだ。
テーブルの上に「おじいさまの用事で出かけてきます」というメモが置いてある。俺はほっとして、その小さな紙切れにすがり付いた。
その時だった。
「……智行」
好きではない声の響きだった。
「お父さん……」
振り向くと、そこに父がいた。こんな平日の昼間に彼が帰ってきたことなどなかった。この前の法事の時だって帰って来なかったのに、明らかに俺は不審の目を投げかけていたと思う。これまでも、父を苦手だとは思っても、怖いと感じていたわけではなかった。だが、明らかな拒絶を感じるので、どう接していいのかわからなかったのだ。なのに、その日の彼は妙に優しげだった。
「久しぶりだな。学校から帰ったのか?」
「うん」
身内に優しくされることに慣れていなかった当時の俺は、その父の様子に違和感を覚えながらも、やはり少し嬉しかったのかもしれない。
「学校は、楽しいか?」
「え……うん。楽しいよ」
「そうか……」
何気ない会話に緊張しながらも、父が俺に話しかけてくれることが、嬉しくなかったとは言えない。
ーーだから、俺は油断して捕まってしまったのだ。
「じゃあ、これから出かけるから、ランドセルを置いて来なさい」
父はそう言った。
「え? 今から? どこへ……」
「早く行こう。母さんもあっちで待ってるから」
母さんも……彼は確かにあの時そう言った。
そう、確かに。
俺は、出かけた母さんが出先で俺を待っているのだと思い、素直に父に従った。
「おじいさまやおばあさまに、出かけるって言わなくていいの?」
靴を履きながら、俺は父に尋ねたが、
「ああ、いいんだ」
父は離れの方をちらっと見たが、あっさりとそう言って、俺の手を取った。
ダメだ!
行っては行けない!
行っちゃダメだ!
俺は、何も知らない幼い自分に必死で叫んだ。
だが、その声は届くはずもなく。わかっていても俺は必死で叫び、父に取られたその小さな手を引き剥がそうと、必死で手を伸ばす。
「行くな!」
絶叫にも似た、その自分の声を俺は聞き、誰かが、必死で伸ばした俺の手を握った。
誰?
だって止めなくちゃ。
行ったらダメなんだよ。
誰が俺を止めるんだ。
邪魔するなよ……。
「トモ!」
呼ばれて目を開けた。
眠っていたのか、どこからどこまでが夢で、どこからどこまでが現実なのか、よくわからない。誰なんだ? 幼い俺自身に伸ばしたはずの俺の手を握り、俺を呼び戻したのは。
「カオル……?」
俺は周囲を見回す。
そこは、見慣れたリビングだった。あの、息の詰まる大嫌いな家じゃない。俺はソファに横になっていて、カオルが俺の手を握ったまま心配そうな顔で側に居る。俺は深く息をついた。
「どうした? すごくお前うなされてて……」
「悪い……俺、寝てた?」
「そこでうたた寝してたんだけど、ほんと大丈夫? すごい汗」
「夢、見てた」
俺は、そこで握ったままのカオルの手に気がついた。ああ、この手が俺を連れ戻してくれたのか。
「あ、ああ、ゴメン!」
カオルは俺の目線に気付いて、握っていた手をぱっと離す。途端に、俺の手は頼りなくなった。
カオルが持ってきてくれたタオルと水を受け取って、俺はひと息ついた。
「ちょっと嫌な夢見た」
言い訳のように俺は言った。
「うん……」
カオルはそれだけ言って、何も聞こうとしない。異常な取り乱し方だったはずなのに、それでもカオルは俺をそっとしておいてくれた。その優しさが嬉しくもあり……何故だか初めて物足りなく感じた。
俺はカオルを見つめていたらしい。カオルは俺の視線から逃げるように背を向け、ちょっとわざとらしいような明るさで言った。
「今日、僕がメシ作るよ」
そうだった、父さんと母さんはもうシアトルに発った。二人だけの生活が始まって数日が過ぎている。
やっと、頭の中の整理ができてきた。二人で、父さんと母さんの使っていた部屋や残していったものを整理していた。ちょっと飽きてきて、ソファに横になって、カオルに「忙しいんだから寝るなよ!」なんて言われてたような気がする。でも、結局寝入ってしまって……。
「パスタでいい?」
「うん」
「落ち着いたら、そのへん片しといて」
カオルに言われて、ごちゃごちゃ散らかったリビングのテーブルの上にふと目をとめる。すると、見覚えのある皮表紙のアルバムが目に入った。はじかれたように起き上がって、俺はそのアルバムをめくる。それは、俺の小さい頃のアルバムだった。ページを繰ると、入学式や七五三の写真が当たり前に貼ってある。
ほとんどは俺と母さんだけが写っていたけれど、赤ん坊の俺を抱いている母さんの隣に、あの夢で見た父が写っている写真が一枚だけあった。さっきの悪夢が、逆流するように、どんどん俺の中に流れ込んでくる。
「カオル……このアルバム……」
「ああ、玲子母さんがトモに渡してくれって言って」
「見た?」
俺の声は低く冷たかった。その口調に何かを感じたのか、カオルが俺の側に戻って来た。
「見てないよ」
カオルのその言葉に嘘はない。そして、見られても別にカオルにだったらかまわない。でも、母さんが何でこれをカオルに託したのかがわからずに混乱した。
俺は、たまらなくなって、カオルの首に手を回して縋りついた。抱きしめてほしかったのかもしれない。あの日の母さんのように。
俺が首にからめた腕に力をこめると、一瞬、カオルの身体が緊張した。
「あんなものがあるから……」
俺は、カオルの肩に顔を埋めて言った。
「あんな夢見たんだよ……」
「何? アルバムのこと?」
俺の耳のすぐ上から、カオルの声が聞こえる。俺はカオルの肩に顔を押し付けるように、こくこくと頷いた。
カオルは、抱きしめ返してくれない。
俺はそれが寂しかった。俺は、あの時の小さな子どもじゃない。カオルも母さんじゃない。けれど……。
とにかく、俺は縋りつける存在があることに感謝した。でないと、崩れ落ちそうな自分を支えていることができなかった。
「……何も聞かないんだな。相変わらず」
俺はちょっと拗ねたように言った。カオルの心臓の音が痛いほどに鳴っているのがわかる。けれど、この時の俺は全然自分に余裕がなくて、その鼓動が母さんのあの時の鼓動とは違う意味を持つものだということが、まったくわかっていなかった。
「聞かない俺が好きだって言ったから」
そう言ったカオルの声がどれだけ切なかったのか、俺は何もわかっちゃいなかった。だから、こんなことが言えたんだ。
「うん……好き……大好きだよ……」
俺はカオルに回した手に力をこめた。そうすることが、どれだかカオルを傷つけていたのか知りもせずに。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
