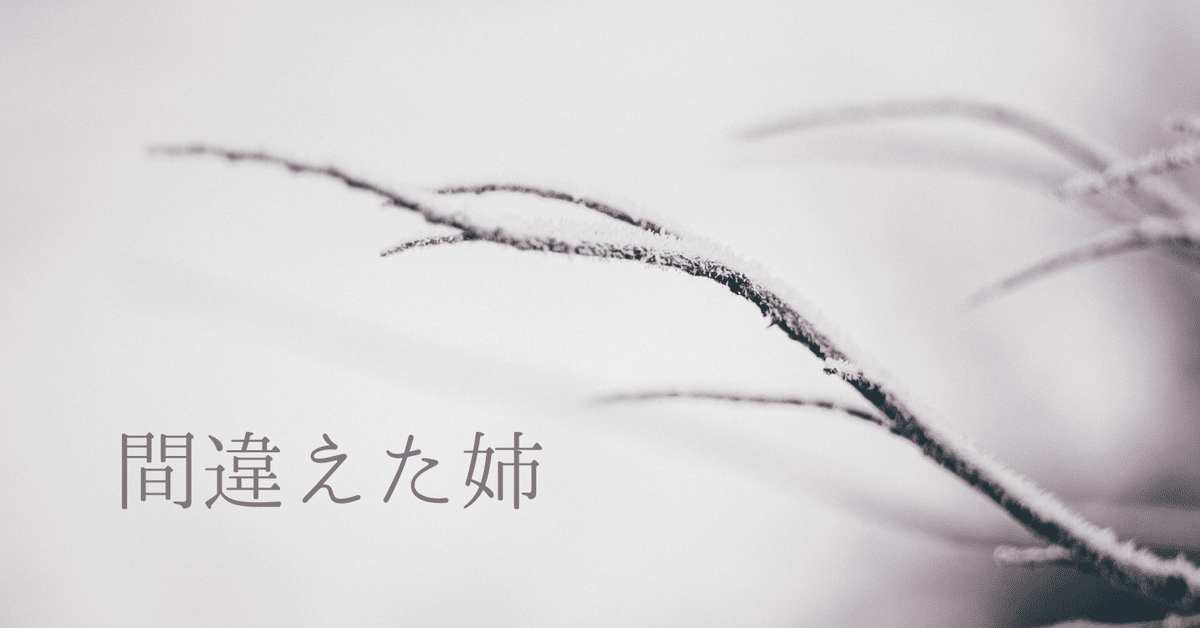
間違えた姉
K市の暮林産婦人科で生まれた。
二十年前の春のことだ。
それから何度か引越しを繰り返し、7歳上の姉と両親の下で育った。
どこに住んでも、近くにかならず湖があった。
「水を間違えたらいけない。体に入れる水を選び間違えたら、こんなに惨めなことはない。」
母は姉がいないときに、よくそういって私に聞かせた。洗濯物を畳みながら、蜜柑の皮をむきながら、鍋の中身をかき混ぜながら、ことあるたびに水の大切さを説いた。
「お姉ちゃんがお腹にいた頃はね、お父さんの仕事も景気がよかったから山奥から湧き水を取り寄せて綺麗な羊水で育ててあげられた。だからあの子の瞳は澄んでいたでしょう。晴れた日にあの子の目をのぞくとね、よく湖が見えたものよ。そのたびに綺麗な水で産んであげられてよかったって思ったわ。」
私は真面目な顔で頷いた。
姉は確かに父と母の遺伝子から作られたはずなのに、とびぬけて美しかった。透き通るほど白い肌に、真っ黒な髪。切長の一重とすっとした鼻梁のおかげで、ふとした瞬間男の子に見えることがあった。姉に憧れる女の子も多くて、よく手紙をもらっていた。
町の写真館のおじさんが、ショーウィンドウに飾る写真のモデルになってほしいというので、節目の行事ごとに姉は綺麗な服や着物をきて額縁に収まり続けた。だから、姉のことを写真館の娘だと勘違いする人も多かった。
対する私は父に似て、地黒で奥二重で鼻が低い。。
それでもおでこの形が良かったのと顔が小さかったおかげで悲観するほどの容姿ではなかった、というかあの姉の妹でなければごく普通の容姿だったと思う。
それでも姉とは歳が離れていたし、比べられて嫌だと思うのはおこがましいというほど遠いひとだった。美しい姉はいつでも私の自慢であり、家の中でも彼女は異質の存在だったから。
「あんたが産まれた頃にはねぇ、もうお父さんの太鼓の仕事も減り始めて。だからあんたを綺麗な水で育ててあげられなくて悪かったわね。」
涙ながらに謝られても、大怪我も大病もなく心身ともに頑丈に育ったので、なんて返していいのかいつも分からなかった。
高2の春、姉は失踪した。
「友達と買いものにいってくる。」
土曜日の昼下がり、そう言って家を出たきり二度と帰ってこなかった。
後から聞いてまわっても、姉と約束をしていた友達はいなかった。
町一番の美人だった姉の失踪は、小さなコミュニティの中でたちまちトップニュースになり、そのうちに喫茶店で男の人と会っているのを見たという人が現れた。店のマスターも確かにあの日姉を見たと証言した。
「ちょっと見ないような美人だったからよく覚えていますよ。お連れの方もね、あれは異国の血が入ってるのか背が高くてね、恐ろしく白い肌に青みがかった目をしてまして。私なんかはいろんなお客様を見てきましたけどね、あとにもさきにもあんなに美しいひとたちはみたことがない。ああ、美男美女とはこういうことかと思いましたよ。」
恋人のようだったという彼の証言で、姉は駆け落ちしたのだろうということで警察もそれ以上積極的には動いてくれなかった。
「よくあることです。落ち着いた頃に必ず連絡がありますから、その時にどうか否定しないであげてください。」
と言ったけど、そんなことは絶対ないだろうという不思議な確信があった。
姉は一体、誰と会っていたのだろう。
姉とならんで遜色ないほど綺麗な男の人なら、私も見て見たかった。
不思議なことに半狂乱になって姉を探していた母は、喫茶店での目撃情報を聞いてから急に大人しくなった。
それまでは姉の友達に何度も話を聞いたり、警察にも何度も足を運んだり、私には秘密にしていたみたいだけど探偵だって雇っていたのだ。
それがぱったりと止んで、刑事さんが様子を伺いに立ち寄ってくれた時でさえ母は無関心だった。
私たちが生まれた暮林産婦人科に、わざわざ新幹線に乗って先生に話をしに行ったのが、母の姉に対する最後の執着だった。
暮林先生はかなりの高齢で、老木のような人だった。
この皺々の手から、真新しい命が取り出されるのだと思うとなんだかとても敬虔な気持ちになった。
「あんなに綺麗な水で育てたのに、なにがいけなかったのでしょうか。」
涙ぐむ母の手に、先生は皺々の手を重ねてしずかに答えた。
「なにもいけないことはありません。あなたは母親として最善を尽くしたが、あの子は特別だった。…特別すぎたんです。十七歳まで親元にいられただけでも奇跡といっていいでしょう。」
「そんな…。」
「今年は大雪が降るでしょうな。娘さんはいつもそばにいると思うしかない。彼女は、幸せになったのですよ。」
暮林先生の深い穏やかさに、不思議と気持ちが落ち着いてくるのか母は「そうですね。」と言って暇をつげた。
帰りの新幹線では、一緒にお弁当を食べて私の学校生活についていくつか聞いてきたりした。姉が失踪する前の、いつもの母だった。ただもう、水の話は二度とすることはなかった。
その年の冬は記録的な大寒波が押し寄せて大雪が降った。
死人が何人も出て、古い木造の家が何軒も雪の重さに耐えかねて潰れたりした。古くからこの町に住む人たちは、冬将軍になにかあったのだろうと低い声で噂しあった。
水を間違えたのはお姉ちゃんのほうだったね。
灰色の空にむかってぽつりとつぶやいた。
私の言葉を肯定するように、あとからあとから雪は降り続けた。
姉に会いたいと思ったが、これで良かったのだとも思った。
間違いが正されて、姉はあるべきところへ還ったのだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
