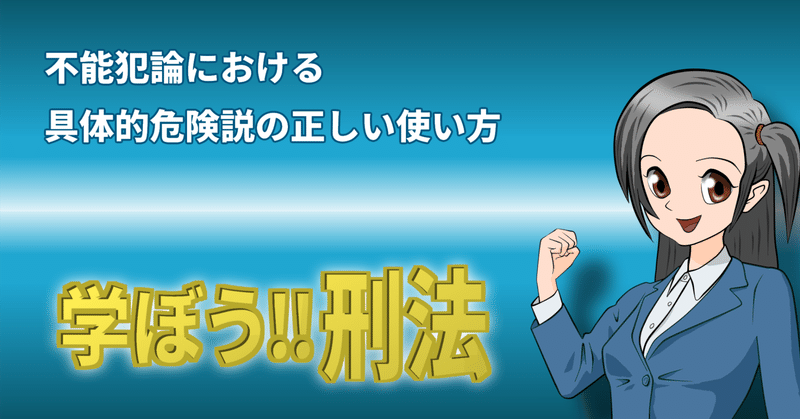
【学ぼう‼刑法】不能犯論における具体的危険説の正しい使い方
第1 はじめに
今回のテーマは「不能犯論」です。
不能犯とは何か?
これを教科書で調べてみると、結構、表現に違いがあります。
犯罪を遂行しようとした者の行為が、外形的には実行の着手にあたるようでありながら、構成要件的結果を発生することが不可能であるため、未遂罪とはならず、不可罰とされる場合
犯罪をしようとした者の行為が、結果発生の現実的危険性を有しないため、未遂罪とはならなず、不可罰とされる場合
などというような定義が比較的多いでしょうか?
もちろん、教科書に書かれている定義ですから、このような定義が間違いであるとは言いません。しかし、相変わらず天邪鬼なようですが、私としては、次のように表現したほうがより適切なのではないかと思うワケです。
ある犯罪を遂行しようとした者の行為が、その犯罪における実行行為の特質を備えないために、その犯罪の実行行為を行ったとは認められず、既遂罪はもちろん、未遂罪にも該当しない場合
私がこだわっている点は、2つあります。
1つは、不能犯は、未遂罪との区別だけが問題となるのかという点、別の言い方をすると、既遂罪との区別が問題となる不能犯もあるのではないかという点、もう1つは、不能犯は、構成要件的結果発生の可能性(危険性)がないということだけの問題なのかという点です。
もちろん、不能犯論がもともと未遂罪との区別をめぐって議論されて来たことは間違いなく、また、その区別の基準として、現在、構成要件的結果発生の現実的危険があるか否かの問題と解されていることも間違いのないでしょう。
不能犯論において現在、双璧をなしている具体的危険説も客観的危険説も、行為者の行為に結果発生の現実的危険があるか否かを判断するための方法に関する学説です。
ですから「こんなところに妙な突っ込みを入れられてもねぇ……」と言いたくなる気持ちもよく解ります。ですが、しかし、この認識は、これら具体的危険説や客観的危険説で解決できることの射程を図る意味でも重要だと思うのです、主観的には。
……ですが、そんな「こだわり」ばかり述べていると、そのうちだんだんだれも読んでくれなくなるので、まずは、不能犯論の王道である具体的危険説、客観的危険説の対立などについてお話ししたうえで、最後にちょっとだけその問題にも触れたいと思います。
第2 不能犯と未遂罪の区別
1 結果犯の実行行為の特質
不能犯とは、行為者はある犯罪をするつもりで行為しているのに、その行為がその犯罪の実行行為の特質を有しないために、その未遂罪にすらならない場合です。
不能犯は、殺人罪(刑法199条)を題材として議論される場合がほとんどです。最も有名なものは「呪いによって人を殺そうとした」という事例で、日本では「丑の刻参り」を題材としていることが多いようです。ドイツに「丑の刻参り」はないでしょうが。
次のような事例です。

この場合が不能犯の典型とされています。
A女はBの妻V女を殺そうと企みましたが、Vは死んでいないので、もちろん殺人罪(199条。既遂)にはなりません。しかしそれだけでなく、Aには殺人未遂罪(刑法203条、199条)も成立しません。
その理由は、Aの行為には、殺人罪の実行行為の特質である「人の死亡を発生させる現実的危険性」がないからです。
殺人罪の構成要件は、結果犯の最も単純な形をしています。そして、結果犯の実行行為は、基本的には「構成要件的結果を発生する現実的危険のある行為」であることが必要です。これは、殺人罪の場合であれば、その構成要件的結果は「人の死亡」なので、殺人罪の実行行為は「人を死亡させる現実的危険のある行為」であるということになります。
ところが、上記の「丑の刻参り」の事例では、A女の強い怨念にもかかわらず、A女の行為には、人を死亡させる現実的危険がありません。そのため、その行為は殺人罪の実行行為とは認められず、そこに殺人罪の実行の着手を認めることができません。未遂は「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった」場合なので(刑法43条本文)、Aの行為は、殺人未遂罪にもならないということになります。
2 現実的危険性の判断方法
「丑の刻参り」の事例では、そこに人を死亡させる現実的危険性がないことは誰の目にも明らかで、その危険性(結果発生の可能性)を判断するための方法は特に問題とはなりません。
しかし、事例が変わると、そこに結果発生の現実的危険があるのかどうかが一目瞭然とは言えなくなるため、これが問題となります。例えば、次のような事例です。


これらの場合に、BやCの行為には「人を死亡させる現実的危険」があるでしょうか?
3 学説の対立
このような場合にどうやって「結果発生の現実的危険」があるか否かを判断するかをめぐり、これまでいろいろな学説が主張されてきました。

これらの学説を概観して気付くでしょうが、これらの学説は、どれも、どのような事情を基礎として、だれの見地で、危険性(結果の発生する可能性)の有無を判断するかという内容のものとして作られています。
そして、その判断の基礎とする事情(情報)のことを「基礎事情」とか「判断基底」と呼び、誰の見地で判断するかという問題を「判断基準」と呼んでいます。基礎事情と判断基準の観点から上記の学説を整理すると、次の一覧表のようになります。

第3 各説の内容
1 主観説
主観説は、判断基準を行為者の見地としています。その意味は、行為者の知的レベル(科学的知識)を基準とするということです。そのため、この説に立つと、行為者がその行為によって人を殺すことができると信じている場合は、その行為には人を死亡させる現実的危険があることになってしまいます。
それゆえ、この説を純粋に貫くのであれば、「丑の刻参り」の事例ですら殺人未遂となるというのが論理的帰結です。もちろん、主観説もそのようなことは言わず「迷信犯は例外的に不能犯だ」と言いますが、それゆえに、主観説は筋が通らないと批判されます。
2 主観的危険説
他方、主観的危険説は、判断基準は一般人の見地、つまり一般人の知的レベル(科学的知識)に求めますが、基礎事情は「行為者が認識または誤認した事情」であり、主観説と同じです。
そうすると、行為者がある事実を信じている場合は、仮にそれが客観的事実と反しているとしても、事実はそうであることを前提として(仮定して)、結果発生の可能性の有無が判断されます。
そこで、主観的危険説では、次のような事例では、行為者に殺人未遂罪が認められることになります。

しかし、行為者がいかにそれを「毒」であると思っていても、金平糖のような特徴的な形状をしたお菓子は、一般人から見ればそれが「毒」ではないことは一目瞭然でしょう。ですから、行為者がこれを「毒」だと信じて、殺意をもって人に飲ませたとしても、周囲の人は笑ってしまうハズです。
しかし、主観的危険説では、たとえ客観的事実に反しても、行為者が「誤認」していた事実も、そのものとして基礎事情に入るため、「毒」であることを前提に結果発生の危険性を判断することになります。そのため、人が死ぬ可能性はある、という判断になり、殺人未遂罪が認められることになります。
主観説も、主観的危険説も、客観的事実と合致しているかどうかを抜きにして「行為者が内心で思っていた事情」をそのまま基礎事情とします。そのため、この両説では「結果発生の可能性」という本来客観的であるべきものが、主観的になものとなってしまいます。そこで、この点が批判され、現在ではこれらの説を採っている論者は、我が国にはいないと言ってよいでしょう。
3 具体的危険説
具体的危険説の基礎事情は、主観説や主観的危険説とは異なります。
上記の学説の説明では「行為者が認識していた事情および行為当時の行為者の立場に立って一般人であれば認識できたであろう事情」となっています。
ただ、多くの教科書では、順序を逆にして「行為当時の行為者の立場に立って一般人であれば認識できたであろう事情および行為者が特に認識していた事情」と表現されることが多いと思います。
どちらも意味内容としては同じですが、この説が一体どのような説なのかということを考えると、どちらを先にするかには論者の考え方の違いが反映していると言えます。
具体的危険説を理解するうえで注意すべき点としては、
まず、行為者については「認識していた」であるのに対し、一般人については「認識できたであろう」となっていることです。
これは「行為者」は、現実の存在なので「認識していた」か「認識していなかった」かのどちらかですが、「一般人」については、それは現実の存在ではなく「仮に一般人が行為当時、行為者の立場にいたら」という仮定の話をしているので、必然的に「認識できたであろう」「認識できなかったであろう」という推測の話になるからです。
なお、ここにいう「一般人」とは、平均的な注意能力を有する人(平均人)のことを意味しています。
次に、ここに言う「認識」はあくまで客観的事実に沿った正しい認識のことを意味し、「誤認」を含みません。この点が、具体的危険説の基礎事情が、主観説や主観的危険説のそれとは異なるところです。
では、具体的危険説が、基礎事情を「行為者が認識していた事実」と「一般人が認識できたであろう事実」とに求める理由はどこにあるのでしょうか。
これは「行為当時、行為者に与えられていた情報を基礎とする」という意味だと私は理解しています。つまり、行為時における具体的な危険性を判断しているということです。
そして、行為時において行為者に与えられていた情報と言えば、その第1は「実際に行為者が認識していた事情」でしょうから、まずはこれが基本的な基礎事情となります。
しかし、仮に行為者が行為当時、実際には認識していなかったとしても、平均的な注意能力の人にとって認識可能な事情であれば、行為者もその事情を認識することができたであろうという意味で、これもまた「行為者に与えられていた事情」に加えてよいでしょう。そこで第2に、これもまた基礎事情に含めてよいと考えられます。
ですから、この意味で「行為者が認識していた事情」および「一般人であれば認識できたであろう事情」が危険性判断の基礎になるというのが具体的危険説の考え方であろうと私は理解しています。
これに対して「一般人が認識できたであろう事情」を基本的な基礎事情としつつ、これに「行為者が特に認識していた事情」を付加することで具体的危険説の基礎事情が作られている、と理解する見解もあります。いや、むしろこちらの理解のほうが多数かもしれません。
この見解は、現実の行為者が行為時に具体的にどのような情報をもっていたかということよりも、構成要件的判断が一般人を基準とした抽象的判断であることを重視するものと言えるでしょう。
最後に、具体的危険説の判断基準における「一般人の見地で」ということの意味は、一般人の知的レベル(科学的知識)を基準としてという意味です。この点は主観的危険説と共通です。また、この場合の「一般人」とは、社会における平均的な科学的知識を有する人を意味しています。
もっとも、社会における平均的な科学的知識のレベルというと、かなり低いものとなると考えられるため、科学的見地からは絶対に結果が発生しないという場合であっても、一般人からは結果の発生する可能性を否定できず、未遂となる場合が多くなると考えられます。そこで、判断基準を一般人の見地に求める場合は、結果的に科学的知識に乏しい一般人の「不安感」を理由に行為者を処罰することになるとも言われます。
4 客観的危険説
客観的危険説に属する学説には、微妙な違いをもついくつかのものが含まれています。
まず、基礎事情に関しては「行為時の全事情(A)」なのか「行為時・行為後の全事情(B)」なのか、という違いがあります。「行為時・行為後」の全事情の意味は、現実の裁判を前提とすれば、判断時である「裁判時までに明らかとなったすべての事情」と表現する場合と同義です。
次に、判断基準については「科学的一般人の見地(1)」とする見解と「科学的見地(2)」とする見解とがあります。
そして、これらを組み合わせた「A1」「A2」「B2」という3つの見解が主張されていると言えます。
なお、判断基準である「科学的一般人」とは、刑事裁判で鑑定人などを務める専門家の科学的知識のレベルという意味です。他方「科学的見地」とは純粋に現在の人類の到達点である科学的知識によるという意味です。
また「B2」の見解は、特に、純客観的危険説とか純粋客観説などと呼ばれたりしています。
第4 事例の検討
1 死体事例
冒頭にも述べたとおり、不能犯論において現在、有力に主張されているのは、具体的危険説と客観的危険説です。
そこで、まずこの2つの見解では「死体事例」と「空ピストル事例」について、それぞれどのような判断となるのかについて見ておくことにしましょう。

この場合のBについてWに対する殺人未遂罪が成立するかについて考えてみましょう。
まず、客観的危険説の立場からの結論は簡単です。BがWに向かってピストルを撃った時点で、すでにWを死亡しており、「行為時に存在した事情」なので、このことが危険性判断の基礎事情に入ります。
そして、これが基礎事情に入る以上、死者が死ぬことはないので、Wに向かってピストルを撃ったBの行為が人を死亡させる可能性はありません。あえて科学的一般人や科学的見地を持ち出すまでもないでしょう。
よって、客観的危険説によれば、この「死体事例」のBは不能犯となります。
では、具体的危険説ではどうなるでしょうか?
まず、基礎事情についてです。
この場合、よくやってしまいがちな過ちは
「行為者BはWが生きていると認識していた」
「一般人もWを生きていると認識したであろう」
「したがって、Wは生きていたということが基礎事情となる」
という論法です。
これは具体的危険説の基礎事情の選別方法として正しくありません。なぜなら、行為当時「Wはすでに死んでいた」からです。つまり「Wが生きていると認識していた」というのは正しくはなく行為者Bは「Wが生きていると誤認していた」に過ぎません。
これは一般人についても同様で、夜の暗がりの中、Wが布団の中で、心臓麻痺で死んでいたのであれば、死亡したことの外形的特徴もなく、一般人であっても「生きている」と思い込んでしまう(=誤認する)ことはやむを得ないと言えるような状況かもしれません。が、しかし、それでもこれが事実ではない以上「一般人もWが認識したであろう」とは言えません。
では、具体的危険説の基礎事情の選別は、この場合にどのように行われるべきなのか?
「行為者は、Wが死亡していたことを認識していなかった」
「行為当時の行為者の立場に一般人がいたとしても、Wがすでに死亡していたということは認識できなかったであろう」
「そうすると、すでにWが死亡していたということは、危険性判断の基礎事情から除かれる」
「そこで、この事情を除くと、生きているか死んでいるか不明なWの人体という事情を基礎として、これに向かってピストルを撃つ行為の危険性、つまりこれによってWが死亡する可能性の有無を判断すべきことなる」
以上のとおり、「Wが死んでいた」という事実は、行為者も認識しておらず、一般人にも認識できなかったであろうという場合は、基礎事情から除かれます。
しかし、だからと言って、反対事実(本件では「Wは生きていた」)が判断の基礎に置かれるワケではありません。それは客観的事実ではないからです。そこが主観的危険説と具体的危険説との違いです。
この場合は「Wが死んでいる事実」が基礎事情に入らない以上、それは「不明」となります。そこで、Bの行為は「生きているか死んでいるか不明なWの人体」に向かってピストルを撃つ行為と把握され、そこに人を死亡させる可能性(危険性)があるか否かが判断されることになります。
これが具体的危険説の正しい使い方です。
そして「生きているか死んでいるか不明」であれば、生きている可能性を払拭できない以上は、そのようなWに向かってピストルを撃つ行為の危険性(これによってWが死亡する可能性)は否定できないので、このBの行為は殺人未遂となるというワケです。
2 空ピストル事例
では、空ピストル事例ではどうなるでしょうか?
Cには、Xに対する殺人未遂罪が成立するでしょうか?
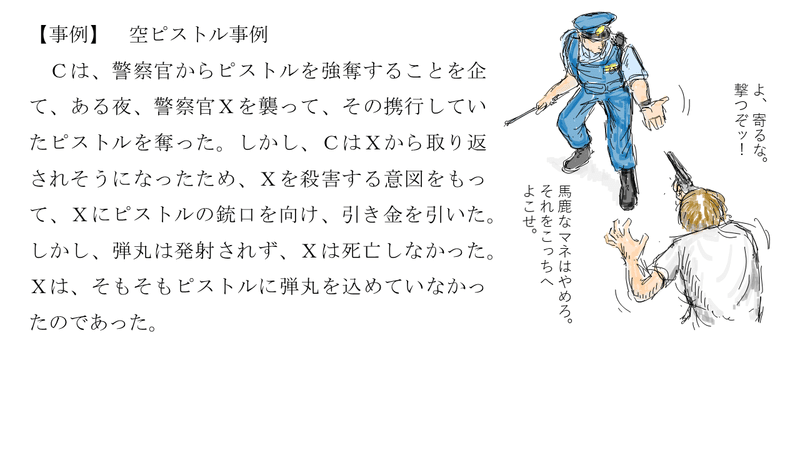
客観的危険説では、死体事例と同様に、Cの行為は不能犯となり、殺人未遂罪は成立しません。なぜなら、CがXに向かってピストルの引き金を引いた行為の時点で、ピストルの中には弾丸は込められていなかったので「行為時の全事情」または「行為時・行為後の全事情」を基礎とする客観的危険説によれば、これが基礎事情となります。
そして、弾丸が入っていないピストルを人に向けて引き金を引いても、人が死ぬことはないので、そこに「人を死亡させる危険性」は存在しないことになります。よって、Cの行為は不能犯と判断されます。
他方、具体的危険説ではどうでしょうか?
まず、行為者であるCは、ピストルの中に弾丸が込められていないという事実を知りません。また、行為時の行為者の立場にいたのが一般人(平均的な注意能力をもつ者)であったとしても、ピストルの中に弾丸が込められていないことを短い時間の中で見抜くことなどできないでしょう。そうすると「ピストルの中に弾丸が込められていなかった」という事実は、危険性判断の基礎事情から除かれ、この場合、「弾丸が込められているかどうか不明な、警察官から奪ったピストルを、人に向けて引き金を引く行為」の危険性が判断されることになります。
そして、この場合に、そのピストルに弾丸が込められている可能性は、四囲の状況から判断されることとなります。
そこで、これが例えば博物館に陳列されている拳銃だったら、弾丸が装填されていることはまずないと考えられるでしょう。
しかし、警察官が携行していたピストルということになると、むしろ弾丸が装填されている場合のほうがほとんどだと考えられます。
そうするとこうした「弾丸が込められているかどうか不明な、警察官から奪ったピストルを、人に向けて引き金を引く行為」によって人が死亡する可能性は否定できません。弾丸が入っている可能性を否定できないからです。
そのため、この場合のCの行為はXに対する殺人未遂罪となるものと判断されます。
3 空気注射事例
上記の「死体事例」「空ピストル事例」とともに不能犯が問題となる事例としてよく引き合いに出されるものに「空気注射事例」があります。これは、基礎事情の限定が問題となるのではなく、判断基準のほうが問題となる事例です。

Fにつき、Zに対する殺人未遂罪が成立するか否かが問題となります。
この事例では、Fには事実の誤認などはなく、基礎事情は客観的危険説でも具体的危険説でも変わりません。「酔っ払って寝ているZの静脈に注射器で空気20ccを注射した」ということです。
問題なのは、Fは、これによってZが死ぬと思っていましたが、Zと死なず、実際、この程度の空気注射では人が死ぬことはない、という事実です。
つまり、一般人の見地(=いい加減な科学的知識)からすれば、Zは死ぬかもしれないと思われますが、科学的一般人の見地や科学的見地からすると、これによってZが死ぬ可能性はない、ということです。
そこで、この場合、具体的危険説からはCの行為は殺人未遂罪となりますが、客観的危険説からはCの行為は、殺人罪としては不能犯となるのが論理的な帰結です(客観的危険説を採りながら、異なる結論を導く先生もいらっしゃいます)。
4 学説の比較
以上のとおり、具体的危険説、客観的危険説の適用例を見てきました。
これらの結果を見比べて、どちらがよいかを検討するというのも1つの考え方です。しかし、すでに見たように、危険性判断の方法をめぐってこれまで主張されてきた学説は、結局のところ「基礎事情」と「判断基準」との組み合わせによってできています。
そこで、これまでになかった組み合わせとして「行為者が認識していた事情および行為当時の行為者の立場に立って一般人であれば認識できたであろう事情」を基礎として「科学的一般人」や「科学的見地」を基準として危険性を判断する、という説が主張されてもよいのかもしれません。

客観的危険説が結果無価値論の立場から主張されるのに対し、具体的危険説は行為無価値論の立場から主張されるという指摘があるようです。
しかし私自身は、この指摘の正当性については懐疑的です。実際、結果無価値の立場から具体的危険説が主張されている論者もいます。例えば、平野龍一先生などはその代表例でしょう。
具体的危険説が主張する基礎事情自体は、必ずしも行為無価値的だとは私は思いません。結局のところ、危険性の判断とは、結果発生の可能性の判断なので、どのような情報を前提とするかによって判断の結果は変わります。その判断基底を「行為時に行為者に与えられていた事情」に限定することは、危険性を事前的・具体的に捉えているというにすぎず、法益侵害の危険性を問題としていることには変わりがないのです。
しかし、判断基準を科学的知識に乏しい「一般人」の見地で考えることは、結果的に「一般人の不安感」を「危険」と把握し、処罰する結果になるという指摘は当を得たものと思います。その意味では、判断基準については「科学的見地」を採用したほうがよいのではないかなというのが私の印象です。
また、多少技巧的ですが、判断基準たる科学的知識について「行為者が知っていた科学的知識および一般人であれば知ることができたであろう科学的知識」という基準を用いることも考えられるように思います。
第5 具体的危険説の射程
最後にこれら不能犯論で主張されている学説がどのような罪についてまで使えるのかという問題について触れたいと思います。
1 強盗罪と不能犯
次の事例において、Aにはどのような罪が成立するでしょうか?
【事例】 Aはコンビニ強盗をしようと計画し、人の少ない真夜中の時間を狙って、コンビニに入ると、バールを振り回しながら「ゴルァ! ぶち殺されたくなかったら金を出せ!」と大声で叫んだ。だが、どういうワケかそのコンビニには、店員も、お客もだれもいなかった。そこで、Aは、カウンターの内側に回り、バールでレジをこじ開け、現金5万円を持って逃走した。一方、アルバイト店員のVは、どうせ客など来ないと思い、店舗の裏でケータイで友だちと無駄話をしていたが、店に戻るとレジが壊され、中にあった現金が奪われていたので驚いて警察に通報した。Vは友だちとの話に夢中で、Aが来たことにはまったく気づいていかなかった。
すでに「死体事例」で見たように、具体的危険説では、行為時に行為者も認識せず、一般人でも認識できなかったであろうという場合には、死体に対して弾丸を打ち込んだ行為であっても殺人未遂罪の成立を認めました。
そこで、同様の思考を働かせれば、この事例でも、店員がいないことをAが認識しておらず、また、行為当時のAの立場に立って一般人でもこれを認識しえなかったであろうという場合であれば、Aに強盗罪の実行の着手を認め、強盗未遂罪(と窃盗罪)の罪責を問うことができる、ということになるでしょうか?
しかし、これは無理なのです。
それは、強盗罪(刑法236条1項)の実行行為が「暴行又は脅迫」だからです。
この点「暴行」は、人の身体に直接向けられた有形力の行使です。強盗罪の場合は特に最狭義の暴行とされ、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものであることが必要とされます。
また「脅迫」は、人に対して害悪を告知することであり、こちらについても強盗罪の場合は最狭義の脅迫とされ、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものとされています。
いずれも「相手方の反抗を抑圧するに足りる程度」という点はともかく、暴行であれば「人の身体に」向けられていることが必要であり、脅迫であれば「人に対して」害悪が告知される必要があります。
ところが、この事例では「人」がその場にいないのです。そして「人」がいなければ、暴行も、脅迫も、成り立ちません。
しかもこの「人の存在」の要求は、その行為における「構成要件的結果発生の現実的危険」の有無の判断をする場面ではなく、その行為に対して「暴行」や「脅迫」といった文言の概念によって要求されている特質です。
そのため、これに対して具体的危険説などの「危険性を有無を判断する方法」を適用する余地はありません。
そこで、Aがコンビニの中でバールを振り回しながら「ゴルァ! ぶち殺されたくなかったら金を出せ!」と大声で叫んだ行為も、暴行や脅迫とは認められません。つまり、不能犯なのです。
したがって「死体事例」においては殺人未遂罪の成立を認める具体的危険説に立場に立つ場合でも、この事例の場合には、Aに強盗罪の実行の着手を認めることはできず、Aを強盗未遂罪とすることはできません。
せいぜいレジの中から現金を奪ったことについてAに窃盗罪(刑法235条)の成立を認めることができるということになります。なお、強盗をするつもりでバールを準備していたことについて強盗予備罪(刑法237条)の成立を認めることは、もちろんできるでしょう。
2 暴行罪と不能犯
【事例】 Bは、ある日、公園でそれまで見たことのない彫像が立っているのを見つけた。そこでこれはきっと大道芸人が彫像のフリをしているパフォーマンスだろうと思い、ちょっとからかってやろうと考えて、その頭の上からペンキを掛けた。ところが、それは大道芸人ではなく、本物の彫像だった。
この事例は、抽象的事実の錯誤の問題でもあります。Bが結果的に発生させたのは器物損壊罪(刑法261条)に該当する事実であるのに対し、Bが企図していたのは暴行罪(刑法208条)の事実でした。
この場合、器物損壊罪の法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」であり、暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」なので、まずは法定刑の重い器物損壊罪の成否から論じるのが定石です。
ですが、この事例の場合、Aに器物損壊罪の構成要件的故意を認めることはできません。法定的符合説でも具体的符合説でも同様です。ちょっと変わった説を採れば別ですが。
次に、暴行罪を認めることができるかは、不能犯の問題とも言えます。この場合に暴行罪の実行の着手を認めることができれば、未遂……ではなく、暴行罪(既遂)が認められることとなります。暴行罪は挙動犯ですから。
そこで、具体的危険説に立てば……と言いたいところですが、しかし、結論的にはこれも無理です。強盗罪の場合について論じた場合と基本的には同じです。
暴行罪の実行行為である「暴行」は、人の身体に直接向けられた有形力の行使であり、Bが人に対して有形力を行使していない以上、これを暴行と評価することはできません。これは危険性の問題ではなく、概念の問題です。
不能犯論において論じた未遂罪との区別をめぐる学説は、いずれも結果犯における実行行為が「構成要件的結果発生の現実的危険のある行為」とされることを前提に展開されたものです。これが通用しない挙動犯の実行行為や、結果犯であっても結果発生の危険性に加え、重ねて概念による枠付けがされている場合は、この不能犯に関する学説は適用することができません。
そこで、この事例の場合、Aが遂行しようとした犯罪である暴行罪については不能犯ということです。したがって、この事例においては、Aは犯罪不成立とせざるを得ない、というのが結論です。
もっとも、前述したとおりちょっと変わった説を採れば話は別です。これについては、いずれまた触れる機会が来るでしょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
