
『人間の証明』[各話解説]第十回
『銀座カンカン娘』をバックに、戦後、社会問題になっていた、アメリカ兵と日本人女性との間に生まれた混血児や、そうした子どもたちを保護する施設「エリザベス・サンダースホーム」などが紹介される。ジョニー・ヘイワードもまた、そうした子どもの一人だった。

今回のオープニングは、いつものタイトル曲がジャス風にアレンジされていて新鮮だ。『銀座カンカン娘』からの流れを計算した、ちょっとお洒落な演出。
◾️霧積で名優競演!
八杉恭子は、棟居・横渡より先に高崎駅に到着する。

上野駅に向かったのは棟居たちの方が早かったが、映像をよく見ると、恭子は特急か急行、棟居たちは普通列車に乗っている。車中では「捜査で使った経費の領収書がなかなか経理に通らない」という会話まであり、鈍行で行かざるを得ない事情を丁寧に描いている。

さて、ここから・・・棟居、恭子が群馬に入ってからは、かなり原作に沿った展開をすることになる。そして、原作のイメージを最大限に引き出す名優たちが続々と登場する。
棟居と横渡は、信越本線・横川駅から12.5キロ先の霧積温泉・金湯館へ、タクシーで向かう。

ただの移動中を楽しく演出してくれる
2人を運ぶ運転手は、車だん吉。萩本欽一のもとで芸人としてスタートし、コンビ解消後は『お笑いマンガ道場』『ぶらり途中下車の旅』などのバラエティ番組で、お茶の間の人気を博した。
この場面でも、霧積ダムの提頂で“途中下車”をする。
深い谷沿いを眺めながら、棟居がつぶやく。
「ここかもしれんな。母さん、僕のあの帽子・・・」
詩にある「碓氷から霧積へ行く道」は、今走っている道しかないという。

試しに棟居は、だん吉運転手に西条八十の詩のことを聞いてみる。
「運転手さん、知ってるかね? 『母さん、僕のあの帽子、どうしたでしょうね?』」
「帽子?」と、ダムの底を覗き込む。
「いや、いいんだ」
これは、西条八十の麦わら帽子の詩が、地元民でも知らないような古い詩であることを示唆しているが、車だん吉の妙演によって、コミカルな場面に仕上がっている。
金湯館に到着すると、舞台・映画・ドラマと幅広く活躍した川口敦子の女将が出迎える。川口の特徴である古風な持ち味と上品な語り口は、山峡の温泉旅館の女将にピッタリだ。

その女将が、長旅を経て一息つく棟居たちに、愛想よく話しかける。
女将「お客さんのご職業を当ててみましょうか? 新聞記者・・・と言いたいところですが、刑事さんでしょ」

男が2人で泊まることはまずない。だから仕事で来たのだろう。新聞記者なら一人はカメラを持っている。故に刑事である・・・と推理した女将。
ここの会話は、原作をかなり忠実に再現しているのだが、客の職業を一発で当ててみせる女将なら、さぞかし有益な情報が期待出来そうである。
早速、棟居が「麦わら帽子」の詩について聞いてみると、即答が返って来た。

「この詩なら、よく承知しております」
それもそのはず、かつて金湯館では、麦わら帽子の詩をパンフレットや色紙に使っていたというのだ。
しかし、それはもう10年以上前のこと。昔の話であれば姑が知ってるかも?ということで、金湯館老主人のお出ましとなる。配役は藤原釜足!

どこまでが演技なのか分からない、芝居のナチュラル度では日本映画史上屈指の名優から語られる古い記憶は、棟居でなくても聴き入ってしまう。
釜足主人は、昭和24,5年頃に黒人の宿泊客があったことを思い出す。
当時の宿帳をしらみ潰しに調べると・・・



「Will Heyword」のサイン。
その下に「Chieko」という日本人女性らしき名前が。
しかし、その客のことなら、もっとよく知る人物が居るという。かつて女中として働いていた中山種。霧積ダム付近の湯の沢という集落に1人で暮らしているという。
その中山種の孫・静枝が金湯館で働いており、棟居たちの部屋に呼ばれる。
静枝は、明日、中山種の家に案内して欲しいという棟居の頼みを快諾する。

「婆ちゃん、急に帰ったら喜びます!」
…しかしツラい悲劇が待っている(泣)
「昔、黒人と日本人女性が、子ども連れで宿泊していた」という話を種から聞いたことがある、と語る静枝。
棟居「ジョニーだ」
静枝が、さらに気になることを言う。
「お婆ちゃん、その女の人、知ってる人だって言ってました」
これは聞き捨てならない。
中山種が重要な事実を知ってる可能性がある。
・・・その頃、八杉恭子が湯の沢に到着していた。

夜になると真っ暗闇になるような山奥に、中山種の家はあった。
種が、ちゃぶ台に突っ伏してテレビを見ている。ブラウン管には「春一番」を歌うキャンディーズの映像。
恭子が声を掛けると、種がえっちらおっちら出て来る。霧積キャラクターズの極め付け、千石規子の登場である。

絵沢萠子、藤原釜足もかなりな存在感だったが、千石規子の〈寒村で一人暮らしの老婆〉も結構なインパクトである。
しかも、ふいに来た訪問客が誰であるのか、あっという間に思い出してしまうのだ。


一連の霧積キャラクターズの卓抜したプレイバック能力に包囲された八杉恭子に、もはや選択肢は無かった。
・・・翌朝。
棟居たちは、湯の沢に向かう途中、ダムに集まる人たちに遭遇する。みんなダムの底の方を覗いている。誰かが落ちたらしい。


ダム底に墜落したのは、中山種だった。
お婆ちゃんっ子の静枝が泣き叫ぶ姿は、何度観ても涙を誘う。

◾️文枝捜索隊、恭平を直撃!
一方、文枝捜索隊は、セントフェリス大学を訪れていた。

はじめの頃は会社に休暇を取って捜索していた新見だが、今や仕事のことなど気にもしなくなり、すっかり手慣れた聞き込みで、恭平が付近の喫茶店にいるという情報を掴む。

すぐさま恭平と路子に突撃!
「郡恭平さんですよね?」新見が声を掛ける。
小山田が、間髪入れずにぬいぐるみを突き出す。
見事に息の合った、よどみない連携プレイだ。
不意を突かれた恭平と路子は、激しく動揺する。

「そんなもの知らないよ!」
「これが恭平のもんだって、どこに証拠があるの!?」
「あんたら、アタマおかしいんじゃないの?!」
たちまち反撃の言葉が尽きた恭平と路子は、猛ダッシュで逃げて行く。
ほぼ犯人確定のリアクションを得ることは出来たが、しかしそれは同時に、文枝が二度と戻らないことも示唆していた・・・。

・・・群馬から帰宅する恭子。
讃美歌のようなイントロから、アコースティックにアレンジされたテーマ曲が、恭子の心理を映し出す。

最早、一片の余裕もない恭子。
その様子を見た陽子が、モノローグで語る。
「ママは、恭平兄ちゃんが帰って来てるというのに、嬉しそうな顔をしない。きっとママは疲れてるんです」
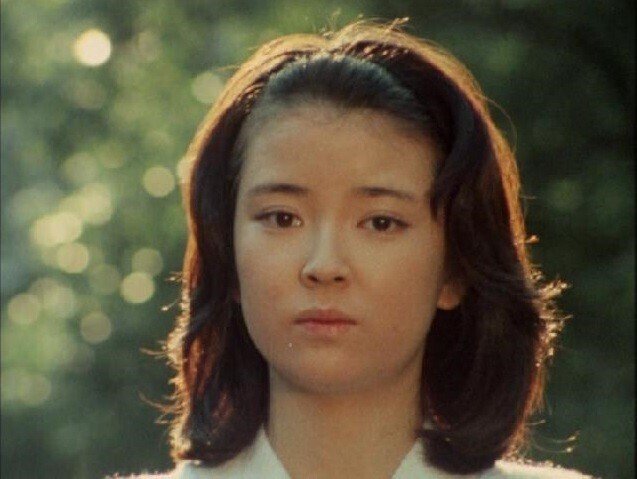
これから終盤に向けて畳み掛けてくる悪夢を、陽子はまだ知らない。
郡家の大邸宅に、秋の西陽が射す。

◾️第十回まとめ
罪を犯した恭子と恭平に、一気に追及の手が伸びていく回だった。これまでの誤魔化し、はぐらかし、すっとぼけは、もう通用しない。残り三回、郡・八杉一家は、追う者たちの執念によって、審判の道へと追い詰められていく。




【コラム「鉄道と観光とミステリー」】
松本清張は、推理小説に社会性を持ち込んだが、鉄道や観光の要素を取り入れたという点でも、その後の日本のミステリーに多大な影響を与えた。 『ゼロの焦点』の能登金剛、『砂の器』の東北と山陰、『球形の荒野』の唐招提寺、『山峡の章』の阿蘇。『点と線』『時間の習俗』などは、雑誌「旅」で連載された。
これらの背景には、昭和30年代以降に拡大した観光の大衆化があるだろう。その時代、時刻表を駆使したアリバイ・トリックを得意とした鮎川哲也も、鉄道趣味のミステリーを多数発表している。
それらは、後の国内ミステリーに大いに継承され、2時間ドラマの定番にもなったことは今さら説明不要だが、森村誠一の初期にも『新幹線殺人事件』『虚構の空路』といった公共交通をトリックに使った作品や、『日本アルプス殺人事件』『密閉山脈』といった山岳ミステリーがある。
『人間の証明』においては、霧積のみならず、ニューヨークにまで場面が飛び、地下鉄やスラム街が写実的に描写されている。そのため、映画化された作品で初の本格アメリカ・ロケが行われるなど、『人間の証明』という作品が、日本のエンターテイメントを飛翔させる起爆剤となったことは、間違いないだろう。
本作第十回のタイトル・バックが疾走する高崎線であるところも、我が国のミステリーと鉄道の親和性を感じさせる。 いずれにしても、日本のミステリーと観光・鉄道は、他国では類を見ないほどの親密な関係性にあると言えるだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
