
今年出会えた本の事
この1~2年でどういう訳か、自分でも驚くほど読書量が増えた。
もともと読書は好きな方ではあるが、それにしても増えた。演芸に関する本を中心に、今まで手を付けてこなかった小説に、エッセイ、果ては歌集まで、ジャンルを問わず読むようになった。
年々娯楽や楽しみが多様化している昨今、ここに来て「読書」が今、自分の中の娯楽の最上位に来ている。暇さえあれば、本屋や古書店に行き、自分の琴線に触れた本を躊躇なく買っては、寝食忘れて読みふけるなんて事がざらにある。いちいちテレビやパソコンの電源を入れるなんて煩わしい事をせずに、世界観に簡単に没入できる所に、人間33年目にして今更ながら楽しみを感じ始めた。本当に「今更ながら」である。
1冊1冊を丁寧に読み進めるのが基本スタンスだが、読む速度がべらぼうに遅い読解力に難があるくせに、読みたい本を見つけると有無を言わず入手するテンポが反比例にどんどん加速していき、ついには人生で初めて「詰み本」なんて状況も経験した。読んでも読んでも減る気配がない。現在進行でこの「詰み本」の山を日々マイペースに登り続けている。嬉しい悲鳴である。
そんな訳で今回は、今年1年で読んだ本の中で印象的だった物を何冊かピックアップして紹介してみようと思う。
西村賢太『苦役列車』(新潮文庫)

この人の書く強烈な私小説の魅力を知れた事が、今年一番の収穫だと断言できる。まさかこの年齢で、好きな小説家が出来るなんて夢にも思っていなかった。それも肝心の著者が亡くなった年にファンになるとは。せっかく人生で初めてハマった小説家が出来たというのに、もう永遠に新作を読む事ができない。
そうだ。西村賢太はもうこの世にいないんだ。
本著で第144回芥川賞を受賞。その受賞会見で「そろそろ風俗に行こうかなと思ったところ」と発言し、日本中から爆笑と顰蹙を一瞬で獲得。その荒々しくも、どこかチャーミングな人物像に世間は釘付けになった。ご多分にもれず自分もその一人である。
その特異なキャラクターをメディアがほっておく訳がなく、芥川賞受賞特需であらゆる媒体から引っ張りだこ。抱いていた「小説家」のイメージを大きくかけ離れた熊のような大男が、朴訥で不器用な感じを醸し出しながらメディアの仕事をこなす様は、他のタレントには無い異様な存在感を放っていて、自分の中で妙に気になる存在になっていった。「普段小説なんて読まないけど、この人の書いた物なら読んでみたいかも」なんて事を思っていたが、いかんせんその当時はそこまで読書が習慣づいていなかった事と、いつでも読めるという安心感についつい胡坐をかいてしまい、時間だけ過ぎていった。
2022年2月4日。西村賢太死去。
「苦役列車」はある日突然何の前触れもなく脱線した。
一報をツイッターで知った瞬間に、強烈な後悔の念が胸を埋め尽くした。
「なんでこの人が生きている間に、作品を読まなかったんだ」
すぐさま書店に向かい、手に入れたのが本著である。
私小説も、そもそも純文学すらまともに読んだ事がない自分にとって、この本は、まさに「目から鱗」だった。純文学って、私小説って、こんなに荒々しくて、堅苦しくなくて、メッセージ性が無くていいんだ。むしろ、そういった小説に対する凝り固まった固定概念に真っ向から中指を立て、足蹴にしているかのようなそのハードボイルドな作風に、得も言われぬカッコよさを感じた。
主人公・北町寛多が厄介な自意識と劣等感を抱えながら、将来への希望も無く肉体労働に従事して生きる日々を描くスピード感のある文体が、興味を引き離さない。同時に、強烈なまでの「男の体臭」みたいな物がガツンと鼻を突いてきて、頭がクラクラとしてくる。小説を読んているのに、匂いで表現するのはおかしな話だが、読みながら本当にそんな感覚を味わった。
果たして、一瞬でこの人の書く私小説の虜になってしまった。
そこから現在までの数か月の間、書店や古本屋でこの人の作品を見つけ出しては読みふける日々が続いている。『小銭を数える』『どうで死ぬ身の一踊り』『芝公園六角堂跡』『疒(やまいだれ)の歌』『暗渠の宿』…と山のように残された私小説。
小説以外にも随談集や対談集も面白いが、特に好きだったのが『一私小説書きの日乗』という日記シリーズ。多忙に追われながら、あらゆる出来事・剥き出しの感情が凝縮された日常が淡々と綴られている。現代に生きる破滅型私小説家の日常。面白くない訳が無い。
ここまで読んでいただいて察しがつくと思うが、この人の書く私小説はかなりクセが強い。故に、合う人は底なし沼が如くその魅力に飲み込まれる事必至だが、肌に合わない人は、おそらく他の作品も合わないと思った方がいい。そういう意味では、『苦役列車』は西村賢太作品に対するリトマス紙の役目になっている基準のような作品だと思う。
生きている間に追いかけられなかった後悔を胸に抱きつつ、遅ればせながら西村賢太が敷いていったレールを追いかけられる事を幸運に思う。
立川談四楼『文字助のはなし 立川談志を困らせた男』(筑摩書房)
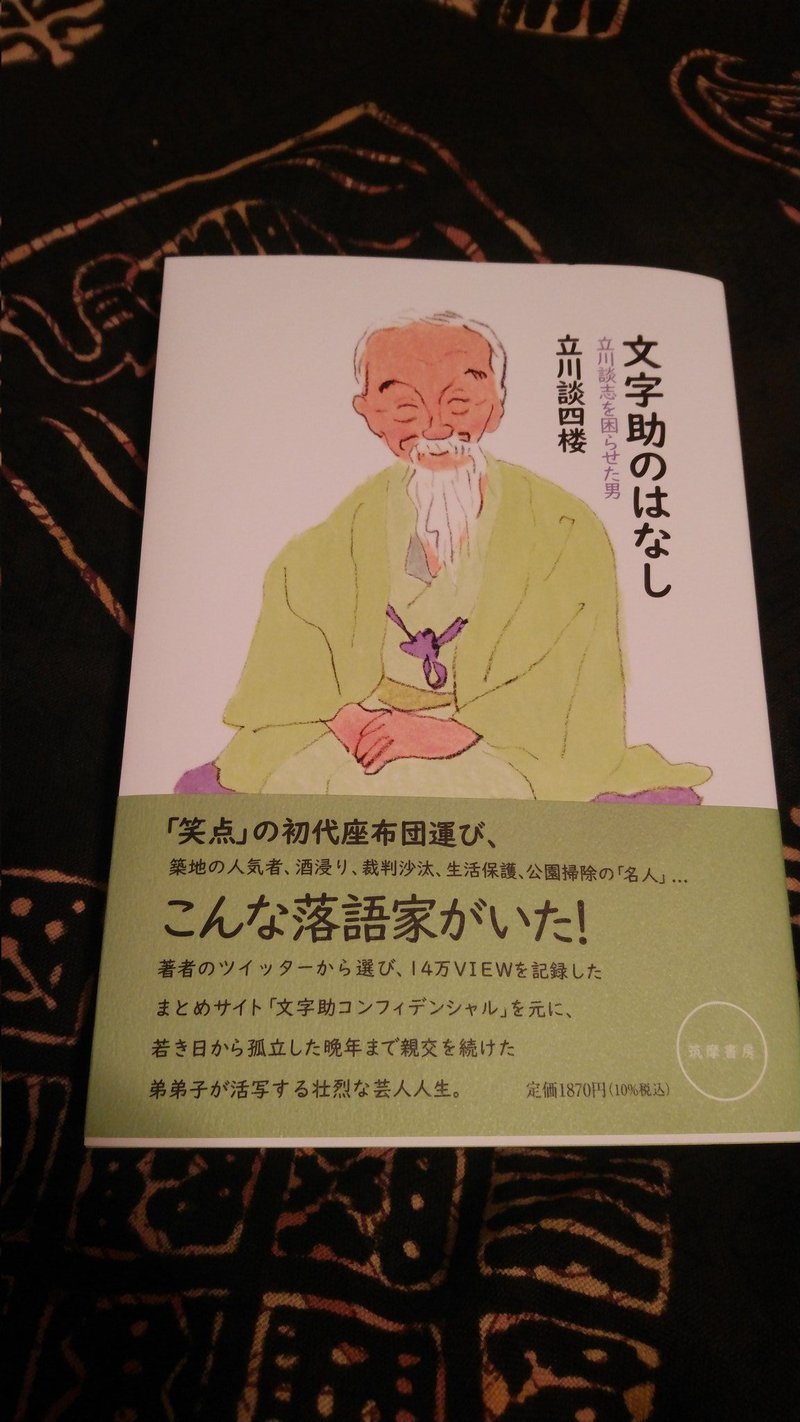
「桂文字助」という名を聞いてピンとくる人は、かなり、というか相当に拗らせている落語ファンだと誇っていい。
六代目三升家小勝へ入門し、前座・三升家勝松としてそのキャリアをスタート。本寸法の落語と礼儀作法を徹底的に仕込まれ、仕事ができる前座として頭角を現した所に目を付けたのが、あの立川談志。そこから『笑点』の初代座布団運びに前座ながら抜擢された。ちなみに、二代目座布団運びは、ご存知毒蝮三太夫。「マムシの師匠」である。
小勝没後、談志門下へ移籍し、立川談平と改名。そのまま真打に昇進し「四代目桂文字助」を襲名。
立川流フリークの自分にとって、桂文字助という落語家のイメージというと「立川流きっての武闘派」「兎角喧嘩っ早い」「築地市場に顔がきく」「相撲噺の名人」云々。
群雄割拠、個性が乱立している落語立川流という組織の中で、強烈に恐れられていて、組織全体に睨みを利かせている。そんなイメージが関連著書を読み漁っていく内に練りあげられていった。
いつか生の高座を見てみたいと思う落語家の一人だった。
自分がTwitterを始めた2012年頃。著者である立川談四楼のTwitterアカウントに辿りついた。小説家・文筆家の面を持つ多才な師匠だけに、その文章力が冴えるツイートのファンになった自分はすぐにアカウントをフォローして、定期的に更新されるツイートを読むのを日々の小さな楽しみにしていた。
そのツイートの中で、不定期に文字助の話題が混ざっている事があった。
この時点で、文字助はもう殆ど落語家としての活動はしておらず、近所の公園清掃のボランティアを生業にしながら生活しているという。そこでの日常、騒動などが端的なツイートとして流れてくる。
これがべらぼうに面白い。
気づけば「今日は文字助師匠関連のツイートあるだろうか」と、ツイートが更新される度にワクワクしていた。すっかり文字助のファンになっていたのである。
同じような気持ちのファンは多いようで、とある奇特なファンが文字助関連ツイートをまとめた「文字助コンフィデンシャル」なんて物まで拵えた。今も検索をかければ楽々とヒットするので、興味ある人は是非とも読んでみる事をお勧めする。酒でも吞みながら読むと、なお良し。
本書は、破天荒な兄弟子・桂文字助と最後まで付き合い続けた著者・立川談四楼による、愛と葛藤が交錯する「四代目桂文字助」ただ唯一の評伝である。
先述した通り、前座ながら「笑点」の座布団運びに抜擢され、築地市場に多くの贔屓客を持ち、地域寄席まで開催。演者としても本寸法の落語を演じる腕を持つ。
そんな「順風満帆」と言える芸人人生に陰りを落とした原因が、天賦としか言いようのない酒癖の悪さと傍若無人な振る舞いだった。
次第に贔屓筋からどんどん人が離れてゆき、ついには立川流の中でも孤立するようになってしまう。そして、いつしか落語から離れてしまい、気づけば「公園の主」に収まっていた。
「文字コン」(文字助コンフィデンシャルの略)からは、どこか悠々自適に今の暮らしを満喫している文字助の様が想像された。でも、その様を堂々と胸を張って語る文字助の様には、どこか「ひけらかしている」というか、違和感のような物が同時に感じ取れた。
元々六代目小勝門で、徹底的に礼儀作法から人への気配りまでを仕込まれている。文字助は、人からどう見られるかに関しては、常人以上に、いや同業者である芸人以上に過敏に感じ取る人だったのではないだろうか。だから、そのコンプレックスの裏返しで、あえて悠々自適とした様を看板として見せていたのではないだろうか。やがて生活保護を受給する事になるのだが、文字助は著者を始め周りに受給した事を実に誇らしく吹聴していたという。芸人らしい見栄と、その裏側に潜んでいる「負い目」「後ろめたさ」のような物が見え隠れしているその様は、可笑しくもあって、でもやっぱりどこか悲しい。
終盤、それまで淡々と過去の文字助ツイート紹介しつつ、補足のエピソードを付け加えるなど軽妙な文を展開していた著者の想いが噴出する。冷静を保ちつつ、ギャグも交えてはいるんだけど、得も言われぬ熱い物が文に通っている。ラストおよそ30ページ、贔屓にしていた客、立川流の仲間と沢山の人が離れていっても、最後の最後まで兄弟弟子としての関係を続けてきた著者だからこその、文字助に対する愛情・苛立ち・葛藤が凝縮された文が一気に放出されて、読み手の心を鷲掴みにして離さない。
四代目桂文字助
傍若無人。唯我独尊。酒癖最悪。
こんな芸人が、つい1年前まで実在していた。
-----
ひょんなきっかけで、ある時期から「相撲噺」しか演じなくなり、ついた異名が「相撲噺の文字助」。その名演がなんとYouTubeに上がっている。YouTube、恐るべし。
興味ある方は、是非聞いてみて欲しい。本著を読んだ後に聞くも良し。
まさに本寸法。看板に偽りなしの名演である。
,
さらに、これは本著を読んだ後に是非聞いて欲しい。
著者以外に数少ない交流があった柳家小袁治が自身のYouTubeチャンネルに上げた、文字助からの留守電。
本の世界を追体験できる貴重な資料である。
松垣透『落語狂人 快楽亭ブラック』(彩流社)

本著に帯が付いていて、そこに「祝・古希記念」と大きく記されていた。
あの快楽亭ブラックが、古希を迎えた。古来より稀な70歳である。
二代目快楽亭ブラック
今、一番「生き様を魅せてくれる」落語家だと思っている。「今どの芸人を追いかけていて、一番楽しいか」と聞かれれば、問答無用で快楽亭の名を上げる。
今、快楽亭ブラックが面白い。とにかく面白い。
大好きな映画、歌舞伎、競馬を楽しみ、旅、酒、食、温泉を味わい、そして落語を極める。
芸、人生、哲学、思考… 年齢を重ね、あらゆる楽しみを吸収し、落語を洗練させてゆく度に、快楽亭は常人が到達した事のない「高み」へと昇ってゆく。
本著は、新聞記者である著者が快楽亭ブラックに長期密着し、その思考と感性を見届けたドキュメントである。時に至近距離から、時に一定の距離を置きながら「落語」の、いや「人生の達人」になりつつある快楽亭の真髄に迫っている。
立川談志に入門、真打昇進まで計16回の改名、二千万円の借金問題が発覚し立川流を除名、大動脈解離で死線を彷徨い、元弟子とその彼女から名誉棄損で訴えられ…
物凄く端折ったが、この短文でも快楽亭ブラックという芸人の強烈すぎる人生が伝わってくると思う。本著と、快楽亭が執筆した『立川談志の正体 愛憎相克的落語家師弟論』(彩流社)と合わせて読むと、この強烈な人生を原液レベルの濃度で面白可笑しく味わえる。
自分は今まで見てきた演芸のライブについて記録メモを残す事をライフワークにしている。
過去のメモを引っ張り出すと、初めて生のブラック落語に触れたのは今から5年前の2017年8月とあった。快楽亭は毎年夏と冬に、札幌へ毒演会を打ちに来てくれて、コロナで2年ほど中止の期間もあったが、自分は以来ほぼ皆勤でこの毒演会に参加し続けている。
下ネタ、宗教…と現世のあらゆるタブーをぶち込んだブラック落語、正調の古典落語が楽しみなのは大前提だが、本題前の時事ネタを織り込んだ一切口外できない刺激の強すぎるマクラも醍醐味である。
世間で何か禍々しかったり、きな臭い事件が起きたりすると、「快楽亭なら、この話題をどう話すだろう」という思考が頭の中の片隅にあり、不謹慎だが次の毒演会までに何か事件が起きてくれないかというワクワク感さえ抱いている時もある。
立川談志が存命の頃、多くの談志ファンは何か世間で事件が起こると、「談志ならこの事件に何と言うか、どう考えるか」を聞きに、寄席や独演会に詰めかけたという。常識を鼻で笑い、体制に噛みつく、その反社会的なマクラや漫談は、日頃常識に縛れた生活を送る大衆からすれば実に刺激的で、そして痛快だったと聞く。
自分は立川談志に間に合う事が出来なかったが、この系譜を自分の形で継承している快楽亭ブラックには間に合う事ができた。どれだけ幸運な事だろう。舌鋒鋭く、タブーの際限という概念が存在しない快楽亭の芸から、在りし日の立川談志の毒舌をオーバーラップし思いを馳せつつ、毎回の毒演会を存分に楽しませてもらっている。
本著の紹介のつもりが、快楽亭への想いが長くなってしまった。
先にも書いた通り、本著は快楽亭へ長期密着し、そこでのインタビューを主軸に展開されている。新型コロナ禍の中、著者は旅にも同行し、その土地の物を共に食べ、温泉に浸かり、酒を傾けた。そんな中でいつしか心を許し、ついつい漏れ出た快楽亭が抱く人生観、落語論、芸や人に対する本音がどれも深くて、そして切れ味があり、実に興味深く読ませる。
読み終わった後、間違いなく思う。「快楽亭ブラックは、今が頂点ではなく、到達点に過ぎない。これからも進化を続け、我々を楽しませ続けてくれる」と。
何度も書く。
今、快楽亭ブラックが面白い。
東野幸治『この素晴らしき世界』(新潮文庫)

最近自分の中で、「吉本の白い悪魔」が熱い。
理由は2つある。
1つは、北海道で土曜の昼に「マルコポロリ!」(関テレ)の放送が始まった事。東京の番組でも扱わないようなニッチな芸人の掘り下げ企画を毎週やり、そこで先陣を切ってツッコんで、イジって、けなして、嘲笑し、爆笑を量産している東野幸治の様は、まさに「無双」。毎週あれこれ形を変えながら、高品質の悪意を維持し爆笑を量産する様を見て、自分の中の「東野幸治」株が急騰の予感を見せ始めた。
※余談だが、この「マルコポロリ!」のレギュラーメンバーに漫才コンビ・メッセンジャーあいはら(通称パラちゃん)がいる。全国的な知名度は高いとは言えない人だが、この人もメチャクチャ面白い。性格が歪みきったクソ人間っぷりが最高。
そして、「東野幸治」株の急騰を決定づけたもう1つの理由が、この本である。
本著は、「週刊新潮」で連載されてきた、芸歴30年を超えた東野幸治が今まで出会ってきた吉本興業の芸人の、奇行蛮行をスケッチしたコラムの書籍化である。
西川きよし、坂田利夫といった大ベテラン、トミーズ健、130Rほんこん、リットン調査団といった同じ時代を生きてきた先輩、品川庄司・品川、キングコング西野といったテレビだけでなくあらゆる分野で活躍を見せる後輩と、扱われる吉本芸人の幅は多岐にわたる。その交遊の広さも凄いが、紹介されるエピソードがくだらない物から耳を疑う衝撃的な物まで、全編面白い。
読み始めてから読み終わるまで、ずっと腹を抱えて笑いっぱなしだったという本は、人生で初めてかもしれない。
著者である東野幸治のスタンスは「語り手」である。当事者本人から聞いた話であったり、他者から伝わってきた話を「こういう事があってね」といった感じで、終始俯瞰から眺め、淡々と冷めた文で活写してゆく。
その様は、「心の無い司会者」「サイボーグ」「サイコパス」と評される、テレビでの普段のあの容赦ない振る舞いを彷彿とさせる。特に、ダメなエピソード、イタい恥ずかしいエピソードの時などは淡々としながらも、どこか嬉々としている感じが文章の裏側から如実に強烈に伝わってくる。あの嘲笑が全面に出た悪い笑顔をニヤニヤとたたえながら文章を楽しそうに書いている様が、容易く脳裏に浮かんでくる。
基本的に、悪意しかない笑いに満ち満ちた本著だが、同じ時代を生きてきた先輩・リットン調査団とのおっさんになっても変わらない関係性や、宮川大助・花子の漫才に対する執念と愛の物語など、胸がいっぱいになるエピソードもあり、東野幸治の文章力・スケッチ力の妙に打ちひしがれた。
吉本の白い悪魔・東野幸治が語る「この素晴らしき世界」は、異常で、混沌としていて、くだらなくて、バカバカしくて、そしてとにかく愛おしい。
皐月彩『バックヤード』

特撮ドラマ「ウルトラマン」シリーズや数々のアニメやドラマの脚本を担当し、小説、ライターと幅広く文筆の分野で活躍する脚本家・皐月彩さんのエッセイ。
脚本だけで生活が出来ていなかった当時に飛び込んだ、秋葉原のメイドカフェでのバイト模様や、そこで交錯する人間模様などの体験談を凝縮させた一冊である。
今から4年ほど前に、脚本を担当していた「ウルトラマン」シリーズでその存在を知り、担当する脚本回が妙に自分の中で印象に残り、そこから次第に彼女の書く作品のファンになっていった。まさかそこから、ひょんなきっかけで「お笑い大好き仲間」として当たり前のようにやり取りをさせてもらえるようになるなんて、縁なんて物はどこでどう繋がるか分からない。
作品をあれこれ見ていく内に、次第に「皐月さんのパーソナルな文を読んでみたい。エッセイとか書かないんだろうか。」なんて漠然と思っていた矢先に、この本が出る事を知った。それも内容は「メイドカフェでのバイト時代の話」を書くという。絶対面白くない訳がない。
デジタル音痴を拗らせに拗らせた自分だが、四苦八苦しながらネットを駆使し、人生で初めてネット通販で「同人誌」という物を買った。
秋葉原といえば、日本のメイドカフェ、いやコンセプトカフェの総本山。一体どんな華やかな所で働いていたのか楽しみしながら読み始めたが、そこは「宇宙メイドカフェ」という謎過ぎるコンセプト、内装は銀紙みたいな壁紙がびっちり貼られていて、所々破れ、調理場はコンクリ剥き出しで薄濡れていて、カビ臭いクローゼットにはいつ洗ったか分からないような衣装が積み上がっている、「世紀末」みたいな飲食店だった。そのツッコミ所が多すぎる、荒みきった光景の描写に、思わず噴き出し、一気に心を鷲掴みされた。
皐月さんは最初はその環境に戸惑いながらも、次第に順応していき、最終的にはメイド服の上からスカジャンを着て、電気ブランのメロンソーダ割りを呑み、自分のバースデーイベントの時には、自身の出身地であるエジプトの料理「コシャリ」を振る舞うメイドへと華麗に進化してゆく。どんなメイドだ。
自分は20代の前半から終わり位まで、贔屓していたメイドカフェを持っていて、今の交友関係の99%はコンセプトバーで形成された。※因みに、そのバーは「特撮」をコンセプトにしたバーで、そこで繋がった友人達と東京旅行に行くまで仲良くなった。
長い間、メイドカフェ・コンセプトカフェ(通称コンカフェ)の良い面も、悪い面も眺めてきた身として、本著で描かれるエピソードは共感しかない物から、身につまされる物まで、全編ストライクゾーンど真ん中。
個性が爆発しているご主人様、自分のバースデーイベントに対する苦労、チェキなどのコンカフェあるあるに笑いながら共感するその一方、理由も分からないまま突然消えてしまうメイド、卒業しても現実社会になじめず「転生」を繰り返すメイド、自分にとってメイドを「都合のいい人形」としか思っていない客など、目を背けたくなるような受難や苦悩に思いを馳せた。
主人公である皐月さんは、決して器用な人ではない。器用な人だったら、自分のバースデーイベントに「コシャリ」は出さない。
不器用かもしれないが、とても真っ直ぐで気取らず、等身大の自分を隠さない。そんな人柄が文章から伝わってくる。
そして、心底「人」が大好きなんだと思う。
メイドを傷つけた心無い客に熱く怒りを燃やし、ひっそりと消えていってしまったメイド達をに対して、何かもっと寄り添ってあげれたら、救ってあげられたのではないかと後悔の念に苛まれる。
こんなに素直に誰かのために怒れて、後悔ができる人はなかなかいない。
だから、この人の描く作品の登場人物達はみんな優しくて、温かい。
皐月さんはこれから一体どんな仕事をやってのけてくれるのだろうか。
これからもファンの一人として、「お笑い大好き仲間」として、活躍が楽しみで仕方ない。
上坂あゆ美『老人ホームで死ぬほどモテたい』(書肆侃侃房)
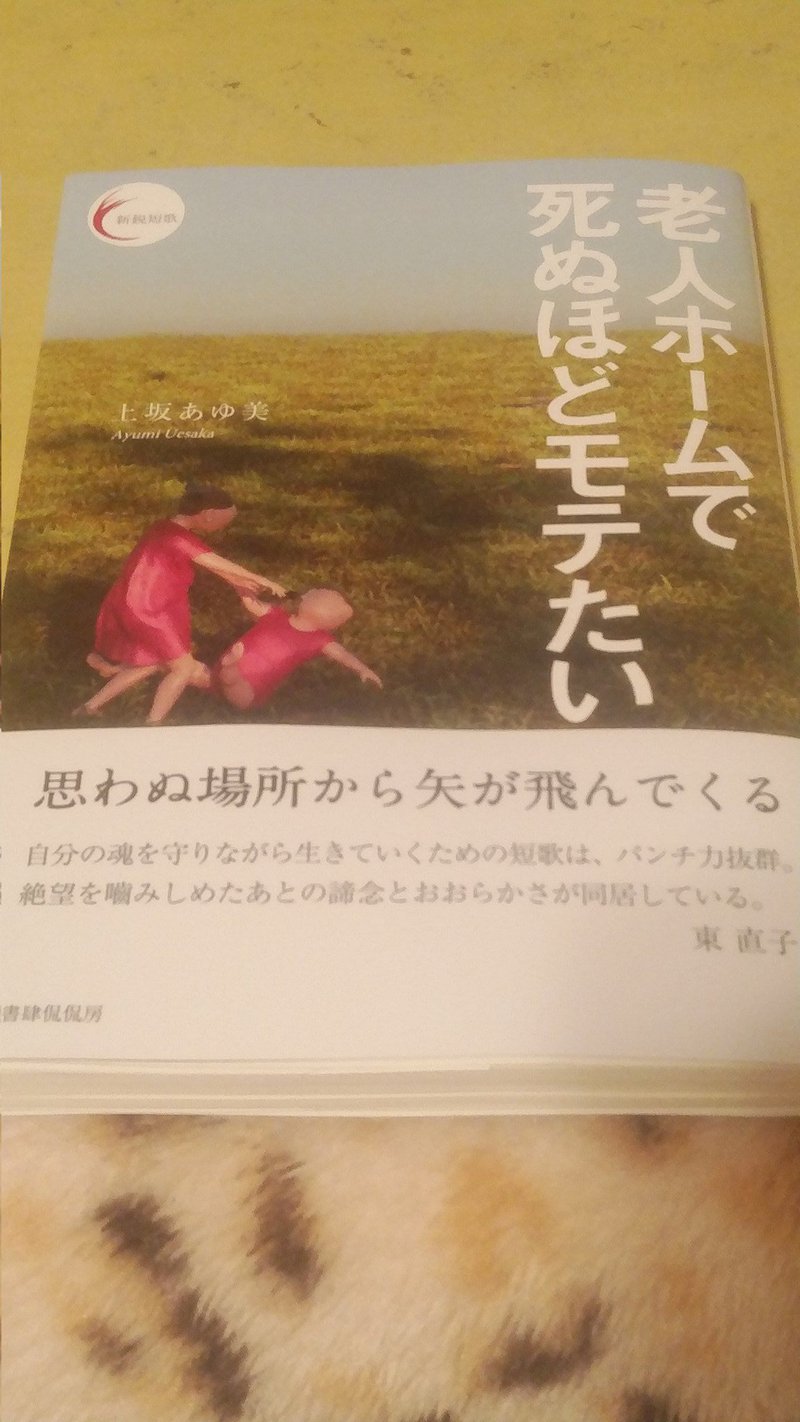
この33年の人生で、まさか自分の稼いだ金で「歌集」を買う人生になるとは、夢にも思わなかった。
「短歌」という文化にちゃんと触れてきた事も無いくせに、なぜか苦手意識だけは持っていた。「何かあれば、恋愛とか、色恋の事ばかり題材にして、あれこれ小難しくのたまわってる文学」という偏見以外の何物でもない偏見が、いつの間にか脳にデフォルトで設定されてしまっていた。
何がどうしてそうなったのかという原因は、自分でもよく分からない。中学か高校の国語の授業で、何となく触れた事は朧気に記憶にあるが、自分の人生の中での「短歌」の位置は、普通の人よりもマイナスの所にあった。
そこから多分十数年後。何気なくツイッターのタイムラインを眺めていたら、誰からのリツイートでこの歌集がもうじき発売されるという告知ツイートが流れてきた。その歌集とは思えないアバンギャルドなタイトルに、興味の琴線がざわついた。
近所にある行き慣れた本屋の、それまで一度も行った事のない歌集コーナーに行くと数冊並んでいて、一番手前にあったカバーのされていない物のページを開く。「歌集なぁ… 言い回しとかよく分かんなくて小難しいんよな」とか思いながら、2,3首ほど読んでみる。
気付いたら、会計が終わっていた。
あまりにも自然な流れで購入してた事に気付いた時は一瞬戸惑ったが、「あ、巡り会うってこういう事か」と腑に落ちた。
個性的な家庭環境に振り回されながら、閉塞感が漂う地元で学生時代を過ごし、進学で東京へ上京。そのまま就職し、それなりの恋愛を経験し、日々の生活を営んでゆく。どこにでもありそう典型的な人生の流れを辿りながら、場面ごとに短歌が編まれていくのだが、これが実に独創的で斬新。
どことなく「諦観」のような視点が見え隠れしていて、常に状況を俯瞰から眺め冷静にスケッチしているかと思いきや、その刹那全く予想していなかった言葉が、読み手の死角をめがけて投げつけられる。予想だにしない言葉のチョイスに「プッ」と噴き出したかと思えば、次の歌ではさっきとは全く違う方向からの言い回しに心がどよめく。
たかが31文字に、頭と心が振り回される初めての感覚。
「短歌って、こんなにカジュアルで、シニカルで、不条理でいいんだ」と、目から魚数十匹分の鱗がボロボロと落ち続けた。
ボコボコにされヘロヘロになりながら、最後の「あとがき」に目を通す。どうしてこの歌集のタイトルが「老人ホームで死ぬほどモテたい」なのか。その理由が書かれていた。その理由が知った時、「そういう事かい」と笑いながら、この歌人を素直に心から応援していきたくなった。
本書は「歌集」という形を借りた、上坂あゆ美という一人の新進気鋭で不器用な女性歌人の人生サバイバルドキュメンタリーである。
本の紹介のつもりが、色々脱線して、こんなに長くなってしまった。
拙いくせに、ダラダラと長い文章で恐縮だが、これを読んで一人でも今回紹介した本を手に取ってくれるきっかけになる事をささやかに願いつつ、今回のnoteはこれにて。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
