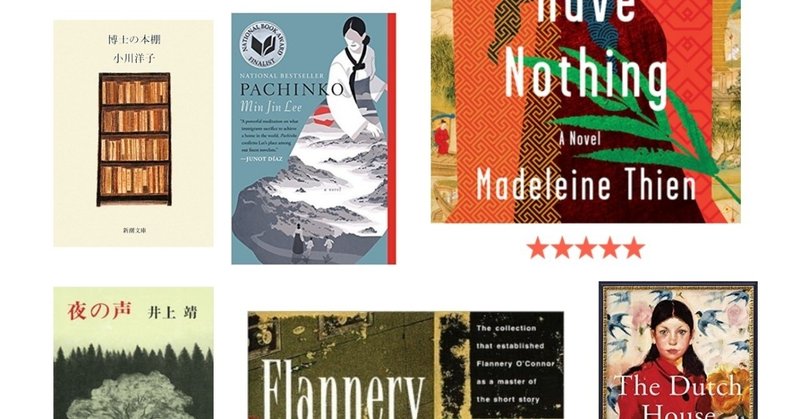
Goodreads Reading Challenge 2020から軽く書評など
Goodreads今年の読書チャレンジ、結構本がたまってきたのでここらで中間発表+特に印象的だったものの書評。早い話が「これだけ本読んだぜ偉いだろう」アピール。やってみたかったのでうざいけどお付き合いください。
基本的に、小説に関しては構成や描写の巧みさ、エッセイやノンフィクションに関しては公正性や正確性、着眼の面白さについてで評価してるので、全体的に評価は辛めです。キャラクターへの思い入れ、著者の視点や見解に賛同するかしないか、といった点はほぼ勘案してないのでファンの方は叩いたりしないで。
和書、洋書に関わらず、登録した本の版は基本的には自分が読んだ言語の版です。なので日本語版を読んでる場合、データベースに登録されてる書名がローマ字表記だったり、データ少なすぎて表紙画像が登録されてない、など見づらい場合があります。
原語版を読んでる場合、レビュー内の表記と翻訳された語では固有名詞等違う可能性があります。
★★★★★
Do Not Say We Have Nothing
/Madeleine Thien
天安門事件後のバンクーバー。中国系カナダ人のマリーの家庭に、家族を捨てた父の友人の娘だというアイミン(愛明)が到着する。アイミンが持っていたミステリアスな「記録の書」を通じて、マリーはアイミンの家族の歴史、父とその友人の絆、父が失踪した背景を紐解いていく。
「小説に関しては構成や描写を〜」とか言っといて初っ端からアレですが、これに関してはそれだけでは評価できなかった。構成自体はややぎこちなく、全体の構成に不可欠とはいえ、現在の章が過去との強いつながりを持たないので、これらの章が挟まるとちょっと白ける。
評価の主は過去の章。描写が瑞々しくうつくしい。文化大革命の中、中国の伝統音楽やグレン・グールドのピアノの調べに彩られた3世代の物語が絵画的で静謐。その背景で不気味にうねる時代のダイナミズムが、露悪的な描写は控えめなのに、登場人物たちを翻弄していく様を通じて肌身に感じられて圧巻。特に終盤の天安門事件に至る描写は、激動なのに静謐という独特の趣があって忘れられない。
登場人物たちもみんな、おとぎ話のようなのに人間的な奥行きがあって良い。
アンダース・ゾーンが撮ったラストエンペラーを観たような読後感。
Little Fires Everywhere
/Caleste Ng
リチャードソン夫人の人生は完璧だった。ある朝、末の娘が家に放火して出奔するまでは。どこでボタンをかけ違えたのか。シングルマザーの写真家に借家を貸したから?親友がアジア人の捨て子を引き取ったから?
ページをめくる手が止まらない、というくらい面白い本に久々に出会った。同時進行で語られるストーリーラインはそれぞれ展開としてはありきたりだし予測できてしまうのに、パズルのピースのようにうまいことはまり合ってピタゴラスイッチ的に話が進んでいく。そのはまり具合にニヤニヤする。
キャラクターどうしのダイナミクスが巧みで、特に主人公のひとり、リチャードソン夫人の善意の中にある欺瞞が徐々に悪意に変わっていく、という心理描写がリアル。話を転がしているのはそういうひとの嫌なところなのに、描写が意地悪くなくコミカルですらあるので、読後感は軽やかで嫌味がない。
作者自身のサイレントマイノリティとしての怒りが時として前面に出過ぎてるのが難といえば難か(でもアジア系としてアメリカで暮らした身としては、あるある過ぎて逆に面白いけど)。
各段階で読者がキャラクターにどういう感情を抱くかとか、話の展開をどう先読みするかとか、全部計算されてるんだろうなあという、作者の掌で転がされてる感じが心地いい。
★★★★
The Shell Collector
/Anthony Doerr
短篇集。ケニアの浜辺で貝を収集する盲目の男に訪れた奇妙な巡り合わせ。別れた妻から20年ぶりに届いた手紙。妻には、死んだものの体に触れて心の断片を読み取る力があった。海辺の街に引っ越してきたグリセルダは、フライフィッシングをする少年に魅せられる。
自然と人間の関わり、が耳触りのいい要約なんだろうけど、それだけでは語りきれない。
自然はいかにも大陸的な自然で、共存するとか包み込むとかでも優しいとか厳しいとかもなく、ただそこにある。出てくる人たちは障害者だったり難民だったり、だいたい何か欠けてたりなくしてたりする(著者の別の作品 'All the Light We Cannot See'でも主人公は盲目の女の子だったので、何か根源的なテーマなのかもしれない)。その両者が何か与え合うでもなくただオーバーラップして、跡にはただオーバーラップした事実だけ残る。結果なんて確固としたものではない。癒やされるなんて陳腐な手応えもない。その匙加減が美しい。
文体がとにかく美しい作家さんで、読んでるだけでも心地良い。短篇らしい構成の妙もある。個人的には短篇の方が巧い人だと思う。
A Good Man is Hard to Find
/Flannery O'Connor
短篇集。ドライブに出かけた家族を襲ったのは、脱輪と3人のアウトロー。祖父に連れられて初めて街へ出てきた少年は、生まれて初めて黒人を目にする。農園主が雇い入れた移民の家族は、農園に予期しなかった波紋を投げかける。
友人からの推薦。マーガレット・アトウッドを何冊か読んだ(そして後に嫌いだと気づいた)と言ったらおすすめされた。自分的にはオコナーの方が全然好みだったので感謝してる。
アメリカ南部を舞台に、色濃く残る奴隷制の影響をモチーフにした作品が多い。
差別や暴力といったものに対する善悪から意図的に引いた視点で、南部のある種異様な光景を淡々と描き出す。視線は観察でもするように恐ろしく正直。引いてるからこそ構成の巧さが半端ない。大抵の作品が2段構えの落ちで、1段目でも巧いのにもう1段あるのかと唸らされる。
無邪気で突拍子もない暴力はタランティーノに通じるものがあるけど、それに伴う乾いた笑いが、暴力それ自体とその結果ではなくて純粋に状況という点でかなり独特だと思う。ヒリヒリするような皮肉さが爽快感すらある。
The Road(邦題: ザ・ロード)
/Cormac McCarthy
世界が崩壊した後のアメリカ東海岸。幼い息子を連れた男が、灰と雪の降る中を、たった一筋、道を辿って南を目指している。動物も草も絶え果てた大地。たどり着いた先に何があるのかは分からない。
究極のセカイ系。閉塞感と絶望感が圧倒的。嫌でも情景が浮かぶので、灰の降りしきる寒々とした荒野に息が詰まりそうになる。
簡潔かつ詳細な描写を積み重ねるスタイルは好みが分かれそう(自分にはハマらなかった)。読点のない文章は、英語ネイティブではない自分には時々意味が取りづらく、若干読みづらかった。
おおかたの終末ものと違って、旅の途上で他者との交流はかなり少ないし、頼りになったり足を引っ張ったりする仲間なんかいない。何かが起こっても劇的な展開には発展しないし、前々からの目的が達せられてもカタルシスなんかない。だから男と息子のシンプルな関係性がすごく印象に残る。あと桃の缶詰が食べたくなる。
呑まれるような静かな緊張感、淡々としてるのに中だるみのない構成、緩急、象徴的な関係性、会話。とにかく巧いなーと思う。
結末は予想できるものだろうけど、丁寧に積み上げられた過程のおかげで、読後残ったものを言葉にできない。
以上です
読書感想文は大嫌いだけど書評って楽しいですね。
次回は来年か、また本がたまったらやります。それまでにまた誰かに話したくなるほど好きな本が増えるといい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
