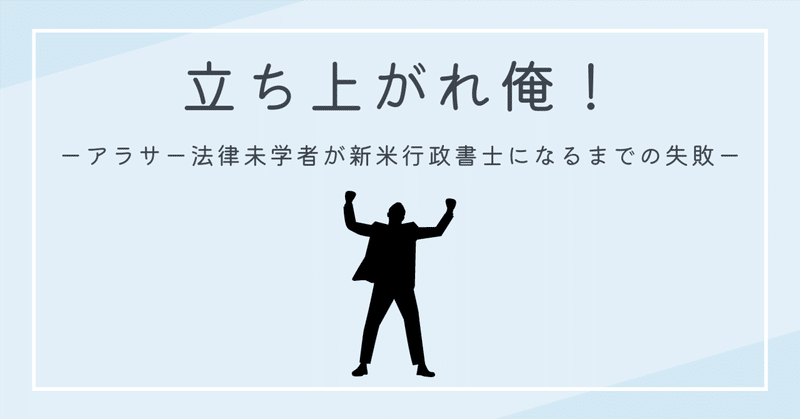
【行政書士試験失敗記】16話 一般知識の問題はみんな不安(池上彰さんは除く)
なんとなく。なんとなく行政書士試験における一般知識対策について語っておけばいいんじゃないかという風潮がそこにはある。
行政書士試験には一般知識という科目がある。今回はこの科目の対策について私の失敗を語っていこうと思う。
結論から言うと、一般知識対策は2回目の受験まではちゃんと対策していなかった。
というより、ネットで転がっている対策がいまいちピンとこなかったというのが正直なところだ。それでも私なりに解説していこうと思う。
まず、一般知識という科目をどう説明するかと言われると少し頭を悩ませなければならない。
主に「これ! これが一般知識」と言えればそもそも対策に悩んだりしない。
明確に相手が分かっていれば怖いものなどない。
しかし、「なんかこう……この辺りが出るんでしょ?」みたいな認識だとどこまで勉強したらいいのか、大枠が掴めない。世の中の一般知識対策記事が飛ぶように売れるのもその辺りが原因だろう。
かつての私は前述の通り、この対策の必要性を感じていなかった。なぜならば、ほとんどの模試で足切り点数を下回ることが無かったからだ。
改めて足切り点数について説明しておくと、行政書士試験には一般知識科目にだけ、足切り点数が明確に設定されている(法令科目にもあるにはあるのだが、足切り点数を下回った時点でどっちみち合格はほぼ不可能なので割愛)。
一般知識科目は14問のうち、6問以上正解しないと、他でどんなに点数を取っていたとしても問答無用で不合格になる。
行政書士試験は法令科目を必死に勉強していたところで、合格できない。
もっと世間一般のことも知っておかなければならないよ、という試験センターの意思を感じる。基本的に常識が無かったあの頃の私は、この脅し文句に毎回心底怯えていた。
しかしながら、一般知識の難易度を上げて、足切りされる受験生を続出させた、なんてことをここ数年聞いたことはない。
受験生の中でも、「なんとなーく怖いけど、蓋を開けてみれば大丈夫だった」みたいな印象を持っている人も多いと思う。私もそうだった。
なんとなーく点数取れるし、一般知識勉強するより、法令科目勉強するか。
と、当時の「できる限り勉強したくない俺」はそうやって一般知識を避ける傾向だったと思う。
このなんとなーくできる。これこそが非常に大きな失敗だと今になって思う。
大した対策もせず、なんとなーくできるもんだから「本番で出来なかったらどうしよう」という不安もずっとなんとなーくあるのだ。
確かに本番で何が出てくるか分からないといったギャンブル要素もあるが、対策をすればそういった不安もなくなるし、もしかしたら「得点源」にすらなり得たかもしれない。そこに気が付けないあたり、怠け者である愚か者な私だ。
もっと一般知識問題に対して確実な対策ができていれば、足切りに怯えるのではなく、自らの武器にもできるというのに。
では、我々はどういった対策をとればいいか。
身も蓋もないことを言えば、「予備校に頼る」なんてことを言ってしまっていいかもしれない。
この記事は他のnoteで語られているような「これで安心! 記述対策! ○○円!」みたいなものでは無い。
最初から言っているように、これは私の失敗記である。
なぜ私が失敗記なんてものを書いているのかと言えば、それは私がこれから行政書士試験を受験する方々に対して信頼のおける情報をお渡しすることができないからだ。
率直に言ってしまえば、私ではここでいくら流ちょうに一般知識対策を長々と鼻につく口調で語ったとしても責任が取れない。これに尽きる。
それ故に私は一般知識対策はどうしたらいいか、という疑問に対して「予備校に頼ればいいんじゃない?」なんて不真面目な対応が許されているのだと言っていい。
ただ、それではあまりにも傍若無人であるからして、なにか受験生の実になるようなものを提供しなければならないとは思っている。もちろん本気で。
なので一般知識対策は予備校の良質な教材に任せるとして、どう準備するのがいいかという点について語っていこうと思う。私がお勧めするのは以下に記す4つの準備だ。
1.模試の問題を集めておき、解答とセットで一つにまとめておく
これが一番重要だと思う。結局のところ、どこが出るんだ? という問いについて肌で感じるためにはこれしかない。何回も模試をやっていると頻出の単語が見えてくる。私の実感ではあるが、環境保全に関する協定や、次で語る日本の歴代内閣総理大臣、海外の大統領や首相を中心とした政治制度なんてものが良く問われる傾向にある。あとはIT関係の用語についても問われることが多い。
もっとも、この準備をするために少なくとも5回以上は模試は受けておくことをお勧めする。時間が無い? 時間は有るものではない。捻出するものだ。
2.YouTubeを利用して、近代~現代までの歴史を把握する(特に歴代内閣総理大臣)
これが意外と重要。一般知識とは我々が生きる現代までの近代史を扱った歴史問題だと考えると良いかもしれない。特に戦後から現代に至るまでの内閣総理大臣とそれに伴う事件は一度さらっとでもいいので勉強しておくことをお勧めする。お勧めは中田敦彦さんのYouTube大学。ここの近代史や自民党の歴史の動画を強くお勧めする。
ちなみに私の見立てでは、予備校も、試験センターも竹下登と田中角栄が大好きだと思っている。
3.IT関係については模試で出た単語とその周辺をチェックしておく
その手の仕事をしていないと全く想像もつかないのがIT関係の単語だ。私も幾度となく「なんじゃこりゃ!?」となった単語があった。
例えば「メタバース」「VR技術」「DX」なんていうのはなんとなく理解できる(別に詳細に説明できるほどの知識を身に着ける必要はない)。
しかし、「SOHO」、「ブロックチェーン」、「Web3.0」、「DAO」なんて問われたときに
「ああ、あれね。あれだよ。ネットのね。あれだよね?」
なんてことになってしまったらお手上げだ。せめて模試で問われた部分の周辺知識は押さえておきたい。今は大塚紹介で「IT用語辞典」なるものがあるのでそれをちらっと見ておくといい。これだけで意識高い系の人とも話が合うはずだ。
ちなみに先ほど出た「DAO」とは「ブロックチェーン技術の発展により実現可能となった新しい組織形態」のことである。なんのこっちゃ分からないと思うが、要は管理者とか指導者がいなくても、共通の目的に向かって動く集団、といったところか。要約しても「?」になりそうだが。
恐ろしいことにこういった知識も必要になる。IT関係の用語はそれらを構成する単語の頭文字を組み合わせていることが多いので、単語自体に意味が無い。そのために暗記するのに苦労する。早めに対策しておきたい。
しかし、この単語らを一から懇切丁寧に覚える必要はない。「DAO」と聞かれたら「あのー、あれでしょ? ネット系の組織のなんちゃらでしょ?」で答えられるレベルの問題のはずだ。
4.文章問題を解く時間を確保する
よく、「文章問題ってどうやったら解けるのか分からない」という質問を目にする。
こればっかりはもう本当に困る。国語の先生にお任せするしかない。だが、一般知識を攻略するためには文章題の全問正解、せめて3問中2問の正解は絶対条件であると言っていい。足切りを回避するためにはここで3問全問正解して、残り3問という形にしておきたいのが全受験生の本音のはずだ。
では、どうやって対策をするのか。
他の問題と違って、文章問題にはほとんどの場合、事前に暗記しておかなければならない知識を要求してこない。答えは全て文章の中に隠れていると言っていい。
よく、文章問題対策の講義を見ると「文章問題は全てテクニックで解ける!」と主張する方も中にはいるが、個人的な見解を述べるとすると「それでは文章問題の意義が失われるのではないか」と小生意気にも思ってしまう私だ。
中には「文章問題なんて文章ほとんど読まなくてもいいから!」と主張する人もいる。いやいや、とんでもない。なんのための文章だと聞きたい。
そもそも、この文章問題は行政書士試験の最後に配置される設問である。多くの場合、時間の無い中でこの問題を解かなければならない。そうなるとどうなるか。異常な精神状態で読むとケアレスミスが発生するのだ。試験センターはその辺も狙っているのではないかと勝手に推測している。
文章問題は落ち着いて、長い時間掛ければ解ける問題なのだ。なぜならば答えはそこに書いてあるからだ。
我々に必要なのはその問題を解くための適切な時間だ。
私の場合、最終的に文章問題3問に対し、30分の時間を設けた。1問5分かけると問題を3周は読み込める。その上で回答を吟味する。
私は必ず文章問題は最後にとっておく。いわば試験問題をフルコースと称するのであれば、文章問題はデザートだ。ゆっくりと全てを味わい尽くすかのように食する。そういう心構えで臨む。
私もテクニック偏重に傾いていた時期があった。しかしこれは失敗だった。
「文章を読む前にまず、選択肢を読んで……ありえなさそうな選択肢を消して……」なんてやっているとどんどん焦ってくるのだ。最終的に何が何だかよく分からないまま選択し、間違える。その繰り返しだった。
最後の問題なのだから、どっしりと構え、骨までしゃぶりつくすかのように味わい尽くす気持ちで一度やってみて欲しい。
味わい尽くすためには適切な時間配分も必要になるので、その点も気を付けて進めるようにしたい。
以上が私が勧める一般知識対策だ。しかし、これだけ説明してもやっぱり不安が残る。絶対に大丈夫と言い切れないところに行政書士試験の難しさを感じる。
足切り、という明確な恐怖を見せびらかされながら受験生はひたむきに進んでいかなければならないと思うと私としてもなんとも歯がゆい気持ちでいっぱいになる。
そういう時は安心して欲しい。
私も含め、誰もが不安だったのだ。
試験会場において「一般知識? 余裕でしょ!」と言える人間は全体の1%もいないだろう。そんなことができる人間といえば、日本で池上彰先生くらいなものではないだろうか。
私もあなたも池上彰先生ではない。
だから不安になる。それは当然だ。
そんなこと、本当は分かっていたのにも関わらずちゃんと対策をしてこなかった私は、やっぱり失敗して当然だったのだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
