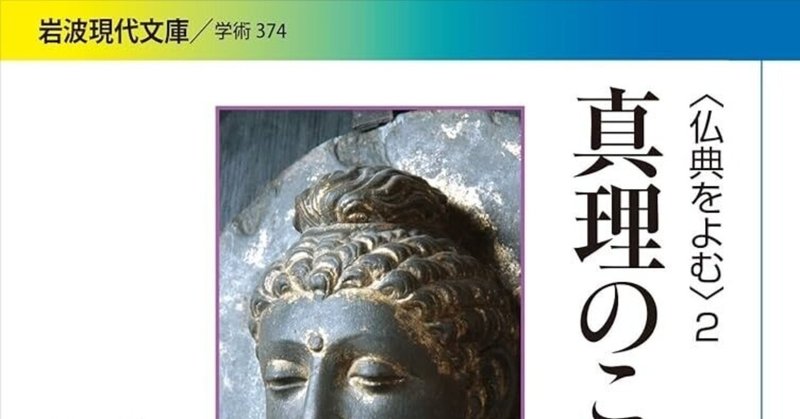
《書評》仏を目指し日々励め│「〈仏典をよむ〉2 真理のことば」中村元
本書は、中村元先生によるNHKラジオの放送を文字起こししたものである。原始仏典を引用し、それに対して中村元先生が簡潔に解説をするといった内容となっている。元がラジオ番組というのもあって、あまり深い議論はされない。平易な解説書といった所だろう。
本書は、原始仏典のうち、『ダンマパダ』『テーラガーター』『テーリーガーター』『シンガーラへの教え』を扱う。引用されるのは全体の極一部、しかし中でも重要な箇所をピックアップしてある。原始仏教では、重要視されるのは実践である。その為、具体的実践を指南している箇所が多い。
指南を幾つか取り上げてみよう。
つとめはげむのは不死の境地である。怠りなまけるのは死の境涯である。つとめはげむ人々は死ぬことが無い。怠りなまける人々は、死者のごとくである。このことをはっきりと知って、つとめはげみを能く知る人々は、つとめはげみを喜び、聖者たちの境地を楽しむ。
日々はげめ。いくら宗教に抵抗がある人でも、この教えに対して「間違っている」という事は難しい。しかし、宗教の教義とは往々にしてそういうものが多い。つまり、教えが普遍性を持ち、反論の余地もないものが多いのだ。中村元先生の解説を見てみよう。
人々が自覚し、自分のなすべきことはこれであるときめて、その理想に向かって進んでいくとき、その人は生きている。さとりというのも、そのつとめはげむ道筋のなかに求められるわけです。後代の日本の仏教では、「修証一如」というようなことを申します。これは、「修行することと、さとりとは、一体である」ということです。つまり、さとりとは、遠い彼方にあるのではない。いまここで自分のなすべきことを行なう、それがさとりの境地であり、それが不死の境地である。
修行というと、一般的には滝行のようなものを想像する。しかし、形式は問題ではない。修行の本質は、自分を制し、自分に打ち勝つ事である。日々の仕事を行う。これもまた、修行の一つだという。一般人が、仏教の教えを真理だと思ったとする。しかし、出家するのは並大抵の道ではない。ならば、まず日々の生活において、自らのやるべき事をこなし、自己を制する事から始めてみる。そういった方法もありかもしれない。
在家者へ向けて、戒めを説いた『シンガーラへの教え』で説かれている戒律は以下の通りである。
では、かれの捨て去った四つの行為の汚れとは何であるか? 資産者の子よ、生きものを殺すこと、与えられないものを取ること、欲望に関する邪な行ない、 虚言――――は、行為の汚れである。これらの四つの行為の汚れを、かれは捨てっているのである。
この戒律は、モーゼの十戒と非常に類似しているのが見て取れる。「あなたの父と母とを敬え」(第五戒)以外の全ては対応している(ただし、十戒の「殺してはならない」は一般的に人殺しと解釈される)。そして、仏教にも父母を敬えという教えは存在する。これらの戒律が共通しているという事実からは、人間の道徳は普遍的なものであるという考えの根拠にもなるだろう。
さて、このように、本書は原始仏教の中の本質部分を取り上げて、平易に解説を加えているのが分かるだろう。この書評では、もう少し踏み入って、このような形式で仏教を知る事について考えてみたい。さて、このような形式、というのは、部分的にかいつまんでざっと理解する、という事である。
本書では、仏典を読む時に起こる、ある種の厳かな気持ちというのはもたらされない。代わりに仏教に関する親近感を持つ。実際、原始仏典自体、非常に明快な書物であり、読んでみると、衒学的な類のものではないのはすぐに分かる。しかし、それでもある種の壮大な体系を感じる事にはなる。本書だけでは、良い意味でも悪い意味でも簡単なものである。
私は、本書が非常に優れた概説となっていると思うし、実際、本書自体に何ら問題はない。ただ、この本を読んだ事が、原始仏典を読むきっかけとなって欲しいと思う。というのも、やはり本書では込み入った深い議論はなされないし、ラジオ番組の為に平易な内容となっているからだ。本書は、大いなる海原へ至る、広く歩きやすい道、といった所だろう。というところで、筆を置こうと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
