
競技特性をふまえた対応を考える。脳振盪から選手を守るためにも現場の理解が必要不可欠
中山晴雄
東邦大学医療センター大橋病院 脳神経外科 講師、院内感染対策室副室長、専任感染制御医師、臨床検査部部長

2023年に『アムステルダム声明』が出され、国際的にスポーツに関わる脳振盪に関する研究、現場の対応は急速に進み始めています。ですが、日本は国際的に見て、特に脳振盪の分野では遅れをとってしまっている状況です。そんな状況を打破しようと、前回のベルリン声明の日本語版制作にも携わり、現在はアムステルダム声明の日本語版の制作を進めている中山晴雄先生をはじめとする、多くの先生方が取り組まれています。その現状と日本のスポーツ界が抱える課題などについてもお話を伺ってきました。
――今、脳振盪に対する世界の動きは活発になってきているように思えます。2022年10月に会議が行われ、2023年7月にはそれをまとめた論文『アムステルダム声明』が出されました。あらためて、この『アムステルダム声明』についてお話いただけますか?
中山晴雄(以下、中山):まず始めに、IOCやFIFAなども含めたスポーツ団体が協力して立ち上げた国際スポーツ脳振盪会議の第1回が2001年に行われました。その後、おおよそ4年に1回、夏季五輪に合わせて開催されてきました。そして、コロナ禍もあって開催がずれたのですが、第6回が2022年に行われて、前回大会からアップデートされた内容をふまえた『アムステルダム声明』が出されたということになります。
その内容ですが、基本的には前回大会に出されたベルリン声明を大きなものを踏襲して、これ以後国際的に発表されたスポーツに関わるさまざまな論文、研究結果を事前に2年くらい検証して、ベルリン声明からより科学に裏打ちされた最新の物に変えていこう、ということですね。
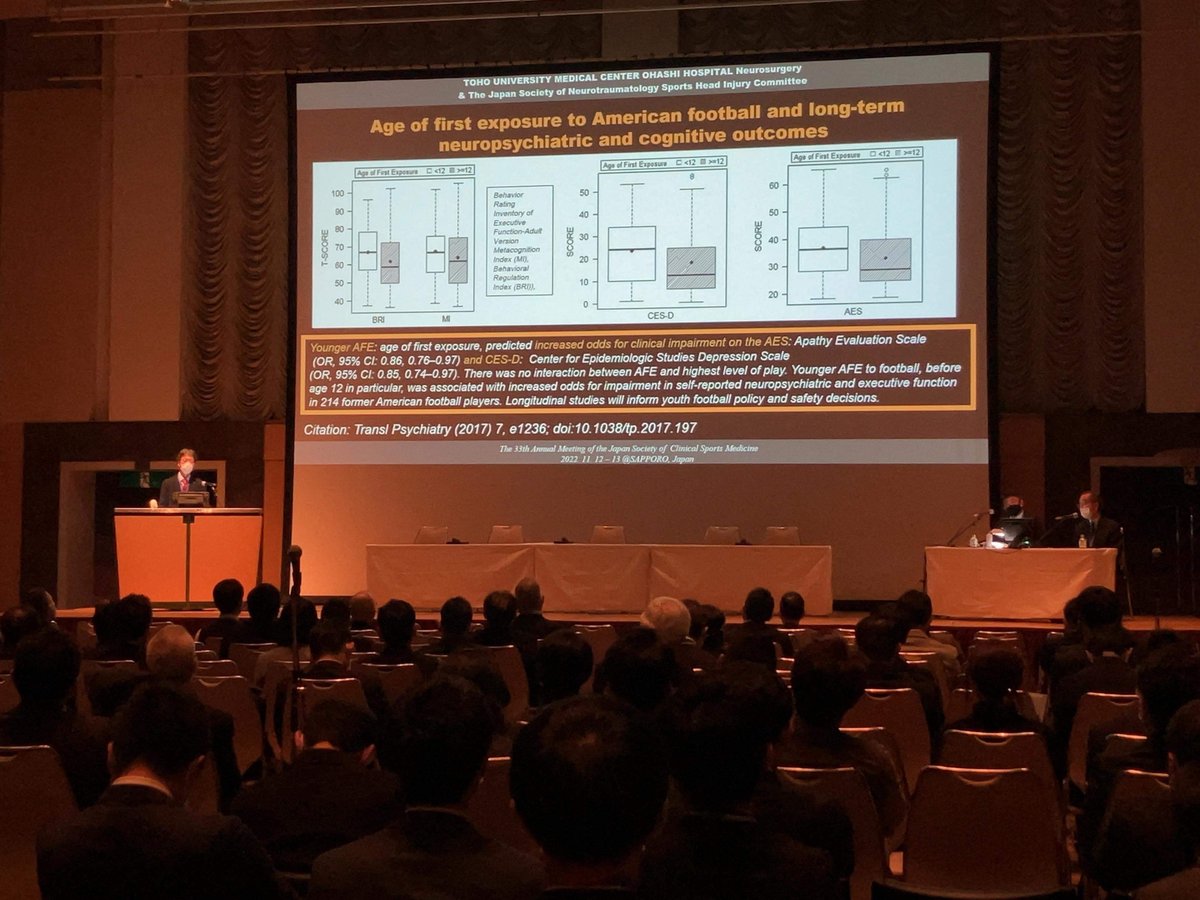
――なるほど。では脳振盪発生後の安静指示であったり、復帰プログラムに関する内容の方向性は、ベルリン声明とあまり変わっていないと考えてよいのでしょうか。
中山:大きな方向性としては変わっていないと思っています。つまり安全のために、もしくは将来的な脳機能などに与えてしまう悪い影響を抑止するためには何をすべきなのか、という方向性は変わっていないですね。ただ、各論レベルで少しだけ管理の仕方が変わっている、という印象です。
たとえば、以前は「脳振盪と診断されたら休みましょう」という判断から段階的な競技復帰プログラムを踏んでいきましょう、最短でも1週間くらいはかかりますよ、という感じです。『アムステルダム声明』は、そこをさらにもう一歩踏み込んだというか、早期の段階からでのリハビリも有効だよね、という考え方に変わってきたというのが実際のところだと思います。
まずは、もう「休め、休め」ではないということです。長期に休ませすぎても症状が残ってしまったりとか、競技への復帰が思うように進まなかったり、ということがさまざまな研究結果から示されてきたのです。実はこのあたりはベルリン声明時にも指摘はされていたのですが、そこがより明確になった、というか。いわゆる日常生活動作に対して支障があるかないか、ある程度症状限定的であって、完全に消えていなかったとしても、日常生活動作が営めるのであれば、身体を動かす、という段階に進めたほうがよいですね、ということを明確に示したというイメージです。
――ただ休むのではなく、日常生活が問題ないなら軽い運動を行ったほうが、復帰がよりスムーズになる、ということですね。
中山:そうですね。たとえば段階的な競技復帰のプロセスには6段階あるのですが、今まではこれがひとつのパッケージになっていました。それが今回、3段階ずつの都合6段階ありますよ、という形になったのが大きな変化じゃないかと思います。
――復帰プログラムが前後半に分かれた、ということですか。
中山:どちらかというと、前半の3段階というのは競技に特化したものではなく、基本的な身体的動作のなかで、安全面を確認しながら進めましょうというフェーズです。そして後半の3段階が、よりその競技に特化した動作であったり練習であったりという内容になってくるのです。そのなかで支障が出ないかどうか、ということを確認しながら進めていきましょう、というのが後半の3段階です。
ただ、一つひとつのステップが非常に細かくなってきています。たとえばステップ2が有酸素運動、ステップ2-A、2-Bで最大心拍数に対しての55%とか70%という明確なターゲットが記載されていて、マイナーからモデレートというところでの心拍負荷をかけながら症状の出現の有無であったり増悪であったりを確認していきます。
もうひとつ大きく変わっているな、と感じたのは、メディカルクリアランスを受けるラインですね。このメディカルクリアランスというのは、日本ではメディカルチェックに当たるのだろうと思いますが、接触などが要求される動作を行う前には、一度精密に検査をしていき、問題なければコンタクトのある動作に入っていくという流れになります。これが以前はステージ5に入るときにやりましょうと言われていたのですが、今回は「復帰プログラムの後半4、5、6のステップに入る前にはやりましょう」とひとつステップが前倒しになりました。細かく見ていくと、ステップ3に入るときに、偶発的にでも接触が起こる危険性があるならステップ3の前でやってもよい、という形になりました。
――そういった世界的な動きがあるなかで、日本の対応について現状はどうなのでしょうか。
中山:競技にもよりますが、ラグビーだったり、アメリカンフットボール、バスケットボールなどではかなり早めにアップデートされている印象ですね。いずれにせよ、今回の『アムステルダム声明』を受けて、ステップ3に入る前の段階と、後半に入る前の2段階でメディカルクリアランスを行うのか、それとも後半のフェーズに入るところで包括的に行うのか。これらを自分たちの競技特性に合わせて考えていく必要はあると思っています。
――日本ももっと世界の動きについていきたいものですね。たとえばですが、こういった復帰プログラムを作る際に大事なことは何かありますか。

スポーツ頭部外傷の知見では個別の事例が極めて重要。
中山:脳振盪の場合、予防するとか復帰プログラムを組むとなったとき、現場の空気感というのは非常に大切だと思います。それこそ、脚の靱帯を切った、となると、松葉杖を着いたり車いすを使ったりするので、周りの誰もが「これはケガで動けないんだ」ということがわかると思うんです。ですが、スポーツの現場で起こる脳振盪というのは、意識を失って倒れる、というケースはほぼありません。脳振盪を起こした9割くらいの選手たちは、ぱっと見ただけでは症状がわからないのです。
実際は脳振盪を起こしているのに、ふっと起き上がるし、なんとなく動けて、なんとなく競技に戻ることができてしまうんです。頭の中で起こっている出来事からすれば、決して良い選択ではないのですが、ただ実際、脳振盪を起こしている選手の多くは、“なんとなくできてしまう”ので、こちらが止めなければ競技を続けようとしてしまう、というのが現実だと思います。
――そのときに、周りの人たちが「脳振盪かもしれない」と止める判断ができる現場の空気感が大事、ということですね。
中山:そうです。指導者やチームメイト、保護者の方々やもちろん選手本人が、いかに脳振盪を疑って競技を止められるか、ということが大事なのです。
本来、脳振盪は可逆性があって、一定の時間はかかるけど元に戻るよね、という理解だと思います。ただそれが回数を重ねたり、短期間で繰り返し脳振盪を起こすことで、どこかのタイミングで不可逆的になってしまう可能性がある。もしそうなってしまうと、それを治してあげることが非常に難しくなってしまいます。そうさせないためにはどうするのかを私たちは考え、行動していかなければならないと思います。

スポーツドクターの先輩後輩は貴重な財産。
競技をする以上、脳振盪を含めてケガをするリスクはゼロではありませんし、ゼロにすることはできません。ただ、特定の選手がその競技が持っている本来のケガのリスクを遥かに逸脱するほどリスクが高まっている状態は、良いとは言えませんよね。それを何とかその競技が本来持っているリスクと同じくらいにまでギャップを埋めて上げる作業が必要です。それを理解し、実践できているかどうかということになると、正直に申し上げて、日本は国際的に見ても非常に遅れているところだと思います。
――たとえば、ラグビー選手が健康な状態で脳振盪を起こすリスクは、その競技が本来持っているケガのリスクですよね。そうではなくて、脳振盪を起こした可能性のある選手がそのまま競技を続けるということは、ラグビー本来のケガのリスクからは逸脱している、ということですね。そのギャップを埋めるために、脳振盪の場合は復帰プログラムが組まれているわけですものね。そういう理解をもっと深め、広めていくためにはどうしていかなければならないのでしょうか。

中山:協会や連盟といった、スポーツ団体にアプローチすることは非常に大切です。そうすればルール化することで、スピーディーに対応を広めることはできます。ただし、強制力を持って止めているだけなので、現場においてそのルールが正しく“理解”されて、自らが進んでそういう行動をしなくなる、ということではありません。やはりなぜそうしなければならないのかを理解してもらうことも大切なポイントになります。
たとえばですが、公益社団法人日本アメリカンフットボール協会はどこよりも早く、先ほどの新しい脳振盪の復帰プログラムをホームページ(https://americanfootball.jp/safety)上で公開しました。やはり競技の特性を考えたうえで、現場に対してポジティブなアクションをしなければならない、という考えに基づいて行っているアプローチ方法ですよね。
――競技特性を考えて行動する、あるいはアプローチしていく、ということが大事ということですね。
中山:チアリーディングで言えば、大会当日に発生する脳振盪やケガは数%しかありません。実はそのほとんどは練習中に起こっているんです。難しい技や新しい技など、できなかったものをできるように練習するのは大会ではありませんから、失敗してケガにつながる可能性は大会よりも練習のほうが高くなりますよね。そう考えると、安全面で言えば大会中よりも普段の練習環境を優先しなければなりません。そういう面も考慮して、何を優先して物事を伝えていくかを考える必要はあると思います。
――そう考えると、先のアムステルダム声明に戻りますけど、それをただ日本語に訳するだけではなく、日本の現状に促したものにして伝えていくことも大事なことですね。
中山:そうですね。日本の現状を理解したうえで、そこにどう落とし込むか。根底としては正しいことを正しく伝えたうえで、なぜ必要なのかを理解し、実践し、それを徹底してもらえるように啓発していくことが大事なところになってくると思います。
――最後になりますが、中山先生からあらためてスポーツの現場に携わる方々に向けたメッセージをお願いします。

中山:そうですね、やはり正しい知識をいかに多く伝えていけるかが大事です。誤解を恐れずに言うならば、その知識を持つのは何も専門家じゃないといけないわけではありません。お医者さんではないけれど、たとえばスポーツ医学検定であるとか、こういう教育プログラムを受けることで、適切な知識を持っていただいて、いろいろな現場などで対応を含めて伝えていっていただくことが、広く知ってもらうためには大切なことです。1人ができることには限界がありますからスピード感は出ませんので、一緒に知識を広めていく人たちをいかに増やしていくかも大きな課題なのではないでしょうか。
あともうひとつ申し上げるなら、とにかく現場に答えがある、ということです。診察室で待っていたとしても、経験を積むことはできません。特にスポーツ脳振盪という領域に関しては、スポーツの現場で経験を積むことが非常に大事です。現場で選手たちと同じように汗を流して、泥にまみれてはじめてわかることもたくさんあります。是非そういうことにも前向きに取り組んでもらえるような若い医療者やスポーツの現場の方々が増えてくるとうれしいですね。そして、その魅力をいかに後進の方々に伝えていくか、ということも、私たちに残された課題かなと思っています。
――貴重なお話をいただき、ありがとうございました!
<編集後記>
この取材の前に、アーティスティックスイミングの選手が練習中に脳振盪を起こしたという話を聞きました。まさにチアリーディングと同じで、練習中にアクロバティックなリフトやジャンプを練習するため、大会よりも練習中のほうが脳振盪のリスクが高い競技です。ラグビーなどは練習中もそうですが、大会になるとリミッターが外れた状態でコンタクトするスポーツなので、大会での対応が非常に大切になります。このような競技特性によって、脳振盪はもちろんですが、ケガや故障の予防含め、安全に競技を続けられる環境作りが必要なのだと感じました。そして、最後の『答えは現場にある』。私たち取材する人間にも言えること。現場でたくさんの経験を積まれた中山先生の言葉をあらためて多くの人たちに伝えたいと感じました。
◇プロフィール◇

中山晴雄(なかやま・はるお)
アメリカンフットボールを行っていた経験を通じてスポーツドクターの道に。2003年東邦大学医学部卒、2005年同大大学院医学研究科博士課程入学。長くスポーツ脳振盪に取り組み、2022年に行われた国際スポーツ脳振盪会議でアップデートされた国際共同声明、アムステルダム声明の日本語版の制作を進める。東邦大学医療センター大橋病院 脳神経外科・講師・院内感染対策室副室長・専任感染制御医師・臨床検査部部長。日本医療安全学会・高度医療安全推進者。日本感染症学会研修認定施設・指導医。
