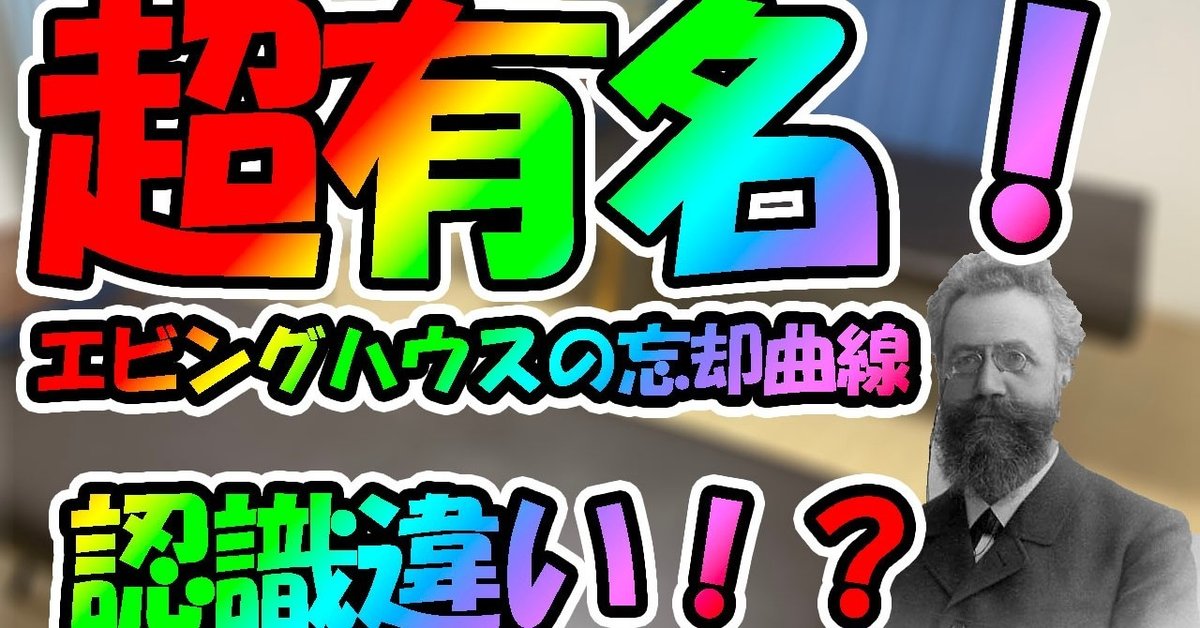
エビングハウスの忘却曲線
こんにちは!パーソナルケアソーヴィスの須田です!
本日はエビングハウスの忘却曲線というものを解説していきたいと思います。
このエビングハウスの忘却曲線はヘルマン・エビングハウスというドイツの心理学者が研究した内容になります。
こちらのエビングハウスの忘却曲線は記憶に関する実験で、一般的には人が覚えた内容をどれぐらいの時間で忘れてしまうかの忘れやすさについてを説いている内容だと認識されています、、実はこれが誤解であることは後ほどお話しします。
まずエビングハウスの忘却曲線の多くの方が認識している内容をお話しします。

グラフをご覧ください。
こちらのグラフの縦軸は覚えてる割合、横軸は時間軸となっています。
時間の経過と共にグラフは下降しているのが分かるかと思います。
20分後には42%、一時間後には56%、一日後には66%、一週間後は75%、一か月後には79%忘れているというグラフです。
このグラフを見て多くのブログや、企業の研修では一日以内に復習をして忘れないようにしようと指導しているのが多く見られます。
僕も企業にいて研修等を受けている際には振り返りって言葉で一日以内に日報を出しなさいとか言われてました。良く日報を出すのを忘れてましたが、、(笑)ありません?忘れない為にメモ取ったのにそのメモを見ない人(笑)
はい、それは置いといて先ほどお話しした内容が主に世間で認識していることになりますが。
この内容はずばり間違っています。
エビングハウスは記憶に関する実験的研究の先駆者で初めて学習曲線という練習量と反応時間の関係を示す内容を出したのですが、それがエビングハウスの忘却曲線だったんです。
確かに記憶に注目する実験ではあるのですが、忘れやすさを示した実験ではないのです。
心理学者エビングハウスは「子音・母音・子音」から成り立つ無意味な音節をリストアップして実験の参加者に覚えさせました。つまりは覚えさせられる側の人にとっては何の意味もなければ興味もわかない、そんな情報をいくつも暗記させられるというのが実験の詳細だったわけですね。日本語におきかえると、例えば(かあき)のように意味のない言葉を複数覚えるみたいな感じですね。
エビングハウスの実験はあくまでこうした無意味な情報を覚えるという内容だったので、被験者が「興味のある、しりたい!」と思えるような情報は対象では無かったということです。興味のない内容ましてや、覚えても何にも意味ない情報だからこそ記憶にとどめにくいわけですね。
そしてここで節約率という言葉が登場します、
エビングハウスは実験の後で1時間、1日と時間をあけて、記憶の再生率を調べることで忘却曲線を発見しました。再生というのは、もう一度同じことを覚えなおすということです。さきほど挙げた(かあき)のように意味ない言葉を再度覚えるという事です。
この記憶の再生にかかる負担の違いについて説明したのが「節約率」です。
(節約率)
=(節約された時間または回数)÷(1回目に必要だった時間または回数)です。
ある程度時間をおいてから再び記憶するまでにかかる手間をどれだけ節約できたか?ということを表すのが節約率です。
エビングハウスの忘却曲線が誤解されている理由は、この節約率の存在があって成り立っているグラフであることが抜けてしまっているのでただの忘れやすさを証明するものと誤認されてしまったというわけなんですね。
だって一時間後には56%忘れていたらお昼何食べたかすら忘れていて三歩進んで忘れるニワトリみたいな感じになっていますからね(笑)こんなだったら生活にもそこそこ支障があると思いますが、皆さんそんな極端なことにはなりませんよね。
なのでどうでもいい事は1日たてば、すぐに忘れてしまい、必要であれば覚えているという事です。
自分にとって必要ではないという認識でも繰り返し行っていれば勿論反復回数に従って覚えていられる確率は上がります。
そして人間の脳にとって「忘れる」機能はとても重要です。もし脳に入ってきた情報をすべてコンピュータのように記憶していたら、逆に混乱してしまいます。脳科学の分野では記憶は「短期記憶」と「長期記憶」の2種類に分けられます。短期記憶にある情報はすぐに忘れ去られてしまいます。ですから受験勉強などをがんばる人たちにとっては、どれだけ長期記憶のほうに情報をたくさん蓄積していくかが勝負の分かれ目になるわけですね。
あとはあまりにも忘れられないという人は頭の中でのデトックスが上手くいっていない人でもあるので、鬱病の発症率が高くなるという研究データもあるので、すべて記憶が出来たらいいという事でもないという事を覚えておきましょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
