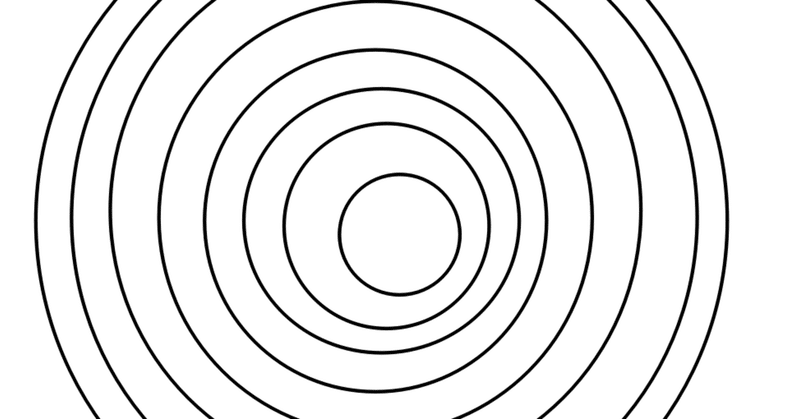
ようこそ映画音響の世界へ【感想】 立川シネマシティー
多くの仲間が公式HPにコメントを寄せていたので、真似してちょいと感想など書いてみようかと思います。こういうのやったことないので、どうなるか自分でもドキドキ。
極端なネタバレはしない予定ですが、自分の初見を大事にしたい方はブラウザバックでどうぞ。
まいります
さて、個人的には「音響」って電気的作用より空間やそれ以外に関する分量が多い気がしていて、映画音響ってワードにはちょいと違和感を抱えつつ、
じゃあ何が適切な日本語なんだろ?って言われても、
明確に思い至らないから、やっぱり音響でいいのかなあ。
もともとスタジオの中で
「テープバイアスを0.3dBなのか0.5dBなのか?」
とか
「3khzと2.5khzどっちがいいか?」
「0VUの針のみかた」
なんて超細かい世界で生きてきたので作品の本質的要素より、電気信号の正確さとか、データ転送の正確さとかそっちに傾向してる自覚はあるんですが、映画では非常にいい意味で大まかな話にまとめられていて、とっかかりの意味では良いと思いました。
映画の導入部分を見ていて、「映像は静止画の連続だけど音はそもそも連続してるんだよなあ」って気持ちになったんですが、そりゃまあ「Making Waves」がオリジナルタイトルですから、然もありなんって事で。
それを思ったってことは良い構成なんだろうなあと。
しかし、ハリウッドの諸先輩エンジニアが映画の音についてしっかりと自分の言葉で、「映画録音」の歴史を語っていたのが印象的でした。
あそこまで語れる日本のエンジニアは果たして何人居るか。
自分もアナログマルチの時代は体感していますが、それより前のポジで音を出していた時代や、現場録音ならナグラより前の時代は知りません。
ん?気がつきました?しれっと私が言い換えたの。
そうなんですよね、個人的には「映画録音」なんですよ。
正確な意味とか、まあ個人の主義主張の部分なんで難しいですが。
どこか根本でSound Recording Engineerだと自分の思ってる部分があって。
特にアナログ時代は、スタジオで出ている音をそのまま録音して、
そのまま映画館で再生するということが困難でした。
電気的接点や、アンプの性能。
記録方法、光学録音や磁気録音。デジタル圧縮の規格。
全てを駆使して0を0で収録することの難しさがあったので、
「録音」音を録るというところに執着していた気がします。
真鍮の110ケーブルをピカールで磨くと、「音の輪郭がくっきり出てくる」
ということを体感していると、
まるでバケツリレーでいかに水をこぼさず届けるか?みたいなことに終始していたんですよ。
映画の後半では現在の映画の作り方の解説をしていますが、
ここの部分が日本とは大きく異なるので、あんまり参考にならんなあという想いです。
もちろんアメリカ的専業性もそれはそれとしてメリットが沢山あります。
が文化として日本では根付かないだろうなあという気持ちですし、分業のデメリットもありますし。
まあ本筋から離れますんでこの話はこのくらいで。
感想としてSNSで少し触れましたが、歴史を学ぶ録音関係者はもちろん、
プロデューサー、演出家、演者、これから映画を作りたい学生に是非とも見ていただきたい映画です。
音の世界は楽しいよ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
