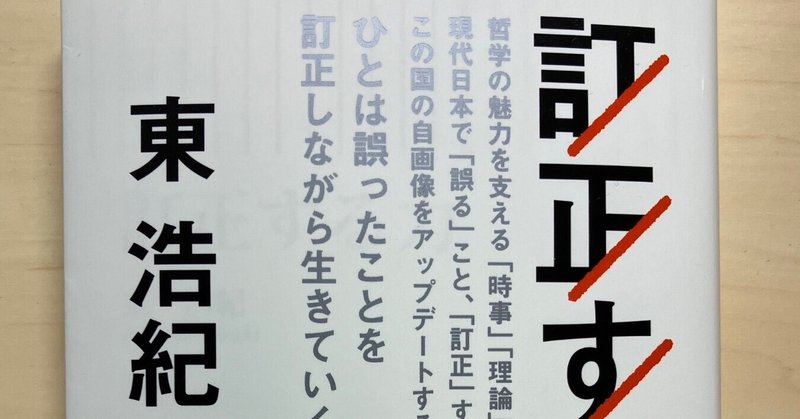
東浩紀『訂正する力』を読んで
東浩紀の『訂正する力』(朝日新書)を読みました。ついこの前、同氏の『訂正可能性の哲学』を読んだばかりだったので、正直同じような内容かなと思っていたのですが、結構な変化球に驚かされました。
とても分かりやすい文章であっという間に読めてしまううえに、東氏自身の同時代的な経験に裏打ちされているため深くて刺さるという魅力あふれる本書ですが、私がここで取り上げたい感動ポイントは、①リベラル批判と②丸山眞男論の2つです。
1.「ぶれない」リベラルへの批判
個人的に一番刺さったのは、同時代のリベラルに対する批判です。(「批判」とひとくちに言っても、応援の意味が大きいと私は感じました。)
数年前の私は、同時代のいわゆる左派リベラル知識人に感化されて「ぶれない」ことの価値を信じ、保守的な意見に対する反論(はたまた攻撃)に熱心だったように思います。今思えば、「ぶれたら負けだ」という強迫観念のようなものに囚われていたような気もします。
東氏の現状認識とリベラル批判は、シンプルです。
いまの日本には訂正できない土壌がある。だからみな訂正する力を発揮できない。これを変えねばなりません。(中略)議論を成立させるためには相手が意見を変える可能性をたがいに認めあわなくてはいけません。だれの意見も変わらない議論なんて、なんの意味もありません。
「訂正しない勢力」は権力批判側にもいます。いわゆる左派リベラル勢力です。彼らはとにかく「絶対反対」「変わらない」「ぶれない」。
ところがいまの左派はそういう主張ができない。「条文が変わっても同じ憲法の精神を守ることができる」という社会への信頼がないからです。(中略)その神経質な純粋主義が事態を膠着させています。
憲法改正などの各論に関する賛否はいったん措くとして、「自分の意見が相手によって変わりうることを前提としていない議論など意味がない」という主張は、確かにその通りだと思います。ディベートのような勝ち負けがはっきり決まるかのように見える議論は、「論破」した側に一時的な爽快感や熱狂をもたらすかもしれませんが、結局のところ何の解決にもなっていないことは明白です。
今思い返すと、左派リベラル特有の「ぶれたら負け」論には、カール・ポパーの「寛容のパラドックス」が引き合いに出されることが多いように思います。寛容な社会を維持するためには、社会は不寛容に不寛容であらねばならない。「だから、不寛容な保守派の意見を看過してはならないのだ」といった具合です。
しかし、そのときに「不寛容」と名指されている保守派の意見が一様に、寛容な社会を棄損するような危険なものなのか。相手側の意見にも顧みるべき現実的・建設的な論点が含まれてはいないか。むしろ自分たちの主張の方が実は相手に対する人格的な攻撃にまみれていて、社会の寛容さをむしばんではいないか。そういった謙虚な反省的態度が議論の前提として必要なのではないでしょうか。
もちろん、すべてにおいて妥協すべきだとは思いません。寛容な社会をむしばむ危険な不寛容さが「保守」と自称する論者によって吹聴されることはあるし、ただ黙ってみているわけにはいかないと思います。また、各論において東氏と政治的な立場が必ずしも一致するとは思いません。しかし、互いに議論を成立させ、政治を前進させるために必要な態度として、東氏の指摘は今の時代だからこそ傾聴に値するのではないでしょうか。
2.丸山眞男の批判的継承
もう一つ、この場で取り上げたいのは、丸山眞男です。
というのも、先日『〈悪の凡庸さ〉を問い直す』を読んで、なんとなく丸山眞男に立ち返る必要性を感じて宇野重規の『日本の保守とリベラル』を読み終えた後、手に取ったこの『訂正する力』でまた丸山眞男と出会い直したからです。やはり丸山眞男か!とうれしく思うと同時に、本人の著作をいい加減読まないとなあ、という気持ちになっています。
作為と自然を対立させ、日本文化を「つぎつぎになりゆくいきほひ」と特徴づけたうえで、日本人はもっと作為性を発揮しないとだめだ、というのが丸山の指摘でした。東はこれを踏まえて「自然を作為する」という第三の道を大胆にも提示しています。
日本はもともと文化の国だった。政治と交わらない繊細な感性と独自の芸術をたくさん生み出す国だった。その伝統のうえに戦後日本がある。クールジャパンもある。だから日本は武力を放棄したという理由で平和国家なわけではない。そもそもそういう伝統をもっているからこそ平和国家なのだ―。
ぼくは戦後日本の平和主義をそんなふうに「訂正」してみたいと思うのですが、いかがでしょうか。
そんな時代だからこそ、平和とは政治の欠如であり、その欠如にこそ価値があると訴えてみたいのです。「つぎつぎになりゆくいきほひ」を、主体の欠如ではなく、政治の欠如(への志向)だと捉えることで、新しい日本=平和論の可能性が拓けないでしょうか。
ここでいう「政治」とは、いわゆる政治的な行為全般を意味しているわけではありません。カール・シュミットの友敵理論のような決断主義のことを指しています。すなわち、「だれもが『敵か味方か』の二者択一で評価され、些細な異論や生活上の独自の判断も利敵行為として批判され」る。そのような意味での政治。日本にはこの意味での政治が欠如してきた、もしくはそれを避けようとする伝統、美学があるのだから、それを生かしていこう、という呼びかけです。
このように整理すれば、かつての日本が植民地支配や戦争に突き進んだ過去に対する反省を踏まえつつ、それよりも前からある伝統を誇りにしながら国際情勢に柔軟に対応していく平和論を展開する、という道筋が見えてくるように思います。
東の指摘している通り、シュミットのような決断主義を避けることは、先ほどのリベラル批判とつながっています。世界を敵と味方に色分けし、敵を排除して味方とだけ仲良くしていればよいという態度を退ける。境界のあいまいさを保ちながらそれでもなお一つの共同体としてのアイデンティティを保持し続ける。そのような新しい共同体像が提示されていると思いました。
そしてそれは、これまで想定されてきた「主体」とは異なる、新しい主体像の到来をも予感させます。
ただ、丸山眞男が論じた主体にも実は多様性があり、複眼的な視座において丸山の主体像を捉え直す必要があると、宇野重規は指摘しています。3つ挙げられている主体像のうち、特に3つ目の「結社形成的主体」については、トクヴィルの重視した結社の自由、東の喧噪論とも連関しており、注目に値すると思います。
丸山眞男については、いわゆる近代的な主体の重要性を説いたイメージが根強いがゆえに、改めて再読する意義も大きいように思います。これも、東の言っている通り、理系とは異なる文系特有の「訂正する力」の醍醐味ではないかと思います。
3.まとめ
良い本や言葉には、私たちがいかに狭い檻に囚われているかを自覚させ、知的な旅へといざなうきっかけを与えてくれるような、そんな力が詰まっているものだと思います。同書を読んで、東さんのような書き手に導かれながら、私も在野の一会社員として知的な営為の担い手になれればとの気持ちを強くしました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
