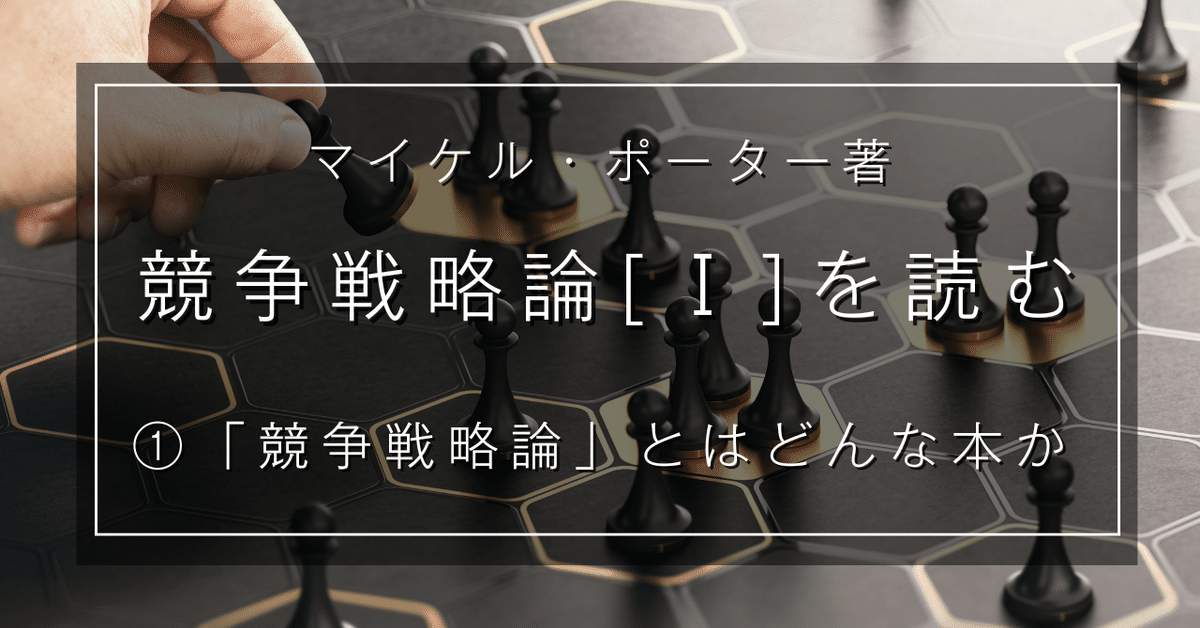
競争戦略論[Ⅰ]を読む - ①「競争戦略論」とはどんな本か
さあ、水曜日だ。
水曜日は経営戦略について学ぶ日だ。
先週まで孫子の兵法の13篇を順を追って書いてきたが、それも終了したので次の本に進んでいこう。
経営戦略というカテゴリーで言うなら、この本を外すわけにはいかないだろう。マイケル・ポーター著「競争戦略論」だ。
「競争戦略論」概略
マイケル・ポーターは1947年5月23日生まれ、明日で77歳になるアメリカの経済学者だ。ハーバード大学 経営大学院教授で、企業戦略や国際競争、競争戦略に関する研究の第一人者として知られている人物だ。
「競争戦略論」は1980年に初版が出版されて以来、40年にわたって世界中の経営者に読まれているビジネス書の名著の中のひとつだ。日本語版はDIAMOND社から発刊されており、翻訳は同じくハーバード大学 経営大学院シニアフェローの竹内 弘高氏によるものだ。
この本は「Ⅰ」と「Ⅱ」の2部構成になっているが、まずは「Ⅰ」から読み進めていこう。
競争戦略論Ⅰは、3部構成になっていて、それぞれ「競争と戦略」「戦略・フィランソロピー・企業の社会的責任」「戦略とリーダーシップ」が論じられている。一方、競争戦略論Ⅱは「立地の競争優位」「競争によって社会問題を解決する」という2部構成で、どちらかというとクラスター(企業が地理的に近接していること)と競争の関連性、立地戦略、都市問題などが中心に論じられているようなので、こちらは余裕があったら読み解いていこうと思う。
戦略について考えさせられた事例
「戦略」というワードは比較的頻繁に使われるが、なかなかイメージしづらい。ググってみると、戦略とは「特定の目的を達成するために、長期的・大局的視野に基づいて組織行動を立案・遂行するための策略のこと」と出てくる。イメージしやすく書くならば、目的(Purpose /最終的に目指したい場所、あるべき姿)→戦略(Strategy /目的を達成するためのシナリオ、方向性)→戦術(Tactics /戦略を進めていくための具体的な手法や手段)となる。
先日、地方の小さな会社の社長と会話する機会があった。
彼は過疎地域(特に離島)で医薬品が必要な時に手に入らない現状を苦慮され、複数の医薬品卸の会社の配送を統合されて、いくつかの地域で住民の課題を解決するソリューションを提供されている、社会問題の解決という面で非常に素晴らしい事業を行われている人物である。
一方で、彼は野心家でもある。
いや、どちらかというと「シリアルアントレプレナー」的な気質を持っている人物かもしれない。彼は東京に進出して事業を拡大したいという野心を隠し持っていらっしゃる。そのための方策を模索するためにボクと会話する流れとなったのだが…
ボクは東京進出を勧めることはしなかった。なぜなら方向性(戦略)がブレるからだ。彼の会社はまだ小さいので使えるリソースは限られている。彼はとても素晴らしい目的(ここは会社のミッションと表現してもいいだろう)を持っていらっしゃって、本人はそれを偶然と思っているようだが、ビジネスに落とし込むことができている。しかし戦略が練られていないことによって、目的さえも見失ってしまっていると感じたのだ。
ボクの気づきや思考を混ぜていく
さて、そんな会話をする機会があり、ボク自身も改めて「戦略」について学びたくなった。そんなボクにうってつけの本が「競争戦略論」だろう。この本の中でマイケル・ポーターは、以下の3つのフレームワークと分析方法で企業が生き残っていくためのポジショニングや戦い方を提唱している。
● コスト・リーダーシップ戦略
● 差別化戦略
● 集中戦略
さあ、この分厚い本を読み解いていこうと思っているが(例によって)ただの本の解説にはならないと思っている。ボクの気づきや思考を盛り込みながら、またあちこちに寄り道しながら、数週間かけて読み解いていくことになるだろうと思っている。
ご興味おありの方はお付き合いいただけると幸いだ。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
最後まで読んでくださってありがとうございます。
これまで書いた記事をサイトマップに一覧にしています。
ぜひ、ご覧ください。
<<科学的に考える人>>
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
