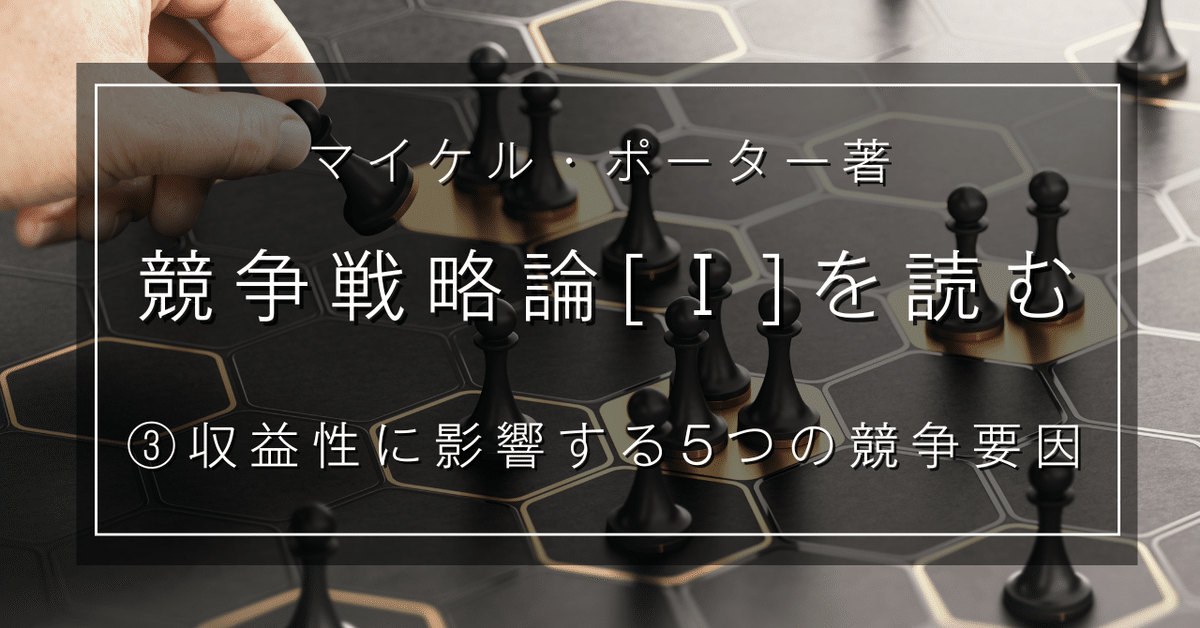
競争戦略論[Ⅰ]を読む - ③ 収益性に影響する5つの競争要因
さあ、水曜日だ。
毎週水曜日はマイケル・ポーター著「競争戦略論」をベースに、ボクの気づきや思考をアウトプットするシリーズを展開している。
先週は「企業の競争とはなにか」という記事を書いたが、今週は競争を左右する5つの要因の詳細について書いていこうと思う。
先週の記事で、企業の競争を「自社の収益性が、業界の平均に対してどのくらいのポジションにいるかを可視化して、そのポジションを上げていくこと」と定義した。そして、その業界内の自社の収益性の順位を引き上げるためには、影響する5つの競争要因を知らなければならない。
では、ひとつずつ詳しく見ていこう。
1. 同業界の中の他社の動向
改めて言うまでもなく、同業他社の動向は、あなたの会社の業界の中における順位に影響する。しかし、例えば有力なライバルがいて、その会社が派手な動き(その会社がわかりやすいマス広告を展開したり、何かのニュースに取り上げられたり、急激に従業員や協力会社を拡充したり)をしたとしても、それに一喜一憂してはいけない。
先週の記事で書いた通り、企業の競争とは「自社の収益性が業界の中でどのくらいの順位を占めているか」だ。つまり、そのライバル会社の「収益性」がわからない限り、勝っているとか負けているという概念で比較することはできないのだ。
2. 自社や自業界に対する顧客の交渉力
その業界の商品やサービスを購入する層に優位性がある場合、つまりいろいろな要因によって製品やサービスを薄利で提供しなければならない場合も、当然であるがその会社の収益性を下げてしまう。
買い手の数が少なく、大手の買い手が複数の売り手を跨いで大量購入する場合は、買い手側の交渉力が強くなる。また、その業界の製品やサービスが標準化されていて、スイッチングコスト(購入先を替えたときにかかるコスト)が安い場合、つまりどこの会社から購入しても大差がないと買い手が判断する場合も同様だ。さらに買い手が川上統合によって、自ら製品やサービスを生産/販売することができてしまう場合も、買い手側の交渉力が強くなる=つまり買い手側の価格交渉力が強くなる(というより、売り手側が過当競争に陥ってしまう)のだ。
現在の運送業界がまさにこの状態だ。
運送業界においては、上で書いた条件がすべて当てはまる。
3. 自社や自業界に対するサプライヤーの交渉力
サプライヤーをどう定義しようか…
製造業の場合、商品を作るための原材料や部品を供給してくれる会社がサプライヤーだ。小売業の場合、販売する商品の仕入れ先がサプライヤーとなる。物流業界の場合は、配送に使う車両やマテハン機器を取り扱う会社、梱包資材や緩衝材、労働力の提供企業(派遣会社や人材サービス会社など)、車両の燃料を提供する石油会社、車両や各種機材のメンテナンスを行ってくれる会社もサプライヤーに括ってもいいだろう。
こういったサプライヤーが、あなたの業界に対して優位性を持っている場合、当然のように納入価格が吊り上がることになる。それは買い手側の企業のコストを引き上げることにつながり、その会社の収益率を下げてしまう。
例えば(物流業界の話ばかりで恐縮だが)、2020年頃から、コロナ禍やロシア・ウクライナ情勢の悪化などの影響で半導体不足になったことにより、自動車(新車)の納車が遅れているが、その影響で中古車の相場が高騰しているので、運送会社の車両導入コストを押し上げている。そして、昨今のガソリンや軽油価格の高騰も同様だ。また、少子高齢化や2024年問題などの影響により、物流に関係する労働力の確保が難しくなっていることで、人材募集広告媒体やエージェント会社に支払うコストが年々吊り上がっていることなども、サプライヤーの交渉力が強い例として挙げることができる。
4. 将来的に参入してくるかもしれない新規の同業他社
新規参入の脅威は、参入障壁がどれくらい高いか低いかによる。参入障壁とは、その業界内の既存の企業が持っている優位性だ。「既得権益」と言い換えても良いかもしれない。
もし、あなたの会社が業界内ですでに一定の規模を有している場合、大量生産することや複数の業務間でリソースを共有することなどによって、コストを抑えることができていると思う。そうなると、新規参入者はそれを超える生産性やコスト感で新規参入することが難しくなる。また、その規模感は購入する側にも安心感や信頼感を与えることになるので、購入者の「新規参入者から商品を買おう(サービスを受けよう)」という意欲を抑制することになる。
また、あなたの会社が製品やサービスの独自の流通チャネルを持っている場合も、新規参入の障壁を高くすることができる。それが独自のものでなくても、卸売りや小売りのチャネルが非常に限定されているような業界で、すでに一定の規模を有しているなら、新規参入の壁を高くすることができる。
商品やサービスの内容によっては、サプライヤーを変更することにかかるコスト(スイッチングコスト)が大きい場合がある。それは、例えば新製品を導入するのにかかる仕様変更や従業員の研修、バックエンドの仕組みの変更などにかかるコストだ。また新規参入のために施設や設備が必要な業界も少なくないと思うが、そういったコストが高ければ高いほど新規参入は難しくなる。
5. 自社製品の代替となる新製品や新サービスの参入
代替品とは、ある業界の製品やサービスと同等もしくは類似の機能を、異なる形で果たすことができるもののことを指す。オンライン会議は出張の代替となり、eメールやショートメッセージサービスは速達郵便の代替品となり、レンタルビデオ店はオンライン動画配信サービスによって苦戦を強いられている。そういった代替品は、突然現れて元の業界の構造を一変させる影響力を持つ。
代替品は常に存在しているが、あまりに既存のサービスと姿形が異なっているため、将来的な脅威として見落とされてしまうことが多い。
来週は、競争要因と誤解されやすい、その他の収益性に影響する要素について書いていこうと思う。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
最後まで読んでくださってありがとうございます。
これまで書いた記事をサイトマップに一覧にしています。
ぜひ、ご覧ください。
<<科学的に考える人>>
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
