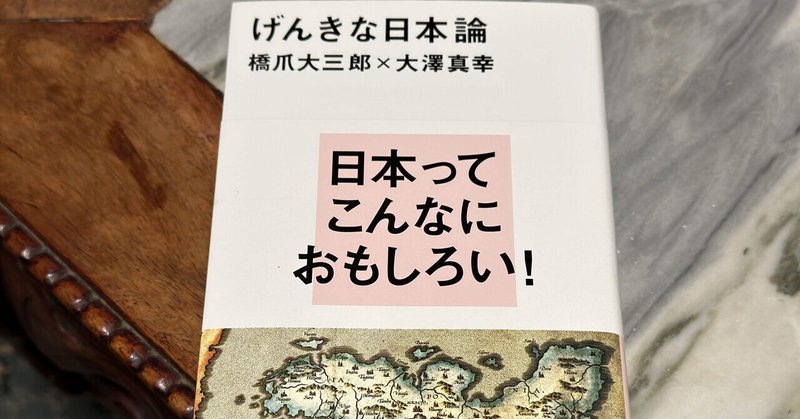
拒絶において受容する——外来の普遍思想に対する日本の「拒絶的受容」
日本の場合は両極に揺れず、中間にとどまるところに特徴がある。
昔、ある論文で、外来の普遍思想に対する日本の態度を「拒絶的受容」という語で表現したことがあるのですが、受け入れているのか、拒絶しているのか、わからないみたいな状態になるのですね。
極端な例は、お経ですね。中国語(漢訳)のお経をそのままにして、音として聞いているんだけど、それで何かわかったような、わかっていないような。いや、ほぼわかってない。わからないものとして受け入れているわけです。拒絶において受容する、と言いたくなる状態になる。(中略)
でも、不思議ですよね。最初は外来の思想や語彙のはずが、長年の間に、自分のものなのか他人のものなのか、わからないぐらい自分のものになっていく。これがふつうのプロセスです。キリスト教だって、西ヨーロッパにとっては、外来のシステムだったのが、気がついてみれば、すっかり内面化され、本来的なものになっている。
ところが、日本の場合は、どんなに時間が経っても、究極的には内面化されないというシステムも、いまだに使っているみたいな状況ですよね。
社会学者の橋爪大三郎さんと社会学者の大澤真幸さんの対談による『げんきな日本論』。なぜ日本には天皇がいるのか、なぜ日本人は仏教を受け入れたのか、なぜ日本には院政が生まれたのか、なぜ秀吉は朝鮮に攻め込んだのかなど、日本史におけるさまざまな疑問を、社会学の方法で、日本の「いま」と関連させる仕方で掘り下げた本である。
引用したのは「なぜ日本人は仏教を受け入れたのか」というところから。仏教は単なる思想や宗教ということではなく、当時は建築、暦法、冶金、漢字、衣料などの精神文化と科学技術のパッケージであって、それを取り入れることで社会を改革しようとした。でも仏教がもたらした矛盾もあった。それは、日本人の精神文化にはウジ(氏)集団と天皇がいて、その統治をいろどる神々がいた。このローカルな神々の伝承と仏教は何の関係もない。仏教という普遍思想を必要としたのは、社会のエリート層であって、普通の人びとは仏教をまったく理解できなかった。今で言えば素粒子物理学ぐらい理解が難しかった。そもそも仏典は漢訳されているのみで、漢字を読めるのはエリートだけであり、普通の人びとにとっては何だかありがたいものと感じながらも、腑に落ちるような心底自分のものにはならず、よそよそしく感じる。この分裂感覚というか、精神の二重性を仏教はもたらした。
この状態を、大澤真幸さんは「拒絶的受容」と表現する。受け入れているのか、拒絶しているのか、わからないみたいな状態である。この極端な例が、お経をその音のままに理解できずに聞いているという状態である。お経というのは、本来は意味をもつ漢訳の仏典なのであり、漢字の意味が分かればその文章は意味をなすものであるが、普通の人びとは意味を分からずにその音のままに聞いて、それを「何だか意味がわからないけれどありがたい」と思い、受け入れている。この二重性をもつ状態を「拒絶的受容」と表現したのである。
これは、キリスト教で言えば、宗教改革のときにルターがラテン語で書かれていた聖書をドイツ語訳したように、日本においても本当に仏教を自分たちのものにしようとしたら日本語訳できたはずなのに、あえて日本語訳されなかったところにもポイントがある。仏教が伝来した当時は、まだ仮名文字がなかったということもあるが、その後もずっと日本語訳で仏典に接するのではなく、漢訳のまま私たちは「お経」を聞いている。日本の場合は、原典を読むエリートと、ローカルな言葉に翻訳されたものを読む庶民という二極に分かれるのではなく、その中間にとどまるような状態、つまり「拒絶的受容」という状態であると言える。
「拒絶的受容」のより一般的な例は、日本語の文字の使い方である。日本は、自分たちで文字を発明しなかったので、漢字を導入し、さらにそれをカスタマイズすることで二つのかなを作った。そして三つの文字を、漢字かな交じり文で表現する。この文字システムは、外来語と土着のやまとことばとの区別が永遠に消えないようにできている。外来語は漢字で表記され、土着のことばはひらがなで表記される。西洋の語も明治時代に翻訳するときに造語してでも漢字にして使う。「philosophy」は「哲学」に、「metaphysics」は「形而上学」にと。本来の日本語とされたものはひらがな表記が可能で、漢字を当てれば訓読みになる。普通の文化では、外来の思想や語彙は長年の間にかなり内面化されていくのだが、日本の場合は、どんなに時間がたっても、究極的には内面化されない形で残る。この根底に「拒絶的受容」というものがあるのではないか。
なぜ日本人が外来の普遍思想を取り入れるときに「拒絶的受容」の形をとるのか。その理由を、大澤さんは、取り入れなければいけなかった普遍思想や法の観念を、ほんとうの意味では日本社会は必要としていなかったからではないか、と考える。日本にはもともとウジ社会と神々の思想があったのだけれど、そこに二重性を抱える形で仏教の思想が入ってきた。わざわざ輸入するわけだから、国の統治とか技術の導入とか、そういう意味で半分は必要としていたのだろうけれども、日本の庶民の多くにとっては「ありがた迷惑」だったのかもしれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
