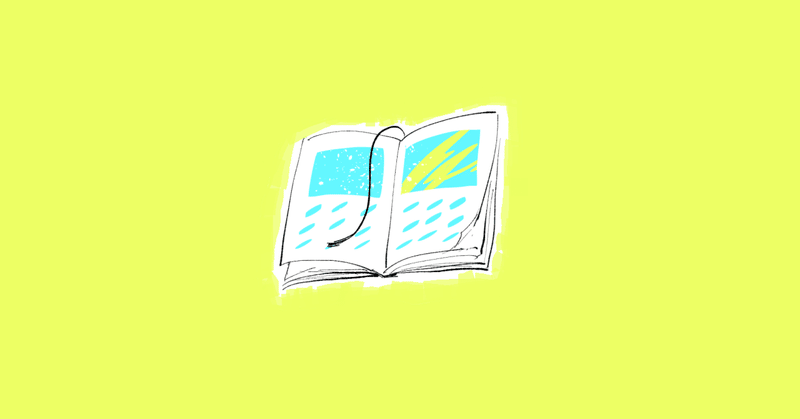
片山杜秀『左京・遼太郎・安二郎 見果てぬ日本』
SF作家の小松左京、歴史小説家の司馬遼太郎、映画監督の小津安二郎を通して日本の近現代を語ろうとする野心的な試みの一冊。
まず「この国に真の終末観を」と題された小松左京。
70年万博のテーマ「人類の進歩と調和」を立案した一人である小松左京は、科学の発展による原子力の制御に未来を託しましたが、一方でそのリスクを誰よりも知り尽くしていました。そんな小松の日本人に対する怒りと求めた覚悟とはなにか。なぜ『復活の日』や『日本沈没』のような人類滅亡物を書き続けたのか、そしてその未来へのヴィジョンの大誤算とはなんだったのかがまず語られます。
次に「島国の超克、漂白者の夢」と題された司馬遼太郎。
主に経営者やビジネスマンに愛読され、国民的作家と祭り上げられた感のある司馬遼太郎ですが、実はデビュー作の舞台はモンゴルであり、「騎馬民族と海洋民族への果てしなき共感と、定住者への猜疑心に貫かれた作家」だったと片山さんは指摘します。
こうした視点から一連の作品を読み解き、その特徴を顕にすると同時に、司馬の日本人に対する問題意識を浮き彫りにしていく本章が、質・量ともに本作の中心でしょう。しかし過去から現代を撃とうとした司馬文学は、皮肉にも撃とうとした対象である政治家や経営者に喜ばれるものとして機能してしまいます。そうならざるを得なかった「本質的に悲劇」な司馬文学の構造がここでは語られています。
そして最後は「持たざる国の省力法」と題された小津安二郎。ここでは主に黒澤明との対比を中心として、「持たざる国、日本の映画」のための思想と方法を小津がいかに確立させていったのかが語られます。そこには過去に憧れず、未来の理想も確定しなかった小津にしか持てない「最後の五分」を待つ覚悟が込められていると片山さんは説き、「それゆえに小津は今日もアクチュアルである」と述べて、現代に生きる私たちは、未来への展望や幸福になるための答えをもっていなくても生きていかねばならないと本書を締め括っています。
性急に答えをもとめるのではなく、宙吊りの状態に耐え続けること。その先になにが見えてくるのかは、読者それぞれに託されているといえるでしょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
