
どんな事業をやりたいか
この記事は 個人としてどう生きたいか に続き、僕がWebサイトに掲載するための引き出しとして書いている。
今回は事業、仕事、ビジネスに絞って思っていることを書き連ね、今後やるべき事業の優先順を決定する。
なぜ会社員ではなく「個人」として働くことになったのか
僕は元々「仕事」「働く」というものは、やりたくないことをやることでお金がもらえる苦役だと考えていた。
だから働くということが本当に嫌だった。お金にも興味はなかった。それよりも一日中ゲームをしていたかったのが本音だ。ここらへんは先の投稿でも書いた。
まず何より嫌だったのが、楽しそうに働いている大人をほぼ見たことがない点だった。少なくとも僕の周りにいた大人たちは、みな苦しそうに仕事をしていた。
先日会った友人で比較的心のままに生きているだろう彼が「進路について先生に『寅さんみたいになりたい』と言ったらめっちゃ怒られた」という話が印象的だった。
— 塩川まこと (@makoto_shiokawa) July 25, 2023
好きな時に好きなところへ行き、いろんな人と出会い自由に生きる。最高のはずなのだが、
なぜか教育機関では「ありえない生き方」らしい
このツイートでも触れた通り、大人になって働くこと、仕事というのは、(『男はつらいよ』シリーズの)寅さんのように自由気ままでは「あってはならない」らしい。こういった点にものすごく違和感を抱えたまま、大学を卒業して無理に就職した僕は、結局鬱になり仕事ができなくなって退職した。
うまくやっていけるのなら、別にサラリーマンでもなんでもよかったのだけど、働くことそのものに違和感を感じているような僕は、人から言われた仕事をやるのは残念ながら無理だった。この時はみんなと同じことができないのが絶望でしかなかった。
そうなると自分で仕事を生み出すしかない。そんなことは学校でも教わらなかったし、これまで考えたこともなかった。でもそれしか道がないのだから仕方がない。
次なる仕事の選択で気をつけたのは、「とにかく好きなこと、楽しいと思えることをやろう。もうお金が稼げるとか、経歴がどうとか関係ない」と決めて行動したことだ。
とりあえずWebデザイナーになったのだけど、理由としてはインターネットがかなり好きだったのと、美大やデザインの専門学校も出ていなくともHTMLのコーディングがわかればデザイナーと名乗れそう… という単純なものだった。
Webデザイナーもサラリーマンに変わりがなかったのだが、心から好きなものをベースに選択した仕事だったので、以前とは打って変わって仕事が楽しく、「好きなことをやってお金がもらえるなんて最高だ!」とさえ思っていた。その後調子に乗ってフリーランスとして独立し、大変な目に遭うのだけど笑
この世界で何を成したいか
様々な経験をした結果、僕がこの世界に対して疑問を抱いていたり、重要だと思うことを挙げてみる。
「自分」というものが重視されない
具体的な内容は前回の投稿 ↓
に譲るが、偏差値上げろだとか、良い大学に行こう、大企業に就職しよう、そうすれば人生勝ち組だ!(そうできないのは良くないことだ)といった論調が世の中を支配しており、僕がフリーランスとして独立した13年前ならいざ知らず、令和になった今でもあまり変わっていないのは、絶望を通り越して諦めすらしている。
せめて自分の周りの人、僕の投稿を真面目に読んでくれるようなごくわずかな人にだけでも、「自分」を大切にして幸せに生きていくための力になりたいと考えている。
様々な企業、それこそ大企業の方々からもお誘いがあるのだけど、すべて断ってフリーランスを続けているのは、「自分」というものを重視し、一人で活動してもしっかり稼いで楽しく生きていけることを僕自身が体現するためでもある。
はっきり白黒つけられる物事は実は少なく、中途半端な中間に「若干マシ」な解がある
対立したように見える2つがあっても、どちらにも良い面、悪い面があり、結果「両方取り入れるのがいい」ということがよくある。
— 塩川まこと (@makoto_shiokawa) July 31, 2023
白黒つけるのは実は悪手。
子どもの言うことは未熟ゆえの見当違いが多いが、かといって大人の考えが常に良いかというとそうでもなく、子どものほうが遥かに柔軟だ。… https://t.co/io3I4KSC0T
大人になると(特に仕事をして合理性を求められ続けると)、どうしても物事に白黒つけるクセがついてしまう(YesなのかNoなのか、AなのかBなのか等)。確かに仕事でこれはうまくいくことが多い。「商品Aと商品B、どっちが売れるかわからないんで、両方売っちゃいましょう!」なんてのはビジネスとしては最悪の選択だ。
しかし、同時に「これはA、Bどちらを選んでもデメリットが大きい…」「かと言ってCのような奇策が良いわけでもない」といった問題、場面も確実にある。両者が混ざったような、とても中途半端で上司やクライアントに納得してもらいづらいが、その中間のなんともいえない場所にちょうど良い何かがあることが確かにあるのだ。
この考え方をとても洗練し発信されているのが松岡正剛さんだ。彼は「duality デュアリティ(双対性)」という言葉で何度も説明している。
僕自身、「デザイナーだけど、エンジニアでもある」「クライアントの仕事をしているが、自分の事業も手掛けている」「お金儲けを目的とした投資を行いつつ、お金儲けを目的としないクリエーションを行う」といった両者が混ざり合った、中途半端な場所に身を置きつつ活動している。
「自分」「個人」といったものを大事にする → 学校や組織はダメだ!というのはまさに二項対立なので、そんな短絡的な戦いはしたくない。一人が最高!と言いたいわけでもない。ここは「ちょうど良い」のがどういう状態なのかを探っていきたい。
ソライトのロゴはこういった「デュアリティ」な姿勢を宣言するものとして、二重円が重なったグラフィックで作られている。正確には2つの二重、ダブル・デュアリティで形作っている。

現実世界をワクワクするものに書き換えたい
僕はゲーム(特にMMORPGといった多人数接続型大規模オンラインゲーム)、アニメ、漫画などが大好きだ。FFXIは寝食を忘れて朝から朝までやっていた。その後はSecond Lifeという仮想世界にもハマった。単純に楽しい、というのはもちろんあるが、僕の場合は廃人レベルになるまで没頭してしまうので、一体この願望はどこから来るのか?と考えてみた。
1つはこの現実世界がつまらないということだ。
上で挙げたように、他人に価値観を押し付けられたり、何かとお金が必要な世界でしたくもない労働をさせられたり、何か新しいこと・奇抜なことをやろうとすると頭を抑えつけてくる輩が現れる。「全体」「組織」「調和」「常識」といったものが重視されており、「単独」「個人」「革新」「異端」といったものは嫌がられる。特に日本はそういった「輪から外れる」ことが軽蔑される風潮があるようだ。「ゲームをして生きていきたい」など「バカなの?」と一蹴されるのが目に浮かぶ。
この世界がつまらない原因はいくつかあるが、僕が分析した結果としては
お金を稼がないと食っていけない(資本主義の強制)
つまり食っていくことが目的になっていて、それだけだとつまらない
やりたいことをやってお金も稼ぐやり方を誰も教えない(知らない)
だから「やりたいことをやるな!求められることをやれ!」という教えになってしまう
安定を目指すほど会う人もいる場所も固定化し、変化がなくなる

もう1つはゲームなどの世界観があまりに解放的なのもあるだろう。
ゲームや漫画の設定というのは、単純化されてはいるもののこの世界のもう1つの可能性だ。ガンツや進撃の巨人などは非常に辛辣な設定だけど、そこには自分たちで世界を変革するという自由やワクワクが見え隠れする。
任天堂の「あつ森」やFortnite、Robloxなどが異様なほどの人気を博すのも、そこには現実世界にはない自由と創造があるからだ。学校に行って二次関数とか古文を学び、就職してそういったものがどこにも出てこない(むしろ「あんなの必要なかったよねぇ」と誰もが口にする)、なんてことを何度も何度も経験すると、ゲーム世界のフィードバック・ループ(何かアクションをすると必ず結果が返ってくる)や漫画世界の荒々しくも自由に生きれる世界観に憧れてしまうのも無理はない。
だから僕は、ゲームや漫画の世界観を現実世界にフィードバックした方が良いと真面目に考えている。昨今は「ゲーミフィケーション」という手法が勉強や仕事にも取り入れられている。
ただ僕がイメージしているものは、空間的にゲームのような世界観と融合したり、アバターをまとって誰かと会話するような、リアルとバーチャルが交錯する世界観だ。
インターネットが世界を書き換えたことは誰しも疑わないと思うが、それをもっとアップデートした、空間的にも身体的にも現実が塗り替わるかのような世界をイメージしている。
この世界を支配する「資本主義」に向き合う
デザイン、クリエイティブな仕事にのめり込んでいく一方で、まったく毛色の違う「金融」の世界についても僕は取り組んでいる。
昔はとても毛嫌いしていた「お金」の領域だけど、この世界を構成する中核の1つだと捉え直してから、しっかり向き合うことに決めた。またお金を忌避しているとお金が寄ってこない、というのはよく言われていて、零細個人事業として何かと資金繰りに困ることが多かったのもあって、真剣に「金儲け」を考え直してみよう、と思ったのもある。
数分で50万円の利益を得る投機と、一日中あくせく働いて2万円の売上になる仕事の両方を経験して、それでも好きな仕事に取り組めているなら後者の方が断然良いと思えるマインドが養えたのはとても良かった。
と同時に、資本主義の世界で身を守るためには投資の知識・経験は必須だ。馬鹿馬鹿しい経済政策に巻き込まれて、僕らの生活が散々なものになっているのも事実である。自衛をするため、家族など大切な人たちを守るためにもお金の知識は欠かせない。
以上をまとめると、
資本主義に対抗しつつ、「自分」というものを大事にできる、リアルとバーチャルが融合した新しい場
が僕が追求すべき事業ということになる。
現在どういったことに手を出しているか
上で挙げた経験、そこから生まれた思考から僕は以下のようなことに興味があり、すべてに手を出している。
デザイン
人について深く知ることができる。
Webデザイン、情報デザイン、UXデザイン、UIデザイン、ロゴデザイン など
プログラミング
人力では不可能な機能を作り出せる。
PHP、Javascript、C#、Swift など
xR、メタバース、空間コンピューティング
現実の限界を超えた空間で、人の可能性を広げられる。
Blender、Unity、各社xRデバイス購入、クリエイターEXPOで毎年出展
キャラクターデザイン・アバター制作
「もう1つの身体」を生み出せる。
「どういった存在に人は惹かれるのか」も追求できる。
Blender、テクスチャ作成、アニメーション など
ゲーム開発
人がワクワクするものを生み出せる。
Unity
投資
現実世界を支配する「資本主義」に対して対抗する力をつける。
株式投資、エンジェル投資、CFD など
SNSでの発信・投稿
思考をまとめ、文章化して人に伝える訓練になる。
またわずかながら、人の助けになる言葉を書けるときもある。
X(Twitter), Facebook, Threads, Quora, note など
しかし、すべてをやるには人間の一生は短すぎる
あらゆることに手を出し続けてきたのだけど、40代半ばを迎え、若干「人生の終わり」が視界の奥にチラつき始めている。
僕は 羽海野チカさん の作品が好きなのだけど、『ハチミツとクローバー』の中で忘れられないシーンがある。


この箱を全部開けたい
ーーーでも全部開けるには人間の一生は短すぎる
人生が400年あればいいのにと仕方のない事を考えてしまう
人ひとりの人生では 開ける箱の数に限界がある
この「地平まで続く果てしない箱」の場面が脳裏に焼き付いている。クリエイターの端くれとして、新しいものを見つける度にものづくりの喜びを感じると同時に、自分の生の短さを悔しく思うことが増えた。
「ビジネスで成功するためにはやることを絞り込め」とはよく言われるが、そもそも人の一生というスパンで考えたら、やりたいことは絞るしかないのだ。
どんな事業、仕事を優先すべきか
ではいったいどこに僕は集中すべきなのか? 取り組んできたことを振り返り、探ってみる。
情報デザイン
僕の場合、まず一番に挙がるのはこれだ。「デザイン」という分野そのものが誤解されて伝わっていることが多い中、さらにほとんど知られていないと思う領域だけど、僕を「ちょっとコードが書けるWebデザイナー」から「しっかり稼げるUXデザイナー」にジョブチェンジさせたきっかけが情報デザインだ。はっきり言って情報デザインを知ることができて人生一変した。
デザインがわかってくると(つまり人間について理解を深めると)、「情報」について突き詰めるのはとても正しい選択となる。Google, Appleなどに代表されるGAFAMが成功したのも、彼らが情報の価値を深く理解していたからだ。
だからといって人に、つまりクライアントに伝わりやすいわけではない。情報デザインそのもので事業を営んでいくことは困難を極める。よってこの領域は事業ではなく、縁の下の力持ちとして支えてもらうものになる。
UXデザイン
情報デザインは「情報とは何か」という問いに答えていく領域だが、UXデザインは「人間とは何か」を突き詰める領域だ。僕の事業売上の80%以上を占める領域で、それほどにUX絡みの困りごとは多く、かつプレイヤーも少ないのが実情。この領域に比較的早い段階から取り組めたのは、フリーランスになってから一番の収穫だった。
この領域は個人的にも興味がある。「人間について知りたい」と思ったのは、システム開発の現場であまりにも同じようなことで問題が繰り返されるのに気づいたからだ。システム開発はいつも「機能」に着目していて、それが実際の使用シーンでどう使われるか?の「人間の体験」には無頓着。だから検収や納品後にトラブルになるケースが後を絶たない。
また「人間について知る」ということが今後突出した価値を持つことは、ピーター・ティール氏著『ZERO to ONE』の一節からも明らかだった。
隠れた真実には二種類ある──自然についての隠れた真実と人間についての隠れた真実だ。自然についての隠れた真実はいたるところに存在する。それを見つけるには、物理世界で発見されていないものを探さなければならない。でも、人間についての隠れた真実は違う。自分自身について知らないこともあれば、他人に知られたくなくて隠していることもある。だとすれば、どんな会社を立ち上げるべきかを考える時、問うべき質問は二つ──自然が語らない真実は何か? 人が語らない真実は何か?
これを読んだ時、僕はUXデザインが「人が語らない真実」の一角をなすことを確信した。この事業は今後も僕のビジネスの中核を担うだろう。ただ一点、クライアント・ワークであるため、僕の生涯を賭けた事業とはなれない。
UIデザイン
Webサービスやアプリに人が触れる、インターフェースをデザインする仕事。よくUI/UXと一緒くたに語られることが多いが、この表現は間違っている。UXデザインにはそれの専門家がいるし、UIデザインも同様だ。UX改善のアウトプットとしてUIが改修されることはもちろんあるが、UIの世界も奥が深い。
GoogleのMaterial Designといった一大コンポーネントの設計もUIデザインだし、Atomic Designといった原子や分子に基づいたUI要素の考え方もそれだけで専門職が成り立つ分野であり、とても面白い。
ただこちらはエンジニアリングと相性が良いというか、突き詰めるには面白いが「人間について知る」という僕が重視する方向からはやや離れてしまうため、UXデザインよりも優先度は下がる。
システム開発・アプリ開発
これはまさにエンジニアリングの領域で、「機能を作る」「効率を上げる」といった追求する人には面白いし、ニーズもあり単価も高い。僕も一時はWebエンジニアをやっていて実際単価も高かった。(デザイナーの単価が安すぎだとは思うが)
しかし僕がいまデザイナーを名乗っているのは、「いくらエンジニアリングを極めても、それを使う人間の性質がわかっていなければ、要件定義、それ以前の目的設定から間違える」ということに気づいてしまってデザイナーに戻った経緯があるので、この優先順が上がることはない。(ハチクロの引用であるように、人生が400年あったらもちろんやりたいが)
xRデザイン
xRというのはAR/VR/MRをまとめたもの、といった言われ方がよくあるのだけど、僕の考えは違っていて、「現実」がそれらと融合して「新たな現実」をつくることだと定義している。
正確にいうと「現実」とはあるがままの物理的な現実そのものではなく、人が現実だと認識している現実らしさ、つまり「現実感」(専門的にはRR リアル・リアリティと呼ぶ)のことで、「現実感」というものは実は決定的なものではなく、かくもフワッとしたものなので、だからこそARやVRなどで拡張、変容が可能だと考えている。(何言ってるのかわけわからん、っていう人がいると思うけど笑)
一応図解もしてあるので、こちらも見てほしい。

詳細の説明は省くが、xRに関わることは僕の事業の中核に絡むという確信はある。だからこそクリエイターEXPOという展示会で何度も出展してきた。しかしxRという領域もまた広大であるし、何よりこの言葉では人に伝わらない。もっと絞り込み、具体化が必要だ。
キャラクター・アバター制作
これはxRに絡みつつ、とても具体的である。Blenderで制作するのだけど、その過程もとても楽しい。(苦しい時もあるけど笑)
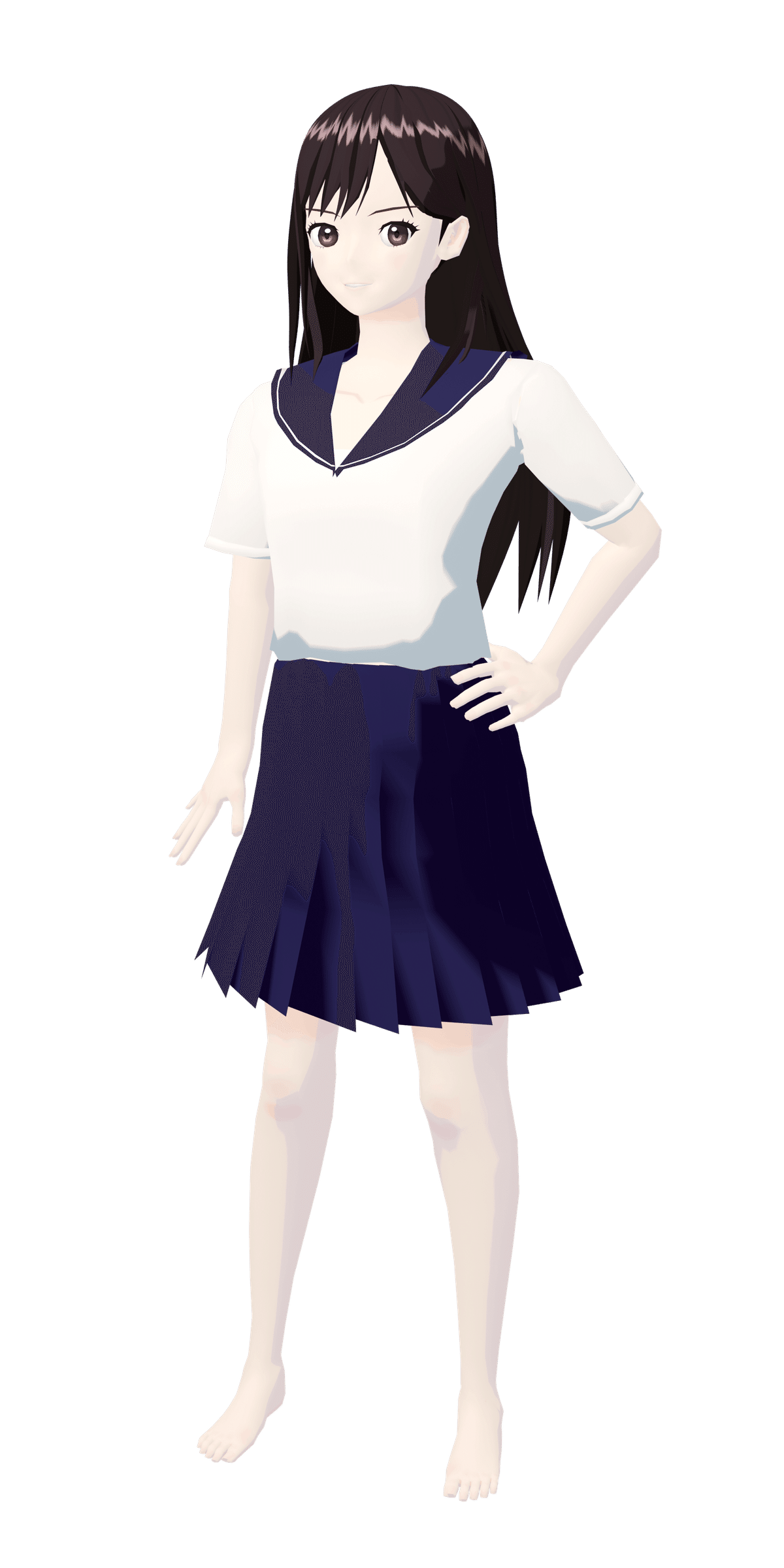
また人体を丸ごと作るというのは、「人を知る」ということでもある。UXデザインと同じく、キャラクター・アバター制作も続けていくと思うが、残念ながらこれも「場を作る」というものではない。
ゲーム開発
「とりあえずゲームが好きなんだから、思いつくままゲームも作ってみたい」と初めてまともに作ったゲームがこちらのVRゲーム。
「xRを絡めたい」「手をかざすだけで撃てる魔法のような体験を」といった思いを込めたこちらのゲームは2022年のクリエイターEXPOに出展した。普段VRゲームをされている方からも高評価をいただいたので、とても嬉しかった。
ただ同時に、一人でゲーム開発をする大変さも身に沁みてわかった。ゲームというのは、企画、ストーリー、世界観、自身を含むキャラクター、敵、戦闘システム、グラフィック、音楽、エフェクト、照明など膨大な作業を行わなければならない。設計するだけではダメで、それらをすべてプログラミングして実装しなくてはいけない。そのバグ取りも大変だ。
とはいえゲームは、先ほど見出した
資本主義に対抗しつつ、「自分」というものを大事にできる、リアルとバーチャルが融合した新しい場
にとても近い。FortniteやRobloxは「自分」ならではの創作を可能としつつ、リアルとバーチャルの交差点に新たな経済圏を築く可能性を秘めた良い事例だ。
【結論】事業コンセプトの決定
右往左往しながら長々書いてきたが、
仮に定めた言葉は、資本主義に対抗しつつ、「自分」というものを大事にできる、リアルとバーチャルが融合した新しい場をつくる である。
これをコンセプトに直すと、
「わたしだけの空想的現実」
「現実にはない居場所をつくる」
「空想的現実製作所」
念のため奥さんに確認してみると「難しく考えすぎ!」と一蹴笑
もっと簡単に、シンプルに。
「イメージを現実に。」
これだとシンプル過ぎてボヤけてしまう。
辿りつきたいのは、空想の街に暮らすような未来。
「空想と暮らそう。」
これだ。

このひと言に、今まで書いてきたすべてが含まれている。
このコンセプトに沿って、具体的な事業を洗い出すと
個人の空想を育めるツールの開発
そこで暮らしたくなるような空想空間のデザイン
つい夢中になってしまうゲーム開発
イメージした通りの体験に改善するUXコンサルティング
こういったところだろう。
やることは見えた。あとは、やるだけだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
