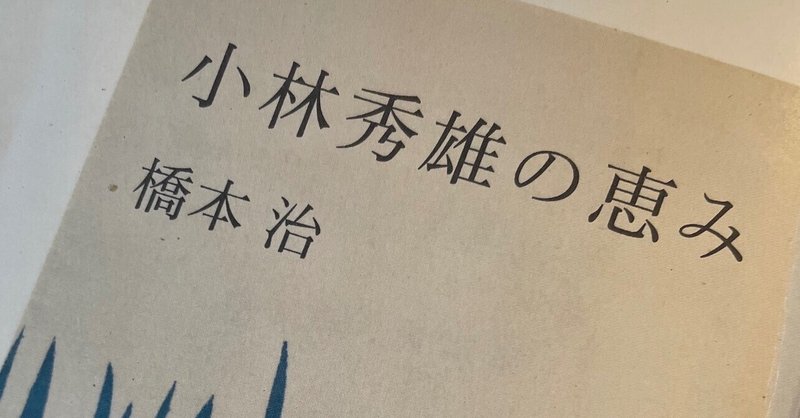
橋本治『小林秀雄の恵み』書評
以前に『新潮』に載せてもらった橋本治『小林秀雄の恵み』の書評が発掘されたので、『橋本治「再読」ノート』の販促をかねてnoteに転載します。編集段階の校閲を経ていない草稿であることをご承知おきのうえお読みください。
* * *
それを批評と呼んでも評論と呼んでもいいのだが、人が何かを対象として、とことん「考える」という営みが、ひどく貶められる世の中になってしまった。批評や評論など無用である、という意見がとくに異論もなく通ってしまう時代に、あらためて「考える」という営みが再生されるためには、その成立の根本まで遡ってみる必要がある――ということを、橋本治が考えたのかどうかは分からない。だが、結果としてこの本は「ものを考える」ということの根本とはなんであるか、という問いを読む者に突きつける。
だから本書は、まちがっても「橋本治による小林秀雄論」などではない。あくまでも橋本治が小林秀雄の『本居宣長』を読むことで受け取った感動――それを橋本治は「恵み」という言葉で表現する――についての論なのである。
橋本治がはじめて『本居宣長』を読んだのは、小林秀雄が亡くなった後のことで、ましてや小林秀雄が生前の宣長に会えたはずもない。だがこの本を読む人は、橋本治が『本居宣長』を読みすすむ過程に寄り添って、小林秀雄に出会い、小林の同時代人である折口信夫に会い、小林が論じている対象である宣長自身に出会うことができる。宣長の同時代人である賀茂真淵や上田秋成に出会い、日本における個人としての「思想家」の原点である中江藤樹にも出会い、さらには源氏物語や古事記が書かれた時代にまで遡り、その時代に人々がどのようにものを考え、感じていたかについてにも思いをはせることもできる。
だからといって、近世から近代に至る一直線の「日本思想史」がこの本で展開されているわけではない。個々の登場人物から「恵み」を感じとれるかどうかは読む側の問題であり、本書はあくまでも、「考えるということはどういうことか」を考える手がかりを与えてくれるだけである。
橋本治は『本居宣長』を再読し、再々読すると同時に、批評家・小林秀雄にとって転機となったのは、『無常という事』の冒頭におかれた「当麻」という文章であり、そこには最終的に『本居宣長』として結実する小林秀雄の「思想」の原点がある、との見極めをした上で、「無常という事」「平家物語」「西行」へも論をすすめていく。そうしたまわりくどい手続きを踏んで再び『本居宣長』に立ち戻り、小林秀雄がこの著作を書くことで考えようとしたことの核心に、じわじわと迫っていく。
この本が、どうしても込み入った構造をもってしまうのは、そうした迂回路のためだけではない。『本居宣長』で小林秀雄は宣長の著作から膨大な引用をしているが、橋本治も小林が引いた宣長の言葉を、小林自身の言葉とともに存分に引用する。「『本居宣長』を書いた小林秀雄」が論じられているのではなく、『本居宣長』を書くことで小林秀雄が考えたのと同じように、この本を書くことで橋本治は両者の「考えたこと」の筋道をとらえようとするのである。
小林秀雄は日本の文芸評論において、近代的な批評を確立した人だと言われる。だが、小林はやがて「文芸評論」なるものの外へ出てしまった。だが同時に、批評の大家であるとされたために、正統な学問の側からも排除され、その「外」にいるということにもされてしまった。なにより小林秀雄自身が、自分の書いた文章を「随筆」「感想」と称している。だがなぜ、それを「学問」と呼んではいけないのか、と橋本治は問う。
小林の論旨を追いつつ、随所で橋本治は立ち止まり、論の展開に疑問符をつける。だが、そのときこそが、「考える」という行為に意味が生まれる瞬間なのだ。そもそも『本居宣長』は、理路整然とした「評論」ではない。ひとつひとつの文章の論旨は明瞭でも、全体としては、枝道のたくさんある一種の悪路であり迷路である。だが橋本治は、『本居宣長』を初めて読んだときに受け取った「恵み」の感触を手放さず、ずいずいと悪路に踏み込んでいく。他人が「考えたこと」を「読む」という行為は、込み入った路を通過し、最終的にその向こう側へと抜け出ることだと信じながら。当然、この本を読む人間も、そのように読み、考えることが要求される。その意味で本書は、とてもしんどい作業を読者に強いる本でもある。
この本で「主張」されていることは、それ自体はとても簡単なことだ。「考えること」と「歌うこと」、「理知的であること」と「エモーショナルであること」は決して別のことではなくて、ひとつのことでありうる。だがその二つを一つのこととして達成するには、とてつもない力業が必要だ、という事実を確認することである。
小林秀雄が生きた「近代」という時代は、理知的であろうとすることが、宣長のいう「物のあはれ=エモーション」を排除することと同義となり、そのために知性そのものが痩せ細っていった時代だ、と橋本治は断じる。自らの「歌」を植えるべき土壌を同時代に見出せず、「源氏物語」や「古事記」の世界を必要とした本居宣長はとても孤独な人だった。その宣長の孤独を正しく「孤独」として指し示すことができた小林秀雄もやはり、彼が生きた近代において孤独だったのだ、と。
小林秀雄という人は、中原中也や冨永太郎と同時代を生き、ランボーの詩を訳し、かれら詩人のように「歌う」ことに恋い焦がれながらも、中也の死にあたって書いた下手くそな追悼の詩を除いて、みずからには歌うことを禁じた人だと、私はずっと思いこんでいた。だが小林秀雄もまた、彼なりのやり方で自らの歌を歌い続けていたのだと、この本を読んで気づかされた。それが私が『小林秀雄の恵み』から与えられた、最大の「恵み」である。
近世において宣長が孤立しており、近代において小林秀雄が孤立していたのと同様に、橋本治という作家は現在において孤立している。だが宣長と小林秀雄と橋本治に共通するものは、そのような「孤立」だけではない。この三人は、傍からいかに下手くそと思われようと、憶することなく、自分自身の声で「詩/歌」を歌ったことにおいて、意外にもそっくりなのだ。橋本治が一九八三年(小林秀雄の没年でもある)に出した「詩集」のタイトルは、『大戦序曲』という。「古代社会というシステムの崩壊」という、あまりにも巨大なテーマを担った戦記として『双調平家物語』全十五巻を書き上げた橋本治は、そのずっと以前から、彼自身の「歌」を歌い続けてきたのだ。
その声を――「恵み」として――本書から聴き取れた人は幸いである。
(了)
【お知らせ】
『橋本治再読ノート』は文学フリマ東京38にてインディー文芸誌「ウィッチンケア」のブースで印刷版を販売します。それに先立ち、印刷部数決定の参考にするためBOOTHでPDF版の先行販売を行ってます(価格は700円)。著者との対面販売時に印刷版を割引価格で購入できる割引券付きです。よろしくお願いいたします
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
