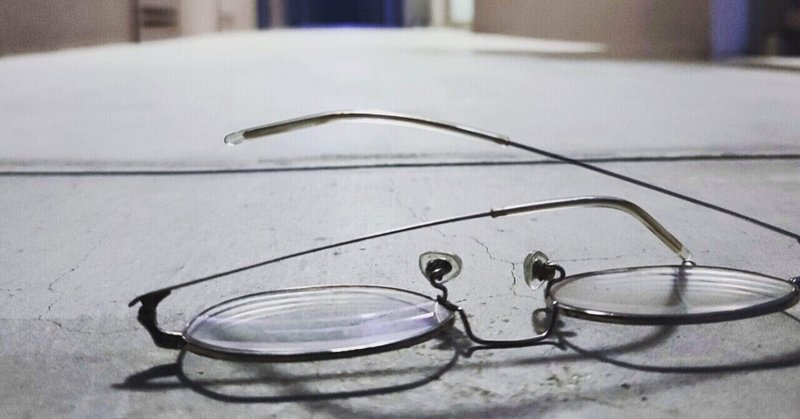
ジジイが書く詩【短編】
艶が失われた瞼に文字が羅列している携帯の光が当たって黒い筋が明瞭に現れている。
横臥したまま、文字を淡々と入力していく。
こんなはずではなかった。
俺は興味本位に作詩教室に入会したのだが、同年代の者はおらず、ジジイばかりだ。
加えて、初回で3ヶ月分の月謝を払ってしまったらしく、良心の呵責に苛まれつつも、抜けるにも勿体ないので3ヶ月間は続けてみることにした。
ここのジジイの書く詩には共通点がある。
どれも懐古に囚われたまだるっこさを持ち合わせ、ときに説教臭いものであるということだ。
そんな詩が嫌いで嫌いでたまらない。
ボコボコにしてやりたくなる。
手っ取り早く人を馬鹿にする方法は、人と同じ立場で誇張した愚行をはたらくことだと思う。
そこで俺はジジイどもの書くしをマネして嘲てやろうと企んだ。
しかし、何故か頭に考えが巡らない。
「どうしてだ。大学の中では頭がきれると持て囃されているのに。」
図らずも声に出てしまった。どう足掻いても、自画自賛することしか出来なくなったからだ。
そんな喚声を耳にしたジジイは俺を気ちがいと思ったか、面白半分に詩を探しはじめた。
先週書いた詩たちを見つけたジジイは言った。
「まったく、最近の若い奴の書く詩は、どれも手前味噌を並べたものばかりで、まだるっこしくて面白くないのぅ。」
俺はジジイをボコボコにした。
すぐさま、やばい、と感じ、2000円だけジジイの頭上に置いてその場を飛び出した。
「それにしても何故、ジジイが書くような詩が頭に現れないんだ?まてよ、そもそもジジイが書く詩というのは何なんだ?俺は知ったような口を叩いているが、本当に見たことがあると言えるのか?ん?何故こんなことを考えているんだ?」
走りながら口々に言葉を連ねるのが好きだ。
そして、考えのランプが点きやんだ。
「そうか、分かったぞ。このnoteを書いているやつは作詩教室なんかに入会したこともないし、そもそもジジイが書いた詩をまじまじと見たことがないからだ!」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
