
個人的動画制作メモ
前置き
「衣玖の使い方」シリーズを作るにあたっての自分用メモみたいなもの。カスコンテンツの作り方。
自分の思考整理、抽出のためだけに書いてあるので参考にしてもしなくても皆の自由です。正解なんてどこにも無いぞ。
動画を作る際の前提条件は以下の通り。
1動画内容はニコニコの雰囲気寄り
2自分が面白いと感じた要素を入れるので合わない人はいくらでもいる
3アップロード最優先
1
ニコニコの雰囲気寄りなのになんでyoutubeで上げだしたのかは俺もよくわからない、だからどっちにも投稿することにした。
2
自分が面白いと思う編集をするのは当然のことではあるが、より多くの人に見て欲しい!と思うなら話は変わる。
合わない人を減らす努力が必要になるということ。
俺は大してそんな努力してないのでこの前提になる。
3
動画に関わらず創作物において最も重要なポイント。
絶対完成させろ。
これだけは死ぬ気で守っていきたい。
なのである程度楽出来る部分は楽をする、大体どのぐらいの期間で完成させるか・いつまでに完成させたいかは明確に決めておく。
(自分のモチベーションが長続きすると思ってはいけない、という認識も持っておくこと)
創作物への強いプライドを持ち、ある期日に間に合えばタイミングが良い!という内容なら尚更設定日に間に合わせるため強い義務感を持つ。
前提はここら辺にしてメモを書き出していく。
ニコニコ向け、というより情報量に慣れたオタク向け

最初から偏見の塊みたいな見出しで書いていく。
一つの動画に詰め込まれた情報量がスッカスカだとつまらないと感じる人種が増えている、はず。俺もその一人。
ニコニコとyoutubeではどのように動画を作っても情報量に格差が出る。
それは弾幕コメントの有無かなと考えた。
動画自体に集中しながらも弾幕コメントで視聴者達が投げた反応を見て脳で認識、更に視聴者が投げたネタも拾って脳で処理。
多すぎる場合は一時停止してネタを追っていく、わからないネタがある時はggったりすることもあるかも知れない。
どう考えてもニコニコユーザーの方が情報量過多に慣れているのではないかと思った。
なので「いかに飽きさせず情報量を詰め込むか」を自然と意識するようになった。
もちろん情報の組み合わせや脈絡を考えないと伝わらないこともあるので、「これ伝わるか……?」「こいつらに伝わればいいや!」を天秤に乗せることになる。
マイナー過ぎるネタをやめる、流行りを理解する、視聴層のざっくりとした年齢を鑑みて知ってそうなネタに切り替える等。
展開を増やしすぎても方向性を統一しなければついていけない人が出まくるので、方向性を変えたい時は適度な一呼吸を入れることも必要。
息継ぎをさせないといくら洗練された視聴者ともいえど溺れることはある。
あとは再生数がやたら多い情報量過多なのに面白い動画をいくつも見る。センスは元々持ち得るものではなくパクリの集大成だと思ってたり。
嘘をつく

人間は嘘をつき、嘘に騙される生き物。
人の苦手要素に関連しない、笑える嘘であれば動画内で何度か使用可能。
嘘しかついてないと「これもまた嘘予告だな」と読み合いが終了してしまう。
格ゲーと同じで下段を見せたり上段を見せたり適度なバランスで出すことにより投稿者と視聴者の間で読み合いを発生させた方がいい。
1字幕で建前を見せているのに音声は本音になっている
2さっきもう出ないって言ったのに当然のように出てきた
3お約束の流れを丁度いいタイミングでぶった切る
ざっくり例としてはこんな感じ。
1は動画内で数回に留めておいた方がいい、多すぎると視聴者は「今なんて言ったこいつ?」と巻き戻す回数が増えてしまうため。
2は嘘の伏線。伏線の張りすぎは視聴者に記憶力勝負を持ちかける羽目になってしまうので、多くても2つぐらいでいいんじゃないかなと思う。
伏線を張る時はインパクトを強くするか、伏線要素が表示されている時間を
長めにとって視聴者の記憶に植え付ける方が良い。
3は「あぁこのBGMが流れたら動画の終わりだな」等の視聴者に植え付けた固定観念を利用する方法である。
エンディングの流れを何度か見せてpart3、4あたりで死ぬほど長いおまけを後半にぶち込んだり、いつもの解説コーナーが始まった!と思ったら本編要素に自然に戻したり等。
もちろんシークバーを見れば一目瞭然なのだが、「いやちょっと待てまだ〇分もあるじゃねぇか!」まで視聴者に考えさせられたなら嘘成功である。
情報量に慣れたオタクは着眼点の広さと認識速度が高い場合が多い、なので
「投稿者はボケ役のみに徹してツッコミは視聴者の脳内で行ってもらう」
これを随所で使っていきたい。
音は脳に快感をもたらす

タイミングよく音を鳴らすと気持ちが良い、これは人類が原始から感じてきたものなので疑いようが無い。
なので音は積極的に取り入れていきたい。
※権利関係に気を付け、調べながら使う事
音ハメ
音楽と動画内要素と関連した音をミックスする。
この時点で作業量がお辛いことになるが、ちゃんと作れば決め手部分にもなる上に尺稼ぎも出来る。
もちろん音MADもどきを作る時は映像のタイミングも合わせないと意味が無いので、「作るか」と決定したら逃げてはならない。成せば成る。
効果音の厳選
方針は人それぞれだが俺は「よく聞いたことのある効果音」をメインに使うことにしている。
一発で「これアレだ!」「昔よく聞いた」と共感性に訴えかけることが出来るので楽で便利。
同じ場面で使う効果音は大体統一し、雰囲気がやや変わる場面では似ていても違う質感の効果音を使うのもアリ。
BGMもそうだが、「これが欲しい!」と直感で思った音は出て来るまで死ぬ気で探すべき。妥協しちゃいけない点。
蜂と仏を意識する
「蜂は二度刺す」
「仏の顔も三度まで」
これを意識しておいた方がいい。

蜂
同じネタを擦るのは基本2度まで。
そして蜂を使うのも2度ぐらい、間隔はやや長めに空けないとくどくなる。薬の服用と同じだと思っておけばいい。
2回目を擦る時は勢いとインパクトを強めにした映像作りを心がけていきたい。
仏
同じネタの三度目は既に耐性が出来ておりクリティカルヒットしない場合が多い。薬の服用と同じだと思っておけばいい。
怒り狂った仏を誕生させてはいけない。
オリジナリティ
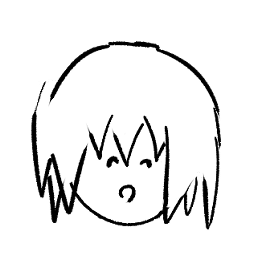
オリジナリティを出すつもりは毛頭無かったが、気付いたら「天則の解説はおまけで料理を始めるクソ野郎」と化した。唯一無二のカス。
そもそも衣玖の使い方 その1に関しては料理要素も無い。
俺の場合は「非想天則要素」を入れながら嘘をつきたい……嘘をつく内容は自分が手慣れている分野が良い、じゃあ料理でもすっか!といった風に即決で出来上がっている。
自らが手慣れている、且つ大衆に伝わるコンテンツを混ぜるのは比較的楽な手法ではないかとは思う。
(自分で描いた絵、というのも続ければオリジナリティになりやすいのでこれも楽な手法の一つになり得るはず)
そして重要だと思っているのはパクりの集大成はオリジナリティになる、という個人的解釈である。
「面白い動画を作ってた人の音の使い方を真似しよう」「皆がよく見て話題にしてるあのネタを一部取り入れよう」「面白い映像加工の仕方を見た、調べて取り入れよう」
これらはどんどんやるべき。歴史が人を進歩させたのは結局のところ「成功した誰かの真似をし続ける」ことなので大体合ってるはず。
もし間違ったら皆の反応に出たりすると思うので反省点のチェックもしていく。ミスは活かせ。
投稿するまでに気を付けること

承認欲求を抑え、出来上がるまでそのほとんどを途中公開しないこと。
「作りまーす」「明日できます」ぐらいは全然良いと思う。投稿される動画への心の準備は出来る限りさせない方がいい。
基本は奇襲して背後から刺す意識。
カスコンテンツは鮮度と暗殺。
なんか他にもあった気がするけど思いつくメモとりあえずここまで。
自分の思考をテキストに出力するのは積極的にやっておきたい。
今回は表に出せる内容なので特に深く考えず放出。
またいつか動画作ったらゴミを見るような目で再生ボタン押してください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
