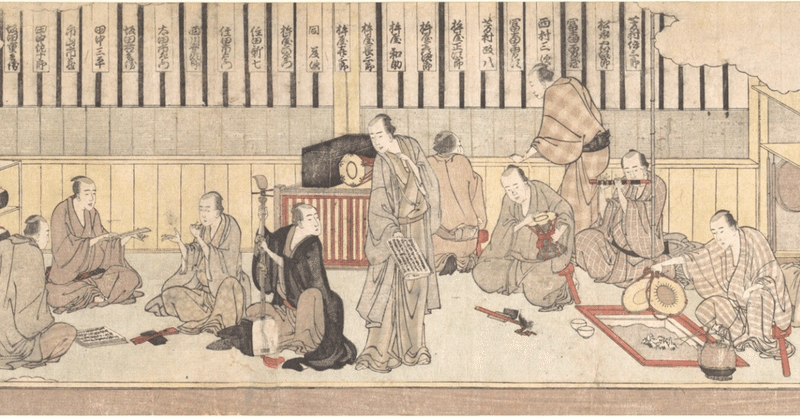
著作権とフォントの教養のハナシ
著作権法界隈ってこの30年でそれなりに変わっていて、直近の教養として、
※後でリンクを追加するかも…しましたw
・著作物には創作性が必要
・コンピュータの学習データに使うのは自由
・機械学習系で原著作権者の権利を害する場合は自由利用の例外
・著作者名を騙るのは犯罪
・著作物と実演家との枠に財産権と人格権がある
・AI生成が著作者や実演家の財産権を侵害する場合は違法
・AI生成が許諾無くソースをアレンジしたら人格権侵害疑惑
・なお、AIアレンジ解釈なら二次著作物なので親告罪枠
・著作権侵害が親告罪から非親告罪になった
・プロテクトを解除する行為が罰則はないけど違法
・期間が70年まで伸びたが最近米政府内でこれ以上伸ばすのは嫌みたい
この辺りはネット記事そこそこ拾ってれば誰でも知ってるレベルなんだが、まるっきり知らないばかりか古い知識のままアップデートされずにいる人がかなり多い。前述の「70年以上にするのが嫌みたい」は 2023 末でオールド・ネズミーの著作権が切れたことからも実際に結論は出た模様w
で、結構誤解のあるのがフォントとタイプフェイスの混同で、判例を読んでみるとフォントのデジタルデータにはプログラム著作物の適応がなされるため著作権は生じるものの、単なるタイプフェイスとしてのフォントの著作権は有るかと云うと無いので、デッドコピーは著作権侵害になるけど似せて作ったタイプフェイス自体には著作権ないし、デジタル化されると同じようなタイプフェイスでも別建てのプログラムの著作物枠になる場合がある。90年代以降は特にアメリカの方針も変わったし…
で、以下の記事にもあるが、90年の大阪の判例の、
「モリサワ対エヌアイシー事件」(大阪地裁1989年3月判決、大阪高裁1990年3 月和解)でも、書体(タイプフェイス)に著作権を認めないという判定が下っている。し かもこの問題について大阪地裁は「原告の書体は実用性の強いものであって、美的創作性 を持っていない。したがって著作物性を認めることはできない。」というものである。
とのことなので、詳しく勉強したい人は以下のサイトを確認の事2003年という20年前の記事なので常識の範疇だと思う。
ソース:フォント関連の知的財産権 ─フォント千夜一夜物語
(1)https://www.jagat.or.jp/past_archives/story/6112.html
(2)https://www.jagat.or.jp/past_archives/story/6167.html
(3)https://www.jagat.or.jp/past_archives/story/6223.html
(4)https://www.jagat.or.jp/past_archives/story/6279.html
(5)https://www.jagat.or.jp/past_archives/story/6316.html
(6)https://www.jagat.or.jp/past_archives/story/6410.html
で、ここで付加的な問題として70-80年代には24ドットといった低解像度ビットマップフォントには、誰がやっても似たものになるので創作性が無いという観点から著作権が無いというハナシがあって、元を辿ると83年年のJIS規格で24ドット明朝体のタイプフェイスが策定されていたので、それに基づいた24ドットフォントには著作権が無く独自にデータ化すれば基本フリーフォント化するという文脈があったのが90年代のアウトラインフォントより前の基礎の教養。
ソース:ドットフォントの雑学(3)─フォント千夜一夜物語(24)
https://www.jagat.or.jp/past_archives/story/6612.html
まぁ、そうなるとゴシック体はJISで整備されてないから著作権があるのか?ってなると無いけど、データのデッドコピーではなくタイプフェイスが同じなら誰がやっても24ドット以下だと似たようなフォントになるんで自前でデータ化できれば著作権侵害にはならないハズってのが基本的な建付け。
で、じゃぁ、著作権で保護されていないフォントの利用はどうするのとなると、基本的に民事契約になるので民事契約を結んでない人のフォント利用自体が民事契約違反で民法710条枠とかで損害賠償請求の対象であり、不正競争防止法の剽窃に抵触すると考える方が妥当。
因みに、アウトラインフォント以降は基本平成(90)年代になるんだけど、JIS規格主導での平成明朝、平成ゴシックって枠があってアウトライン技術はNECの特許だったのでライセンスを許諾して結果平成アウトラインフォントが普及したというのが基本。で、NECの特許も93年ぐらいに切れてるので、Win95 ではアウトラインフォント使い放題だったんじゃないかな?サムさんが頑張って、明朝とゴシック入れたってのは有名過ぎて常識レベルの話ねw
ソース:平成フォント誕生物語─フォント千夜一夜物語(12)
https://www.jagat.or.jp/past_archives/story/5915.html
で、ここ迄の教養があったうえで著作権とかフォントの話をするのであれば話は噛み合うけど、この程度の教養もないとなると、そもそも会話がかみ合わないので、なんだかなぁ…という…
何より、フォントは著作物ではないという建付けの場合、該当フォントの利用は民事契約に基づくものなので、私的複製の許可という著作物に対する建付けは当然生じない。だから、使用の権利はフォントのデータを売る側と買う側の民事契約になるので著作物ではなくなり契約の当事者以外が勝手に複製して使用するのは前記民事契約の外側になる。更には著作物であっても利用に際しての民事契約がどうなってるのか判らないと手に負えない。ということはつまりフォント製作者と民事契約のない人が勝手に低解像度フォントをコピーして使うのは、手短に云うとタダのデジタル万引きにしかならないんだけど解ってない痛い人が結構いるので雑草も生えない。
もっと勉強したい人はこちらを参照のこと。
【DTP玉手箱】【フォント千夜一夜物語】澤田善彦 コラム集
https://www.jagat.or.jp/archives/7443
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
